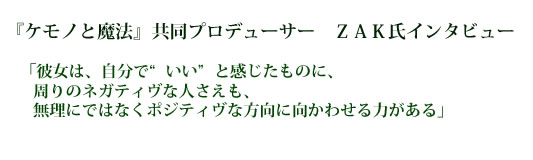
“濃いものを濃いままに表現したい”という原田郁子の願いを見事な手腕で具現化したのが、彼女と共に『ケモノと魔法』の共同プロデュースを手掛けたZAK。日本を代表する名エンジニアとして数々の名盤に携わってきた彼に、今作の制作秘話と “アーティスト”原田郁子の魅力を語ってもらった。 ──原田さんと最初に本格的なお仕事をされたのは?
ZAK 「最初は、たぶん『Re-clammbon』(※2002年に発表された
クラムボンのリミックス・アルバム)のレコーディング。でも、彼女のことを本格的に意識して仕事をしたのは
ohanaのアルバム(
『オハナ百景』/2006年)ですね」
──第一印象はどんな感じだったんですか?
ZAK 「九州女そのものというか、“優しいけど頑固”という側面と、あと、普段は見えない彼女の深い影の部分っていうのが、そのときに強く感じた印象です。長く残っていくアーティストは、みんなピュアで頑固な部分を持っていると思うんだけど、郁子ちゃんの場合、自分の中にある譲れない部分を頑固に貫き通しながらも、周りを決して傷つけないように注意を払っている。“苦しくても優しい”みたいなところがある。周りのいろんなことを否定しながら、どんどん前に進んでいく人もいますよね。それはそれで大きな力がいるんだけど、彼女は、自分で“いい”と感じたものに、周りのネガティヴな人さえも、無理にではなくポジティヴな方向に向かわせる力がある。そこがすごく魅力的だと思います」
──そのあと、原田さんとは
フィッシュマンズのライヴでも共演されてますね。
ZAK 「いろんなヴォーカリストに参加してもらったんですけど、なぜか郁子ちゃんには最初にステージに出てきてほしいなと思ったんですよ。彼女が初めに出てくれることによってライヴの雰囲気が重くならないというか。さーっと吹きぬける風のような感じが欲しかった」
──『ケモノと魔法』で共同プロデュースを手掛けられることになったキッカケは?
ZAK 「郁子ちゃんとはフェスでやたら会うんですよね。いちばんよく覚えてるのは去年の5月に福岡で行なわれたCIRCLEというイベント。そのときに、二人で割としっかりしたことを喋って、意思を確認しあったりして。その後、メールでやり取りするようになっても、共に連絡不精なところがあって、1カ月ご無沙汰みたいな感じもあったんだけど、あるときから急にこまめに連絡を取り合うようになって。それで、今回ソロ・アルバムを作るっていうことで、声をかけてもらったんですけど」
──レコーディングで使われてるギャラリー・トラックスを訪れたときに、「ここでZAKさんに録ってもらったら面白いだろうな」と原田さんは思ったみたいですね。
ZAK 「ギャラリー・トラックスという場所は、今回の大事なポイントのひとつでした。下見に行ったときにも、“ここには何かあるぞ”と思ったし。何かが起こってるというか……何かが起こった気配を感じたんです」
──作業はどんな感じで進めていったんですか?
ZAK 「なんか試しに録ってみようかっていう感じで、ギャラリーの隅に置いてあったピアノを真ん中に動かそうと思ったんですけど、そこに置いてあったということは、なんらかの意味があるんだろうと思って、まずはそのピアノで1曲、彼女に弾いてもらったんですよ。調弦も何もされていない状態のまま。そうしたら、やっぱりすごいものが録れて」
──
おおはた雄一くんと原田さんが二人で、やってる「こだま」という曲も当初、収録する予定がなかったんですよね。
ZAK 「何か面白いことが起こりそうな気配を感じたら、ぱっと機材をセットするようにしていたんです。“さあ、録るぞ!”みたいな雰囲気になってから準備しはじめても絶対に遅いから。いろいろなことを気にしていない、めちゃくちゃ油断してるときのほうが、いいものが録れることが多いんです。いいテイクが録れたのに、“あそこの演奏を間違えちゃったから、もう1回録りなおしてほしい”みたいなことをたまに言う人がいるんだけど、“間違いって何?”って、僕はいつも思ってしまうんです。それって、自分で “間違えた”と決め付けているだけで、こちらからみれば何の問題もなくて、大きく全体でみれば、それがあるから今のテイクが良かったとさえ言えることだってあるんです。予想もつかないようなものが出てくるから面白い。そう考えるとミスタッチだって、“天からの贈り物”みたいなものじゃないですか。もちろん何でも容認するというわけではないけど郁子ちゃんは、そういう部分も積極的に楽しめるタイプだから、一緒にものを作っていても、すごく嬉しいです。たとえば、おおはた君とやってる曲では、彼が鼻をすすってる音とか、ストーブの薪がパチパチ燃える音も入ってるんですけど、逆にそれがあるからよかったんだと思います。それを作品として聴いてもらえるようにするのが僕の仕事というか役目やから。何かをするかもしれないし、何もしないかもしれない。それは、その都度、状況を見ながら考えます。」
──出来上がった作品を聴いてみて、いかがですか?
ZAK 「喜びにあふれた音でいっぱいで、郁子ちゃんの愛の結晶じゃないでしょうか。表に現れていないことが、どれだけ本当で大事なことか、というのが音で表わされていると思います。今回のアルバムって、普段、調味料をいっぱい使ったような音楽を聴いている人の耳には、ちょっと物足りなく感じてしまうと思うんですよ。だからといって、無理やり塩を入れて味を濃くするつもりもないし。“美味しいものは、手を加えず、そのままの形で出せばいい”って僕は思うから。原田郁子というアーティストが持っている愛を表現すること。それに孤独でいることの寂しさ、それを受け容れる悲しみや喜び、その大事さ、もちろん彼女の持っている美ししさも、全部詰まったようなものを、手を抜かず丁寧に作ることができたと思うんで、あとは聴く人がこのアルバムから、いろんなことを思い思いに感じ取ってくれたらいいんじゃないかと思います」
──今後の原田さんに望むことは何かありますか?
ZAK 「今のままで十分なんじゃないですか(笑)。しいて言うならば、今回、このアルバムが出来て、彼女の中にまた新しい何かが芽生えただろうし、音楽の表現の仕方も広がったんじゃないかと思うので、今後も素直な気持ちでどんどん、作品を創り続けていってもらえたらと思います。彼女の音楽には、すごくエッジがあると思あうんですけど、それが刺々しく感じられないのは、やっぱり彼女自身の優しい人柄があるからこそだと思うんですね。そういうものって、やっぱり音楽に現れてくるから。郁子ちゃんには、健康にこのまま音楽をやり続けてほしいですね。そして、これからも一緒に音楽を続けられたらいいなと思います」
取材・文/望月 哲(2008年5月)
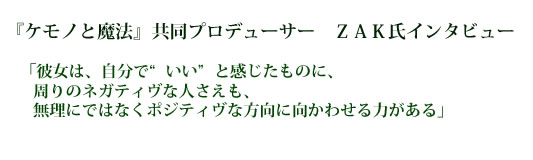




 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。