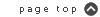掲載日:2015年03月20日
01 音楽の目覚め - ミドルティーン(中学卒業まで)

――音楽にまつわる最初の記憶は?
――細野さんの曲ですね。
「あ、そうですよね。父親は小さいレコードプレイヤーを集めていて、テントウ虫のカタチしたプレイヤーで〈北京ダック〉をかけながら踊るのが好きで。あと、クラシックの全集をおばあちゃんが持っていて、それをかけながら新体操みたいに踊ったり。とにかく歌うことと踊ることが大好きだったんです。いちばん最初に好きになった洋楽は“ビーチ・ボーイズ”だったんです。『ペット・サウンズ』の2曲目の……」
――“僕を信じて”。
「衝撃だったんですよね、ホントに。父親のルノーの助手席に乗ってるときに聴いたんですけど、“この素敵な曲は何なんだ?!”って。雨上がりの虹が出ていて、その曲が流れてきて……そのときの光景をはっきり覚えてるんです。なぜか恥ずかしくて曲の名前を聴けなかったんですけどね。で、曲名を知らないまま大学生になって(笑)」
――え(笑)?
「大学生のときに『ペット・サウンズ』を手にして……それも親からもらったんですけど……“うわ、これだ!”って。感動の再会ですよ。生き別れの兄弟に会ったくらいの(笑)。曲の名前もわかったし、よかったーって」
――(笑)。やっぱり音楽好きの家族だったんですね。お父さんはロック好きなんですか?
「ロックが中心だったんですけど、洋楽・邦楽を問わず、いろんなレコードを持ってましたね。ブルースとかモンドミュージック的なものとか、フランスの音楽とか。お色気レコードのコーナー、演歌コーナー、ご当地ソングのコレクションもありました(笑)。私がロックをやり始めたときも“まずはこれを聴いておけ”って“裸のラリーズ”のカセットテープを渡されたり。あとは“フリクション”とか」
――いきなりコアなところに行きますね(笑)。
――逆にレミさんから“あのバンドのレコードが聴きたいんだけど”って言えば、“あるよ”っていう感じだったんですよね?
「そうですね、ほとんど何でもありました(笑)。それだけはホントに恵まれてたと思いますね。小さいときの記憶はかなり細かく残ってるんですけど、保育園くらいまでは音楽よりも本のイメージが強かったんですよね。絵本もお父さんが選んで読んでくれてたんですけど、“保育園で先生が読んでくれる絵本とはだいぶ違うな”って思っていて。親のセレクトのなかで育ってきた感じはありますね」

――なるほど。ちなみにお父さんはどういう方なんですか?
「“カルチャーの人”みたいな感じですかね。お金を稼ぐための仕事もしてたんですけど、父親が言うには“あれは仕事じゃない”って。本当は好きなことだけやっていたいけど、悔しいことにそういうわけにはいかない。だから、稼いだお金で個展を開いたり、ライブをやったりするんだって言ってて。うちの家族はそういう感じなんですよね。おじいちゃんも絵を描いてるし、画家の親戚もいるし、母親もプロではないけどイラストのお仕事とかをしていて」
――芸術一家だ。
「そこまでではないですけど、みんなヘンでした(笑)。たとえば朝食のときも、母親が“今日のメニューはカリフォルニアの大地を感じさせる色合いでしょ”って言ったりとか。あと、家の前にガレージがあって、そこにいろんな人が集まってたんですよ。DJやバンドやってる人とか、絵描きとか。どんなつながりか知らないけど、都会から来るお客さんも多くて、その人たちがやる展示会やコンサートにも行ったり。保育園の頃はすでに“ウチはちょっと変わってるな”って思ってましたね」
――お父さんだけじゃなく、みなさん個性的なんですね。
「母親もおもしろくて、私、毎日違う髪型で保育園に行ってたんですよ。ふつうのツインテールの日もあれば、髪の毛でお団子を8個くらい作る日もあったり。私も好奇心旺盛だったと思います。保育園の運動会や行事も大好きだったし、どんどんやりたがって。負けず嫌いだったし、目立ちたがり屋だったかもしれないですね、いま思うと」
――その頃の夢は画家だったんですよね?
「はい。好きな絵画があったんですよ。母親のドレッサーのところに飾ってあったポストカードの絵なんですけど、夕方の空の下で、蒸気機関車が煙を吐きながら走っていて、まわりにはお花が咲いていて。こういうふうに説明するときれいな絵っていう感じかもしれないですけど、ただきれいなだけではなくて、独特の幻想的なイメージがあったんです。私はそれを見て“この世界に行きたい”みたいに思っていたんですよね。で、“これはどうやって描くの?”って聞いたら、“絵具を使って描くんだ”って言われたから、“私もやりたい!”って。で、おじいちゃんに画板と絵具の道具を買ってもらって、写生大会に出て桜並木を描いたんです。そこから中学まではずっと描いてましたね。小学校のときも県展に出品したり」
――絵の教室に通ったりもしてたんですか?
「いや、田舎すぎて絵の教室なんてないんですよ。だからおじいちゃんとか母親と一緒に描いてました」
――そんなに田舎なんですか?
「ド田舎もド田舎、沢蟹が歩いてますから。長野県の南のほうなんですけど、夏、窓を開けたらカブトムシが飛んで来ますからね(笑)。家の目の前は田んぼで、後ろは果樹園と森。ゲームの『ぼくのなつやすみ』みたいな感じです」
――いいところじゃないですか。
「そうなんですけどね。村の伝説みたいなものもいっぱい残ってるんですよ。あの神社にはアレが埋まって……とか、狐に化かされて、アレが出来たとか。そんなところだから、ウチの家族はかなりヘンだったと思いますね。まあ、家族はみんな“それでいいんだ”って気にしてなかったですけど」

――小学生のときも活発だったんですか?
「そうですね。絵を描いたり、ケンカしたり」
――ケンカ?
「よく男子とケンカしてたんですよ。とにかく負けず嫌いだったんで。鉄パイプ事件っていうのがあって……こんな個人的はこと話していいのかな?」
――お願いします(笑)。
「ケンカしてるとき、相手の男の子がサッカーのゴールのところで鉄パイプを拾って、それを振り回してきたんです。で、私も負けずに鉄パイプを持って振り回してたら、先生が集まってきて止められて。その後は職員室に呼ばれて正座ですよ、みんなが授業を受けてるときに。そういうことが何回もあったし、クラスで議題に上ったりもしてたんですよ。そのうち女子対男子みたいになって、“さん付けで呼ぶべき”“呼び捨てはダメ”みたいな討論をしたり。くだらないんですけど、そこでもめっちゃ負けず嫌いだったんですよね」
――すごい(笑)。学芸会とかも目立ってました?
「主人公以外の目立つ役をやりたがってましたね。たとえばシンデレラをやったときは、絶対に魔法使いがいい!とか。そういう立ち位置が好きだったんですよね、なぜか」
――もちろん音楽も聴いてたんですよね?
「小学生のときは自分から積極的に手を出す感じではなかったですね。いつも何かがかかってるので、それを聴いて“これはいいな”って思うくらいで。その頃はピチカート・ファイヴとかカジヒデキが好きでした。あとは初期のコーネリアスとか。カヒミ・カリィが『ちびまる子ちゃん』の歌(〈ハミングがきこえる〉)を歌ってたんですけど、それもいいなって思ってましたね。音楽というより、カルチャーとして捉えてのかもしれないです。ピチカート・ファイヴってオシャレだなとか」
――いわゆる渋谷系ですね。それもお父さん経由?
「そうですね。うちの父親、いつも新しいアーティストをチェックしてるんですよ。いまでも私より詳しいと思います。“東京でバンドやってるからって、みくびるなよ。俺はいつもアンテナを張ってるんだ”って言ってるんで(笑)」
――楽器にもまだ興味がなかったんですか?
「小学校のときはぜんぜん。父親がいつもギターを弾いてたから、あえて自分から手を出さなかったのかもしれないです。ギターを弾き始めたのは中学生になってからですね。クラスに3人だけ音楽の話が出来る友達がいたんですけど、その子たちと“どうやら〈BUMP OF CHICKEN〉が流行ってるらしい”っていう話になって。そのときに“バンドって楽しそうだな”って思ったんですよね。最初はベースをやりたいと思ってたんです、じつは。弦が4本だから簡単そうだなっていう(笑)。で、叔父がベースを持ってるって言うから、“使ってないんだったら、ちょうだい”って取りに行ったんですけど、それがギターだったんですよ。しょうがないからギターと小さいアンプをもらってきて、練習するようになって。だから、ギターを始めたのは、たまたまですね」
――バンドも組んだんですか?
「しばらくひとりで弾いて楽しんでたんですけど、どうしてもバンドがやりたくなって、メンバーを集めました。親友が吹奏楽部でパーカッションをやってたから、その子にドラムをやってもらって。でも、すごい田舎の中学だから、文化祭でバンドをやるなんてことは1度もなかったんですよ。で、職員室に行って“バンドをやらせてください”って頼み込んで。幸運なことに担任の先生がビートルズ・オタクで、校長に頼んでくれたんです。そしたら校長もロック好きな人で、すぐに“やろうやろう”ってことになって」
――何だか映画みたいな話ですね〜。そのときはどんな曲を演奏したんですか?
「練習したのはディープ・パープルの〈スモーク・オン・ザ・ウォーター〉とビートルズの〈ツイスト・アンド・シャウト〉とBUMP OF CHICKENの〈ダイヤモンド〉です。〈ツイスト・アンド・シャウト〉は時間切れで出来なくなったんですけどね。〈スモーク・オン・ザ・ウォーター〉は登場ソングみたいな感じですね。イントロのリフが始まったら体育館のステージの幕が開いて、後ろからライトが当たってっていう演出(笑)。だから結局、ちゃんと演奏したのは〈ダイヤモンド〉だけなんですけどね」

――BUMP OF CHICKENはどのあたりに惹かれてたんですか?
「曲もすごくロックだなと思ったし、ラジオでメンバーが好きなバンドを話してたのも良かったんですよ。ザ・フー、ビートルズ、ローリング・ストーンズ、モンキーズとか。“今度ストーンズのライブに行くんだ”とか“ビートルズの曲はぜんぶ弾ける”みたいな話をしているのを聞いて、“この人たちはそういう音楽を聴いて、自分たちの音楽を作ってきたんだな”ということがわかってきて。当時はライブの登場SEもザ・フー(〈A Quick One While He's Away〉)だったし。ウエストコースト・ロックにたどり着いたのもバンプがきっかけだったし、そういう意味では本当に影響を受けてますね」
――そこから本格的にオールド・ロックを聴き始めたと。
「最初は親にも言わず、TSUTAYAで借りてたんですけどね。それを部屋で聴いてたら、父親がいきなり“何聴いてるの?!”って入ってきて。そのときにモンキーズの〈デイドリーム・ビリーバー〉のシングル盤を聴かせてくれたんですよね」
――ストーンズやビートルズもすぐに好きになったんですか?
「最初は違和感がありましたね。現代のサウンドはもっと音圧があるじゃないですか。ビートルズやストーンズはもっと隙間があるというか、本当に弾いてる感、生々しさがあり過ぎて。でも、ずっと聴いているうちに“すごいイイ曲”って思い始めました。どんどんわかってきたというか。いちばん大きかったのは、ホワイト・ストライプスですね。最初に聴いたのは『エレファント』(03年)だったんですけど、ブルース、ロックの土台を大事にしながら、すごく新しさがあるなって思って。レッド・ツェッペリンとか、そのあたりの時代の音楽をいまのサウンドにしたらこうなるんだなっていう」
――ルーツをしっかり持ちつつ、サウンドの手触りは新しい。それはもうGLIM SPANKYのテーマと同じですね。
「中学生ときは“王道のロックは好きだけど、もっと迫力があったらいいのに”っていう感じだったんですけどね。ストライプスを知ったときは“私が求めていたものはコレだ!”って思ったし、それからはストライプスばっかり聴いてました。ギターもシンプルだったから、耳コピして部屋で弾いてましたね。アンプ全開で」
――現代のロックで他に好きなアーティストは?
「レニー・クラヴィッツにもホワイト・ストライプと同じような衝撃がありましたね。古いロックの要素を現代的に表現しているというか。ジェイク・バグもカッコいいと思いました、歌のなかに芯の強さがあって。やっぱり、ただ古っぽいロックをやってるのは好きじゃないんですよ。ジャンルや時代に関係なく、魂に響くものが好きなので」
取材・文 / 森 朋之(2015年2月)

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。JASRAC許諾番号:9009376005Y31015
Copyright © CDJournal All Rights Reserved.