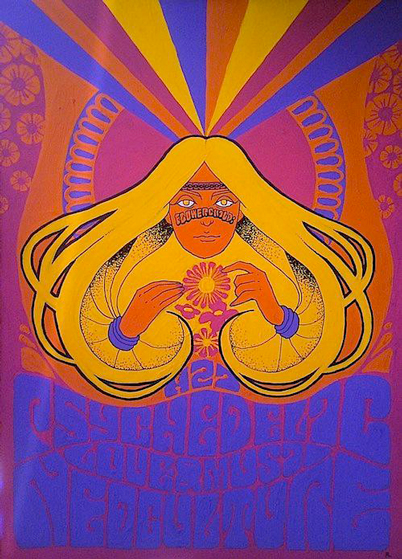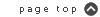掲載日:2015年04月22日
02 バンド結成 - ハイティーン(高校生活)
――高校に入ってからのバンド活動はどうだったんですか?
「高校に入ってすぐにバンドを組んだんです。最初は文化祭のためだったんですけど……軽音楽部が禁止されてたんですよね、うちの学校。昔、暴走族が学校を荒らしたことがあったみたいなんですけど、それがなぜか“軽音楽部のせい”みたいになっていて。有志で文化祭に出るのは許可されてたから、メンバーを探したんですけど、やっぱりなかなか見つからなかったんですよね。でも、なんとか見つけて……ギターをやってる先輩とドラムをやってる友達なんですけど……文化祭で1曲だけやったんです。BUMP OF CHICKENの〈アルエ〉なんですけど、ほとんど私の弾き語りみたいな感じでした(笑)。他のメンバーはほぼ初心者だったんで」
――ちなみにそのときのバンド名って……?
「GLIM SPANKYです。私、バンドは GLIM SPANKYしかやったことないんで。バンド名はすごく真剣に考えました。“濁点が付いていたほうが印象に残るだろうか”とか“自分の好きな世界観を表現できる言葉にしたい”とか。自分がやりたい音楽性につなげたかったんですよね」
――なるほど。現在のメンバーである亀本寛貴さんと出会ったのも高校のときですよね?
「そうです。文化祭が終わったあと、頼んでやってもらっていたメンバーが抜けるんですよ。ドラムの男の子だけは続けるって言ってくれたんですけど、あとのふたりは“部活とかもあるし……”って。でも、私はバンドを続けたかったんですね。そのときはもう、次のライヴを決めちゃってたし」
――いつの間にかすっかりやる気になっていた、と。
「そうだったんですよ ね、きっと。しかもライヴまであと1週間のときに辞められちゃったから、あと1週間で5曲くらい覚えられる人を探さなくちゃいけなくて。先輩にも協力してもらっていて、まず“ベースやってるヤツがいるよ”って連絡があって。その人からメールが送られてきたんですけど、“とりまよろしく”って書いてあったんです。“とりあえず、まあ、よろしく”ってことらしくて(笑)。で、楽譜を渡しに行ったら、めっちゃギャル男で」
――ハハハハハ(笑)。
「最初は大丈夫かなって思ったんですけど、とてもいい人だったんですよ。超やる気もあって、まずは3人でライヴを1回やって。そしたら ベースが“ギターでいいヤツいるんだけど、入れない?(ギターが)レミちゃんひとりだと大変だからさ”って言い出したんですよ。私はそのとき“絶対入れない!”って断ったんです」
――どうして?
「とりあえず自分でギターソロが弾きたくて。でも、“やっぱり大変そうだから、入れといた”って勝手に入ることになってたんですよ。しょうがないから楽譜を渡しにいったら、それが亀本で。顔だけは知ってたんですよね、じつは。亀本はサッカー部でけっこう目 立ったので。私の友達のなかにも、亀本の追っかけみたいなことをやってた子がいたし」
――モテてたんだ。
「そうそう。私はイヤだったんですけどね、チャラくて。髪の毛が長くて、腰パンで。部活の勧誘の時期に“サッカー部、入らない?”って教室に来たりすると、女の子たちが“亀本先輩来たよ!メアド交換してもらおうよ”なんて騒いで。“いや、私はいい!”って」
――その亀本先輩とバンドをやることになって。
「“うわ、この人か”って思いました(笑)。でも、ベース と同じで、すごいマジメだったんですよ。学校ではカッコつけてる印象だったのに、バンドはちゃんとやってくれて。最初のスタジオのときも、全部練習してきたんですよ。そこからですね、初期GLIM SPANKYが始まったのは。高校1年の11月です」
――オリジナル曲を作り始めたのもその頃?
「はい。まず私がアコギで弾き語りして、それをメンバーに聴いてもらってバンドサウンドを作って。やり方はいまとほとんど同じです。ただ、最初は見よう見まねというか、どうやっていいかわからなかったんですけど、とにかく自分たちの曲を創作するのが楽しくて」
――その頃、ギタリストとしての亀本さんに対してはどんなふうに感じたんですか?
「最初の曲を作ったときから思ってたんですけど、私が“こういう世界観がいいな”と思い浮かべながら作った曲に対して、私のイメージにプラスアルファで返してくるんですよね。亀本がフレーズを付けてくれると、いつも“そうそう、こういうのが欲しかったんだよ!”って。いちばん最初からかなり手ごたえがあったし、何よりも“この人、私が作ろうとしてる曲を理解してくれようとしてるんだ”っていうのが嬉しくて。曲を作り始めたばかりのときって、不安でしょうがなかったんですよ。そういうときにちゃんと曲を聴いてくれるメンバーがいるっていうのは、すごい感動でした」
――音楽的なルーツも近かった?
「いや、音楽の話はまったく合わなくて。亀本はGLAYとラルク(L'Arc-en-Ciel)が好きだったんですよ。ベース もGLAYが好きだったから、そこで話が合って仲良くなったみたいで。ドラムはX Japanが好きだったから、こっちも話が合わないし(笑)。まあ、そこはヴォーカル・ギターなので、私が引っ張らせてもらいましたけどね。ただ、亀本はすぐにビートルズなんかを聴くようになりましたけどね。GLAYのメンバーがビートルズ好きっていうことを知って、そこから遡って。私がバンプ(BUMP OF CHICKEN)のルーツを辿ったのと同じですよね」
――そうなると曲のイメージもさらに深く共有できるようになりますよね。
「休 日はひとりでずっと曲を作って、学校のある日も夜中までみんなでアレンジしたり。とても充実してましたね、ホントに。 ベースの先輩もドラマーの子も、いまでもすごく仲がいいんですよ。誰よりも学校生活を楽しんだ自信がありますね。輝かしい高校時代でした」
――そう言い切れるのは素晴らしいですね。音楽以外の部分でも楽しかったんですか?
「人に恵まれてたんですよね。友達もそうだし、先生もみんないい人で。夢の話をしても、絶対に笑ったりしないんですよ。たとえば文化祭のポスターなんかもめちゃくちゃ一生懸命やってたから、“この子は本気なんだな”って気づいてくれたんだと思うんですけど」
――基本的にすごくポジティブですよね。いつも自分のやりたいことに忠実だし、まっすぐに立ち向かうじゃないですか。
「そうですね。私、生徒会の副会長だったんですけど、“学校を変えてやろう”って思ってましたから。ロックが流れる学校にしたかったんですよ」
――すごい!
「文化祭で“ネオフラワーチルドレン”っていう名前で街中を花で埋め尽くすっていうイベントをやったり。もちろん、その時代のロックをガンガンかけて。すごく負けず嫌いだから“見てろ。絶対におもしろいことをやってやる”っていう気持ちもあったし」
――でも以前のインタビューでは、“夢を語るだけでバカにされるような環境だった”って言ってましたよね?
「それは学校以外の場所ですね。地域の人だったり、先生以外の大人にはかなりいろいろ言われたので……。いちばん最初に言われたのは 、生徒会と地域の 人との交流会だったんですよ。そのなかで“どんな大人になりたいか、どんな職業に就きたいか。高校生のみなさんの夢をひとりずつ聞かせてください”というコーナーがあって。まず生徒会長が“町の企業に就職して、幸せな家庭を持ちたいです”と言ったら、拍手喝采だったんですね。“素晴らしい。うちの町に貢献してくれるんですね”って。次は私の番だったんですけど、まさかミュージシャンになりたいとは言えなかったから、“美術大学に進みたい”って言ったんです。そしたらもう、“美術大学”って言った時点で大人たちがクスクス笑いはじめて。何言ってんの?美術大学なんて行けるわけないでしょって」
――なるほど……。
「私の地元では、美術大学に行くことさえ夢物語なんですよ。“どうやってごはんを食べていくつもり?”みたいな。そのあと“美術大学に通いながら音楽を続けようと思ってるんですけど、おかしいですか?”って言ったら、今度はドッと笑いが起きたんです、会議室全体で。すごい屈辱というか、怒りを通り越して、悲しくて。“ちょっと待ってください。私はただ、自分の好きなことをやれる大人になりたいんです”って言ったんですけど、“これ以上、この人たちには何も言えないな”と思って」
――その悔しさはいまも残っている?
「そうですね。“いつか見てろよ”って思ったし……。すぐに“こいつらさえも、私の曲で感動させてやる”っていう気持ちになりましたけどね。それで書いたのが『焦燥』だったんですよ。あの曲で〈閃光ライオット〉のファイナリストになれたし、自分たちの曲が世間に流れ始めた第一歩になったっていう」
――ホントに負けず嫌いというか、逆境をバネにするタイプなのかも。
「そうですね(笑)。それでも“どうせすぐダメになる”とか言われましたからね。親の前で“親不孝者”って言われたこともあるし。うちの親は“こいつ、話にならんわ。気にしなくていい”という感じでいてくれたし、友達と学校の先生もずっと応援してくれてたから、大丈夫でしたけどね。私のことを支えてくれる人がいるとわかって、もっとがんばろうって思えたし。〈閃光ライオット〉のときも、学校全体で応援してくれたんですよ。部活でもないのに壮行会を開いてくれて。ファイナリストのライヴのときも、生徒会の担当の先生はみんな見に来てくれたんです」
――〈閃光ライオット〉でファイナリストに選出されてからは、音楽の道に進む決心が固まったんですか?
「いや、迷ってましたね。高校のときは、絵かファッションのどちらかをやりたいと思ってたんですよ。祖母が文化服装のいちばん最初の生徒で、よく洋服を作ってくれてたんですね。母親もそういうことが好きだったし、私も“自分で何かを作りたい”っていうのがあって。バンドに関しては、なかなか現実的なものとして見れなかったんです。ただ、〈閃光ライオット〉のライヴで都会のバンドを目にしてからは、少しずつ考え方が変わってきましたけどね。ちゃんと音楽をやっている同年代の人がいるって確認できて、“やってみたい”という気持ちが湧いてきたんじゃないかな。自信があったわけではないけど、自分たちはいい曲をやっているし、届くはずだという思いもあったし」
――最終的には芸大に進んだんですよね。
「はい。どこでもバンドは続けられると思ったし、ジャケットやグッズのデザインも自分でやりたいと思うようになって、だったらデザインの勉強をしたほうがいいなって。いま振り返ってみると、すべてはバンドのためだったんですよね。で、“東京五美大”(多摩美術大学, 武蔵野美術大学, 東京造形大学, 女子美術大学, 日本大学藝術学部)のどこかに行きたいと思って、いちばん学費が安かった日藝にしようと。しかも日藝には映像や写真をやる人も来るから、バンドをやる環境としては最適じゃないか!と思ったんですよ」
――バンドの写真やミュージック・ビデオも撮ってもらいやすい、と。
「そうです。高校の先生もすごく協力してくれて、ひとりだけ違うカリキュラムを組んでもらえたんです。美術の先生が“俺が一から全部教えてやる。校長に頼んで、(美大受験用の)カリキュラムを組む”って言ってくれて。あるとき美術室に行ったら、画材や筆がドサッと置いてあったんですよ。そしたら美術の先生が'それをプレゼントするから、いっしょにがんばろう'って」
――すごい。そんな素晴らしい先生がいるんですね。
「そうなんです!進路担当の先生も映画や演劇に詳しい人で、いろいろ教えてくれたんですよね。'普通の面接のやり方を知ってはいけない。とにかく他の人と違うことを考えろ'って。合格したときはめちゃくちゃうれしかったですね。受験自体もすごく楽しかったんですよ。また受験した いくらいです(笑)」
取材・文 / 森 朋之(2015年2月)

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。JASRAC許諾番号:9009376005Y31015
Copyright © CDJournal All Rights Reserved.