自身の名曲群を“再定義”した佐野元春の最新アルバム『HAYABUSA JET I(ファースト)』がリリースされた。ノスタルジーに浸ることなく、現在ライヴにレコーディングに活動をともにしている盟友、THE COYOTE BANDと、最新のサウンドで楽曲の新たな魅力を引き出すことに成功している。新世代に向けた“再定義アルバム”である本作、その制作の裏側と、盟友THE COYOTE BANDについて話を聞いた。
――2020年1月24日に放映された、フジテレビ系『ダウンタウンなう』に佐野さんが出演された際、「隼ジェットに改名したい」と発言されて大きな話題となりました。この「隼ジェット」が今回アルバム・タイトルとして使われた理由について教えていただけますか。
「当時、佐野元春という名前に飽きてしまって、隼ジェットでいこうと決心したんだけど、周囲に話したら猛反対された。それで僕も思いとどまったんだ。しかし、それ以降も隼ジェットは僕の心の中に生きていた。僕本人が隼ジェットを名乗るのがダメならば、アバターだったらいいだろうと。アバターの僕を隼ジェットにというアイディアで、今回アルバム・タイトルにした」
――「隼ジェット」は我々ファンの中でも生きていたので、とても驚きました。これまでThe Hobo King Band(以下、HKB)との『月と専制君主』や『自由の岸辺』といったカヴァー・アルバムがリリースされています。『HAYABUSA JET I』では“再定義”という言葉を使っていますが、カヴァーと再定義の違いについて教えてください。
「HKBとの作業は“再解釈”。そして、現在一緒にやっているTHE COYOTE BANDとの作業は“再定義”。これは僕の中では、明確に違う作業なんだ」
――2025年は佐野さんのデビュー45周年となるアニバーサリー・イヤーです。また、THE COYOTE BANDも結成20周年を迎えました。そのアニバーサリー・イヤーにHAYABUSA JET I』がリリースしたのは何か理由があったのでしょうか。
「アニバーサリー・イヤーには、これまで応援してきてくれたファンの人たちに感謝を伝えたい、そう思っている。『HAYABUSA JET I』は、ファンのみなさんへの僕からのプレゼントです」
――2022年には『今、何処』という傑作をリリースされました。『今、何処』の次の作品を作るにあたって、プレッシャーのようなものはありませんでしたか?
「プレッシャーはなかった。確かに『ENTERTAINMENT!』と『今、何処』。どちらもTHE COYOTE BANDの英知と経験を集めた、とてもいいアルバムだと自負している。THE COYOTE BANDも結成20年目を迎えてクリエイティブ的に高いレベルにある。今、この時期に彼らと一緒にレコーディングをしたいし、できるだけ多くライヴをしたいという気持ちなんだ。なので、悩んだり迷ったりすることはほとんどなく自然に楽しんで作った」
――これまで応援してきてくれた古いファンだけではなく、新しい時代のリスナーも楽しめるサウンドになっていますね。
「新旧のファンに楽しんでもらいたいというのが『HAYABUSA JET I』のテーマのひとつです」
――しかも、かつての楽曲なんですけど、THE COYOTE BANDの新曲としても楽しめるサウンドになっていますよね。
「はい。サウンドは毎回気を遣っているけど、今回レコーディング・エンジニアは渡辺省二郎。マスタリングはマット・コルトンというUKの若いエンジニアに頼んだ。特徴は低音の解像度が非常に高いこと。とても現代的なサウンドだ。いいヘッドフォン、スピーカーで聴いてもらうとサウンドの良さがわかってもらえると思う」
――THE COYOTE BANDとは結成から20年にわたってライヴとレコーディングを続けてこられましたが、バンドを率いている佐野さんご自身は、THE COYOTE BANDの成長をどのように感じていますか。
「THE COYOTE BANDはこの20年で偉大なロックバンドになったと思う。以前は先輩バンドのザ・ハートランドやHKBに対して少し忖度している部分があった。でも今は違う」
――THE COYOTE BANDの曲だけで会場が盛り上がるところまで来ました。
「うれしいよね。ほとんどのキャリアアーティストは、よく知られた曲を演奏することで、ファンの期待に応えようとするんだけれども、その点、僕は若干無頓着かもしれない。ただ、アニバーサリー・ツアーでは新しいファンはもちろん、今まで応援してきてくれたファンにも喜んでもらえるようなセットリストにしたいと思っている」
――佐野さんのザ・ハートランド時代にはTOKYO BE-BOPというホーンセクションがいて、HKB時代には山本拓夫さんというサックス・プレイヤーがいました。佐野さんのクラシック曲においてホーンセクションが非常に重要な位置を占めていたと思います。今回、『HAYABUSA JET I』で再定義を行なうにあたって、ブラスセクションが印象的だった曲をホーンのいないTHE COYOTE BANDで最適化できるようにしようといった意図はありましたか?
「自分の中でブラスセクションを加えたバンドサウンドは、80年代のザ・ハートランド、90年代のHKBの時代で終わっている。現在はTHE COYOTE BANDと一緒にモダンなギターロックサウンドを追求している。だからブラスセクションが印象的だった曲はみんなTHE COYOTE BANDに最適化するように定義し直しました」
――振り返ってみると、THE COYOTE BANDのライヴでの初お披露目は、HKBと行なった2006年の〈星の下 路の上ツアー〉の最終日、東京国際フォーラム公演でしたね。
「そうでした。HKBの舞台の最後、アンコールでTHE COYOTE BANDを初披露した。その時のメンバーは高桑圭のベース、深沢元昭のギター、小松シゲルのドラム、そして僕の4人。急な登場だったからファンを驚かせてしまったと思う」
――あれから20年経ち、佐野さんの音楽を見事に体現できるバンドに成長しました。
「そうだね、正直に言ってうれしい。途中からキーボードの渡辺シュンスケともう一人のギタリストである藤田顕の加入によってサウンドの可能性が広がった。ザ・ハートランドともHKBとも違う、真にオリジナルなバンドになってくれたと思っている」
――そしてスタジオ・アルバムとして、佐野さんのクラシック・ナンバーを再定義した『HAYABUSA JET I』を作るところまで来た。
「THE COYOTE BANDは新しい段階に入った。振りかえってみれば、バンドのアイデンティティがはっきりしたのがアルバム『Blood Moon』。その後マスターピースとなった『今、何処』を経て、今回の『HAYABUSA JET I』にたどり着いたと思う」
――THE COYOTE BANDとは、最初は小さなライヴハウスで全国を回っていましたね。
「はい、一時期、全国のライヴハウスで武者修行的にライヴをやっていた。ロック・バンドはオーディエンスとのやりとりを通じてパフォーマンスを学ぶ。ザ・ハートランドもHKBもそうだった。この経験がレコーディングにつながる。それを何度も経験してきた」
――その後、THE COYOTE BANDはホール規模の会場を満員にし、大規模な野外コンサートでも若い世代の音楽ファンたちに熱狂的に受け入れられるバンドへと成長していきました。
「大きな会場で若いオーディエンスの前で演奏する、その景色は感動的だ。バンドもそう思っていると思う」
――『HAYABUSA JET I』は、ザ・ハートランド時代の楽曲を中心に収録されている中で、「だいじょうぶ、と彼女は言った」だけHKB時代のアルバム『Stones & Eggs』から収録されています。選曲はどのように決めていったのでしょうか。
「僕は自分が作った曲をどの時代の曲と区切ってはいない。なので、今回『HAYABUSA JET I』を作るときにもどの時代からこの曲をピックアップという発想はなかった。そもそも、これまでのライヴ・ツアーで、今回収録したクラシック曲をTHE COYOTE BANDと演奏していたので、まずはゴキゲンな演奏になった曲をレコーディングしてレコード化しようというところから始まったんだ」
――「ガラスのジェネレーション」という、ファンにとって非常に大切な曲を、今回「つまらない大人にはなりたくない」として再定義しました。この曲には今回、どのような想いを込めたのでしょうか。
「新しいジェネレーションに、この曲を聴いてもらいたいという気持ちがあった。もちろん、昔から応援してきてくれるファンのみなさんも大切だし、彼らに楽しんでもらえなければ意味がない」
――『HAYABUSA JET I』に収録されている楽曲は、かつてのザ・ハートランドまたはHKBと演奏していたエッセンスやアレンジが、THE COYOTE BANDも加えた3つのバンドの要素として最新の形で表現されているように聴こえました。
「そうだね。かつてのザ・ハートランド、HKBのサウンドが現在のTHE COYOTE BANDに活きている。そこには正しい伝統がある。僕はそう持っている」
――DNAが連綿と続いているようなイメージですね。
「そうだね。コヨーテバンドのミュージシャンはみんな、ザ・ハートランド、そしてHKBのメンバーに対して、きちんとしたリスペクトを持っている。だからこそ、彼らの演奏を伝統として捉えた上で新しい革新的なサウンドを自分たちが作っていくんだという、とても高い信念を持って関わってくれているんだ。こんなミュージシャンを、ほかに僕は見つけることができないよ」
――2024年に行なわれたHKBとのプレミアム・ライヴ〈Smoke & Blue〉をTHE COYOTE BANDのメンバーが観客席で見ていたのですが、誰よりも楽しんでいるように見えました。
「HKBとの演奏を現在のTHE COYOTE BANDのメンバーが見て楽しんでくれる。これほど、光栄でうれしいことはないね」
――『HAYABUSA JET I』には10曲が収録されています。実際のレコーディングでは何曲くらいトライされたのでしょうか。
「15曲くらいやった。今回入れなかった曲は、次の『セカンド』にまとめたいと思っている」
――『HAYABUSA JET I』には新しい世代へという主要なコンセプトがあるかと思います。一方で、これまで長く佐野さんの楽曲を聴いてきたファンのみなさんには、「今後、再定義された楽曲のオリジナル・アレンジはライヴで聴けないのかもしれない」といった寂しさを感じる方々もいるかもしれません。
「そうかもしれない。そうだとしたらどうしようか。僕はエンタテイナーでもあるし、表現者でもある。どちらかを選べと言われたら困ってしまう。ひとつ確かなのはあまりノスタルジーは浸りたくない」
――今回、10曲収録された中でまとめるのが難しかった曲などはありましたか。
「特になかった。バンドやレコーディング・エンジニアと相談しながら楽しくやったよ」
――佐野さんのライヴといえば、かつては原曲がわからないところまで破壊して再構築してみせる楽曲がたくさんありました。ライヴでの再アレンジと再解釈または再定義とでは、佐野さんのなかで違いはありましたか。
「違いはあまりない。以前はジャムバンドみたいに大胆にアレンジを変えていた。でも最近はレコードサウンドに忠実に演奏している。ジャムバンド・オリエンテッドな演奏をして原曲を変えていくと、面白くないと感じるファンも、面白いと言ってくれるファンもいる。でも今はコヨーテ以降の新しいファンも多い。今はTHE COYOTE BANDと構築した演奏をみんなに楽しんでもらうことが大切だと思っている」
――7月からはデビュー45周年のアニバーサリー・ツアーが始まります。『HAYABUSA JET I』からの曲もふんだんに演奏される予定ですか?
「そうだね。今回は長いツアーになる。いろいろな街で演奏してその街の音楽ファンと音楽を通じて楽しい時間を過ごす。みんなに今の僕を見てほしい。体力が続く限りローカルな街に行ってたくさん演奏してみたいと思っている」
――半年間にわたる大規模なツアーになりますね。
「ツアーというものはそういうものだ。新旧のファンが集まってくれると思うし、僕も楽しみにしている」
――ちなみに、なかなかライヴのチケットが取れない、プレミアムチケットになっています。
「チケットが取れないのは……申し訳ないけども、僕はうれしい(笑)。なので、今回のツアーでは全国のホールを中心に大きな会場を用意します」
――新作が出たばかりですが、次作の予定はありますか。
「今はまだ考えていない。今は眼の前の45周年に集中したいし、『HAYABUSA JET I』をできるだけ多くの音楽リスナーに楽しんでもらいたい。そのために何ができるか考えている」
――45周年を迎えた2025年は、全国ツアーだけではなく3月12日には『元春TVショー Vol.3』も配信され、『HAYABUSA JET I』の楽曲も5枚組のアナログレコードでリリースされるなど、序盤から盛りだくさんの発表がされていますね。
「みんなで楽しんでほしい。『HAYABUSA JET I』のアナログ7インチ5枚組ボックスは僕も楽しみだ。僕が最後に出したアナログ7インチレコードは〈約束の橋〉だったと思う。ずいぶん間があいたけれど、最近ではアナログレコードがまた復活してきているみたいだ。5月にリリースするよ」
――『HAYABUSA JET I』に収録された「Youngbloods」も、シングル時に入っていた冒頭のメッセージがカットされていました。そのあたりはどのように判断されているのでしょうか。
「スタートボタンを押して毎回あの挨拶が出てくるのも鬱陶しいと思ってはずしました」
――佐野さんは現在に連なる日本の音楽の黎明期から活動され、日本語と英語が混在する歌詞を自然なメロディとアレンジに乗せて提示する手法を切り拓いてきた第一人者だと思っています。今回の再定義も、HKBとの再構築も、かつて英語表現だった歌詞をあえて日本語に変更して作品化されています。このあたりの意図はどのあたりにあるのでしょうか。
「そこにあまりクリエイティブな思いはない。その時代のファンが喜んでくれることをしたいだけ。80年代はリリックに英語を混ぜると聴き手が楽しんでくれた。しかし、時代が過ぎると、リリックに日本語の美しさを感じたいというファンが増えてきた。そこで『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』というアルバムを作った。リリックは自由だ。今は僕なりのやり方でビートを感じる日本語表現を試みている」
――そういった変遷の中で、かつての曲を再定義する際に「ポップチルドレン」であれば「最新マシンを手にした子供達」に変えてみる、そういった変化が起こっているということですね。
「そうだね。グルーヴの中に日本語をどうフックさせていくかというのは、デビュー以来の僕のテーマ。いろいろなやり方で試している。実験的ではあるけれどもうまくいっているものもあると思う。真に革新的なことは、気が付かないうちにやってきて、スッとなじんでいく。だからみんなそれが革新的だと気づかない」
――日本語へのアプローチを行なう際、言葉に対してメロディを当てる、それともメロディが含んでいる言葉を引き出すイメージ、どちらですか。
「その両方だ。僕がやっているのは音楽の言語化、そして言語の音楽化。これをずっと続けてきた。僕が理想とする形は、言葉とビートとメロディ、この3つの要素が分断されていない状態、それぞれに壁を作っていない状態。言葉とビートとメロディがひとつの表現として塊になっている状態。これがベストだね」
――最後に、今後のビジョンについてイメージされていることがあれば教えてください。
「僕は根っからのミュージシャン。理知よりも僕の中から湧き起こる感情を形にしていく創造、そこに言葉やメロディを与えていくのが僕の役割なので、しっかりやっていくためには、あまり理知的になりすぎないように気をつけている。だから、自分がOKだと思うことに沿ってこれからもやっていきたいと思っているよ」
取材・文/富岡蒼介

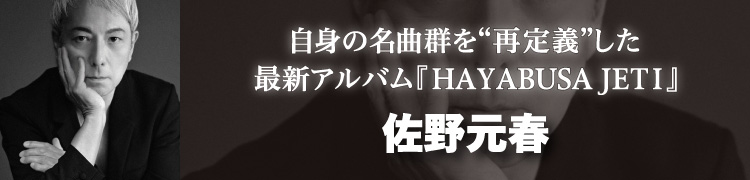


 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。