数々のコンクール受賞歴を誇る若手の実力派ピアニスト、
ベンヤミン・ヌスがドイツ・グラモフォンからCDデビューを果たした。ここで注目されるのが、収録された楽曲が『ファイナルファンタジー』などのゲーム作品を彩った音楽ということである。
みずからも根っからのゲーマーであり、
植松伸夫の作品を愛してやまないと明るい笑顔で話すヌス。彼の演奏はピアノからさまざまな音色を引き出し、ゲームの情景や、登場するキャラクターの雰囲気や感情といったものを鮮やかに表現している。ゲームをプレイした人はもちろん、ゲームや曲を知らなくても、音楽とともに彼の演奏に引き込まれていくことだろう。この前例のない試みに至ったいきさつや思いを語ってもらった。

(C) Dieter Eikelpoth
――ゲーム音楽をピアノで演奏、しかもドイツ・グラモフォンからリリースされることになったわけですが、こういったことは非常に稀だと思います。どのようなきっかけで、今回のプロジェクトが生まれたのでしょうか?
ベンヤミン・ヌス(以下、同)「まず、このアルバムのコンセプトは、若い人たちがどうすればクラシックのコンサートに足を運んでくれるようになるのだろう、という問題をもとに考えたものです。自分自身がかなりのゲーマーということもあり(笑)、それを使って若い人たちに興味を持ってもらえたらと思い、いくつかのレコード会社にプレゼンをしたところ、ドイツのユニバーサルが“それはいいアイディアだ”と興味を持ってくれたのです」
――ヌスさんはずっとクラシックのピアニストとして勉強、活動されていますよね。周りの方、とくに先生の反応などはどのようなものでしたか?
「たしかに先生は驚いていましたが、彼は非常に音楽に対してオープンな視野の持ち主で、ジャズやポップス、
マイケル・ジャクソンも好んで聴いているので、今回の話を非常に喜んでくれました。今回収録した曲も実際に聴いていただいたところ、とても気に入ってくださり、クラシックの曲とともにレッスンもしてくださいました」
――このような曲に対して、先生はどのようなレッスンをしてくださったのですか?
「自分ではゲームの物語や登場人物の心情などをわかって弾いているつもりだったのですが、先生からは悲しみや喜びといった感情の差をもっと出すようにと言われました。この“差”というものを明確に示すことで、聴く人たちに伝わっていくのではないだろうか、というようなアドバイスをいただきました」
――今まで学んできたクラシックの経験が今回のアルバムでも活きているのですね。
「もちろんです。すごく助けられました。というのも、収録された曲がほとんどクラシックのスタイルによるアレンジがされているので、今までのピアノで学んだことすべてを活かすことができました」

(C) Dieter Eikelpoth
――アルバムにはヌスさんの書いた作品も収められていますね。とても美しくドラマティックな作品だと思いました。植松さんからの影響はあるのでしょうか?
「実際に作曲するときは、植松さんのメソードを見習おうと思いました。彼は最小限の音しか使わず、表現にまったく無駄がありません。植松さんが私のために書いてくださった〈イヤーズ&イヤーズ〉も収録されていますが、この曲は、植松さんが私の曲を聴いたインスピレーションから書いてくださったものなんですよ」
――レコーディングにあたって、植松さんとのディスカッションをしたり、アドバイスをいただいたり、ということはありましたか?
「今回の選曲は自分で行なったのですが、その際、植松さんからもたくさん曲を紹介していただきました。『ファイナルファンタジー』に関しては有名ですし、よく知っていたのですが、『ブルードラゴン』や『ロストオデッセイ』に関しては知らなかったのです。でも植松さんから教えていただいたことで、これらが非常に素晴らしい音楽だということを知り、選ぶきっかけになりました」
――「ファイナルファンタジーVIIのテーマによる幻想曲」は規模も大きく、また非常にヴィルトゥオジティが求められる作品になっていますね。まるで
リストがオペラの主題を利用してパラフレーズ作品を作り、演奏していたスタイルを彷彿とさせます。
「そうですね。実際にリストの〈ドン・ジョヴァンニの回想〉などもよく演奏するので、そうした部分も少し意識していました」
――今後の活動を教えてください。これからもゲームの音楽を演奏したりレコーディングしていくのでしょうか?
「今後は
メンデルスゾーンのピアノ協奏曲のオーケストラとの共演や、ガーシュウィンのピアノ協奏曲をレコーディングする予定もあります。中国で協奏曲をたくさん弾くコンクールにも出場しますし、クラシックの活動がメインになっていきますね。もちろん、今後もゲームの音楽を扱ったCDも出したいですし、私の演奏を通じて、若い方々にたくさんクラシックのコンサートに出かけてもらえるようになれば嬉しいですね」
取材・文/長井進之介(2010年10月)
![植松伸夫作品集 ファイナルファンタジー - ロストオデッセイ - ブルードラゴン - ベンヤミン・ヌス [CD] 植松伸夫作品集 ファイナルファンタジー - ロストオデッセイ - ブルードラゴン - ベンヤミン・ヌス [CD]](/image/jacket/large/411009/4110090296.jpg)


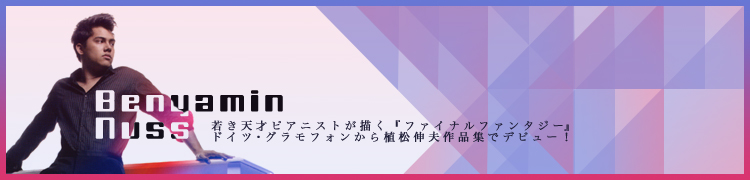



 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。