『そこのみにて光輝く』が国内外の映画賞を受賞して注目を集めた呉美保監督。9年ぶりの新作『ぼくが生きてる、ふたつの世界』は実話を基にした物語だ。ろう者の両親のもとで育てられた聴者=コーダの一人息子、大。子供の頃は社会と両親を繋ぐ“通訳”として頑張っていたが、成長するにつれて周りから特別視されることに苛立ち、両親に反抗するようになる。そして、20歳で田舎から東京に出て自分の人生と向き合うことに。作家/エッセイストの五十嵐大の自伝を映画化した本作は、ろう者の役をろう者の役者が演じて、ある家族の肖像をリアルに、そして、普遍的な家族の物語として描き出す。呉監督に映画について話を伺った。
――映画を拝見して、これは特別な家族の物語ではなく、観客一人ひとりが自分の家族について想いを馳せる身近な物語だと思いました。監督は原作のどういうところに惹かれて映画化されたのでしょうか。
「今、おっしゃっていただいたように、原作を読んだ時に“これは普遍的な家族の物語だ”と思ったんです。どんな家族も多かれ少なかれ問題を抱えているじゃないですか。それに向き合っている家族もいれば、なかなかできない家族もいる。そういう家族の機微みたいなものを五十嵐大さんの原作を読んだ時に感じて、ぜひとも映画でも表現したいと思いました」
――原作を映画化する際に意識したことはありますか?
「原作は現在の“僕”が過去を振り返る回想形式でしたが、映画でそれをやると叙情的すぎると思いました。過去をノスタルジックに語るという形式の映画も多いですしね。それで0歳から28歳まで、主人公の成長する姿を点描していくことにしたんです。人生のちょっとしたエピソードを積み重ねていくことで、その間にあったことを想像し、感じてもらえたらと思いました」

呉美保監督

呉美保監督
――主人公の五十嵐大を、吉沢亮さんと2人の子役で年齢に応じて演じています。一方、大の母親の明子を演じた忍足亜希子さん、父親の陽介役の今井彰人さんは通して演じられています。30年近い時の流れがある物語を描くにあたって、キャスティングや演出で心がけたことはありますか?
「少年時代の大はヴィジュアルを優先にして、吉沢さんに似ている子を探しました。なんとか見つけることができたんですけど、4歳と9歳を演じた2人ともお芝居するのはほぼ初めてだったので時間をかけて細かく撮っていきました。明子役を演じていただいた忍足さんに関しては、どうやって若く見せるのか、どうやって老けさせるのかはいろんな工夫をしました。たとえば大が8年ぶりに母親と病院で再会するシーンでは、メイクなしのすっぴんでやってもらったんです。今井さんは、じつは吉沢さんと3歳しか違わないんですよ(笑)。でも、表現力豊かな方で、映画を繋げた時に全然違和感がなくて驚きました」
――忍足さん、今井さんをはじめ、ろう者のキャラクターを実際にろう者の役者が演じています。それは監督にとって大切なことだったのでしょうか。
「そうですね。最初からろう者の役はろう者にやってもらいたいと思っていました。映画『コーダ あいのうた』でもそうでした。それで撮影に入る前にろう者の方やコーダの方に取材をしたんです。すごく納得したことがあって。これまで映画やドラマで聴者がろう者を演じることが多かったですが、そういう作品をろう者が観た時、海外の俳優がカタコトの日本語を喋って日本人の役をやっているのと同じくらい違和感を感じるそうなんです。その話を聞いた時は、確かにそうだな、と思いました。なんで、こんな当たり前のことに気づけなかったんだろうって」
――製作者側や観客の多くがろう者の視点に気づいていなかったんですね。この映画を拝見して、手話にも方言があることを初めて知りました。話し言葉と同じで手話も多彩で変化しているんですね。
「手話って言語なんです。日本語とは文法が違い、表現も細分化されている。地域による方言をはじめ、家族のなかで使うホームサインというものもあるし、世代によっても表現が違う。聴者に早口の人がいたり、ゆっくりな人がいるように、手話にもスピードの違いがあるんです。そういったことをいろいろと学ばせていただいて、絶対ろう者の役はろう者の方がやるべきだと思いました」
――子供の頃から手話をやっている大を演じた吉沢さんは、手話をマスターするのが大変だったのでは?
「吉沢さんには、これまでのドラマや映画で聴者の俳優さんがやっていた手話表現を更新してほしい、とお願いしました。今回の役では日常的に使う手話をやってもらったのですが、実家の宮城で使っている手話と東京で使っている手話も違います。さらに言えば、大は中学生の時に親に反抗して手話をやめているので、完全には手話をマスターしていないという設定なんです。そういう細かな手話表現を吉沢さんに託したのですが、ろう・手話演出をお願いした早瀬憲太郎さんと石村真由美さんは吉沢さんの手話を絶賛してくれました。吉沢さんが努力してくれたおかげです」
――今回、撮影に入る前に脚本を手話に翻訳する作業に手間暇をかけたそうですね。
「まず、ろう・手話演出の2人と一緒に台本を読みながらキャラクターについて掘り下げ、理解を深めてもらいました。それから、手話翻訳を暫定的に作ってもらって、それをもとに、方言の監修をしてもらい、決定したろう者俳優さんとすり合わせをしていく。そういった作業を何ヵ月も続けました。さらに現場に入ってから、ちょっとしっくりこないな、と思ってセリフを変える時は、その都度、ろう・手話演出の2人と話し合う。だから、撮影時間は通常の2倍はかかったと思います。でも、自分にとっては多様な表現を学べた貴重な時間でした」
――そうやって時間をかけて手話のセリフを仕上げることで、ろう者に対する理解が深まっていったわけですね。本作は家族の物語であると同時に、青春映画の要素もあります。大は自分が何をしたいかわからないまま東京に出て、仕事を転々としながら自分の居場所を探す。作者の五十嵐さんが体験したことではあるのですが、そこに今を生きる若者のリアリティを感じました。
「映画って主人公は成長していくものだと思われているじゃないですか。でも、五十嵐さんがライターになったのは最初からそもそも目指していたわけじゃないから、華々しく描く必要はないと思ったんです。それに今の日本の若者の多くは、自分が何をしたいのかわからないのではないでしょうか。とくに地方の若者は20代でいったん東京に出てきてみたものの、アルバイト生活を送りながら自分探しをしている人も多い。そういう若者が、ちょっとした偶然で人と繋がったり、離れてみて故郷の家族を恋しくなったり。決して劇的ではないけれど、等身大な成長を丁寧に描きたかったんです」
――そんな大に対して両親は頭ごなしに意見せず、息子を信じて東京に送り出します。その姿を見て、どんなことがあっても子供を見守る、という両親の覚悟が伝わってきました。なかでも、母と息子の関係の機微が丁寧に描かれていて、自分と母親の関係を思い出したりもしました。
「観てくれた人によると、昭和生まれで田舎から上京してきた方の琴線に触れるみたいですね。それは昭和のお母さんが育児中心で、子供の頃の記憶が母親に関することが多いからかもしれません。自分自身もそうですし。原作者の五十嵐さんに話を伺うと、お母さんのご両親(五十嵐さんの祖父母)は手話を学んではくれなかったそうです。いまでは考えられないのですが、当時は口話しか認められていなかった時代なんです。五十嵐さんのお母さんは“人から何を言われてもニコニコしてればいい”と言われていたそうです。そんな環境で育ったことで、計らずも芯が強い女性になった。映画の中で明子がいつも明るく笑っているのは彼女本来の性格でもありつつ、時代や環境がそうさせたところもあると思いますね」
――描写は少ないですが、父親と大の関係も心に沁みるものがありました。たとえば、パチンコ屋でばったり出会った父親と、線路脇の道を歩きながら両親の若い頃の話をするシーン。母親と話す時とは違った気恥ずかしさや緊張感を感じさせながら、そこに親子の情を感じさせて印象的でした。
「男同士だから、ちょっと探り探りなんですよね(笑)。あのシーンは親子がちゃんと会話しているように見せたかったんです。ただ、吉沢さんがクランクインしてから初めて手話を使うシーンだったこともあり、ろう・手話演出チームに、吉沢さんの手話がろう者の両親に育てられたネイティヴな手話になっているか厳しくチェックしてほしいとあらためて強くお願いしたんです。リハーサルは念入りにしましたが、長いシーンだし、電車のタイミングもあるし、1回では無理だろうと思っていました。でも、一発OKだったんです」
――大が手話を通じて懸命に自分の気持ちを親に伝える。その様子を観ていると、大が全身で感情を伝えていることが伝わってきて、人とコミュニケーションをとることの大切さを改めて考えさせられました。
「この撮影で知ったことですが、ろう者は手話で会話をする時はかならず相手の目を見るんです。というのも、手話に加えて、顔でも語るんですよ。まゆの上げ下げとか目の開き方とか、表情がすごく豊かで。だから、どんなに喧嘩をしていても相手を見つめ続けるんです。大は反抗期も、喧嘩をしている時も、母親がどんな手話を返してくるのか知るために母親の顔を見なくてはいけないんです」
――どんなに腹が立っていても目をそらさない。
「そうなんです。どんなに怒っていても、相手の目を見て相手が考えていることを理解しようとする。それってじつはとても尊いことだと思いました。手話にそういう側面があることを知れたのは、映画のため以上に、人として重要な学びでした」
――今回、ひとつの家族の物語を描いて、自分の家族についてあらためて考えことはありましたか?
「私は在日韓国人なんですけど、小学生の頃に友達の家に遊びに行ったりすると、家においてある物とかが自分の家と様子が少し違う、と思っていたんです。そして、自分が少数派だと気づき始めると、これは恥ずかしいことなのかな? と思うようになる。周りの家庭と少し環境が違うことを知って戸惑っていたのは、ろう者の家に生まれた五十嵐さんと同じなんです」
――五十嵐さんや監督のように、周囲とは少し変わった家庭で育った人は多いでしょうね。
「原作を読んでいちばん共感できたのは、社会に出て多種多様な人に出会うことで、子供の頃に悩んでいたことはたいしたことなかったんだと思えるようになったこと。たとえば在日の子に出会った時に、正月は雑煮じゃなくてトックで、おせちじゃなくチヂミだとか、そういう在日あるある話を笑ってできたり、自分の生い立ちを達観できるようになりました」

呉美保監督
取材・文/村尾泰郎
撮影/品田裕美
ぼくが生きてる、ふたつの世界('24日本)配給:ギャガ
2024年9月20日(金)より東京 新宿ピカデリー他全国ロードショー
©五十嵐大/幻冬舎©2024「ぼくが生きてる、ふたつの世界」製作委員会

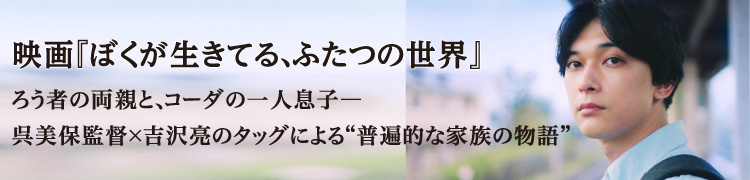












 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。