ジャンルを超えて音楽家が集まり、新たな実験が繰り広げられているフランスの電子音楽シーン最前線をご紹介するシリーズ第3回目は、今年秋に開催された〈オディーブル・フェスティヴァル〉、GRMの〈ミュルティフォニー〉、〈フェスティヴァル・ドートンヌ〉などのレポートをお届けします。
9月21日から23日にかけて、パリ近郊の実験音楽ライヴ・ハウス“アンスタン・シャヴィレ”と、映像&電子音楽のパフォーマンス団体およびレーベル“メタムキン”を率いるジェローム・ノタンジェとの共同企画により、昨年に続いて第2回目となる〈オディーブル(l'audible=聴取可能な/聴き取れるもの)・フェスティヴァル〉が開催された(バニョレのエシャンジュール劇場にて)。今年はスピーカーを周囲に配したスペースの中央に客席を置き、演奏者は客席のさらに中央ないしは脇に位置し、照明は消され、暗闇の中で音だけに集中できる形が取られた。
エリアーヌ・ラディーグらベテラン女性作曲家の作品を集めたコンサートから、実験映像+音楽作品の上映、日本にインスピレーションを得てNHKのスタジオで1977〜78年に作曲された、ジャン=クロード・エロワの4時間にわたる大作「楽の道」の深夜コンサート(夜中の1〜5時)まで、多岐にわたる充実したラインナップ。とくに人気を集めたのは、やはり週末の夜のライヴだ。
初日の口火を切ったのは、2009年までPhroqの名で活動してきたフランシスコ・メイリノ。攻撃的で無機質なハーシュ・ノイズが力強い。続くトマ・ティイーは編集加工なしのフィールド・レコーディングによる具体音楽を詩的に聴かせた。

ロビン・フォックス
ロビン・フォックスはレーザーやオシロスコープなどと組み合わせたパフォーマンスで知られるが、今回は音響のみ。音高のあるキーボード的な電子音の上下行スケールに、ヘリコプターや船のエンジンのような騒音、クリック・ノイズなどが加わり重なって、音が増殖し徐々に発展していく。一つ一つの音が豊かに響くとともに、有機的な展開と構造が際立っていた。
土曜日はセドリック・ペロネの、何かが転がるような物音や水音がさわやかなアンビエント系の音楽から始まった。ヴァレリオ・トリコリとヴェルナー・ダフェルデッカーのデュオは、今年生誕100周年&没後20周年を迎えた
ジョン・ケージの、唯一と言われるミュジック・コンクレート「ウィリアムズ・ミックス」(1952年)の楽譜をもとに、新たにコンピュータで作った「ウィリアムズ・ミックス拡張版」を演奏した。

eRikm
最後は今回の招待アーティストの中でも目玉のデュオ、R/S(ペーター・レーバーグ&マーカス・シュミックラー)。観客の入りも多く、途中入場もあるので照明を完全には落とさずに行なわれた。縦横無尽に勢いよく駆け回るサウンドがぐるぐるとうごめき、ひしめく。リズムの規則感と不規則感のバランスがほどよい。床に響く重低音とともに歪んだノイズがわめくかと思えば、ゲーム・サウンド的な電子音が空間に巻き散され、ぶつかり合う。多様な音を使い変化をつけながらも、流れと盛り上がりを作るのがうまい。期待にかなうパフォーマンスでこの夜集まったパリのノイズ・ミュージック・ファンを大熱狂させた。
続いて9月27日と28日には、パリ4区にあるサン・メリー教会で、電子音響を交えた即興音楽フェスティヴァル〈CRAK(クラック)〉が行なわれ、フランスを代表するターンテーブラー、eRikm(エリックエム)が抜群の手・指さばきを見せた。スピーカーの音質は今ひとつだったが、彼の音選び・運びはいつも通り面白味と音楽性にあふれるものだった。ヴィルトゥオーゾとも言える圧巻の速い動きで、刻々と音の表情を変える。マイナー・コードの響き、グリッチ・ノイズ、ささやき声によるパーカッシヴな音などが混じり、時折ループが規則的な拍動感を作る。演奏後は口笛やブラボーの喝采とともに大きな拍手が贈られた。

ジョー・トーマス(C)GRM Akousma / Ren Pichet
10月5日から7日は、GRM(Ina-GRM=フランス国立視聴覚研究所・音楽研究グループ)の今シーズンの幕開けで、週末のコンサート・シリーズ〈ミュルティフォニー〉がサンジェルマン・デ・プレのオーディトリアムで開かれた。
5日はエリック・ミュラール、ジョー・トーマス、ジュリアン・デペス、ベンジャミン・スィグペンという顔ぶれ。とくにトーマスは今年のアルス・エレクトロニカのゴールデン・ニカを受賞したということで注目を集めた。受賞作の「クリスタル:シンクロトロンの響き」は、イギリスの放射光研究施設“ダイヤモンド・ライト・ソース”の委嘱による。荷電粒子の加速による周波数やシンクロトロン(円形加速器)の内部の音をもとに作曲された。ジェット機のエンジンのような音、グリッチ・ノイズ、吹きすさぶ風のような電子音が繰り返され、地響きを伴うような轟音へと高まっては静まる。規則的な拍動感があり聴きやすい。本人も「サウンド・インスタレーションとして部分的に聴くことも可能」「無限の時間感覚を表現した」と言うだけあり、発展性がなくとりとめないように感じられるが、音そのものはきれいで心地のよい広がりのある楽曲と言えよう。
トリのスィグペンの「スティル」ではゆったりとしたテンポの中、金属的な軋み、後ろからいくつもビー玉がはね転がってくる音、がりがりとした深く力強い低音など、各細部の響きが存在感を持って浮かび上がり、空間をたっぷりと満たした。

フランソワ・ベイル
(C)Ina / Didier Allard
6日はピエール・シェフェールに続きGRMの所長を長く務め、現在のGRMの演奏形式“アクースモニウム(多数のスピーカーによる立体的な演奏)”のコンセプトも作った電子音楽界の大御所、フランソワ・ベイルの80歳を祝う記念コンサートが行なわれた。プログラムは、パリでは初演奏の「何1つ現実ではない」I&II、新作「移動」初演、「極めて穏やかな地震」。全般にドラマティック、かつ忙しない音の隆起が特徴的。音の動きを描いた最新作も上下行する音階、グリッサンドなどがめまぐるしく音楽的な動きを作ると同時に、空間的にも飛びまわる。大きな流れというより、瞬間の活発なエネルギーが変わらずの魅力だ。
ちなみに、彼の50年の軌跡をたどった15枚組のCDボックスがGRMから10月にリリースされた。
また、今年の〈フェスティヴァル・ドートンヌ(パリの秋の現代芸術祭)〉では、11月5日に電子音響を中心に作曲する
ピエール=イヴ・マセを特集したコンサートが、ブッフ・デュ・ノール劇場で行なわれた。32歳とはいえ、すでに2002年のTzadikからのファースト・アルバムに始まり、Sub rosa、Brocoliなどの実験・電子音楽レーベルから5枚のCDをリリースしている領域横断的なアーティスト。音声資料、録音された音のサンプリング主体でミニマル的だが、規則的なループではなく多様な編集加工・変調の仕方が興味深い。
今回はマセの3つの作品(初演2つ)が演奏された。とりわけ、
ブリトニー・スピアーズやリートなどを素人が歌うYouTubeのビデオ音源に逆回転などさまざまな加工を加えた“歌”を、みずから生でピアノ伴奏する「ソング・リサイクル」、それを微細に楽譜に起こしたもの(調子のはずれた音は微分音、むやみに吸う息、加工による意味のない音素など)を声(N.レイボールド)と器楽アンサンブル(アンスタン・ドネ)用に編曲した「ソング・リサイタル」は、それこそジャンル不明な面白い試みとして聴くことができた。今後もチェックしたい作曲家である。
なお、オディーブルでは最終日の午後、パンタン音楽院で電子音楽を学ぶ学生11名に自作演奏の機会が与えられたほか、ミュルティフォニーでも日曜日は、必ずしも若手に限らずオーディションに応募して選考された10名の作品演奏が行なわれ、変わらず気を吐くベイルやエロワなどと相前後して場を共有した。こういった、年齢や活動歴を超えてアーティストたちが交差できる開かれた場所であってこそ、パリの音楽シーンが生き生きとしたものになっていると言えるでのはないだろうか。
取材・文/柿市 如

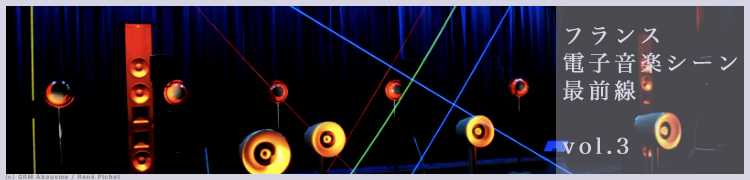





 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。