AATAに
インタビューするのは2019年11月以来 。その間に『LIGHTS』(2021年9月)と『be in bloom』(2024年4月)の2枚のアルバムをリリースし、スタジオ、ライヴとも着実にクオリティを上げてきた。
新作『be in bloom』はAATAのライヴ・サポートも務めているドラマー/作曲家/編曲家の荒山諒との共同プロデュース。荒山は前作から連投のHiroyuki Kondo(2曲)、MO MOMAのShogo Takahashi(3曲、うち1曲は荒山と共同)と並んで8曲をアレンジし、飛躍的に幅を広げたAATAサウンドを彩っている。
今回はAATAと『be in bloom』のキーパーソンである荒山のふたりに、アルバムを深く縦横に語り尽くしてもらった。
――4月18日のワンマン・ライヴ(@荻窪TOP BEAT CLUB)、僕もお邪魔しましたが、ご本人的にはどうでした?
AATA 「いままでのワンマンでいちばんよかったなと思います。ずっとアップアップして楽しめなかったところがあったんですけど、諒くんが本当に細かいところまで、演奏の部分をがっちり支えてくれたので、自分は歌に集中できたのが大きかった。曲間のつなぎとかで迷ったときにアイディアをくれたりとか、逆にぜんぜん気づいていなかったところを“ここ、どうする?”って指摘してくれたりとか」
――ドラマー兼音楽ディレクターというか、バンマス的な立場ですね。
荒山 「あまり自覚はないんですけど、一応やってることはバンマスですね」
――アルバム『be in bloom』をAATAさんと共同プロデュースしていますね。ドラマーであり、ピアノや編曲もできるという感じ?
荒山 「歴で言うとピアノのほうが先なんです。クラシック・ピアノを習い始めたのが小学校1年生ぐらいで、ドラムは小5のときビッグバンドの部活に入ってから。ピアノは真剣にやらなかったのでうまくならなくて(笑)、ドラムのほうが楽しくなって、メインの楽器になりました」
――ジャズ・ドラムがハマったんですね。
荒山 「結局、たぶんああだこうだ言われてやるのが好きじゃなかったんです(笑)。ピアノも小4〜5になってくると、先生に “ポップス弾きたい” って言って譜面を用意してもらって、ぜんぜんクラシック弾いてなかったので。結局行くべくして行った感じだと思います」
――どういうきっかけで一緒にやることになったんですか?
AATA 「ワンマンで鍵盤を弾いてくれていた清野雄翔さんがくっつけてくれたんです。サポート・メンバーを探していたときに相談して、どういう理由かはわからないんですけど、“イケてるからたぶん合うと思う”みたいな感じで(笑)。でもすごいよかったです。同い年っていうのもあるし、相性もたぶんよさげだなって。わたしもひとの好き嫌いというか、合う合わないがはっきりしてるし、少し前にバンド・メンバーを一気に変えたりして“大丈夫かな”という不安な時期だったので」
AATA
――先日のライヴでは、AATAさんがギターを弾く曲はあったけど、ピアノ・トリオに随時ゲストが入るみたいな編成が新鮮でした。ギターもそうだし、トランペットが入ったりとか。
AATA 「ギター入らなくてもいいよねって感じでした」
荒山 「とくに『be in bloom』はそこまでギターが重要じゃない感じの曲が多いので、わざわざ生で弾いてもらう必要もないか、だったらトランペットを呼んだほうがいい感じになるんじゃないかって」
AATA 「諒くんと一緒にやるならジャズっぽいアレンジに振る曲があってもいいなと思って、“トランペットとかサックス入れてみない?”みたいなことは言っていたんですよ」
荒山 「サックスを入れると、ソロ回しで人数ぶん尺が伸びるんです。セッション感が増して楽しげにはなるけど、“AATAのライヴ”感は薄れちゃうのかなとも思って。 “楽器のうまいやつらで遊びはじめたな”みたいな時間が多くなるのもどうかと思って、“やっぱりトランペット1本だけでいいんじゃない?”って言いました」
AATA 「正解だったなと思います。リハのときも、トランペットがほとんど真後ろにいて、初めてだったのでびっくりして “歌いづら!” ってなっちゃったんです(笑)。そこはPAの間瀬(哲史)さんが音のバランスに気をつけてくれたり、トランペットの三上(貴大)さんがベルをちょっと外してくれたり、うまいことやってくれました。だから1本で十分っていうか、三上さんに注目が行くし、スペシャル・ゲスト感もあってよかったんじゃないかなと」
――荒山さんは自分の演奏よりもアンサンブル全体のバランスを気にかけるタイプなんですかね。プロデューサー的というか。
AATA 「それはめっちゃあると思います。ポップスとジャズのバランス感覚がよくて、にぎやかな曲だけじゃなく弾き語りの曲も好きだったりするんです。雑食な感じはわたしと似ているし、もっと音楽的なことがわかってるから、たとえばわたしが違和感を覚えたとき、用語を知らなくてうまく伝えられなくても “こういうことじゃない?”って翻訳してまわりに伝えてくれる。バランス感覚と客観性がすごくよかったなと思います。これからもっと売れっ子になりますよ」
荒山 「ドラマーというポジションも手伝って、やっぱり常に俯瞰してるからそうなっていったんだろうなと、必然的に」
AATA 「あー、理解。アンサンブルでいちばん音も大きいし、めちゃめちゃシビアだろうなって思う」
荒山諒
――アルバム・プロデュースの話はどちらから持ちかけたんですか?
AATA 「わたしからです。前からドラム叩いてくれたりしてたんですけど、“アレンジもしてみたい” とか聞いてたし、やった曲も聴かせてもらったりしてて、こういう感じで話せる人ならきっといいだろうなと思って。これまでアルバムの舵取りは自分がやってたんです。曲ごとに合いそうなトラック・メーカーに投げて、バランスは自分で取るみたいな。でもあまり音楽的なことが言えなかったりして、アルバムのコンセプトやカラーを出すのを自分ひとりでやることに限界を感じていて。諒くんだったら、わたしがざっくりした抽象的な部分の舵取りを担うとして、もっと具体的な、音楽的なバランスをうまく取ってくれそうだなって」
――AATAというアーティストのいいところ、独特なところってどこだと思いますか?
荒山 「やっぱり唯一無二の声、声色ですね。サポートをはじめたときは『Blue Moment』の曲をメインでやってたので、トラック系の曲をやりたい人なのかと思ってたんですけど、付き合いを重ねるなかで、ひらがなのあーた時代のサウンドを聴かせてもらったり、好きな音楽の話をしたりしているうちに、どうやらもっと幅が広そうだなって思ったのと、ラップも歌も関係なく歌手として音楽的に優れてる部分があるので、そういうところも含めて幅を見せれたらいいなと思うようになりました」
VIDEO
――『be in bloom』では荒山さんが12曲中7曲をアレンジしていますが、前作から連投の方もいますね。
AATA 「全体を見てくれたのは諒くんです。わたしが弾き語りしたデモを “この曲はこの人に投げてみようと思うんだけど、構成とかコードとか大丈夫かな?”って相談して、気になったところは直してもらって、譜面を上げてもらって、それをトラックメーカーに投げるみたいな」
――AATAさんは弾き語りもめちゃくちゃいいから、逆にいじりにくさを感じることもありそうな気がしますが、どうですか?
荒山 「そうですね。なるべく飾りをつけずにそのままがいいなっていう曲はシンプルにしています。“こういう曲にしたい”っていうアイディアはいろいろもらったので」
AATA 「そういうのはリファレンス音源と合わせながら」
荒山 「リファレンスをもらうと、こっちもアイディアが湧くから、バーッてアレンジして。そういう使い分けでした」
――AATAさんはリファレンスはわりと明確なほうですよね。
AATA 「けっこう細かくあります。でもぜんぜんないときもあるんですよ。もうなんでもいけるんじゃないか、ぐらいのやつもあれば、作るときから“誰々っぽく”みたいに目指してるアーティストがいる曲もある。そういうのはゴールがもともとあるから明確なんですけど、なんとなくで作りはじたやつは曖昧だったりしますね」
――収録曲からそれぞれの代表例を挙げてもらってもいいですか?
荒山 「〈IKEZU〉は明確でしたね」
AATA 「昔のアニソンです。『キテレツ大百科』のオープニングの〈お嫁さんになってあげないゾ〉っていう曲がイメージにあって。“ちょっといなたくてもいいから、振り切ってこれをやりたい。アルバムの中の1曲だったらいい感じになりそう”みたいに思ってて。あと、諒くんがジャズ出身だから、ジャズの曲を1曲やりたいと思って、3拍子のちょっとマイナー調の曲を作ってみたのが〈koi〉です。これは“諒くん全開で振り切って”みたいに言って」
荒山 「〈koi〉は完全に自分の独断で膨らませていきました」
AATA 「ブン投げです(笑)。あとイメージがなかったやつはどれだろうな……」
荒山 「〈シャンディ・ガフ〉は超ざっくりしてたよね。最初のデモは手癖というか、AATA楽曲でよくあるコード進行だったんですよ。そういう楽曲が多いと単調になっちゃうから、“コード変えていい?”っていうところから始まって、“あ、いいよ”みたいな」
AATA 「“ブッ壊していいよ”って言いました(笑)」
荒山 「曲調とか細かいところは指示がなかったから、自分なりにバラードっぽく作り込んで投げたら“なんか違うな”って言われて、“イメージあるんかい!”みたいな(笑)」
AATA 「本当ですよね。“あるなら初めから言えよ!”みたいな」
荒山 「“もうちょっとこういう感じがいいんだよね”って、そこで初めて参考音源が来て、“あ、こっちかい!” ってなって、完全に作り替えました」
AATA 「この曲は書いた時点ではどうにでもなりそうっていうか、ぜんぜん自分で見えてなかったんです。なのでレコーディングでも苦戦した記憶がありますね」
――「C.H.O.O.O.E」も荒山カラー全開かなと思ったんですが……。
AATA 「これは“せっかくだから共作みたいのもしたいな”と思ってやってみた曲ですね。わたし、ゴスペルがミックスされてるネオソウルとかR&Bが好きで、カーク・フランクリンとかサム・ヘンショウとか。諒くんのおうちにスタジオがあるので、そこで“こういうのをやりたい”って聴かせたら、その場でそれっぽいリフみたいなのをつけてくれて“ちょっとドラム打ってみる”みたいな感じで……」
荒山 「とりあえず8小節のループを作って」
AATA 「それを1回お持ち帰りして、わたしがメロとラップを乗せて投げ返す、みたいなやりとりでできました」
――これは弾き語りから始まった曲ではないんですね。唯一?
AATA 「あとは諒くんが関わってないやつですけど、〈Life is gone〉もそうかな。(Hiroyuki)Kondoさんがトラックを作ってくれて、そこにわたしがメロを乗せて……っていう感じで作っていきました」
――今回、AATAさんに宣伝を手伝ってくれって言われて音源を送ったのがCDジャーナル編集部の川上さんともうひとりいるんですけど、ふたりとも “1曲目からかっこよくてびっくり” と言っていました。
AATA 「うれしい!どこがよかったですか?」
川上 「自分の世代感にちょうど合ったというか、いきなりしっくりきて」
荒山 「サウンド感ですか?」
川上 「サウンド感と、あとスチャダラパーとかのオールドスクールっぽいラップと。1曲めでこれ来るんだと思って」
AATA 「ちょっと意識したんですよ。その感じ。わたしスチャダラパーも好きだし、ちょうど最近また盛り上がってきてるところもあるから、ちょっと自分でもブームがあったんですよね。みんなでライヴで一緒に言える感じのをやりたくて。めっちゃうれしい!そうなんですよ」
――chelmicoが好きだって言っていましたよね。
AATA 「好きです。力が抜けててかっこつけてなくて、あと平和なやつが好きです(笑)。喧嘩しないで “なんか今日もダラダラ過ごしちゃったな〜” みたいな感じがいいんですよ」
――荒山さんもヒップホップは好きですか?
荒山 「聴きますけど、詳しいわけではないですね。なんとな〜くノリを知ってるぐらいで」
AATA 「でもうちらRIP SLYMEの年代じゃない?」
荒山 「そうだ。そういうのはめちゃくちゃ聴いてました」
AATA 「オレンジレンジやRIP SLYMEが学生時代に流行ってて。めちゃくちゃ好きでした」
――RIP SLYMEってちょっとSMAPみたいでしたもんね。歌い上げる感じじゃなく、シンプルなメロディを集団で歌う。
AATA 「みんなでやってるのもよかったですよね」
――「C.H.O.O.O.E」の“超イイ!”とみんなでシャウトしているとこはそういうイメージなんですね。
AATA 「もう自分が歌わなくてもいいじゃんっていう。すごい楽しかったです」
――この曲が1曲目なのはインパクトがありました。「MOMANTAI」や「Life is gone」など先行リリース曲がいくつかあったから、そこから予測していた人にとってはびっくり感があってよかったのでは?
AATA 「超裏切りたかったんで(笑)。サブスクだとアルバムをリリースしてもお気に入りの曲だけ聴いたりとか、1曲目だけ聴いたりとかになりがちじゃないですか。だから“この後どうなるんだろう?”“え、これシングルで出てなかったけど、めっちゃかっこいいじゃん”っていう曲から始めたかったんです」
――アルバムということをすごく考えたんですね。
AATA 「そうです。わたしはサブスクの時代だからこそアルバムの意味がより出てきたなって。しっかりとコンセプトのある内容にして、盤を手に取ってもらうっていうのが、逆にまた来るんじゃないかっていうか。だからアルバムとしてかっこいいものを作りたかったんです」
――そういうヴィジョンを共同プロデューサーふたりで共有していた?
AATA 「……あまり話したことなかったよね(笑)」
荒山 「ここまで明確なのは初めて聞きましたけど “打ち込み系の曲と生演奏だけの曲が分かれすぎると、アルバムとしては美しくないよね” とかは言い合ってました。こっちが作る曲には逆に打ち込みを入れたりとか。曲順はほぼほぼ決めてもらった感じですけど」
AATA 「“こことここは悩んでるんだけど”とか言いながら最後のミックスを決めて、ちょこっと並び替えて」
荒山 「うまくまとまったよね」
AATA 「『Blue Moment』でトラックに振り切ったのは“これがAATAだ”っていうのがわかりやすくてすごくよかったと思いつつも、それまで弾き語りで育ててきた自分の長所を捨ててしまってるような気がしてたんですよ。もっとこういうこともやってみたいし、こういうこともできるのにっていう思いはありながらも“でも、こっちがみんなが言うかっこいいってことなんでしょ?”みたいな気持ちで。そうしてみたからこそ自分の強みみたいなものも発見できたんですけど、今回は活動を始めてから10年の集大成を作ろうっていうところからスタートしたので、バランスを取りたかったんです。トラックだけじゃなくて、ひらがな時代の“あーた”のよさもちゃんと入った、わたしだけのバランスって言うんですかね。こういう声質で、こういう音楽をやってて、がっちり弾き語りができて、たとえば〈無題〉みたいな曲ができる人って、わたしはあんまりいないと思ってて、そこも自分の強みだし、自分らしさになるなと思って。そうなったときに、バンド・サウンドとトラックをきっちり分けるのはわたしっぽくない、両方とも好きだから。そういう感じで、バランスについては話し合いました」
――このアルバムでついにAATAサウンドが完成したみたいなイメージですかね。
AATA 「いま、そういう気持ちです。だからこそこの前のワンマンもめちゃくちゃ楽しかったんだと思うんです。無理がないっていうか。“これが自分らしかったんだ”っていう感じがして、すごくのびのびできました」
――いま「無題」の話が出ましたが、これは歌詞含めてアルバムのなかで一、二を争うぐらい重要な曲なのではないかと思います。これはいわばアルバム・ヴァージョンですよね。途中まで弾き語りで、終盤でストリングスが入ってくるドラマチックなアレンジになっています。
荒山 「シングル・ヴァージョンがオール弾き語りだったんですけど、そのときからなんとなく、“アルバムに入れるときは豪華なアレンジにしたい”みたいな、ゆくゆくの想定があったんです」
AATA 「諒くんに曲を投げたときに、“この生々しい息遣いのデモのまんまでいいけどね”とか言われてたんですよ」
荒山 「シングルのときね。暗い部屋でひとりで歌ってるみたいな空気感で、“それだけでいいんじゃない?逆にそれが聴きたい、飾るより”って」
AATA 「よさを消さないギリギリのところを攻めてくれたのかなって」
荒山 「メリハリついたものが好きなんです(笑)」
――僕はこの曲を聴いて、前のインタビューのときにお聞きした“ぱんだふるらいふ”結成のお話を思い出しました。大学時代に部室で自作曲を歌っていたら、外で聴いていたお友達に“いい曲だね。誰の曲?”って聞かれて“わたしの”と答えたら“一緒にやらない?”と言われたと。
AATA 「そうそう。そのユニットでライヴハウスに出させてもらうことになって。そこからのいまにつながっていくという」
――“「もうダメだ」って俯く度に/「歌って」と言ったあの子がよぎって/ずっと離れないの”というところで、そのエピソードを思い出したわけです。
AATA 「なるほど〜。でも本当に彼女はそういう感じの子でした」
――こういうことって、歌をうたって……いや、歌に限らないな。ひとりで何かやっている人にはかならずある経験だと思うんですよね。こういうエピソードがほかにもあったんですか?
AATA 「ずっとこれの繰り返しです(笑)。たとえば何かリリースするたびに、頑張ったわりに数字も反応もあんまりないなとか(笑)。ずっと支えてくれる人たちがいるのに、精神的に追い詰められると見えなくなってひとりぼっちみたいな気分になっちゃうんです。そういう感覚はずっと付きまとっています。でも、いつも解決してくれるのは弾き語りのライヴだったりするんですよ。たとえば新曲を初めて歌ったときにお客さんがホロッとしてたりとか、初めて歌った場所で、初めて見てくれた人がワーッて来てくれたりとか。そういうことがあると “もうちょっと歌っていてもいいかもな” って引き戻してもらう、その繰り返しです。そうこうしてるうちに仲間が増えて、いろんな人たちに引っ張り上げてもらって10年間やってきたので、みんなに返せる歌を作りたかったんです。と同時に、頑張りを積み重ねてきた自分に贈る歌でもあります」
――うんうん、なるほどね。
AATA 「その結果、(対バンで)共演の子たちがボロボロ泣くっていう(笑)。でもすごいうれしいです。みんなこういう気持ちで戦ってるんだな、って思って」
荒山 「僕も歌詞と最初のデモがLINEで送られてきて、移動中だったんですけど、電車の中で泣きそうになりながら聴きました。芸術家にしろミュージシャンにしろ、何かを作る人ってみんな孤独じゃないですか。自分の音楽性ややりたいことを100理解してくれる人っていないかもしれない。そういうなかでみんな協力し合って生きてて、孤独だったり孤独じゃなかったりしながら、ずっと戦ってるから、響きましたね。だからこそ“何も味つけしなくていいんじゃない?”って言ったんです」
――なるほど。この曲で終わってもいいんだけど、最後にかわいらしい「Dreamy Blue」が入っているのがいいですね。
AATA 「わたしの甥っ子の声が入ってます(ニッコリ)」
――大好きな甥っ子ちゃんですね。
AATA 「家で録りました。わたしこれまで生きてきて、何があっても、始まった瞬間に終わりを予感するっていうのがずっとあるんです。恋愛にしても、付き合いはじめたときに “この人とはいつかお別れするんだよな” と思ってしまったり、ライヴを企画してるときも終わりのことを考えちゃったり。でも、終わりがあるからこその尊さみたいなものもある。そういうことを最後に表現したかったんです」
――甥っ子ちゃんの声が入っていることで、平和かつポジティヴに終わるのもいいと思います。
AATA 「あとトランペットが入ってて、1曲目と管楽器つながりになってるのもあります。そこから〈C.H.O.O.O.E.〉に戻っても聴き心地がいいかなって。〈Dreamy Blue〉で始まって〈C.H.O.O.O.E.〉で終わるパターンも考えたくらい」
VIDEO
――終盤に重めの曲が続くので、やっぱり「C.H.O.O.O.E.」で始まるのが正解だったというか、「MOMANTAI」「Lovely day for music」などのポップで軽快な曲が生きる気がしますね。「MOMANTAI」はどうして広東語を(笑)?
AATA 「最初、モニョモニョ歌いながら曲を作ってるときに、 “大抵のこったぁ モーマンタイ!” って出てきたんですよ(笑)。そこからパズルみたいにして作っていったので、タイトルは絶対〈MOMANTAI〉だなって思ってました」
――そういう作詞のしかたをするって前に言っていましたね。
AATA 「そうなんですよ。口が気持ちいいっていう」
――「IKEZU」もそうですか?突然の京都弁で(笑)。
AATA 「これは違う言葉の類語を調べて出てきたのかな。まずメロができてから歌詞を書いていった曲なので、“3文字でこういう意味の類語ないかな”って探していたときに“いけず”って思いついてハマったんだと思います。あと、口の感覚でできたのは〈Life is gone〉かな。サビはお風呂で鼻歌で作りました。もともとこのトラック用のメロじゃなかったんですよ、これ。弾き語りでもいけそうだなと思って別のコードをつけてたんですけど、それがすごくダサくて(笑)。めっちゃいいメロのはずなのに。ちょうどトラックをやりとりしてたKondoさんの候補のひとつに乗せてみたらビタッとハマって、“奇跡が起きた”って思って送ったら、Kondoさんも“これ僕も久々に歌うわ”って言って、共作になったんです。サビのフレーズと1番のラップはわたしで、サビ以外の2番のフレーズはKondoさんが続きを書いてくれた感じです。恋人同士の男女の対比になってて面白いなって」
――僕は「Lovely day for music」が好きです。レゲエっぽいビートに乗せて、新代田のlive + bar=crossingで働くAATAの日常を歌った感じで(6月からは店長に就任するとか。おめでとうございます!)。
AATA 「これ、もともとcrossingのコンピ用に書いた曲なんですよ。話が進まなかったので、かわいい曲なのにもったいないから自分でリリースしちゃおうと思って。crossingとも10年ぐらいの付き合いなので、自分のルーツみたいなものが入ったアルバムになってうれしいですね。たまたまだけど、呼ばれた感覚っていうか」
荒山 「デモの段階でギターが裏打ちでレゲエっぽいなって思って、よけいな味つけをしないで、トイ・ピアノの音色も裏打ちで、そのまんまみたいな感じで作りました」
AATA 「かわいいね。これは外国の童謡みたいな感じのイメージで作っていて、サビの部分とか。子どもたちが口ずさめるやつ。〈Lovely day for music〉っていうフレーズは、crossingがギネスの樽を置いてて、そこに〈Lovely day for a Guiness〉っていうコピーが書いてあるんですよ」
crossingの「Lovely day for a Guiness」
AATA 「ちょうどバーのカウンターからいちばん見えるとこにそれがあったんで、バイトしてるときに “〈Lovely day for Guiness〉っていい言葉だな。どういう意味だろう?” ってメモしてたんです」
――本当にAATAの日常ソングですね。
AATA 「ラップもゆるい感じで、自分的にはちょっとかせきさいだぁオマージュなんですよ。誰もわかってくれなかったけど(笑)。レコーディングのときに “ここはちょっとかせきさいだぁっぽくしたい” って言っても、きょとん……みたいな。 “いい!自分でそう思ってるからいい”って」
AATA 「ひとりで“違うなぁ”って言って何回かやり直してました」
AATA 「なんでやり直してるか、みんなわかんないっていう(笑)」
――かせきさいだぁ好きの川上さん、どう思いました?
川上 「聴いたとき“あ”って思いました」
AATA 「思いました?うれしい!やっぱ伝わるんだ……やり直してよかった!」
――本当にこの10年間のAATAの集大成のようなアルバムですね。充実感は?
AATA 「すごいあります。いっぱい聴いてほしいですね。わたし自分の音源をあんまり聴き直さないんですけど、このアルバムはすごい聴きます。普通にいいアルバムだなって自分で思えてすごいうれしい」
――それだけ自信作ということですね。
AATA 「本当に一所懸命作ったし、諒くんも寝ないで頑張ってくれたので(笑)。だからわたしは広める努力をしないと」
――最近、AATAさんの名前も売れてきたんじゃないですか?CM(スズキ ラパン)のナレーションとか。
VIDEO
AATA 「びっくりでしたよね」
――声がちょっと違うなって驚きませんでした?
荒山 「わかります。言われないとわからないくらい」
AATA 「そこはやっぱり、ナレーターですから……(笑)」
――ラジオなども含めて、声の仕事が入ってくるのは納得ですし、学びもありそうですね。
AATA 「コロナ禍のときに絵本作家さんと一緒に朗読をやったりしてたんです。役によって声色を変えたりとか、言葉が持ってるテンポ感を意識したりとかっていうのを学びました。メロがないけどメロがあるみたいな感じで面白かったし、ナレーションも似てますね。スズキのCMだと、秒数が決まってるじゃないですか。この長さでこの表現を入れないといけないけど、せかせかしてもダメだし……となると “ここの間をちょっと調整しよう” みたいなさじ加減をするのも面白くて。ちょっとラップに近い感じというか、歌ってるみたいな感じでした」
――去年はポセイドン・石川さんとの「納豆ファンク」もありました。
VIDEO
AATA 「ポセイドンさんは天才です。もともとジャズの人だから理論の詰め方がすごいし、大学で日本画を学んで、日展に入選したこともあるんですよ。日常会話がすごい不思議な感じなんです」
――あれはカヴァーになるんですかね。
AATA 「そうですね。ポセイドンさんとわたしをつないでくれたのが近視のサエ子っていうミュージシャンで、J-WAVEのパーソナリティとかやっているお姉さんなんです。仕事でいろいろお世話になってるんですけど、その人がAATAとポセイドン・石川さんの超ファンという」
――いいところまで来ていますね、AATAさん。
AATA 「なんか着実に、音楽家が好きなミュージシャンみたいになってる感じはある……のかな?ちょっとわかんないですけど。諒くんもミュージシャンのなかでアツいから」
――ふたりで一緒に大きくなっていきたいですね。
AATA 「そうなるといいな。頑張りたいです。せっかくいい1枚ができたので」
荒山 「そうですね。いっぱい聴いてもらいたいです
――自信作『be in bloom』を出して、この後のご予定は?
AATA 「このアルバムを持って7〜8月にあっちこっち行きたいなと思って、いま必死にツアーを組んでるところなんですけど、そのファイナルという形で、ディナー・ショーみたいな、みんなにごはんを食べながら見てもらうライヴを9月にしたいなと思っています。場所をそろそろ決めないと。フリーランスなんで、好きなことやっていけたらって思って」
――僕からはこんなところですが、川上さん何かありますか?
川上 「ベタな質問ですけど、アルバム・タイトルの意味ってなんですか?」
AATA 「『be in bloom』って咲いてるって意味なんですけど、これまでわたしはずっと自分のことを否定することによって成長してきたんですよ。“ここがダメだ、ここを変えないといけない”って、マイナスから入るみたいな。でも最近、“いまのままでいいじゃん”とか“いままでだってずっとすてきだったじゃん”って気持ちに変わってきて、“現時点ですでに咲いてるよね!超いいじゃん”みたいな気分でつけました。曲を作るとき、そのときベースにある感情というかテンションが絶対に影響すると思うんですけど、今回は過去と現在の自分を全肯定してあげるというか、“無理してかっこつけなくても、いまのままですてきじゃん”って、わたしにもみんなにも言ってあげたい気分だったんだと思います。〈C.H.O.O.O.E〉とか〈MOMANTAI〉とか〈無題〉とか、収録曲の歌詞にも通じていますね」
――ますます「C.H.O.O.O.E」が1曲目でよかったというか、その思いがストレートに出ている気がしますね。
AATA 「そうなんですよ。それを言いたかった。けっこうつらそうな人が多いなと思って。わたしだけじゃないなと思ったんですね。とくに20代の女性とか、“いまのままじゃダメだ”とか、“顔面が整ってないとダメなんだ”とか、すごい生きづらいなと思って。昔だったらそんなに気にしなかったことも、いちいち針を刺すみたいにちくちく言われたりするから、そうじゃなくて“いいじゃん!もっとまわりに君のすてきを知ってる人たちがこんなにいるよ”っていう歌を作ってあげたいなと思って。そういうアルバムです」
――最後にAATAさんと荒山さんから何か言っておきたいことがありましたら。
AATA 「言っておきたいこと……諒くん、野望とかないの?」
荒山 「え!?」
AATA 「せっかくの機会だから言っておこうよ」
荒山 「そうですね……ずっとドラマーとしてやってきて、作曲と編曲も好きで学生時代からやってはいたんですけど、去年1年間ぐらいでようやくお仕事としてやれるようになってきた感じがあって。今回みたいにドラムの演奏だけじゃなくて音楽トータルで必要とされる音楽家になりたいっていう野望はあるので、いまはこのアルバムをいろんな人に聴いてもらって、認知してもらいたいです」
AATA 「わたしにはちょっとした目標がありまして。こないだのワンマンで、いまのAATAのチーム全員が“これでいけそう”っていう形がいよいよできた気がするんです。この仲間たちで恵比寿LIQUIDROOMのワンマンを余裕でできるようになりたいです」
――「余裕で」がキモですね。
AATA 「いまのチームを核にして、全体を見渡して自分の考えをみんなと共有しながらできるギリギリのキャパがリキッドかなと思っていて。ずっとお世話になってきた仲間たちとそこでやって、ちゃんと満足のいくギャラを渡せるようになりたい。いまはみんなお仕事やバイトを一日休んでAATAのために使ってくれてるので、そうじゃなくて、AATAの仕事一本入れればちゃんとその日の稼ぎになる、っていうふうになるのがわたしの目標です」
取材・文/高岡洋詞

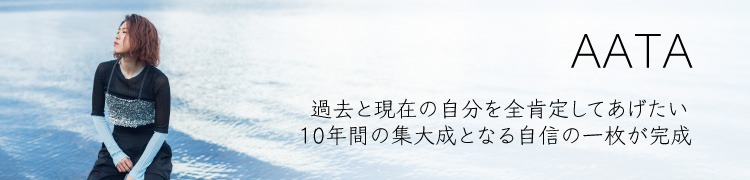




 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。