デンマーク出身で現在はベルリンを拠点に活動するシンガー・ソングライター、アグネス・オベル(Agnes Obel)。作詞作曲だけではなく、アレンジ、ミックス、プロデュースなど、曲作りのすべての過程をひとりで手掛け、ほとんどの楽器を演奏。そのマルチな才能やクラシックやエレクトロニックなどさまざまな音楽性を消化した独自のサウンドが、ヨーロッパを中心に高い評価を得てきた。そんななかで、クラシックの名門、ドイツ・グラモフォンと契約。新作『マイオピア』を作り上げた。2019年11月、リリースに先立って初来日したアグネスは、女性3人のストリングス奏者とライヴを披露したが、そのプロモーション滞在中に新作について話を訊いた。
――今回、初来日だそうですが、日本の音楽や映画で好きなものはありますか?
「日本の古い映画やホラーがすごく好きです。10代の頃、『リング』や『仄暗い水の底から』を観て、怖くて何日も眠れなくなっていました(笑)」
――日本のホラー映画がお好きだとは! でも、アグネスさんの曲には、どこか悪夢的な雰囲気を感じさせるものもありますね。
「(日本のホラー映画からの)影響は絶対あると思います。具体的にどんな風に影響を受けているのかを説明するのは難しいですが、映画というメディアはすごく好きなので。映画が音楽の扉を開けてくれることもよくあります。たとえばデヴィッド・リンチの映画を観て、これまでスウィートなイメージを抱いていたロイ・オービソンのダークな面を知ることができたり」
――なるほど、リンチの世界とアグネスさんの歌の世界も通じるものがあるような気がします。アグネスさんの音楽は映像的ですよね。毎回スタジオでひとりでレコーディングしているそうですが、ひとりのスタジオ・ワークにこだわる理由は?
「プロデュースはプロデューサーに、ミキシングはミキサーに任せていたら、自分の人生はもっとラクだったと思います(笑)。でも、ポップスの分野で、そういうことをしている人はすごく少ないと思うので、そこにこだわりたいと思っているんです。スタジオで作業していると思いがけなくアクシデントで生まれて、“このままいっちゃえ!”って進めていったら、それが美しい花に成長するようなことがあるんです。スタジオ・ワークには、そういうクリエイティヴさがあるのが良くて。自分のスタジオなので、追究したいと思ったらいくらでも続けることができるんですよね」
――5歳の時からピアノを学んでいて、10代の時に本格的にスタジオ技術を学んだそうですね。
「高校に通っていた時、突然“プロデューサーになろう!”と思って、学校を辞めてレコーディングの学校に入ったんです。両親は大反対でしたね。そこでは女の子は私ひとりだけで、テープの使い方やプロトゥールズを勉強しました。結局、後で高校に戻って卒業はしたんですけど」
――その時に学んだことが今のキャリアに活かされているわけですね。今回のアルバム『マイオピア』でも音作りがユニークで、独自の世界を生み出しています。たとえば「ブロークン・スリープ」では、声をさまざまな手法で加工してちりばめていますね。
「これは不眠症の曲なんです。子供の頃から、夜中に起きて眠れないことがあって。そのうち、だんだん慣れてきて、今では眠れなくなっても、古い友だちが遊びに来たみたいな感覚なんです。“あ、また来たの?”って(笑)。夜眠れなくなると、自分の頭のなかでいろんな声が聞こえてくるんですよね。その声を曲のなかで再現しようと思いました。だから、声のピッチを上げたり、下げたり、囁くような声にしたりして、いろんな声を表現してみました。この曲は、眠れない時の自分の頭の中を訪ねる曲なんです」
――声を楽器のように使っているんですね。
「声はいちばんパーソナルな楽器だと思います。じつは自分の歌声や喋り声が好きじゃなかったんです。とくに喋り声は、英語を使っていてもデンマーク語の訛りがあるし、ぜったい聞きたくないと思っていました。ただ、歌声に関しては、声を楽器として捉えるようになってからはだいぶ慣れてきました。でも、声がもっと低かったらいいなと思うこともあって。だから、ピッチを下げられるのが嬉しいんです。逆に上げることもできるし、声を使って遊べるのは良いですね。曲に合った声にすることができる」
――楽器のなかで印象的なのがストリングスです。生々しい質感があって、曲によってはヴォーカルとデュエットしているようにも聞こえます。
「とくにチェロはとても人間の声に近くて、ベースとして使うこともリズムとして使うことも、張感を生み出すこともできる。そういった意味で、声の一部としてチェロを使うのはとても楽しいですね」
――子供の頃にピアノを習っていたあなたにとって、クラシックも音楽のエッセンスのひとつですね。インスト・ナンバー「パーラメント・オブ・オウルズ」はクラシカルなナンバーで、映画音楽みたいに聴き手の想像力を刺激します。
「この曲はコードがどんどん下がって行く下降コードを使っているんです。思考がどんどん深いところまで行くことを音楽で表現したいと思いました。どんどん近視眼的な思考回路に乗ってしまうと、結局は同じことの堂々巡りになってしまう。それをループで表現しようと思って、ストリングスのループを使ってみたんです」
――映画監督がカメラワークや美術にこだわって世界を作っていくように、サウンドのひとつひとつに意味を持たせて。頭の中のイメージを音楽で表現しているんですね。
「たしかに、私の音楽はサウンドグラフィティみたいなところがありますね。音だけど映像的、みたいな。一人で音楽を作ることの良さは、そういうところだと思います。声に色をつけたり、目指しているムードみたいなものをとことん追究できる。そういうことを、他人を信頼して一緒にやるというのもやってみるべきかもしれないけど、ひとりで作る音楽って、誰かと一緒に作る音楽とは違うものができるんです。弱点も含めて、自分らしいものができるのがすごく好きなんですよね」
――10代の頃はバンドをやってたそうですが、その頃はどんな音楽をやっていたんですか。
「15歳の頃にやっていたバンドでは、レディオヘッドのカヴァーをしてました。17歳の時はビートルズの大ファンの男の子とバンドをやっていたので、ビートルズっぽい曲でしたね。その時はベースを弾いていました。ほんとにヘタで、“お願いだから、その時の映像をネットにあげないで!”って友だちに頼んでます(笑)」
――そういうバンド活動から、今のようなサウンドに変化するきっかけは何かあったのでしょうか。
「はっきりとしたきっかけはわからなくて。ロック以外にもいろんな音楽をやっていたけど、一人でやっていたクラシック・ピアノや自分で書いた曲の世界とは混じり合わなかったんです。それで次第に、一人でやる音楽に惹かれていくようになって。その音楽をさらに突き詰めようと思った結果が、今の音楽になったんじゃないかと思います」
――曲作りは自分自身を探求する旅なんですね。
「そうですね。作った本人も答えがわかってない、はっきり説明できないものが入っている音楽が好きです。あと完成した作品を聴くと、その曲を作っていた時のことをいろいろ思い出すんです。曲にしなかったら、忘れてしまっていたようなことを」
――秘密の日記みたいなものなんですね。
「そうですね、秘密の日記だけどナウ・オン・セール(笑)。パーソナルな作品ですが、ぜひ皆さんに聴いてもらいたいですね」
取材・文/村尾泰郎

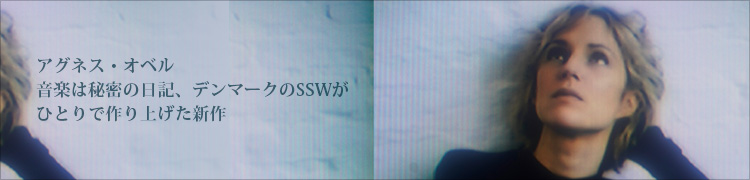



 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。