テイラー・スウィフトをはじめ、ラナ・デル・レイ、ロード、セイント・ヴィンセント、ダイアナ・ロスからThe 1975まで手がける当代一の売れっ子プロデューサー、ジャック・アントノフは、1990年代終わりからFUN.などのバンドで活動、現在はソロ・プロジェクトであるブリーチャーズで活躍する現役バリバリのミュージシャンでもある。最近ではApple TV+のドラマ『ニュールック』のサントラを手がけるなどまさに八面六臂の活躍だ。
この夏はブリーチャーズとしてSUMMER SONIC 2024に出演、ブルース・スプリングスティーン顔負けの熱血ロックンロールで大いに会場を湧かせたのである。
――ブリーチャーズの新作『ブリーチャーズ』を聴いて私が感じたのは、アメリカのポップ・ミュージックの豊かさです。20世紀からずっと積み重ねてきた伝統がちゃんと息づいている。アメリカのポップ・ミュージックそのものが、20世紀以降に起こったすべてのことの集積であって、このアルバムは、その豊かさを如実に示している気がします。
「その意見はすごくうれしいね。アメリカってすごく不思議なところで、伝統的に言いたいことをどんどん言っていい場所ではあった。 その結果として、ものすごく醜いものが生まれてくることもあるし、それが逆にとても面白い表現にもなりうる。それがアメリカのポップ・カルチャーだと思ってる。歴史を振り返っても、ありそうもないものがすごい人気になったりする。なぜそうなるのか、理由なんてないんだ。だってプリンスみたいなアーティストが本来あんなに大勢の人に受け入れられるはずがない(笑)。でもそれがあれだけ売れてしまうという。ジョニ・ミッチェルだってそうだよね。どんなアーティストでも幅広く受け入れる度量がある。そういう中で、時としていちばん変なものがいちばん人気を得たりするのがアメリカのポップ・ミュージックなんだ」
――アメリカのポップ・ミュージックの源流という意味で、あなたが手がけた『ニュールック』のサントラは非常に興味深いですね。20世紀の前半にアメリカで流行ったポップ・ソングを、現代のアーティストがカヴァーしている。あなたも、また多くの人にとってもまだ生まれてもいない時代の楽曲です。
「そのアイディアが気にいったんだ。プリンスもそうだけど、ポップ・カルチャーのさまざまな瞬間に立ち戻って、うわあ、この音楽がみんなを熱狂させたなんてクレイジーだ、と考えるのが面白くてね。なんでこんな変な曲にみんなあんなに夢中になってたんだろうって。それがサイクルを経て普通のものとして受け入れられ、やっぱり変な曲だよねって思われる時代がまた来たりする。そういった変化みたいなものがとても興味深いんだ。すごくシンプルなものが受けてたことがあると思うと、すごく複雑なものが受けてた時代もある。『ニュールック』ではニック・ケイヴがエディット・ピアフの〈バラ色の人生〉をカヴァーしたり、パフューム・ジーニアスがダイナ・ワシントンの〈縁は異なもの〉をカヴァーしたり。アイディアを聞いて、実際にその音が聞こえてくるまで想像して。いろんな世代の人たちといろんな時代の曲について対話をしていくような、そんな体験だったね」
――歌手の人選はあなたがやったんですか。
「そう。知り合いも、そうでない人もいるけど、僕が考えて選んだ」
――あなたは『ミニオンズ フィーバー』(2022年)のサントラでも、60〜70年代のポップ・ソングを今のアーティストがカヴァーするサントラを手がけてますね。
「そうだね。どの時代の音楽も好きなんだ。自分がいいなと思ったものをプレイリストみたいに集めることはふだんからやっている。だからアルバム制作も好きな曲のプレイリストを好きなアーティストと一緒に楽しみながら作ってるような、そんな感覚なんだ。いわば友だちと一緒に好きな曲を聴いたり歌ったりするような感じだね」
――今の曲より昔の曲の方を聴く?
「うーん、いろんなものを聴いてるから、どっちとも言えないんだけれど、自分は音楽を聴くというよりは作る側の人間だから、ふだんはそんなに積極的に聴くことはない。でも映画とか本は自分から動かないと見たり読んだりできないけど、音楽ってのは自然と聞こえてきちゃうものだから、意識しなくても日々音楽に触れているんだ。なんとなく聴いてるうちに好きになっちゃうみたいなこともあると思うんだよね。でも映画や本ではそれは起こりえない。そこが面白いところだと思うんだ。何度も聴いているのに覚えていない曲もあれば、意識しないでも何度も耳にするうちにお気に入りになる曲もある。だから、僕たちはみんな、自分の中にライブラリーを持ってると思うんだ。世代を超えてね。そのライブラリーにあるものを、人生や一日のさまざまな場面で引っ張り出してくるんだ」
――日々の生活で、音楽を聴くのが煩わしいと思う瞬間はありますか。
「いや、それはないな。僕は世の中で起こっていることは何でも聞きたいんだ。トラックが通るとか、誰かが近くでクラクションを鳴らすとか、そういう音は嫌いだけど、音楽が自然に耳に入ってくるのは好きだよ。東京でもニューヨークでも、音楽が流れていたり、人が話していたりするのが好きなんだ」
――ところで、あなたがほかの人のプロデュースを引き受ける際の基準みたいなものってなにかあるんですか。
「これはやっぱり実際に会ってみないと、っていうのがあって。で、会った時にやれるかやれないか予感みたいなものが自分で得られるかどうかということだね。できそうだなと思ったらやってみるけど、できる時もあれば、できない時もある。できない時っていうのはもうどうしようもないんだよね。だから、そこらへんけっこうデリケートではあるし、無理にやろうとしてできることでもない。だから、僕が自分で決断しているという感じでもないんだ。もし運よく、一緒にやっていけそうな人に巡り会えたら……という感じ」
――仮定の質問です。故人・存命を問わず、誰でも好きな人をプロデュースできるなら?
「うわあ(笑)。そりゃ難問だな……1970年代後半のトム・ウェイツとスタジオに入りたいね。でも、実現しても作品が作れるかはわからない。マジックが起きるかどうかなんでね」
――70年代後半の彼の……
「いや、70年代後半じゃなくていいよ(笑)。もうほんと、彼の作品は全部好きだから。もっと作ってほしかった。それだけだよ」
――あなたなら彼のどんな部分を引き出したいですか?
「わからないけど……わからないけど……ただ、彼のことが大好きなんだ」
――最後の質問です。歴代のプロデューサーの中で、尊敬している人、お手本にしている人はいますか?
「ジェフ・リンだね。彼の才能もそうだけれども、バンドをやりつつ、自分の活動もして、プロデュースもしてるっていう。僕も今そういう立場だけれども、それをこなしてる人ってけっして多くないので、 そういう意味においてもね。もちろん、彼の音楽自体も大好き。ふだんの仕事でもジェフのことはよく考える。サブリナ・カーペンターの曲でも彼を参考にしてるんだよ」
取材・文/小野島 大
撮影/西岡浩記

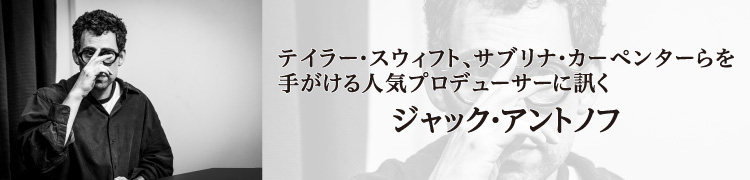



 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。