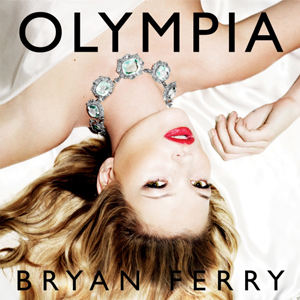
――ロキシー時代の仲間たちとスタジオで音を出した際のケミストリーは変わっていませんでしたか?
ブライアン・フェリー(以下、同)「ああ全然ね。2009年、ちょうど今回のソロ・アルバムの作業を終わらせたまさにその日のうちに、今度はロキシーのライヴをすることになってさ。で、さっそくリハをしたんだけど、これが素晴らしかったんだ。僕はそもそも初期のロキシーの曲が大好きでね。今回の僕のアルバムにはそういうちょっと懐かしい空気もシンクロしてるんじゃないかな。まあ、ブライアン・イーノはいつも自分のことでとても忙しいからツアーには参加しないけどね(笑)。彼とはスタジオだけ。それが僕たちの自然な習慣なんだ(笑)」

――今回のアルバムはとくに若いミュージシャンとも関わっていますし、楽曲も躍動的なものが多くなっています。これは意識的に世代を超えたリベラルな目線を持ち込もうとした結果なのでしょうか?
「どうだろう。自分自身のスタイルって偶然に見つかるもので、デザインされているものではないんだ。そして、それは音楽で一生懸命頑張ることの醍醐味でもある。今回、シザー・シスターズとかグルーヴ・アルマダとコラボレートしたのは、いつも自分のヴィジョンを広げているからなんだと思うよ。たとえばピカソをみてごらん。彼は20世紀の巨匠として知られているけれど、晩年の作品には多くの遊び心と楽しみがある。そこが重要なんだよ。ま、僕も自分をミュージシャンというよりはむしろアーティストだと思っていてね。ハハハ。僕は音楽の枠にはまらない、いい意味でアウトサイダーだと思っているよ。毎日音楽の中で働いているけれどね(笑)」
――カヴァーにチャレンジするのもそういう理由からなのでしょうか? 今作ですと
ティム・バックリィの「ソング・トゥ・ザ・サイレン」と
トラフィックの「ノー・フェイス、ノー・ネーム、ノー・ナンバー」。とりわけ「ソング・トゥ・ザ・サイレン」は
ディス・モータル・コイルが83年にとりあげたヴァージョンにも負けない美しい仕上がりです。
「実はこの曲は、発表された時には知らなかったんだ。最初に聴いたのはまさにそのディス・モータル・コイルによるカヴァーだった。その時に僕もいつかこの曲をやりたいなと思ったよ。ずいぶん時間がかかっちゃったけどね(笑)。でも、ジョニー・グリーンウッドと
デヴィッド・ギルモアの素晴らしいギター・プレイが堪能できる美しい仕上がりになっているよ。そもそも僕は声に特徴のあるミュージシャンの曲を歌いたくなるほうでね」
――そういえば、
スティーヴ・ウィンウッドもあなたも、アングルは違えどいずれも英国産ブルーアイド・ソウル・シンガーですよね。
「そうだね。初めてスティーヴ・ウィンウッドを観た時のことを今でも覚えてるよ。
スペンサー・デイヴィス・グループのライヴだった。僕はまだ大学でアートを勉強していてね。でも、スティーヴはもうステージに立っていた。それで、僕は彼のキャリアの後について行ったんだ。最初はスティーヴを真似していたなあ。もっとも、大人になって自分自身の曲を書き始める頃には独自の世界ができてきてたけどね」
――ええ、あなたの音楽は昔から一環した美学で貫かれていて、たとえば、それは“ダンス”という表現方法とポップ・ミュージックとを結びつける作業にも表われています。かつて「ドント・ストップ・ザ・ダンス」と歌ったあなたは、今作では「ユー・キャン・ダンス」と歌っている、というように。
「まさにそうだよ。ハハハ。とくに音楽とダンスの親和性が高いことは前々から気づいていて、そこが自分の居場所であることはわかっていたんだ。実際、僕はダンスするために生まれてきたようなところがあってね(笑)。今でもいろんな舞台を観に行くんだけど、素晴らしい音楽、衣装、セット、照明……それらが一つになるのを観ると本当に感動して、自分もそういうのを作りたくなるよ。そこで、〈ユー・キャン・ダンス〉のビデオ・クリップで実践したってわけ。もう観てくれた? 30人ものキレイな女の子が、僕の歌に合わせて踊ったり、歌ったりするビデオ。最高だっただろう?(笑)」
取材・文/岡村詩野(2010年7月)


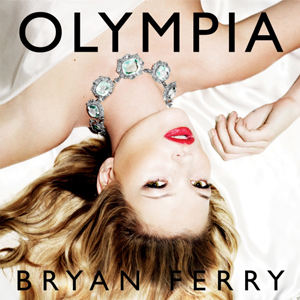



 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。