2017年にドイツ・グラモフォン(DG)レーベル初の専属女性チェロ奏者として契約を結んだ、ベルギー系フランス人のカミーユ・トマが最新アルバム『ヴォイス・オブ・ホープ』をリリースした。ファジル・サイが彼女のために書き下ろしたチェロ協奏曲《ネヴァー・ギブ・アップ》世界初録音に加え、人間を希望の光に導く歌曲やオペラ・アリアをチェロ編曲版で収録した、野心的なアルバムだ。コロナ禍で人々が不安を抱える今だからこそ、アルバムを通じて希望の声(ヴォイス・オブ・ホープ)を届けたいという彼女の思いを、スカイプによるリモート・インタビューで伺った。
――4歳でチェロを始めて、8歳で合唱団に加わったそうですね。だから、声楽曲やアリアの演奏に関心があるんですか?
「ええ。合唱団は母の勧めで加わりましたが、チェリストとしての自分のアイデンティティを確立するため、その経験がとても役に立ちました。どの音符も、人が歌いかけるように演奏すべきだと思っています。たとえ歌詞はなくてもヴィブラート、音色、デュナーミクなど、ありとあらゆるテクニックを総動員して“歌う”という点では、チェロも同じですね」
――2017年にリリースしたDGデビュー盤『サン=サーンス&オッフェンバック』は、チェロのための作品に加え、テノール歌手ローランド・ビリャソンやヴァイオリン奏者ネマニャ・ラドゥロヴィチとの共演も収録されていて、とても楽しいアルバムでした。
「DGデビュー盤は私の“名刺”になると思ったので、自分のルーツでもあるフランス音楽、つまりサン=サーンスとオッフェンバックを演奏しました。たんに彼らの有名曲を演奏するのではなく、比較的知られていない初期の作品、つまり作曲家としてのデビュー的な意味合いを持つ作品を含めることで、DGからデビューした私の幸せな気持ちを反映させたんです。そのデビュー盤で最初に録音したのが、ネマニャと共演したオッフェンバックの《ホフマンの舟歌》でした。ちょうど、ネマニャが(彼のアンサンブル)ドゥーブル・サンスとチャイコフスキーの《ロココの主題による変奏曲》をベオグラードで収録していたので、そこにお邪魔する形で録音しましたが、本当に楽しい経験でした」
――今回のアルバム『ヴォイス・オブ・ホープ』で収録したチェロ協奏曲《ネヴァー・ギブ・アップ》を、ファジル・サイがあなたのために作曲することになったきっかけは?
「2014年にファジルと初めてお会いし、何度かやりとりを重ねた後、彼から“チェロ協奏曲を書きたい”と提案をいただいたんです。その後、2015年11月にパリで同時多発テロが発生し……」
――その時、どこにいらっしゃいましたか?
「たまたまフランスの郊外にいましたが、パリに住んでいる私のような人間にとっては、とても他人事とは思えませんでした。その後、不幸にもイスタンブールやブリュッセルでも同じようなテロ事件が起きました。するとファジルが“協奏曲の第2楽章でテロを描く”と伝えてきたんです。ファジルは音楽的にも政治的にも、つねに自由な表現を目指して諦めず、何度も挑戦していくアーティストです。つまり、彼の生き方そのものが“ネヴァー・ギブ・アップ”なのですが、同時にそれは私自身の人生観でもあるんです。彼が言うには“チェロは、協奏曲全体を通じて人間の声を表現し、我々自身の人生を伝えていく。我々は第2楽章で描かれるテロにもひるまず、人間性や美に対する希望を失ってはならない”と。その後、彼はチェロ・パートの譜面をWhatsAppで少しずつ送ってきたのですが、どのページも素晴らしく書かれていました」
――《ネヴァー・ギブ・アップ》のスコアを拝見したのですが、第1楽章冒頭でチェロが力強いカデンツァを演奏する箇所に、ファジルは“闇に対する闘い”という指示を書き添えていますね。とてもベートーヴェン的ですが、協奏曲全体のメインテーマも有名な「♪タタタ・ター」の運命リズムで始まりますね。
「それは私も気付きませんでした! リズムのことを指摘したのは、あなたが初めてですよ(笑)。今度、ファジルに訊いてみますが、ここ数年、ファジルはベートーヴェン・プロジェクトのために多くの時間を割いていましたから、ベートーヴェンの影響は確実にあると思います。西洋の音楽と(トルコなどの)オリエンタルの音楽の双方に通じるファジルは、西洋と東洋のふたつの世界が互いに手を携えることで、人間がより力強くなれるという“希望”をみずから体現したアーティストだと思います」
――第2楽章で、チェロが(アルメニアのダブルリード楽器)ドゥドゥクそっくりの音色で演奏する部分は、とてもファジルらしい音楽だと思いました。
「C弦で弓をたっぷり使いながら、高音をそよ風のように柔らかく弾くのですが、ファジルの曲以外で、そんな特殊奏法は見たこともありません。彼の偉大な発明ですね。パリ初演のゲネプロの後、普段あまり曲のことを説明しないファジルがステージに上ってきて、こう言ったんです。“この楽章では、チェロと弦楽セクションは(イスタンブールの)ナイトクラブにいる人間で、テナードラムが叩くカラシニコフの機銃掃射が、君たちを無慈悲に射殺する”。それを聞いて、演奏者全員の気持ちが一変しました。感情の入り方が違うんです。第2楽章を演奏するたびに、文字どおり死にそうになりますが、それでもこの楽章が大好きです」
――アルバムに収録された歌曲やアリアが、その協奏曲を補完するように選曲されているのも素晴らしいと思いました。
「協奏曲の録音を決めた段階で、第3楽章〈希望の歌〉に由来する“希望”をアルバム・タイトルにしようと思いました。そこで、どうしたらファジルの曲をひとつの物語の中に組み込むことができるか、長い時間をかけて選曲していったんです。最初に選んだのは、“赦し”の歌でもあるブルッフの《コル・ニドライ》。それからラヴェルの《カディッシュ》は、死者を追悼する“哀歌”であると同時に、イディッシュ音楽の伝統を引き継ぐ音楽という意味で、ファジルの曲とよい組み合わせになると思いました。さらに、私がチェロの演奏で心がけてきた“人間の声”というテーマも盛り込みたかったので、アルバム・コンセプトにふさわしいオペラ・アリアをいくつも探しました。アルバム最後のベッリーニ《清らかな女神よ》は月を歌った曲ですので、まさに希望の光ですね。結果的に、私が選曲した曲はすべて魂を鼓舞するようなスピリチュアルな要素を備え、“暗闇から光に向かう旅”という物語を表現しているんです」
――ラヴェルの《カディッシュ》とウィリアムズの《シンドラーのリストのテーマ》を除いて、全部今回のアルバムのための新編曲ですね。
「アレンジは、エベーヌ四重奏団の元メンバーで現在は指揮活動に専念しているヴィオラ奏者の友人、マチュー・ヘルツォークにお願いしました。これまで、彼が音楽監督を務めているアンサンブル・アパッショナートと何度か共演しているんです。今回の(ファジルの曲以外の)録音ではマチューに指揮もお願いしたので、現場での譜面の修正もすぐにできましたし、とても楽しい録音でした」
――今後、トマさんは協奏曲の演奏で日本デビューが予定されていますが、もし日本でチェロ・リサイタルを開催するとしたら、どんなプログラムを考えていますか?
「ラフマニノフ、ベートーヴェン、ブラームスといったクラシック作品のプログラム、それから私が“ミッドナイト・イン・パリ”と呼んでいるプログラムを演奏してみたいです。有名な音楽教師ナディア・ブーランジェをテーマにして、彼女と同時代に生まれたパリの音楽、それから彼女に師事したピアソラのような作曲家の作品も織り交ぜながら、パリが世界中に与えた音楽的影響を伝えたいと思っています」
取材・文/前島秀国(サウンド&ヴィジュアル・ライター)

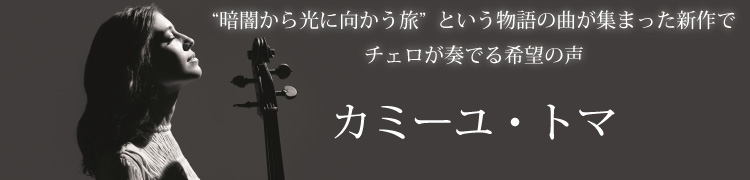



 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。