デビュー25周年を迎えたcoba からニュー・アルバム『coba? 』が届けられた。原点回帰をテーマに制作された本作では、カンツォーネ、スパニッシュ、タンゴ、クラシック、唱歌などを自在に行き来するような旋律、時代と国を超越するサウンドメイクを軸にした“現在進行形のcoba”がリアルに表現されている。「初心に帰ろうと思った結果、まったく新しいものができた」という本作について、coba自身に語ってもらった 。
――新作『coba?』のテーマは“原点回帰”。どうしてこのテーマを選んだんですか?
「アルバムを作るときは毎回テーマを考えるのですが、これまでに36枚もアルバムを作ってきて、たいていのことはやっているんですよ。特に今回はデビュー25周年ということもあって、テーマを決めるのが難しくて。まさかこれほど長く活動を続けられるとは思っていなかったし、自分のなかで“四半世紀”という言葉がすごく重くて。これからさらに25年は続けられないでしょうし、このタイミングで原点に戻ってみるのもいいのかなと思ったんです。ただ、ぜんぜん曲が書けなかったんですよ。人に提供する楽曲はポンポン出てくるんだけど、自分のアルバムの曲はぜんぜん降りてきてくれなくて。曲が難しくて弾けないことはありましたが、曲が書けないことはなかったんです、いままで。25年間で初めての経験だったから、すごく焦ったし、“原点回帰を掲げたのは間違いだったかもしれない”とも思って」
――その状態を抜けたきっかけは何だったんですか?
「きっかけはわからないですけど、最後の1週間で一気に書けたんです。10月の18日、19日にレコーディングすると決めて――それもギリギリのスケジュールだったのですが――その1週間くらい前に突然、雷が落ちるように一気に曲が降りてきて。作っている最中に次の曲が浮かんできてしまって“ちょっと待って、このモチーフだけメモさせて”と思ってしまうような感じだったんです。そのときに150くらい曲のモチーフができて、いきなりラクになりましたけどね(笑)。メロディを掴もうと思えば、いくらでも掴めるんです。でも今回は“初心に帰るというのは、そういうことではない”と自分自身が思っていたんでしょうね。結論はわかってたんですけどね、じつは」
――というと?
「やりたいからやる、好きだからやるということです。好きこそものの上手なれと言いますけど、歌が好きな子はもっと自分の歌を聴いてもらいたいと思って歌手を目指すだろうし、曲を書くのが好きなヤツは作曲家になろうとする。僕の場合はアコーディオンが人よりも上手かったわけだけど、さらに“自分が書く曲によって、アコーディオンに新たな命を吹き込みたい”と思ったんですよね。“こんな曲は誰もやっていない”ということだったり、“まだ誰も聞いたことがない音を作りたい”というテーマがずっとあって。今回のアルバムもまさにそうなんですよね。いままでの自分にはなかった曲ばかりだし、全体を通して、これまでのアルバムの形式を超えているなって。曲が書けない時期の葛藤があったのも良かったんでしょうね。不安を感じたし、“俺はもうダメなのかもしれない”とも思って。そこで初めて自分と向き合えたというか」
――なるほど。アルバムのオープニングは派手なブラス・セクションを取り入れた「Great Britain」ですね。
――「Great Britain」というタイトルからも、cobaさんのイギリスに対する思いが感じられます。イギリスに限らず、現在のヨーロッパは政治的にも重大な局面を迎えていて。そういう状況から何か影響を受けることはありますか?
「あるでしょうね。日本とはまた違いますけど、ヨーロッパもあまり良い状況とは言えなくて。僕はパリという街が好きですが、いまのパリの人々は不安がっているように見えるんですよ。以前は個性的な生き方をしている人が多かったのに、いまはお互いにけん制し合っていて。がんばってほしいなって思いますね。ただ、音楽に関して言えば、アラビア、インド、アジア、もちろんヨーロッパにもたくさんおもしろいものはあって。グローバル化が進めば進むほど、そういう音楽の価値に気付く人も増えるだろうし、そうあってほしいなと思います」
――EDMサウンドを反映させた「She loves you」も新機軸ですよね。cobaさんはデビュー以来、ヨーロッパと日本を行き来していて、ヨーロッパにおけるダンス・ミュージックの流れも肌で感じていると思うのですが。
「そうなんですが、じつは最近はダンス・ミュージックをまったくフォローしてなかったんです。90年代初めにテクノの嵐が吹き荒れていた時期はロンドンにいて。そのときはいろいろと刺激を受けたのですが、2000年代に入ってから沈静化して、つまらなくなってしまったんです。2ステップをはじめ、さまざまなものが出てきましたが、結局は何も変わってないじゃないか、と。それらが統合してEDMと呼ばれるようになったわけですが、コマーシャルになり過ぎていて、さらに興味を失っていたんです。でも、あるときにEDMのアーティストが作ったカントリーのような曲(
Avicii 〈
Wake Me Up 〉)を聴いて、こういうのもアリなんだなと思って。その発想からできたのが〈She love you〉なんですよね」
――昭和の抒情性が伝わる「昭和キネマラヴ」もcobaさんにしか生み出せない楽曲だと思います。
「これは昭和30年代のキャバレーですね(笑)。小学生の頃は新潟に住んでいたんですけど、当時〈キャバレー香港〉というホステスさんが1200人もいる大型のグランドキャバレーがあったんですよ。ウチの父親はお酒が飲めなかったんですが、年に1度だけ、接待でお酒を飲んでくる日があって。それがどうやら〈キャバレー香港〉だったらしいんですよね(笑)」
――cobaさん自身の個人史に紐づいている曲なんですね。
「僕が尊敬している音楽家は、みんな“私小説”なんですよ。
武満 徹 さん然り、
アストル・ピアソラ さん然り、
ニーノ・ロータ さん然り。みなさん世界的な音楽家ですけど、最初から世界を目指していたわけではなくて、“こんなことがありました”という私小説を音楽として表現したのが〈ノヴェンバー・ステップス〉であり、〈リベルタンゴ〉だった。僕自身もそれを続けるしかないなと思っています」
――『coba?』にもカンツォーネ、タンゴ、クラシックなど、cobaさん自身のルーツ・ミュージックがしっかり根付いていて。これらの音楽も一貫してcobaさんの作品に流れていますよね。
「そうですね。話が戻りますが、原点回帰というテーマを決めた時に最初に頭に浮かんだのは、音楽に出会ったときのことなんです。3歳からピアノを始めて、少しずつ弾けるようになってきたときの楽しさ。自分で作った曲を褒めてもらった経験。小学校4年生のときに初めてアコーディオンを持って、“身体全体で抱きしめるように演奏するんだ”と思ったときの驚き。あとはデビュー作『
シチリアの月の下で 』をリリースしたときの、1人でも多くの人に聴いてもらいたいという感覚。そういうものって、時間の流れとともにどうしても埋もれてしまいますからね。そこに立ち返って、自分が何をやってきたかを再確認したかったんでしょうね」
VIDEO
――自らのスタイル、音楽性を再確認したアルバムでありながら、タイトルを『coba?』にしたのはどうしてですか?
「いつも暗中模索だし、最後はいつも“?”ですから。だけど、“あれもこれも”ではなく、“これしかできない”というのはあらためて示すことができたと思います。アコーディオンという楽器と運命を共にしようと決めて、この楽器のソーシャルなイメージを変えたいと思って。たとえばこのアルバムは、旋律をアコーディオンでなくヴォーカルで唄っても成立するんですよ。でも、自分にとってのヴォーカリストは、ずっとアコーディオンなんですよね」
――アコーディオンのイメージは、cobaさんによって完全に変わりましたよね。
「そうですかね? ただ、後から出てきた若いミュージシャンが自分の音楽に対して賛成や反対をしてくれているのを聞くと、少なからず影響を与えられたのかなと思いますけどね。ビックリするのは、アコーディオン、バンドネオンの人だけではなくて、たとえば
沖 仁 くん、
押尾コータロー くん、
上妻宏光 くん、
吉田兄弟 などに“アコーディオンでこんなにカッコいいことがやれるんだから、俺もがんばろうと思いました”と言われることなんです。これも長くやってきたからかな、と。音楽、楽器を通して、彼らにスピリットに語りかけることができていたとしたら、こんなに幸せなことはないですね」
――本当に発見が多いアルバムになりましたね。
「そうですね。最初に申し上げたように、原点回帰、初心に返ることを意識しながら制作に入ったのに、結果として出てきたのは、いままでとはまったく違う曲ばかりで。それがいちばんの発見でした。四半世紀の活動のなかで作ってきた36枚のアルバムとこれからの自分の架け橋にもなってくれたし、記念碑的な作品になったと感じています」
――2017年1月から25周年を記念した全国ツアー〈coba tour 2017 25周年記念〉がスタート。『coba?』ができたことで、cobaさんの音楽はさらに未来に進むことになりそうですね。
「はい。いままで自分がやってきたことを通して、このアルバムができ上がったと思うと“まだまだ音楽を降ろしてもらえそうだな”という実感もあるので。いまの夢はふたつ。ひとつはパリでキャバレーを作ること。もうひとつはオペラを作ること。まだ具体的なものはないんだけど、オペラの概念を変えるというか、“これもオペラと呼んでいいの?”と思ってもらえるようなものを作ってみたい。歌唱法や演奏を含めて、民族意識――もちろん日本だけではなく、世界中の民族意識ですが――から生まれる必然性を持ったオペラをカッコよくやりたいんですよね」

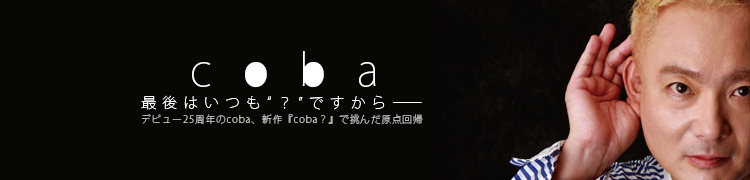

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。