全世界売り上げ3,300万枚以上、全英を含む世界31ヵ国でナンバー・ワンを達成するなど驚異的なヒットを記録した前作『X&Y』から3年。ついにコールドプレイがニュー・アルバム『美しき生命』を発表! 今回の特集では、6月11日の発売に先がけ、メンバーへのスペシャル・インタビュー、新作のクロス・レビュー、活動回顧録を通じ、世界中のロック・ファンが待ちわびた『美しき生命』の魅力に迫ります。
日本について海外のミュージシャンが歌った曲は、これまでにそれなりの数がある。それでも、コールドプレイが最新作『美しき生命』で歌っている「ラヴァーズ・イン・ジャパン」のように、愛を象徴する場所として日本を描くという手法は、本当に珍しい。日本人が歌うラヴ・ソングとはまた違う、ちょっとだけ壮大で、そして新鮮な目線。代々木公園を散歩していたとき「これほど恋人たちに似合う場所は、世界中に他にない!」とクリス・マーティン(vo、g、key)が感動したことが、この曲の起点になっている。
「西洋の人たちは、日本というとテクノロジーを連想するよね。だから、セクシーな感じとか、ロマンティックな感覚を日本というものと繋げない人たちもいる。でも、僕は日本にいるとそういうことを、すごく感じるんだ。……こんなこと言ったら、日本の人たちに失礼かなあ?」 (クリス)
そんなことありませんよ、日本人の私はこの曲を聴いて、なんだか誇らしく、新たな目線を嬉しく感じました−−そう伝えるとクリスは、この曲で描かれる「大阪の太陽」についても語り始めた。
「初めて日本に行ったときに、大阪に滞在したんだ。日本に飛行機で到着してから、何もかもが目新しくて、僕たち全員、眠ることができないでいたんだよね。そうやって大阪で一晩中眠れずにいて、太陽が埠頭から昇ってくるのを見たんだ。そのとき、“ああ、俺の人生もずいぶんと変わったな”って、そういう風に感じたんだよ。だから、僕にとっては大阪の太陽っていうと、すごく幻想的な感じがするものなんだよね」 (クリス)
そうやって、当然のものとしてそこにある何かを、繊細な瞳と感覚でとらえることにコールドプレイは長けている。夜空にまたたく黄色い星に愛を誓った、初期の名曲「イエロー」の大ヒットからこれまでの軌跡も、当たり前の何かを宝石へと転換できるその目線があればこそ、幅広いリスナー層からの共感が可能となった結果だ。
ブライアン・イーノらをプロデューサーに迎え、さまざまな音響的実験を試みたこの『美しき生命』でも、その部分にはまったくブレがない。
「いいメロディがまずあって、それを基本に、いろいろと実験したいと今回は思っていたんだ。いいメロディを作ろうという実験もしていたけれど、それでも僕たちがとても興味があったのは、やっぱり、みんなに何か意味のある音楽を作るということ。それを、このアルバムではこれまでとは違ったやり方でやろうとしたんだ。新しい何かを加えることで、それを可能にしたかったというか。でも、僕たちが主に気にかけていたのは、“これで人は、何かを感じてくれるのだろうか”ということだけだったんだよ」 (ジョニー・バックランド/g)
その最たる例が、アルバム・タイトルにもなった「美しき生命」という曲かもしれない。
ビートルズの「エリナー・リグビー」のそれを彷彿させる、ストリングスをまるでリズム楽器のように使った展開の曲だ。シンフォニックな楽器たちが、たおやかさではなくヴィヴィッドな生命力として響きわたり、それでいて、たとえばフルートのように聴こえるサウンドは実はギターで出しているものだったり。胸の躍るようなメロディ・ラインも含め、一瞬にして心を掴み、生きている喜びを感じさせるこの曲は、実は種明かしをすればキリがないほど丁寧に、細やかに考え抜かれて作られている。
「今回はなるべく、ギターでさまざまなことを試すようにしたよ。僕にはギター以外に、うまく演奏できる楽器はないからね(笑)。だから、ギターで、できる限りいろいろなサウンドを演奏しようとしたんだ。たとえば、ギターのサウンドをキーボードやフルートのように響かせるエフェクト・ボックスを買ったりとかして、ね」 (ジョニー)
「ジョニーがバンドにいてくれて、僕たちはラッキーなんだ。ジョニーはもの静かでシャイだけど、ギターのことになるととても器用で、僕たちの最も強力な武器となっているんだよね」 (クリス)
このアルバムのサウンドには、さまざまな発見があり、歌詞にも、メロディにも、クリスの歌声にも、どの角度から見ても、ちゃんと魅力が宿っている。クリスは、それを「二層になっているアルバム」と説明する。
「僕はとにかく、変化に富んだアルバムにしたかったんだよ。たとえば、歌が気に入らなくても、ギターは楽しめる、といったようにね。言いたいこと、分かってもらえるかな。好きになってもらえる選択肢が、2つあるってことなんだ」 (クリス)
それを実現させるための苦労は、並大抵ではなかったはず。しかし“がんばりました”感なくそれをやってのけているからこそ、今作からはコールドプレイというバンドの凄さが、ひしひしと伝わってくるのだ。
取材・文/妹沢奈美(2008年4月)


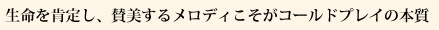

全編をゆるやかに貫くエキゾチックな空気、ロック・バンドというフォーマットを完全に脱却し、一大叙事詩とでも言うべきスケール感が伝わってくる構成力。コールドプレイの3年ぶりの新作は、同時代のバンドとは比較にならないほどに大きく、奥深いストラクチャーを持った作品となった。ブライアン・イーノ、マーカス・ドラヴスをプロデューサーに迎えたこのアルバムは、しかし、決して難解でもなければ、独りよがりでもない。10曲で40数分というコンパクトなサイズからもわかるように、ロック・ミュージックとして――もっといえばポップスとして――誰もが単純に楽しめる作品に仕上がっていて、それこそが本作の凄さなのだと思う。
アイリッシュ・トラッドの雰囲気をたたえたメロディと初期
U2を彷彿とさせるギター・サウンドが一つになった「哀しみのロンドン」、60年代半ばのビートルズにも通じるサイケデリアが全編を覆う「42」、
マイブラっぽいギター・シンフォニーが楽しめる「ラヴァーズ・イン・ジャパン」。まるでUKロックの歴史絵巻のように、先人たちの偉業をしっかりと引用しながら構築されていくサウンド・メイクも高品質だが(音色の一つ一つが恐ろしいほどに美しく、音の位相も緻密に計算されている)、特筆すべきはやはり、クリス・マーティンのメロディメイカーとしてのとんでもない才能だろう。イギリス〜アイルランドの伝統的な音楽、ブルース、90年代以降のギター・ロックまでを包括しながら、あらゆる人種の心の琴線を揺らしていきた彼の旋律は、このアルバムで一つの高みへと達している。とくに賛美歌にも似た普遍性を感じさせる「ロスト!」、そして、オペラ歌劇を想起させるストリングスを用いた「美しき生命」の美しさといったら……。アレックス・ターナーと並び、クリスが2000年代最高のソングライターであることは間違いない。生命を肯定し、賛美するかのような彼のメロディこそがコールドプレイの本質であると、このアルバムはあらためて教えてくれているのだから。
(森 朋之)
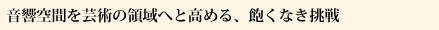

U2好きを公言しているクリス・マーティンだけに、コールドプレイの新作をブライアン・イーノがプロデュースすると聞き、本作1曲目のイントロからU2の
『ヨシュア・トゥリー』を想起するリスナーは筆者だけではないはず。かねてから、曲のアンビエンスにこそ魅力があった彼らは、つまり、4作目にして、イーノと彼の門下生であるマーカス・ドラヴスの助力を得て、その音響空間を芸術の領域へと高めようという飽くなき挑戦に乗り出したというわけだ。
その原動力とは一体何なのか? 2007年に彼らは一時、本作の録音を中断すると、チリ、アルゼンチン、ブラジル、メキシコを回る南米ツアーを行なっているが、そこで生と死がエネルギッシュにせめぎ合う彼の地の開放的なムードに触発されたであろうことは想像に難くない。
フリーダ・カーロの遺作『生命万歳』から取られたアルバム・タイトルやラテン的なハンドクラップを織り込んだ「哀しみのロンドン」からも、その影響の痕跡はそこここに見て取れる一方、生を謳歌する本作は、南米諸国の姿勢がそうであるように、新自由主義に対する柔らかなアンチテーゼが含まれている。いかにも“非常にヘヴィなソフト・ロック”バンド、コールドプレイらしいプレゼンテーションだ。
そんな彼らであるが、いわゆるポップ・ソングのフォーマットやバンドという枠組すら突き破ってみせる本作においては、1曲中に複数のアイディアを同居させ、アレンジを二転三転させ、ボーナス・トラックを除く10曲45分で一続きの世界を描く。クリス・マーティンが彼の大きな武器であるファルセットを敢えて封印し、低いキーのヴォーカルを披露すれば、バンドはストリングスをまとって、時にシンフォニック・ロックのようであったり、「美しき生命」においてはバンド・サウンドそのものをも解体するなど、その発想は自由度が極めて高く、噛みしめれば噛みしめるほど、旨味がにじみ出てくる作品となっている。過去3作の売上げが3,300万枚を超えるモンスター・バンドのアクションとしては、非常にラジカルで挑戦的な一枚と言えるのではないだろうか。
(小野田 雄)

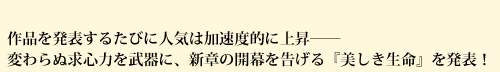
文/土屋京輔
コールドプレイの誕生は、1996年にクリス・マーティン(vo、g、key)とジョニー・バックランド(g)がロンドン大学で出会ったことに端を発する。彼らはバンド結成を企て、その後の1年をかけて音楽的な方向性を思案していたが、そんな中、クラスメイトだったガイ・ベリーマン(b)が合流。しばらくはSTARFISHなる名でショウケース的なライヴを行なっていたという。そして1998年1月にウィル・チャンピオン(ds)が加入。この現在に至る不動のラインナップが揃ったところで、彼らはコールドプレイとしての活動を正式にスタートさせた。
その時点で成功が約束されていたかのように、彼らの躍進は凄まじかった。自主制作を含む3枚のEP発表と並行して1999年春にはEMI傘下のメジャー・レーベル“Parlophone”と契約。先行シングルの好リアクションを経て、2000年7月に発表された1stアルバム『パラシューツ』は何と全英チャートで初登場1位を獲得したのである。
同作を筆頭に、以降の彼らのアルバム
『静寂の世界』(2002年8月)、『X&Y』(2005年6月)もそれぞれ世界累計で1,000万枚以上のセールスになっている。チャート的にも複数週において首位を継続するなど、作品を発表するたびに人気は加速度的に上昇し、イギリスのみならず、他の欧州各国、そしてアメリカなどでも確固たるファン・ベースを築き上げてきた。主要国の賞レースでは欠かせない存在にもなっているが、昨今では南米やアジアでも輝かしい実績を残しつつある。
日本での状況はどうかと言えば、たとえば『X&Y』はチャート6位を記録。また、2006年に実現した初の単独ジャパン・ツアーでは2日間にわたって日本武道館公演を行なったのもエポックメイキングな話題だろう。それまでフェスティヴァルへの参加のみだったコールドプレイだが、この出来事は彼らの実際のパフォーマンスへの注目度が文字通りに増していた証でもあった。
ブリティッシュ・ロックなる言葉の捉え方はさまざまある。ただ、その定義付けはともかくとして、彼らが音楽史における2000年代を代表するアーティストであることに異論を唱える人はいないはずだ。敬意を込めて自身のルーツを咀嚼しながら、前衛性も湛えた個性的な創造物を生み出す姿勢は、さらなる洗練度を備えたように映る。間もなくリリースされる『美しき生命』に収められた楽曲群も、綴られる歌詞も含めて、聴き手を奥深い世界観へと誘う内容だ。今、4人が伝えたいメッセージは何なのか。気づけば結成から早くも10年である。コールドプレイの新章開幕――そう言ってもいいタイミングかもしれない。





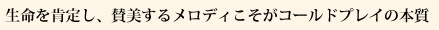
 全編をゆるやかに貫くエキゾチックな空気、ロック・バンドというフォーマットを完全に脱却し、一大叙事詩とでも言うべきスケール感が伝わってくる構成力。コールドプレイの3年ぶりの新作は、同時代のバンドとは比較にならないほどに大きく、奥深いストラクチャーを持った作品となった。ブライアン・イーノ、マーカス・ドラヴスをプロデューサーに迎えたこのアルバムは、しかし、決して難解でもなければ、独りよがりでもない。10曲で40数分というコンパクトなサイズからもわかるように、ロック・ミュージックとして――もっといえばポップスとして――誰もが単純に楽しめる作品に仕上がっていて、それこそが本作の凄さなのだと思う。
全編をゆるやかに貫くエキゾチックな空気、ロック・バンドというフォーマットを完全に脱却し、一大叙事詩とでも言うべきスケール感が伝わってくる構成力。コールドプレイの3年ぶりの新作は、同時代のバンドとは比較にならないほどに大きく、奥深いストラクチャーを持った作品となった。ブライアン・イーノ、マーカス・ドラヴスをプロデューサーに迎えたこのアルバムは、しかし、決して難解でもなければ、独りよがりでもない。10曲で40数分というコンパクトなサイズからもわかるように、ロック・ミュージックとして――もっといえばポップスとして――誰もが単純に楽しめる作品に仕上がっていて、それこそが本作の凄さなのだと思う。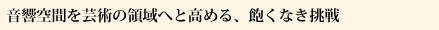
 U2好きを公言しているクリス・マーティンだけに、コールドプレイの新作をブライアン・イーノがプロデュースすると聞き、本作1曲目のイントロからU2の『ヨシュア・トゥリー』を想起するリスナーは筆者だけではないはず。かねてから、曲のアンビエンスにこそ魅力があった彼らは、つまり、4作目にして、イーノと彼の門下生であるマーカス・ドラヴスの助力を得て、その音響空間を芸術の領域へと高めようという飽くなき挑戦に乗り出したというわけだ。
U2好きを公言しているクリス・マーティンだけに、コールドプレイの新作をブライアン・イーノがプロデュースすると聞き、本作1曲目のイントロからU2の『ヨシュア・トゥリー』を想起するリスナーは筆者だけではないはず。かねてから、曲のアンビエンスにこそ魅力があった彼らは、つまり、4作目にして、イーノと彼の門下生であるマーカス・ドラヴスの助力を得て、その音響空間を芸術の領域へと高めようという飽くなき挑戦に乗り出したというわけだ。
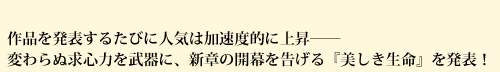


 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。