クレイジーケンバンドのブランニュー・アルバム
『MINT CONDITION』が到着! 1997年のバンド結成以来、絶えずチューンアップを重ねることで、唯一無二のサウンドに磨きをかけてきたクレイジーケンバンド。“極上品質”という意味を持つタイトルが冠せられた今作について、50歳を迎えたばかりの
剣さんに話を訊いた。
 ――今回のアルバムも例年通り、春先に発情して曲がドバドバできはじめるところからスタートしたんですか?
――今回のアルバムも例年通り、春先に発情して曲がドバドバできはじめるところからスタートしたんですか?横山剣(以下、同)「そうですね。その時期に曲がいっぱい出てくる。レコーディングに入ってから、さらに別のアイディアも出てきて。特に今回はスルっとできちゃった曲ばかりなんですよ」
――今まで以上に?
「そうです。今までも曲自体はドバドバできていたんですけど、今回は無痛分娩みたいな(笑)。ウチ、3人目の子が無痛分娩だったんですよ。無痛分娩ブームだ(笑)」
――(笑)。アルバム・タイトルに“極上品質”という意味を持つ『MINT CONDITION』という言葉を選んだのは?
「今年50歳を迎えたということもあって、“製造年月日は古いけど状態は最高だよ”ということを伝えたいなと思った。今の段階では自画自賛になっちゃうけど(笑)」
――実際、50歳になられてどうですか?
「あまり実感がないんです。僕が思い描いてた50歳って、もうちょっと油ギッシュなイメージがあったんですけど、実際になってみると、30年前と何も気分が変わらないので。ただ物事に対して図々しくなったとは思います。どんな球も受けたり返したり、そういう大胆さは出てきましたね。昔は自分のダメなところが出ちゃうんじゃないかと思って、仕事のオファーを断ってしまうようなことがあったんですけど、今はどんな仕事も自分流に格好よくカスタマイズして、納品するっていう、そういうダイナミズムが出てきたように思います」
――そうした剣さんのモードは、西友のテーマ・ソングになった先行シングル「1107」にも如実に現れていますね。 「そうですね。コマーシャリズムを避けてロックだぜっていうのは簡単ですけど、あえて要求の高いところで勝負して、相手が望んでいる以上のものを作り上げるという。それができたという意味で、自分でも特別な曲なので今回アルバムの1曲目に持ってきたんです」
――この曲からは剣さんからの時代に対するメッセージみたいなものも感じます。
「今は何がどうなっちゃうかわからない時代なので、体温だけは上げとかないとダメだと思うんです。戦後のどさくさを生き抜いた人のようにエネルギッシュにやらないと」
――歌詞のなかでも<大変な世の中で縮こまらないでギラギラしたいぜ>と歌われていますね。
「自分の命は燃焼させるためにあるんだから、できる限りのことをやって天命をまっとうするのが大事だと思うんです。その上で、奥さんでも彼女でも愛人でもいいですけど、せっかく自分を愛してくれてる人がいるんだったら、もうちょっと、ちゃんと見てあげようよ、と。長く連れ添った奥さんでも、何かのキッカケで、やっぱりイイ女だと思える瞬間があると思うんです」
――この曲で歌われてるようなことって、いろんなことに当てはまると思うんですよ。
「そうですね、男女間に限らず。“そこに大切なものがあるのに!”っていうね。消費するっていうのは景気がよくなっていいんだけど、もうちょっと、今そこにあるものを完全燃焼させたり、自分の足元を見ることが重要かなと思います。不完全燃焼のまま前に進むと絶対にエンコすると思う。車と同じでね」
――メッセージ的な部分でいうと、「REVOLUTION POP」という曲で、剣さんが“POP”という言葉を選んでいたことがすごく気になりました。
「“POP”っていう大衆音楽の中で革命的なことをやるっていうことですね。外野でコソコソやるんじゃなくて、あえてド真ん中でやるっていう。
勝新太郎さんとか理想的ですよね。あとはイラストレイターの湯村輝彦さん。マイナーからメジャーまで、来た仕事を全部引き受けて、きっちり自分の色を出すっていうね」
――湯村さんが主宰するフラミンゴスタジオは、それこそギャル雑誌(『Popteen』)の表紙デザインも手掛けていますもんね。
「格好いいですよね。メジャーな場所できっちり持ち味を発揮されていて。マニアから見れば、湯村さんのグリッターなカラーが出てますから。マニアックであることも徹底するとポップになっていくんだと思います」
「達郎さんも、マニアックなことを徹底してやり続けた結果、突き抜けてポピュラリティを得た人ですよね。僕らの場合、インチキ臭さもスパイスにしてるんで、達郎さんとはちょっと違うんですけど(笑)。でも、達郎さんのスタンスにはすごく影響を受けています。とにかく突き抜けるっていうのは大事ことですよね。だから、“こんないいことやってるのに誰も分かってくれない!”なんて言ってちゃ絶対ダメだと思います」
――今回、アルバム1枚通しての印象はいかがですか?
「クレイジーケンバンドの今を無理なく出せているような印象がありますね。前作は気合いが入りすぎちゃったところもあったけど、今回は力の抜け具合もちょうどいいのかなと思います。作品全体もカンファタブルな雰囲気で。インパクトの強さみたいなものは今回あんまり打ち出していないんで」
――そこは、あえてですか。
「ええ。“あざとさ”だけ残ると飽きちゃう……とか言って<仮病>とか強烈な曲もありますけど(笑)。それも狙って入れたわけではなく、ごくごく自然に。そのあたりのチューニングが前は雑だったんですけど、ここにきて、やっとスムーズに調整できるようになってきたかなとは思いますね」
取材・文/望月哲(2010年7月)

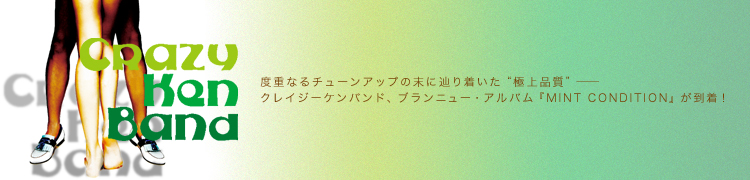
 ――今回のアルバムも例年通り、春先に発情して曲がドバドバできはじめるところからスタートしたんですか?
――今回のアルバムも例年通り、春先に発情して曲がドバドバできはじめるところからスタートしたんですか?

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。