デビュー15周年を迎えても
クレイジーケンバンドは絶好調。前作
『ITALIAN GARDEN』から一年足らずのスパンでの新作にして、通算14枚目のオリジナル・アルバムのタイトルは
『FLYING SAUCER』! 空飛ぶ円盤に乗って地球のいろんなもめ事や、恋人たちの出会いや別れ、サマー・ソングにカー・ソング、エキゾに
小林旭の宇宙ソングと現代社会も時空も駆け抜ける傑作となった。時代の変化に対するメッセージもはらみつつ、今を遊び、未来を楽しみ続けるために必要な歌が今回も濃厚に詰まっている。CKBとして初のチャレンジとなった浅草公会堂での舞台公演『横山剣大座長公演』(2013年5月6日〜9日、浅草公会堂)直前の取材で、その公演への意気込みも語ってもらった。
――新作『FLYING SAUCER』の話に入る前に、前作『ITALIAN GARDEN』も素晴らしいアルバムだったので、まずはその話を剣さんに直接伝えたいなと思っていたんです。タイトルになったイタリアン・ガーデンって、クレイジーケンバンド始まりの地とも言える横浜にあったライヴ・レストランの名前ですよね。あえてそのタイトルを震災後の最初のアルバムに持ってきたことに、みんなの気持ちが沈んでぐらぐらしてる日本で、もう一回遊びというものを原点に戻って考え直そうというメッセージを感じたんです。
横山剣(以下、同) 「そうですね! “夜を取り戻そう”って思いがありました。風営法とかで深夜営業をしなくなった店とか、音楽はかけていいけど踊ったらだめとか、“なんだそれ!”って思ってたんです」
――CKBとして遊びの原点回帰を宣言したような『ITALIAN GARDEN』から一年足らずでリリースされる今回の『FLYING SAUCER』は、さらにそこからまたひとつスケールの大きな視点やスピード感を感じるんです。空飛ぶ円盤に乗って変わってしまった時代や世界をひとっ飛びして見て回るような。
「最初はなんの脈絡もなく直感的に浮かんだ曲名なんですが、未確認飛行物体のように好奇心をくすぐる得体の知れないサウンドということで合点が行きました。で、コンパクト・ディスクという銀色の“円盤”で、いろんな世界、ディメンションにワープするというね。個人的には黒い円盤であるレコードにも想いがあり、それはパッケージに対する思いも含まれてますのでちょうどいい言葉が見つかったなと思ってます」
――そこも踏まえてるんだろうなとは思いました。CD不況と言われて久しい時代ですけど、アナログ・レコードは逆に見直されたりもしていて、また違ったおもしろさも生まれてますけど。
「世界的にみると、日本はまだCDの需要があるし、ミリオン出しちゃう人もいますよね。ニューヨークに行ったときは、もうCDショップ自体がなくなっていて。まだ日本は大きなショップがあるんで、何とかこのへんで喰い止めたい、みたいな願いもありますね」
――それにしてもCKBって、これだけ長く続けて、しかも毎年のように全21曲のボリュームで新作を出していて、それでもまだ自分が未確認飛行物体であることを求めているというのがすごいですよね。ある程度の年齢のベテランになったら、自分を確立して、やりたいことがはっきりしてくるというパターンのほうが多いくらいなのに。
「山手通りじゃないけど、常に工事中みたいなもんです(笑)。まだもっとできるんじゃないか、まだ何か出せるものがあるんじゃないかって思いながらやってますね」
――そういう意識を『FLYING SAUCER』みたいな地球外から来た謎の物体という言葉に定着させる技が、さすがです。
「もともとは、アルバム・タイトルよりもツアー・タイトルを先に決めなくちゃいけなかったんです。そのタイミングでアルバム1曲目に入れた〈円盤〉って曲が出来て、“よし、もうこれでツアー・タイトルは『FLYING SAUCER』だ”って思えたんですね。
『ZERO』(08年)のときもそうだったんですけど、ツアー・タイトルをアルバム・タイトルにしちゃうというパターンは多いですね。タイトルを決めちゃうとそこに全体がつながっていくんです。あとは合う曲を選べばいいと」
――その「円盤」から「地球が一回転する間に」、「太陽 -Sunbeam-」へのアルバム冒頭の流れ、素晴らしいですよね。地球の上では風営法、環境問題とか、戦争とか、領土争いとかいろんな問題があって、それをCKBという空飛ぶ円盤が俯瞰してゆく視点が歌詞にもあって。
「自分のなかのアンビバレンツというか、自分も地球のいろいろな問題に加担してる一人なんじゃないかって思ったりもするんです。大排気量のアメ車に乗って、古いバイクにも乗ってる。でも、新しく子供たちが生まれてくる未来がこういうことじゃまずいなと真剣に悩んだりもする。で、そういった想いをいかにユーモアやグルーヴを損なわず、伝えられるかってことを思ったんですね」
――もちろん今までもCKBには時代とリンクした楽しさやおもしろさを感じる部分はすごくあったんですけど、前作、そして今回の新作と、歌に込められている思いを伝えていくことを、より強く感じるようになってきたんですよ。
「戦争のこととか直接に言ってはいないんですけど、“泣いて笑って怒ったりする日々を展開しながら”(〈地球が一回転する間に〉)とかね、思いをこめたりはしてます。こんな美しい星なのに貧困とかいろんな問題があるなんて、って思うと胸がキューンとする、そんな感じです」
――「太陽 -Sunbeam- 」にも、「こんな世界に誰がした」というフレーズがあります。
「あんまりそういう内省的な歌は作らないんですけど、無理して作ろうとしたんじゃなくて自然に出てきちゃったんで、それはもう抑えられなかったですね」
――剣さんのなかのフォーク・シンガー的な部分がすごく刺激されてるんじゃないかとも思えます。でも、お忙しいのに、作曲のペースが相変わらず旺盛ですごいですよね。
「忙しいほうが結果的に血の巡りがよくなるんで、曲ができますね(笑)。たとえば、2週間休みをとって好きにしていいと言われても、それだと何も出て来ない。じつは2007年の暮れからあんまりレコーダーを使わなくなったんです。曲はみんな頭のなかに鳴ってれば無事ということで。忘れちゃうような曲なら、それは弱いという。イメージできたらそれを直接レコーディング・スタジオでやるという、そんな感じになってますね」
――もちろん、新作に感じるのは、メッセージ性だけじゃなくて、今まで剣さんがしてきたいろんなことがちゃんと一本の木に育っていて、そこから伸びたいろんな枝葉や花を見ている感じも濃厚なんです。エキゾ感も強いですよね。でも、「タイに行きたい」にしても、「路面電車」(07年
『SOUL電波』収録)の頃はモーラムのスタイル一本で押し通していたものが、今回はCKB流のロックンロールが途中にどーんと入ってきて。
「入れました。サンドイッチで(笑)」
――しかも、それがまったく違和感がなくて。
「ありがとうございます。よくノッサンが貸してくれたCDが影響を与えてくれるんです。今回は『Thai Beat A Go-Go』というCDを何年か前に貸してくれたのの影響でしたね。モーラムとかルークトゥンじゃなくて、欧米のガレージパンクとかの要素を取り入れたビートもの。いわゆる“亜モノ”ですね」
――小林旭の「宇宙旅行の渡り鳥」のカヴァーも、CKBオリジナルの和風スペース・エキゾ・ソングだと思う人もいるでしょうね。
「これはよほどの旭ファンでも知らない曲ですよね。僕も
大滝詠一さんが監修されたCD
『アキラ1』『2』『3』『4』のシリーズで初めて知りました(〈宇宙旅行の渡り鳥〉は『アキラ4』に収録)。“ツートト ツートト トツート ツートト”という歌詞を聴いたときに、ぶっとびました。昔、〈宇宙興業〉(『ZERO』収録)っていう宇宙に行ってもチンチロリンをやってるような感じをテーマにした曲を作ったんですが、それを旭さんはとっくにやってたんです(笑)。旭さんは宇宙に行っても別に化学反応は起きない! 渡り鳥のまんまなんだ! そのぶっとさがいいなと思いましたね。だから、聴いたときから、いつかカヴァーしたいなと思ってたんです」
――どういうきっかけでカヴァーすることになったんですか?
「クレイジーケンバンド友の会というファンクラブで〈友の会サミット〉というイベントがあったんですが、そこでお客様から“CKBにカヴァーしてほしい曲”というリクエストを募ったんです。1位は
オリジナル・ラヴの〈接吻〉でした。で、もう一曲、一票しか投票のなかった曲のなかから選ぼうと思って、そしたらそのなかにこの曲があったんです! これはうれしいなと思ってカヴァーして。そのときにやった感じがよくて、これは今のこの感じのまま早く録音しないともったいないなと思ったんで、あんまり煮詰める前にやりました」
――旭さんが宇宙に行っても渡り鳥のまんまだったという認識は、CKBにも通じてるんじゃないですか?
「本当ですか? それはうれしいです。常々そうありたいと思ってるんで」
――世界のいろんなところをテーマにしても、日本中をまわっていても、横浜に戻っても、CKBらしさは変わらない。しかも、CKBというフィルターを通じて、ファンのみんなもいろんな世界に行けるというのが最高です。ところでCKBは今年でデビュー15周年なんですけど、本当に“無事これ名馬”という感じを地で行ってますね。肉体的にも、バンド・メンバーの仲のよさでも。
「前身バンドのCK's時代から数えればもっと年数があるし、廣石さんとはダックテイルズのサポートをやってもらった頃からだから、86年からもうずっとコンビなんです。ノッサンと廣石さんの間柄はもっと古いですからね」
――大人が集ってるバンドなんで、もっとプロ同士のクールな距離感みたいな感じがあるかと思いきや、みなさん、本当に楽屋でも楽しそうなんですよね。
「はたから見たら気持ち悪いくらい仲がいいですよね(笑)。長いあいだにはちょっと距離があった時期もあるんですけど、今はまた特に仲がいいですね。衝突できるくらい仲良くなったというか。お互いに再評価があったりするので。“やっぱりこいつすげえや”みたいなね」
――それも長く続けてきてわかることですよね。
「そうですね」
――その仲のよさがついに芝居の一座として実現したというか、横山剣座長の一座としてCKB総出演の舞台公演『横山剣大座長公演』までやってしまって。
「最初は僕が一番難色を示したんですよ。でも、僕以外のメンバーはみんなお芝居がうまいですよ。ノッサンや廣石さんはいい声だし。あと、ガーチャン(新宮虎児)、(洞口)信也、(河合)わかばさん、みんなうまいですよ。僕は、こういうのが嫌いとかじゃなくて、自分には演技の素質がないと思ったんです。まず、歌詞も覚えられないのに、セリフが覚えられるわけないだろって思ったし(笑)。プロデューサーの
秋元康さんからお話をいただいたときも、今まで映画出演とかも全部断ってきたし、舞台なんてもっとも遠いものだと思ってたんですが、お話してるうちに興奮してきちゃって、気分的に“これ、やったら気持ちいいかも”ってちょっと変態的というか、マゾヒスティックな気分になったんです。それで引き受けて2、3日経って冷静になって、“しまった!”って思ったんですけど、もう取り消せない(笑)。でも、お稽古に入ったら新鮮ですね。やる以上は本気で、自分の持てる力を全部出し切って、終わったらツアーに出て、水を得た魚のように歌えることを楽しみに頑張りたいと思います」
――新宿コマ劇場的な、お芝居+歌謡ショーという二部構成の形態も、剣さんが昔からやりたかったことなんじゃないのかなとも思ったんですが。
「そうなんです。
北島三郎特別公演とかを思い出したら、これってCKBにとって理想的なかたちだとは思いました。それに、バンドがそういうことをやるのは今の日本にないから、うまくいったらかっこいいなと思ったのもひとつの理由でしたね。あと、引き受けるときにふと思ったのは、“そうか、勝新太郎になればいいんだ”って思ったんです。はみだしちゃえばいい。
勝新太郎ならこうするだろうって思えばいい。そしたら、苦手意識が全部弾き飛んで、やる気が出てきました(笑)」
――その感じ方は、最新シングルでもあり、今回のアルバムのラスト・ナンバーでもある
「ま、いいや」につながっていたりもしますか?
「“雑!”という言葉があるんですよ。最初に僕が言ってたいろんなフレーズを、お客さんが歌舞伎の“中村屋!”みたいないいタイミングでかけ声かけてくれたりするんです。そのよく言っていたフレーズに“ま、いいや”も含まれるんですけどね。でもそれは、簡単にあきらめて、何でも曖昧にしとけばいいという“ま、いいか”じゃなくて、ある程度やった上でネガティヴな流れを断ち切って次に進むための“ま、いいや”なんです」
――ちゃんと突き詰める気持ちがあっての「ま、いいや」を、この『FLYING SAUCER』の最後に聴くと、シングルで聴いたときとはまた別の印象も浮かぶんです。地球というか地球人のおもしろおかしさやいざこざとかに対する剣さんなりの強いメッセージのようにも思えるんですよ。
「最後にエンドロール的に持ってきたのも、そういうことだと思います。“ま、いいや”という言葉で、いろいろ突破できることもあるだろうと」
取材・文/松永良平(2013年5月)
![クレイジーケンバンド - フライングソーサー [CD+DVD] [限定] クレイジーケンバンド - フライングソーサー [CD+DVD] [限定]](/image/jacket/large/411303/4113031875.jpg)


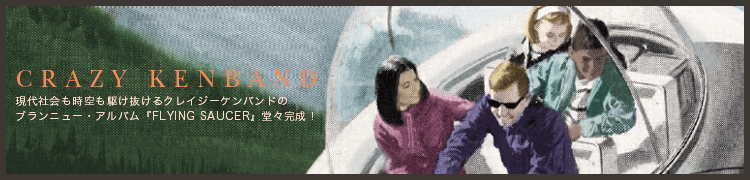




 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。