
近年、ジャズ・オーケストラ(ビッグバンド)作を中心に、数々の大物ジャズ・ミュージシャンが弦楽器を含む編成の作品を発表する動きが活発だ。奇しくも、先日行なわれた第53回グラミー賞で、並み居る大物を押しのけ最優秀新人賞を受賞し注目を集めるベーシスト/ヴォーカリストの
エスペランサの最新作
『チェンバー・ミュージック・ソサイエティ』は、弦楽器を取り入れた室内楽的アンサンブルであるし、ギタリストの
ジョン・スコフィールドのオーケストラ作
『54』でアレンジャーを務めた
ヴィンス・メンドーサが同グラミーの編曲賞を受賞したこともあり、“弦楽とジャズ”の関係はここへきてさらに注目を浴びている。この流れを受け、現在のジャズ界の傾向について考えてみた。
文/青木和富
ビ・バップ革命の延長線上で
時代にコネクトするストリングス
ジャズとクラシックと言うと水と油のような関係のイメージが一般にはある。かつて天才アルト・サックス奏者
チャーリー・パーカーが、ストリングスとの共演(
『エイプリル・イン・パリ』49〜52年録音)を試みたとき、批評家や仲間、ファンからさんざん非難され、ジャズの心を捨て、コマーシャルに走ったなどと言われた。しかし、パーカー自身は、このストリングスとの共演が自慢で、このライヴ・プロジェクトが続けられなくなると、とても悔しがったという。
たしかにパーカーのように信じられないスピードで展開されるリズミックな即興とストリングスは合わないというのが、今でも一般的なイメージだが、パーカーが活躍した1940年代のビ・バップ革命と言われる時代は、単にジャズの演奏スタイルが急進化しただけではなく、ほかにもさまざまな新しい試みが行なわれ、そこにはその後のジャズにつながる重要な新しい音楽の種が蒔かれていた。たとえば
マイルス・デイヴィスが中心となり組織された九重奏団は、“Birth Of The Cool(クールの誕生)”と簡単に言われているが(
『クールの誕生』49〜50年録音)、ここにはそれまでのビッグバンド・ジャズとは違った50年代以後のジャズ・アンサンブルの新しい芽のようなものがたくさんつまっている。その意味では、マイルスよりも
ギル・エヴァンス、
ジョージ・ラッセル、
ジョン・ルイス、
リー・コニッツなどの鬼才たちの存在が重要で、彼らこそその後の枠にとらわれない新しいジャズの流れを作った。
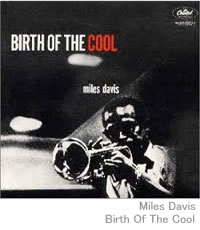
話をストリングスとジャズに戻すと、50年代のバラード演奏の魅力とつながる、たくさんの“ウィズ・ストリングス”ものが制作された。コマーシャルなジャズ・アルバムとも言えるが、それでもそこにはたくさんの才能あるアレンジャーが起用され、それは60年代末のCTIレコードに代表されるイージー・リズニング・ジャズ、さらにはフュージョンの流れへとつながっていく。一方、クラシックとジャズの結合ということで言えば、50年代末のクラシックの
ガンサー・シュラーや
ジョン・ルイスたちが起こしたクラシックともジャズとも違う“サード・ストリーム(第三の流れ)”という運動も忘れられない。この動きは、
エリック・ドルフィーらも巻き込み、さらに
オーネット・コールマンなどの60年代のアヴァンギャルド・ジャズともつながっている。これらはビ・バップ革命の延長にある、革新を続けるジャズの大きな水脈とつながるものとして考えるとわかりやすいだろう。
60年代に入るとスタジオ音楽の世界でも、単なるビッグバンド・ジャズの枠に収まらない大きなアンサンブルとジャズとの連携は、映画音楽を巻き込みながら、新しい土地を開拓する。
ドン・セベスキー、
デイヴ・グルーシンらアレンジャーの出現、そして、
クラウス・オガーマンらの才能は、映画音楽やポップスからロックまで大掛かりな作品の裏方の名職人と言えるだろう。
ところで、こうした大掛かりなアンサンブルは、90年代に入るとデジタル技術の普及によってコンピュータ化され、アコースティックを装いながら、サンプリング音源によるストリングス・サウンドが簡便に作られるようになった。普通に聴いたら区別が付かないほど巧妙になったサウンドは、逆に本当のオーケストラの魅力を再確認することにもなる。単にサウンドを化粧するように使われるのならいいが、しかしそれは音楽の本質の脇にある存在でしかない。ミュージシャンが一堂に会し、響き渡るオーケストラの魅力とは別の世界なのである。結局このような動きは、音楽における演奏家の存在、さらには演奏というものの価値を見直すこと、言い換えれば、音楽はやはり現場で生まれるものということになるのだろう。
気鋭のアレンジャー、ヴィンス・メンドーサと
ジャンルを超えた共演をするオーケストラの動き
現代のオーケストラの動きは、そんな状況を反映している。むろん、それは単なる昔からのアコースティック音楽の繰り返しではない。ジャンルの壁を超えて、これまで積み重ねられたオーケストレーション技術、アイディアをさらに練り上げ、さまざまな顔を持つ世界へと変貌させている。それがオーケストラと聴衆を、もう一度近づけることにもなるはずだ。

こうした流れで、今一番注目を浴びているアレンジャーがヴィンス・メンドーサに違いない。メンドーサは近年オランダの
メトロポール・オルケスト(メトロポール・オーケストラ)の音楽監督を務めており、2010年は、このオケを率いてギタリストのジョン・スコフィールドによる『54』に参加し、大きな話題となった(ちょうど先日のグラミーで、同作品で編曲賞を受賞した)。このオーケストラは、ほかにも
クリス・ミン・ドーキーの『夢風景』(2010年)、
ジョー・ザヴィヌルに捧げた『Fast City A Tribute to Joe Zawinul』(2010年)なども制作している。また、MPB界の重鎮
イヴァン・リンスとの共演(『イヴァン・リンス&メトロポール・オーケストラ』2009年)をはじめ、関わるジャンルも多彩で、むしろこのノンカテゴリーの柔軟性こそが、ヨーロッパの名門ジャズ&ポップス・オーケストラの真骨頂と言える。さらに彼らは新しい才能あるアレンジャーをつねに求めており、そんな動きも新たなオーケストラ文化を切り開く重要な一因となっている。
もうひとつ2010年は、
マーカス・ミラーと
モンテカルロ管弦楽団のアルバム『ナイト・イン・モンテカルロ』も話題だった。このミラーのプロジェクトは、昨年9月の<東京JAZZ>でNHK交響楽団との共演により再現されたが、小編成のアンサンブルでは不可能な圧倒的なサウンドで会場を埋め尽くした。
このようなオーケストラとの共演は、必ずしもすべてが成功とは言えないのは当然である。しかし、ここにはいままで出会ったことのない音楽があり、これこそが過去にとらわれないジャズの未来、可能性を開く鍵となるのだろう。
先日のグラミー賞で、ヴォーカリスト&ベーシストというユニークなパフォーマーのエスペランサ(Esperanza Spalding)が、最優秀新人賞という大賞を受賞した。受賞直後のブルーノート東京での公演は、最新作『チェンバー・ミュージック・ソサイエティ』の再現で、ヴィオラやチェロを使った室内楽的なアンサンブルで、なんとも不思議な世界を聴かせてくれた。すでに弦楽器はクラシックだけの世界ではなく、ジャズにおいてもまったく新しい顔を持った楽器になっている。こういう驚きはこれからも続いていくことだろう。
“弦楽とジャズ”の流れを知る作品厳選5
 ウェス・モンゴメリー
ウェス・モンゴメリー
『ア・デイ・イン・ザ・ライフ』(67年録音) 後にCTIをおこした名プロデューサー、クリード・テイラーがウェスとドン・セベスキーと組んで作った大傑作。ジャズの安易なポップ化と非難もされたが、大人の良質な音楽というのが彼らの主張だった。
 オーネット・コールマン
オーネット・コールマン
『アメリカの空』(72年録音) ジャズと交響楽団との共演で、もっとも衝撃的なアルバム。すべてコールマンの作曲でアンサンブルの浮遊感が小気味よく、いつの間にかはまってしまう。劇場での実際の演奏時間は、アルバム収録時間を超えている。
 マーカス・ミラー フィーチャリング・ラウル・ミドン&ロイ・ハーグローヴ
マーカス・ミラー フィーチャリング・ラウル・ミドン&ロイ・ハーグローヴ
『ナイト・イン・モンテカルロ』(2010年) ミラーとモンテカルロ・フィルとの共演。ロイ・ハーグローヴ、ラウル・ミドンなども参加し、お馴染みのミラー世界が怒涛のサウンドで迫ってくる。荒削りで直感的なアレンジだが、これがまたソウルフル。
 エスペランサ
エスペランサ
『チェンバー・ミュージック・ソサイエティ』(2010年) 歌とベース、そして背後に弦楽奏。どこかアイドル的の雰囲気のエスペランサだが、どっこいその優雅な夢の世界は堅牢かつ広大で奥が深い。新しい想像力は意外な場所から噴出し、時代を突破する。
 ジョン・スコフィールド with メトロポール・オルケスト&ヴィンス・メンドーサ
ジョン・スコフィールド with メトロポール・オルケスト&ヴィンス・メンドーサ
『54』(2010年) “54”とは参加者の総数で、ここで繰り広げられるサウンドの壮大さを暗にほのめかしている。取り上げられているスコフィールドの曲はブルーノート時代の小編成のものだが、メンドーサがこれを大変身させる。まさに魔術師。


 近年、ジャズ・オーケストラ(ビッグバンド)作を中心に、数々の大物ジャズ・ミュージシャンが弦楽器を含む編成の作品を発表する動きが活発だ。奇しくも、先日行なわれた第53回グラミー賞で、並み居る大物を押しのけ最優秀新人賞を受賞し注目を集めるベーシスト/ヴォーカリストのエスペランサの最新作『チェンバー・ミュージック・ソサイエティ』は、弦楽器を取り入れた室内楽的アンサンブルであるし、ギタリストのジョン・スコフィールドのオーケストラ作『54』でアレンジャーを務めたヴィンス・メンドーサが同グラミーの編曲賞を受賞したこともあり、“弦楽とジャズ”の関係はここへきてさらに注目を浴びている。この流れを受け、現在のジャズ界の傾向について考えてみた。
近年、ジャズ・オーケストラ(ビッグバンド)作を中心に、数々の大物ジャズ・ミュージシャンが弦楽器を含む編成の作品を発表する動きが活発だ。奇しくも、先日行なわれた第53回グラミー賞で、並み居る大物を押しのけ最優秀新人賞を受賞し注目を集めるベーシスト/ヴォーカリストのエスペランサの最新作『チェンバー・ミュージック・ソサイエティ』は、弦楽器を取り入れた室内楽的アンサンブルであるし、ギタリストのジョン・スコフィールドのオーケストラ作『54』でアレンジャーを務めたヴィンス・メンドーサが同グラミーの編曲賞を受賞したこともあり、“弦楽とジャズ”の関係はここへきてさらに注目を浴びている。この流れを受け、現在のジャズ界の傾向について考えてみた。 ジャズとクラシックと言うと水と油のような関係のイメージが一般にはある。かつて天才アルト・サックス奏者チャーリー・パーカーが、ストリングスとの共演(『エイプリル・イン・パリ』49〜52年録音)を試みたとき、批評家や仲間、ファンからさんざん非難され、ジャズの心を捨て、コマーシャルに走ったなどと言われた。しかし、パーカー自身は、このストリングスとの共演が自慢で、このライヴ・プロジェクトが続けられなくなると、とても悔しがったという。
ジャズとクラシックと言うと水と油のような関係のイメージが一般にはある。かつて天才アルト・サックス奏者チャーリー・パーカーが、ストリングスとの共演(『エイプリル・イン・パリ』49〜52年録音)を試みたとき、批評家や仲間、ファンからさんざん非難され、ジャズの心を捨て、コマーシャルに走ったなどと言われた。しかし、パーカー自身は、このストリングスとの共演が自慢で、このライヴ・プロジェクトが続けられなくなると、とても悔しがったという。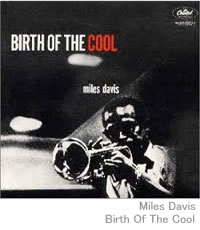 話をストリングスとジャズに戻すと、50年代のバラード演奏の魅力とつながる、たくさんの“ウィズ・ストリングス”ものが制作された。コマーシャルなジャズ・アルバムとも言えるが、それでもそこにはたくさんの才能あるアレンジャーが起用され、それは60年代末のCTIレコードに代表されるイージー・リズニング・ジャズ、さらにはフュージョンの流れへとつながっていく。一方、クラシックとジャズの結合ということで言えば、50年代末のクラシックのガンサー・シュラーやジョン・ルイスたちが起こしたクラシックともジャズとも違う“サード・ストリーム(第三の流れ)”という運動も忘れられない。この動きは、エリック・ドルフィーらも巻き込み、さらにオーネット・コールマンなどの60年代のアヴァンギャルド・ジャズともつながっている。これらはビ・バップ革命の延長にある、革新を続けるジャズの大きな水脈とつながるものとして考えるとわかりやすいだろう。
話をストリングスとジャズに戻すと、50年代のバラード演奏の魅力とつながる、たくさんの“ウィズ・ストリングス”ものが制作された。コマーシャルなジャズ・アルバムとも言えるが、それでもそこにはたくさんの才能あるアレンジャーが起用され、それは60年代末のCTIレコードに代表されるイージー・リズニング・ジャズ、さらにはフュージョンの流れへとつながっていく。一方、クラシックとジャズの結合ということで言えば、50年代末のクラシックのガンサー・シュラーやジョン・ルイスたちが起こしたクラシックともジャズとも違う“サード・ストリーム(第三の流れ)”という運動も忘れられない。この動きは、エリック・ドルフィーらも巻き込み、さらにオーネット・コールマンなどの60年代のアヴァンギャルド・ジャズともつながっている。これらはビ・バップ革命の延長にある、革新を続けるジャズの大きな水脈とつながるものとして考えるとわかりやすいだろう。 現代のオーケストラの動きは、そんな状況を反映している。むろん、それは単なる昔からのアコースティック音楽の繰り返しではない。ジャンルの壁を超えて、これまで積み重ねられたオーケストレーション技術、アイディアをさらに練り上げ、さまざまな顔を持つ世界へと変貌させている。それがオーケストラと聴衆を、もう一度近づけることにもなるはずだ。
現代のオーケストラの動きは、そんな状況を反映している。むろん、それは単なる昔からのアコースティック音楽の繰り返しではない。ジャンルの壁を超えて、これまで積み重ねられたオーケストレーション技術、アイディアをさらに練り上げ、さまざまな顔を持つ世界へと変貌させている。それがオーケストラと聴衆を、もう一度近づけることにもなるはずだ。 こうした流れで、今一番注目を浴びているアレンジャーがヴィンス・メンドーサに違いない。メンドーサは近年オランダのメトロポール・オルケスト(メトロポール・オーケストラ)の音楽監督を務めており、2010年は、このオケを率いてギタリストのジョン・スコフィールドによる『54』に参加し、大きな話題となった(ちょうど先日のグラミーで、同作品で編曲賞を受賞した)。このオーケストラは、ほかにもクリス・ミン・ドーキーの『夢風景』(2010年)、ジョー・ザヴィヌルに捧げた『Fast City A Tribute to Joe Zawinul』(2010年)なども制作している。また、MPB界の重鎮イヴァン・リンスとの共演(『イヴァン・リンス&メトロポール・オーケストラ』2009年)をはじめ、関わるジャンルも多彩で、むしろこのノンカテゴリーの柔軟性こそが、ヨーロッパの名門ジャズ&ポップス・オーケストラの真骨頂と言える。さらに彼らは新しい才能あるアレンジャーをつねに求めており、そんな動きも新たなオーケストラ文化を切り開く重要な一因となっている。
こうした流れで、今一番注目を浴びているアレンジャーがヴィンス・メンドーサに違いない。メンドーサは近年オランダのメトロポール・オルケスト(メトロポール・オーケストラ)の音楽監督を務めており、2010年は、このオケを率いてギタリストのジョン・スコフィールドによる『54』に参加し、大きな話題となった(ちょうど先日のグラミーで、同作品で編曲賞を受賞した)。このオーケストラは、ほかにもクリス・ミン・ドーキーの『夢風景』(2010年)、ジョー・ザヴィヌルに捧げた『Fast City A Tribute to Joe Zawinul』(2010年)なども制作している。また、MPB界の重鎮イヴァン・リンスとの共演(『イヴァン・リンス&メトロポール・オーケストラ』2009年)をはじめ、関わるジャンルも多彩で、むしろこのノンカテゴリーの柔軟性こそが、ヨーロッパの名門ジャズ&ポップス・オーケストラの真骨頂と言える。さらに彼らは新しい才能あるアレンジャーをつねに求めており、そんな動きも新たなオーケストラ文化を切り開く重要な一因となっている。
 ウェス・モンゴメリー
ウェス・モンゴメリー オーネット・コールマン
オーネット・コールマン マーカス・ミラー フィーチャリング・ラウル・ミドン&ロイ・ハーグローヴ
マーカス・ミラー フィーチャリング・ラウル・ミドン&ロイ・ハーグローヴ エスペランサ
エスペランサ ジョン・スコフィールド with メトロポール・オルケスト&ヴィンス・メンドーサ
ジョン・スコフィールド with メトロポール・オルケスト&ヴィンス・メンドーサ
 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。