――まず、グザヴィエとの出会いを教えてもらえますか?
「2013年の〈(韓国)光州ワールド・ミュージック・フェスティヴァル〉で出会いました。このフェスは毎年行なわれていて、ジャズ系の人もいるし、ジャズのなかでもワールド寄りの人もいて。グザヴィエもそういった流れだと思いますが、ソロで来ていたんですね。僕は韓国の打楽器奏者ミン・ヨンチと、オーストラリアのサイモン・バーカーっていうドラマーと、ベーシストのリンダ・オーとで、アジア・オーストラリアの混合バンドで出演しました。グザヴィエが朝食会場で、昨日のステージを観たよと話しかけてきてくれて、そこでいろんな話をして連絡先を交換しました。それが去年になって、これまでやったことがなかったヨーロッパでの公演の計画をたてて、パリとローマとベルリンの3都市を先に決めたんです。フライトもブックして、そのあとに各地のミュージシャンに声をかけました。それでグザヴィエを思いだして連絡したら、トントン拍子でライヴが決まりました」
――グザヴィエの演奏を最初に聴いたのは?
「一緒に演奏するにあたって、作品を聴かせてくれないかということで、自分のアルバムを何作か送って、グザヴィエもリーダー作を送ってくれました。そこで彼の世界に触れたんです。まずわかったのは彼の作曲能力で、とてもキャッチーだなと思いましたし、最初ドラムかなと思っていた演奏が、よく聴いてみたらいろいろな楽器が交じっていることもわかりました。偶然ですが、ここ最近はドラマーや打楽器奏者とデュオでやる機会も多かったので、楽しみだな、と思いました」
――グザヴィエがリーダーのときの音楽は広い意味でのジャズですか?
「ジャズですね。アルバムにはピアノもサックスもダブル・ベースも入っていて、みんなジャズ・ミュージシャンです。でもいわゆるスウィングっていうのはほんの少しで、むしろ最近のヨーロッパの音楽だなと感じました」
――彼の音を聴くと、いろんな種類のパーカッションを使っているようですね。インド的なものもあれば南米的なものもあったりして、クラシックの打楽器的でもあって、いわゆるラテン・パーカッションとは違う人ですね。
「そうですね。ラテンの影響はもちろんあると思いますけど、それにとどまらない、もう死語になりつつありますが、“ワールド・ミュージック”という感じがします」

グザヴィエ・デサンドル・ナヴァル
――今回、ライヴにあたって曲は用意したけどそれはやらなかった、と資料にありますが、それはなぜでしょう?
「事前にこれをやるかもしれないって、グザヴィエの曲を練習しておいたんです。彼にも僕の曲をやってもらおうかなって譜面を用意したのですが、いざリハーサル・スタジオに入って即興で弾き始めたら、彼もいろいろ試し始めて。パーカッションだけでなく、ルーパーやエフェクターも試しだして、その感じがすごくよかったので、結局、ほぼ曲はやらずで、ただ楽しくジャムをしました。会うのはその時が2回目だったので、コーヒーを飲みながら軽く世間話したりして、じゃ明日ねって本番の日を迎えました。この時点で半分以上は即興になるだろうなって予感はありました」
――そのリハで初めて共演したんですね。
「そうです。会場はフランスの有名なジャズ・クラブなので、誰でも出られるものではなく、彼ががんばってブッキングしてくれたようでした。僕はフランスでは無名ですし、彼がクラブのオーナーを説得し、広報活動もやってくれました。彼にとっては、少しプレッシャーなんだなって感じられました。彼は僕のことはCDでしか知らなかったし、なのに本番を即興でやったというのは、ジャムの結果、いちばんお互いがよく出るんじゃないかってことだったんでしょうね。どちらからともなく、そう決まりました」
――このセッションはリリースすることを全然考えてなかったそうですね。
「そもそも僕は録音していることも知りませんでした。これは僕にとってヨーロッパでの初公演だったので、自分としては盛り上がるものもあったんですが、無事に終ってよかったってくらいでした。お客さんもいい反応してくれましたし。演奏したけどドン引きされることもあったかもしれないわけですから(笑)。後から聞いた話ですが、ヨーロッパの観客は、どれだけ有名なアーティストでもその日の演奏がつまらないと途中で帰ってしまう。僕もそうなる可能性があったはずです。でも、自分たちに必要な音楽、演奏を与えてくれるミュージシャンは有名無名に関わらず受け入れてくれるんだと。でも、僕は本番当日になると楽観的になるので、全然緊張しなかったし、むしろ初めての場所で演奏できて楽しいな、と思いながらやれました」
――演奏しているときの客席からのバイブレーションはどうでしたか?
「すごく感じましたね。ことあるごとに反応してくれました。ローマでは演奏後にサイン会をやったのですが、感激して泣いている人もいました。やはり西洋音楽が生まれた土地ですから、音楽への接し方が日本ともアメリカとも、自分がこれまでに演奏してきたどの国とも違っていて。(音楽は)我々のものって感覚が当たり前にあって、人生に必要なものだって認識があるんだなと。いい時間を提供したミュージシャンには、こちらがありがたいくらいに感謝される。だから演奏前と後ではまったく態度が違いました(笑)。演奏した後はニコニコと話しかけてきてくれて」
――そういう意味ではやりがいはあるけど、怖いですね。
「怖いですけど、オーストラリアに居た頃もそうだったなと思い出しました。ポップスは違うかもしれませんが、ジャズ・クラブでみんなが何を聴いているかといえば、その人の音楽であって、いま起きたばかりみたいな人が何を着て演奏しようと、どうでもいいってところがあるので。昨日もYouTubeで僕の好きなピアニストの映像を観たのですがヨレヨレのTシャツで演奏していました(笑)。ヨーロッパのミュージシャンもオーストラリアもそうですが、自分の音楽がジャズかジャズでないか、っていう次元では考えていない。アメリカはアメリカで別の縛りというか、ジャズのトラディションも負っていることがあるので、また違っていると思いますが」
――グザヴィエは音楽に対して幅広い見方をしているミュージシャンだと思いますか?
「幅広いけれど、あまりアヴァンギャルドという発想はなく、やはりパーカッショニストなので基本的にどんなときもグルーヴがある人だと思います。僕はそれをちょっと壊したがるタイプなのですが、グザヴィエじゃない相手だとふたりで混沌としてしまう。それも嫌いじゃないんですが、今回はどこかで何かが保たれている感じがあって、それは彼に作曲力があるので、全体を大きく見ていたのかなと。よくありがちな、ピアニストがアイディアを出して、パーカッションがそれに乗っかるのではなく、彼も僕にアイディアを出していて、そういう意味ではちゃんとしたコラボになっているなって、音源を聴きなおして思いました」
――このアルバムは、全部即興だと知らなければ、ひじょうに美しい曲を弾いてるんだな、とリスナーは思うのではないかしら。その場の瞬間で決まっていった演奏だと思うんですが、ごく自然に流れている感じがします。
「10年に1回出るかどうかっていう演奏です。アルバムにしようと思えたのも、これは本当に曲になっていると思えたからです。僕は普段のライヴで、ハードコアでつかみどころのない演奏もやったりするけど、それをリリースするとなると難しいところはありますよね。そもそもリリースはなぜするのかというと、やはり聴いてほしいから。自分がいいと思う音楽を共有して喜んでもらえたら最高じゃないですか。だから客観的になることも必要だと最近は思います。だからといってアンケートをとって“何がいいですか?”って聞くのもちょっと違う(笑)。でも、これは自然にできた流れだったので、ぜひみなさんと共有したいと思いました」
――ソロでピアノを弾くときとデュオではまったく違うと思いますが、その違いはどういうところにありますか?
「彼も僕もソロ・パフォーマンスを長いことやっているので、その経験がデュオに活きたのかな、と思います。ソロで2時間ステージに上がるのは、まあできるけど、満足いく内容にするのはたいへんです。そのソロ・アーティストとしての経験があるから、いつひとりになっても大丈夫だと思うことが重要なのかもしれません。あと、インプロでいちばん大事なのは相手の音を聴くこと。相手が何を言おうとしているかを察することができるかどうかです。それが誤解だったとしても、受け止めて違うことを提示できるか、もしくは誤解したものに乗ってみるとか。瞬間の細かいところと同時に全体像が見えていればいいんです。ここはこう行っても収拾つけることができるはずだとか、ここはこう行ったほうがいいとか、頭で考えるのではなく身体で覚えている人じゃないとできない。だから、ひとりでやったことがある人とは楽なんです。グザヴィエは、パーカッショニストとしてだけでなく音楽家としてすごい人だと思います。いろんな経験をしてきたことが、一緒に演奏すればわかりました」
――一緒に過ごした時間がそんなにないのに、その人の音楽的人生がリアルタイムでわかるってすごいですね。
「わかった気になっているだけかもしれないですが。演奏が終った後の打ち解け方は、始まる前とは違いました。お互いが出すものを出して、それが成功した時はなんともいえない世界がありますね。逆に、いくら気があっても演奏が終って気まずくなることもあるので(笑)」
――プリミティヴな質問ですが、曲を終えるのはどういう判断するのでしょうか? 自然と終る?
「それは相手によりますね。僕らは演奏しながら作曲したんでしょうね。ここらへんで終わりどころだなってところで。お互い、ちょっと早い・遅いと思ったところもあったと思いますが、間合いというか空気ですね」
――こちらが終ろうと思っても、終らせてもらえないこともあると。
「今、終っておけばよかったってときもあります(笑)。あとはオーディエンスの空気感ですね。それがライヴの面白いところです。なかには意表をつかれることもありますが、この夜はだいたいが自然でしたね」
――アルバムに収録されているのはこの日のステージすべてですか?
「アンコール以外全部です。MCはカットしましたが、曲順もそのままです」
――ハクエイさんは、音楽的な懐が深くて幅が広いピアニストだと思います。即興をやるとき、自分が持ってるそうした蓄積をいかに引き出すかっていうことがあると思いますが、今作ではうまくいきましたか?
「今回、いちばん気に入っているのは自分がオーバープレイしていないことです。そうしがちなんですよ(笑)。オーバープレイしてしまうときは、不安だったりうまくいってなかったりするとき。今回はいろんな準備をグザヴィエに任せていたので、ピアニスト的なエゴが最小限になっていて、なによりもコンサートをいいものにしたいという気持ちがあったと思います。ピアニストとして僕よりうまい人は山ほどいるので、そこで勝負はしないってわかっているのに、いざ弾き始めると悪い癖が出たりすることもたくさんある。でも、この時は知らない土地で、自分もノーバディになれた。お客さんは僕のことを知らないし、自分を証明しなきゃって気がなくて。それよりも楽しくて、いいコンサートにしたいという、それだけでした。インプロはそこが醍醐味で、そう狙ってやれることではないので、よかったと思いました」
――ほかのドラマーとやることも多いと思いますが、グザヴィエとはやはり別の感じですか?
「彼はジャズ・ドラマーではないので、スウィング・ビートが基本になっているドラマーとはアプローチがまったく違います。僕はこれを聴いて
EL&P(エマーソン・レイク&パーマー)みたいだなって思いました。展開が『
展覧会の絵』のような、中学生くらいに聴いていたものが出てきたのかもしれません。何がどうだって具体的なことはなくてただ印象なのですが。彼のドラムやパーカッションから聞こえてくるものが、ジャズかどうかは置いておいて、なじみのあるものだったので、その結果かな。意地の張り合いみたいな、誰が最初に“参りました”って演奏するかを競う道場のような感じじゃなく、そういう意味でお互いにリアルタイムで作曲していたのだと思います」
――パリで録音したって知ってるから思うのかもしれませんが、サウンドが“ヨーロッパ”な感じがして面白いなと思いました。日本でやったらまた違うかもしれませんね。
「国が変わると全然違いますね。ベルリンでもインプロをやりましたが、これと真逆な地獄のようなインプロで(笑)。でもベルリンのオーディエンスはすごかったです。自分でも楽しみにしていたのですが、アヴァンギャルドが生まれた土地で、ジャズにしろロックにしろ、そんなシーンがあるところなので気合入れてやりました。哲学者のようなお客さんがじっと聴いてて帰らないという(笑)」
――ベルリンはハードだと(笑)。
「やはり人生というか、生活の一部なのでしょうね。音楽に何を求めるかというのがそれぞれあると思いますが、音がそうなるっていうのは不思議ですよ……。パリで録音したこのCDは、マスタリングしたら、さらに音がヨーロッパになったんです」
――マスタリングはスウェーデンのスタジオでしたっけ。
「ラーシュ・ニルソンという、グザヴィエが紹介してくれたエンジニアなのですが、パリの地中海的な音に北欧の研ぎ澄まされたキラリと光る音が入ってきて、けっこう印象が変わりました」
――グザヴィエとの共演は今後も予定していますか?
「公演に向けて動き始めています。もともと彼がこの音源を録音していたのは、ヨーロッパのフェス関係者に聴かせるためだったんです」
――これはフランスでもリリースするんですか?
「いま調整しています。これがきっかけで広がるといいですね。まだ行ったことのないところにどんどん行きたいと思います。とくにインプロはジャンルを問わないので、どこに行っても鍵盤があればできると思ったら、とても楽しみになりました」
――音楽は世界共通言語だから。
「ほんとにそうですね。今回は、そういえばそうだったなってことがたくさんありました。仕事だけじゃなくって、ひさしぶりに学生気分に戻ったような一人旅で、さんざん羽も伸ばしてきました(笑)」
――さて、この後の活動はどんなことを?
「もう1枚ソロを録りたいと思っています。トライソニークも焦らずいいものができたらアルバムにしたいです。ソロは定期的にやっていきたいですね。あとは、まだやってないことといったら、大きめのアンサンブルをやってみたい。ピアノを弾いてるどころじゃなくなるかもしれませんが。ラージ・アンサンブルがやれるなら、インプロをたくさん入れ込んだものがやれるといいなと思います。だからといってカオスありきじゃなくて、自然発生的に譜面から離れていけることが共有できるミュージシャンとじゃないと難しいですね。いつどういうタイミングで離れても大丈夫という関係で。ビッグバンド編成で、ここからここはソロだから自由にやっていいってところ以外でも、そうなると面白いなと。あまり売れないと思いますが(笑)」
取材・文/村井康司(2019年3月)

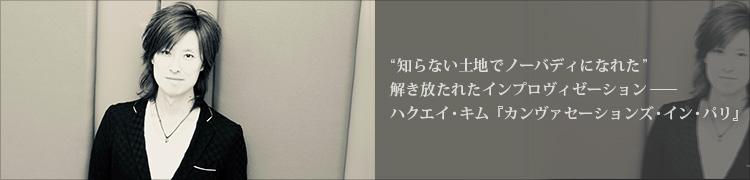






 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。