今年6月に行なわれた<Hostess Club Weekender>の第2回目に出演したアクトの中で、個人的に最も楽しみにしていたのが初来日となる
ヒア・ウィ・ゴー・マジック(Here We Go Magic) だ。もともとソロで活動していた
ルーク・テンプル(Luke Temple) のベッドルーム・プロジェクトとして2009年にスタート。構築的でストイック、かつリズミックで情熱的という、両極端な側面を持つ彼らは決して大きな話題になることはなかったものの、これまでに耳の肥えたリスナーの間で確かな評価を得てきた。言わば、ミニマルな前衛音楽と西アフリカのフォークとが手を結んだようなポップ・ミュージック、といった感覚の彼らの作品は、曲者が揃ったブルックリン勢の中でもとりわけ静かな個性を放っていると言っていいだろう。
レディオヘッド などでお馴染みの
ナイジェル・ゴドリッチ がプロデュースしたニュー・アルバム
『ア・ディファレント・シップ』 でブレイクした彼らから、ルーク・テンプルとノッポのドラマー、ピーター・ヘイルにバンドの哲学について聞いた。
――ルークはソロ時代からかなりリズムに対して自覚的に攻めているシンガー・ソングライターだなと思っていました。このヒア・ウィ・ゴー・マジックでもすごくリズミックなギターや演奏が大きなカギになっている印象です。
ルーク・テンプル(vo) 「そう。少なくとも僕は最初からそういう音楽に影響されてきた。特にギター・プレイに関してはメロディ楽器としてではなくパーカッシヴに弾くスタイルが好きでね。たとえば
キャプテン・ビーフハート とかね。と同時に、
スティーヴ・ライヒ のようなミニマルな音で空間を作り上げていく音楽家の作品にもシンパシーを感じてきたんだ。で、それらを一つにした音楽ができないものかとずっと思索してきた。あとは、西アフリカの音楽とかもかなり聴き込んだね」
ルーク 「そうそうそう。そのあたりが僕にとって最初のアフリカ音楽。高校の頃に初めて聴いて衝撃を受けたよ。パーカッシヴなのにメロウでブルージー。そうそう、僕は日本の琴にも影響を受けたし、スパニッシュ・ギターの奏法も研究したし……僕は世界中の弦楽器に興味があるんだ。今の僕自身やこのヒア・ウィ・ゴー・マジックの基本になっているのは、そういう楽器や音色、奏法に対する好奇心なんだと思うよ」
ピーター・ヘイル(ds) 「ルークに限らず、僕ら自身もまさにそういう音楽性に裏打ちされている。西アフリカの音楽は本当に洗練されているからね」
――ええ、ダーティー・プロジェクターズ のデイヴ・ロングストレスも「マリの音楽の持つリズム感を一つの参考にして曲を作っていた時代がある」と話してくれたことがあります。 ピーター 「デイヴがそう言ったのかい? なるほどね。たしかにブルックリンのミュージシャン連中ではアフリカ音楽は人気だよ」
ルーク 「一つにはブルックリンで活動しているようなバンドの多くは、欧米スタイルのポップ・ミュージックに対してある種の距離を置いているところがある。音楽の構造とかスタイルだけじゃなくて、在り方そのものにも疑問を感じているんじゃないかな」
――たしかにヒア・ウィ・ゴー・マジックは、ルークというすでにソロとして活動していた、ある種のポップ・アイコンを軸にスタートしたわけですが、不思議なことに作家性に寄り過ぎていないというか、作り手のエゴのようなものをあまり持たないようにしていると感じます。実際、ルークたちは欧米スタイルのロックやポップスがこれまで携えていたヒロイズムに対してどのような意識を持っているのでしょうか?
ルーク 「ああ、そこが欧米のポップ・ミュージックと西アフリカなどの音楽との根本的な違いなんじゃないかと思うね。欧米の音楽はある意味、インディヴィジュアルなものだと思うんだ。つまり個の音楽。でもアフリカの音楽は……まあ、アフリカに限ったことじゃないけど、ある種のコミュニティの中から誕生したものが圧倒的だし、常にそうした中に成立している。で、僕はアフリカの音楽のそうしたコミュニズムにも強く影響を受けている。僕個人のメッセージで音楽を作っていくことももちろんいいことだけど、少なくともこのバンドではコミュニティの上に成立しているような音楽を作りたいんだ」
ピーター 「でも、欧米のポップスにも相応のコミュニティがあるじゃない?」
ルーク 「その通り。でも、それはインディ・ロックという極小のサークルだ。僕はそういう中にいたくないんだよ。ブルックリンにもそういう連中はいるし、結局場所がブルックリンってだけで、やっていることに何らクリエイティヴィティがないバンドも多くいるさ。でも、それはスタイルの問題じゃなくて、意識の問題じゃないかと思うんだ。それじゃダメなんだよ!」
――ただ、あなた方の音楽には、アフリカ音楽的コミュニズムを参照していこうとする一方で、欧米スタイルのロックやポップ・ミュージックのレガシーを受け継いでいこうという意志も一方で感じられます。そのあたりはジレンマなのですか? それとも自然に交配させているのでしょうか?
ピーター 「そうだね。たとえばロック・バンドのフォルムをそのまま使用しているのももちろんそうだし、メロディ感覚もそうかもしれない」
ルーク 「それは正直あるよ。むしろ、少なくともアメリカの音楽の歴史をしっかり享受していこうという思いがないと、新しいことだってできないと思う。僕らがこのバンドでずっと目指していたことはまさにそこだからね」
――では、新作をナイジェル・ゴドリッチがプロデュースしてこれまでになく大きな話題になりましたが、このタイミングで急激に人気を集めたことに対してフェアじゃないなと思うことはありますか?
ルーク 「まさか! 全然そんなこと思っていないよ。ナイジェルには感謝しているし、この作品をきっかけに一人でも僕らのような存在を知ってもらえるならこんなに嬉しいことはない。それこそ、僕らはレディオヘッドみたいに強力なフロントマンがいないバンドだから、音楽性のユニークさをまずは知ってもらわないとね」
取材・文/岡村詩野(2012年6月)
VIDEO

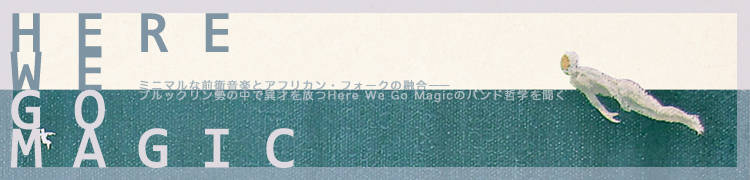




 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。