クラブ・ジャズ系バンドのquasimode(クオシモード)やソロで活動してきたジャズ・ピアニストの平戸祐介が、新レーベルのGENESIS RECORDINGSを立ち上げた。その第1弾となるのが、平戸とシンガーの田中裕梨とのコラボ・シングル「He Loves You」だ。田中はジャズ・バンドのBLU-SWINGのヴォーカリストであり、近年はソロ・シンガーとしてシティ・ポップのカヴァー作『CITY LIGHTS』シリーズでも知られる人で、彼女のエレガントで気品にあふれた歌声と、平戸によるラテン・ファンク的なグルーヴとが見事に溶け合い、都会的で洗練されたムードが色濃く漂うシティ・ポップ的な逸品といえる。その平戸に、新レーベルと今回のシングルを中心に話を聞いた。
――新レーベルのGENESIS RECORDINGSが発足しました。なにかきっかけはあったのでしょうか。
「僕は長崎出身で、父親が以前ジャズ喫茶を経営していて、母親がピアノの先生だったんです。だから幼少の頃からピアノとジャズが身近にあって。デビュー前から長崎市内で演奏会をしたりして、その頃から地元のみなさんに応援してもらって、本当に良くしていただいたんです。自分が若い頃、良くしてもらった感謝というか恩返しを、そろそろやっていかなきゃいけない年になったんじゃないかなと思って。それでこのレーベルで、才能ある若い人をピックアップして、少しでも世に出るようなお手伝いができたらいいなというところから発足させたんです。名称が“GENESIS”=“新世紀”ということで、これから新しい世紀を作るアーティストを輩出していきたいという思いから、この名前を付けました」
――以前からそういうレーベルをやりたかったんですか。
「40歳くらいの頃から、長崎に恩返しがしたいという気持ちがずっとあったんです。ただ、恩返しをするには、それなりに経験も必要だし、力もつけなきゃいけないというところで、この10年間さまざまな取り組みをしてきました。その一環としてFM長崎の番組(2015年スタートの『MUSIC HORIZON』)もあって、今8年目です。ですのでFM長崎で番組を始めたのと、quasimodeの活動休止が同じ頃で、そこからなんですよね。自分なりに故郷に恩返しをするというか、基本を見るというか。そういう時期だったんです。あと、もちろんいろいろ大変だったんですけど、今しかないと思ったのもあります。ここを逃しちゃうと、いろいろ機を失っちゃうかなと」

平戸祐介、田中裕梨

秋元勇気、平戸祐介、田中裕梨、arvin homa aya
――では、平戸さんの個人レーベルというより、新しい人を世に出していくレーベル、という意味合いが強いのでしょうか。
「そうです。今回は第1弾ということで僕の名前を出していますけど、基本的には自分が出たいというよりは、新しい人たちを紹介するレーベルになっていきたいんです。田中裕梨さんは有名なシンガーですけど、それはレーベルを知っていただくためという意味もあって。まずはしっかりと広げるために出して、それ以降は新しいアーティストをフィーチャリングできるようになればいいなと思っています。新しいアーティストたちも“平戸に乗っかればなにかできる”と思ってくれるようなレーベルにしたいですね。それと今回は、コンセプト感のあるジャケット制作及びアートワーク全般を担当してくれた野村匡志君、そして今回の収録された2曲でギター、録音、ミックス、マスタリングとめまぐるしい制作環境でもしっかり異才を放ってくれた秋元勇気君にも賛辞を送りたいと思います」
――田中裕梨さんとは以前からの付き合いなのでしょうか。
「そうですね。quasimodeとBLU-SWINGって、ジャンル的にいうとクラブ・ジャズで、演奏する場所だったりイベントだったりで、よくご一緒させていただいていたんです。僕の番組にも何度かご出演していただいて、そこで親交を深めたのも大きいですね」
――彼女のヴォーカルについてはどういう印象がありましたか。
「僕はオーセンティックなジャズと、クラブ系のジャズとの両輪で活動しているんですけど、彼女はオーソドックスなジャズにない透明感を持っているんです。そこにすごく惹かれます。ジャズ独特の節回しではなく、彼女独自の節回しというか、それを持っている。それで裕梨さんにお話しして、快諾していただいて」
――「He Loves You」はフュージョン・バンドのSeawindが76年に出した曲ですけど、この曲を選んだのは?
「以前から好きだった曲なんです。最初は僕が作ったオリジナルを歌ってもらおうと思っていたんですけど、裕梨さんにお願いしようとなった時に、たまたま僕が〈He Loves You〉を採譜していたので、この曲はすごく合うかなって思って、提案して“どうですか”と言ったら、“なかなか難しい曲ですけど、チャレンジしてみます!”と。そういうところで合ったんですよね。彼女はシティ・ポップの『City Lights』のシリーズを出しているじゃないですか。だったら〈He Loves You〉の感じに合うかなと思って。そういう流れでしたね」
――田中さんは既存の曲を自分のものにして歌うセンスに長けていますよね。
「そうですね。自分の色で料理するのが非常に上手です。やっぱり彼女の音楽性にとても合っていたなあ、よかったなあって、レコーディングが終わって安堵感にあふれる感じがありました。それとバッキング・ヴォーカルのarvin homa ayaさんは、レコーディング当初は参加予定ではなかったんですが、急遽お願いしたにもかかわらず快諾していただき、素晴らしいバッキング・ヴォーカルを披露してもらいました。あの部分は曲の心臓部分でもあるので本当にありがたかったです」
――サウンド的にはラテンのニュアンスが入ったファンキーなダンス・ナンバーで、やっぱりラテンは好きなんですか。
「大好きです。93年から99年までニューヨークにいたんですけど、ハーレムに住んでいて、ヒスパニック・ハーレムのエリアにも近かったので、まわりがラテンを朝から晩まで聴いているような環境だったんです。quasimodeでメンバーにパーカッションを入れていたのも、クラブ・ミュージックもラテン・ミュージックも密接しているという理由からなんです」
――quasimodeはラテンの要素が多分にあったわけですけど、ソロになってからあまりやられていなかったので、今回は久々のラテンだと思ったんです。
「今回作ってみて、意外とラテンになっているなというところはありましたね。ただ、自分ではそこまでラテンにしようとは思っていなかったんですけど、できあがってみて、非常にラテン・タッチが感じられるようなナンバーになりました」
――演奏そのものはすごくシンプルな編成で、とくに石川勇人さんのパーカッションが効いていますね。
「やっぱりパーカッションが入ることでリズムも分厚くなりますし、より勢いが出ます。石川君は、前作の『Higher & Higher』から叩いてくださっている、若手ではピカイチのパーカッション奏者です。今回も素晴らしい演奏をしていただきました」
――平戸さんの近年のソロ・アルバムは、『Tower of Touch』(2019年)や『Higher & Higher』で、ジャム・セッション感の強いファンキーな作風が続いていましたよね。この曲もセッションっぽいラフな感じがあって、そういうモードが持続しているように思えましたけど、どうですか。
「そうですね。おっしゃるように、『Tower of Touch』『Higher & Higher』はセッションが基本になっていて、4つか5つの単純なコード進行で、そこからいかに参加メンバー全員が想像力を膨らませて曲にしていくか、ということにチャレンジしようと思っていました。quasimodeではやってきていなかったので。だから今回もその流れですよね」
――カップリングの「Collision in Blue」はインスト曲で、こちらは得意のファンク・ナンバーですね。
「これも、前2作からの流れと同じですね。基本のコード進行があって、それをどう広げていくかという。BPMは今までにない速さで、けっこう大変だったんですよ(笑)。ファンク系で攻められるギリギリのテンポで攻めてみた感じです」
――じゃあこれはチャレンジングな曲ということですか。
「そうですね。コード進行に関しても一小節に2個入っているんで。そういう意味ではけっこうチャレンジングです」
――そういうアッパーな曲ではあるんですけど、平戸さんのエレピ・プレイはすごくクールに聞こえるんですよね。
「そうですね。これは自分の演奏の課題でもあるんですけど、力いっぱい演奏しないとというところ。ビルボードやブルーノートで海外のアーティストの演奏を見ると、あきらかにめちゃくちゃ熱い演奏をしているんだけど、この人絶対まだ50%くらいしか力を出していないなと思うんですよね。もちろん、真剣に演奏をしているんですが、プレイにすごく余裕があるんです。だから50%くらいの熱でやっていて、残りの50%はたとえばメンバーへのディレクションだったり、観客がどういうものを求めているかをキャッチする能力だったり、そういう事に取っているのかなって思うんです。それは演奏において非常に大事なことで、とくに今回演奏しているジャズファンクに関しては、どれだけ後ろにタメを作れるかが勝負になってくるんです。それがファンクネスっていうか、重いグルーヴにつながっていくので。やっぱり軽くなったらダメじゃないですか、ジャズ・ファンクって。それを作るためには、どれだけ拍に対して前のめりじゃなくて後ろにタメられるかがポイントになってくる。それにチャレンジしたい。だから僕、常に考えているんですよ。すごく熱い演奏をしているんだけど、冷ややかっていう」
――じゃあこの曲も、クールに聞こえますけど、マインド的には熱かったりするんですか。
「めちゃくちゃ熱いですよ。聞こえ方はクールなんですけど、中身はめちゃくちゃ熱かったです。でも熱い自分と冷めた自分がちゃんと同居できるように。このレコーディングだけじゃなくて、ライヴする時も取り組んでいることですね」
――今の平戸さんは、先ほど話したような前2作のセッション感のあるファンキーなモードというのが続いていると思うんですが、今やりたい音楽というのもそういう感じなんですか。
「今はクラシック的なものもやりたくて。クラシックとジャズを混ぜたようなもの、弦楽器のカルテットとかがいて、ジャズとクラシックを行き来するようなものも作りたいなと思っているんです。コロナ禍から、自分の指癖とかを修正しようと思って、ピアノでクラシックを練習していたんです。ガーシュウィンの〈ラプソディ・イン・ブルー〉とかを弾いていたりして、そういう過程でクラシック的なものもやりたいな、というのが沸々と湧いてきて。どういう作品になるかわからないですけど、そういう作品を作りたいな、という漠然とした思いは出てきています」
――平戸さんの活動はquasimodeから始まって、ソロになって、バンドもピアノ・ソロもやって、音楽的にもジャズからファンク、ラテン、ヒップホップなど、ひととおりやったようにも思えるんですけど、さらにやりたいことがあるということですか。
「いつも頭の中は交通渋滞です(笑)。やりたいことは、これからまたたくさん湧いてくるんじゃないかなと思います、ただ自分には正直に音をこれからも紡いでいきたいと思います」
取材・文/小山 守
撮影/持田 薫

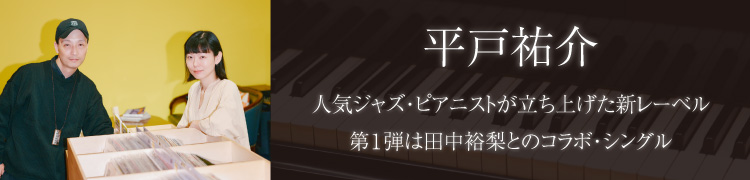









 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。