シュトゥットガルト、ザルツブルクで学んだピアニスト、
今川裕代。ブラームス、サレルノ、A.ルビンシテイン、シューベルトなどの国際コンクールすべてに上位入賞を果たした実力派である。
これまで海外を拠点に活動を展開していたために、日本では一部の幸運な方だけが、たとえば2008年のラ・フォル・ジュルネのミュージック・キオスクや、来日した
アルメニア・フィルのソリストとして、また昨年11月のサントリーホールでのリサイタルなどで彼女の実演を聴くことができたくらいだった。しかし、今年初夏から日本での活動も本格的にスタートし、早くも7、8月には
NHK交響楽団や
新日本フィルと共演。聴衆はもとよりオーケストラのプレイヤーからも、その確かなテクニックと音楽性で賞賛を集めていた。2枚目となるアルバムのリリースと、東京でのリサイタルももう間もなくだ。

――つい最近までザルツブルクにお住まいだったんですよね。
今川裕代(以下、同)「1998年から暮らしはじめ、2002年に大学院を修了しました。卒業してからしばらくは研究生として残っていたんですけれども、その後は芸術家ヴィザを取得しました」
――最初はシュトゥットガルトに留学されていたそうですね。
「アンドレ・マルシャン先生に師事したからです。留学を決めてから、誰につこうかと考えていた時に、ちょうどマルシャン先生が日本にいらっしゃったのでレッスンを受けてみたら、先生がぜひ来なさいとおっしゃってくださったんです」
――それが4年間。その後にザルツブルクのモーツァルテウムでハンス・ライグラフにつかれました。
「2年目くらいから、いずれまた別の土地で、別の先生のもとで勉強したいという気持ちがあったんです。マルシャン先生に相談したところ、ライグラフ先生か、
レオン・フライシャー氏だったらよいと許されて(笑)。それでダルムシュタットの講習会にいらしていたライグラフ先生にお伺いを立てたところ、先生もいいですよって」
――両先生の教え方はどのように異なるんですか?
「奏法からすべてまったく違いました(笑)。マルシャン先生は、まだ私が若かったので、ピアノ以外についても、ドイツの文学や社会についてなど、いろいろなことを熱心に説明してくださいました。また昔の巨匠ピアニストの演奏について情報をたくさん持っていらっしゃったので、そこから私はいろいろな演奏を聴くようになりました。レッスンではよく弾いてくださいましたし、とにかくどんどん新しい曲を勉強しなさい、舞台を踏みなさい、室内楽をやりなさいって感じでしたね。ライグラフ先生に変わってからは、姿勢からすべてやり直し(笑)で、ライグラフ・メソードもやり……」
――マルシャンは、また全然違うメソードなんですよね。
「はい、マルシャン先生は椅子はまず完全に低い状態で……グールドのような(笑)。腕はあまり使わない奏法でしたね」
「ヘブラー先生はレッスンはされないんです。ですが、演奏を聴いていただく機会は何回かありました。いちばん最初に聴いていただいたのが、2002年1月で、その時の出会いがきっかけとなって、先生の75歳と80歳のご自宅での誕生パーティで演奏したり、室内楽の演奏会にもいらしてくださったり……。彼女と出会ったことで、自分の演奏に対する責任や使命感のような意識が強くなったような気がします」
――今後はどのような音楽家、ピアニストを目指してらっしゃいますか?
「もちろん夢や希望を与えられるような演奏をしたいといった気持ちはあります。でもやはりヨーロッパの香りだったり、音の色や香り、その雰囲気などを伝えられるような演奏家になりたい。また、楽しいとか苦しいとか、そういう感情すらも超えたスケールの大きな音楽を表現したいと願っています」
――そのほかに、“日本全国の公共ホールにあるピアノを全部制覇する”という壮大な計画を目標に挙げてらっしゃいますよね(笑)。公共ホールにあるピアノの数って……。
「3,000くらいありますよね」(爆笑)
――今、いくつくらい制覇したんですか?
「まだ数える程度です。1割にも届いていません(笑)。それにしても本当に驚いたのは、日本のホールはどんどんピアノを買い替えますよね。そのために古いピアノが眠っている場合があるんです。でも、古い楽器は独特の魅力を持っていると思うんですよ。上手にオーバーホールすれば、新しいピアノ以上によい楽器になると思うので、何かそういうプロジェクトができないかなと思ったのがきっかけです」
「できるだけ多くの方に聴いていただきたいという思いもあったので、あえて有名な、親しみがある曲ばかりを選びました。収録順は苦労して考えました。まずドビュッシーで始めたいという思いがあり、その後いきなりベートーヴェンだとちょっと重いのでショパンにしました。ショパンの抒情性は、ドビュッシーの後にもあまり抵抗なく聴いていただけるんじゃないかと思ったので」
――いよいよこの11月に新譜『
喜びの島』がリリースされます。
「いつかオール・ドビュッシーでレコーディングをしたいという気持ちがありました。昔から私にとってドビュッシーは特別な作曲家なんです。11、12歳くらいの頃に初めて弾いた時に、それまでまったく聴いたことがなかったにもかかわらず、自分は何か、もう知っているような感覚に陥りました。彼の作品ではピアノとの一体感が強く得られるんです。以来、その音色だとか音質、ほかの作曲家とは違う独特に洗練された優美な世界にとても魅かれてきました。ライグラフ先生のもとで音色に関して学んだことによって、いっそうドビュッシーの世界が見えてきたように思います」
――最初に触れたのはどの曲だったんですか?
「『夢』です」
――アルバムにこの曲を収録したというのは、ドビュッシーとの最初の出会いの思い出というわけなんですね。そのほかにも『映像』第1集と第2集、さらに『忘れられた映像』『2つのアラベスク』などが収められています。
「『忘れられた映像』はタイトルも素敵ですし、たとえば2曲目は『ピアノのために』の〈サラバンド〉、3曲目もモチーフが『版画』の〈雨の庭〉に使われていたり、なかなか面白い曲です。今回のアルバムは、ドビュッシーの瞑想的な部分、そういうところでリラックスしていただければ嬉しいですね」
――11月3日にはアルバム・リリースに合わせてサントリーホールでのリサイタルもあります。プログラムはショパンとドビュッシー。
「ショパンはメモリアル・イヤーでもありますし、ドビュッシーとショパンはとても合うと思います」
――曲順は交互に配置されています。
「これもずいぶん迷ったのですが、お客さまの立場からだと、ドビュッシーを前半なり後半なりで通して聴くよりも、ショパンと交互にした方が、2人の共通点や違いをより感じていただけて、面白いんじゃないかと思ったので」
――アルバムに収録されている『映像』から第2集も演奏されます。
「第1集は1回目のサントリーホール・リサイタルで演奏したので、今回は第2集をとり上げました。第2集の魅力は、陰の部分や静寂の中から浮かび上がる美しさではないでしょうか。東洋への関心が3曲それぞれ異なった形で表現されていて、日本人の繊細な感性に通じるものを感じます」
――ショパンは有名な大作、ピアノ・ソナタ第2番ですね。
「第3番じゃなくて、ね(笑)。ショパンの生誕記念の年に〈葬送〉というのはどうかなとも思ったんですけれど、彼の心の叫びが聞こえるような作品をメインにしたかったんです」
――思いの詰まったアルバムとリサイタルですね。楽しみにしています。
取材・文:松本 學(2010年10月)
![喜びの島 今川裕代(P) [CD] 喜びの島 今川裕代(P) [CD]](/image/jacket/large/411010/4110100085.jpg)


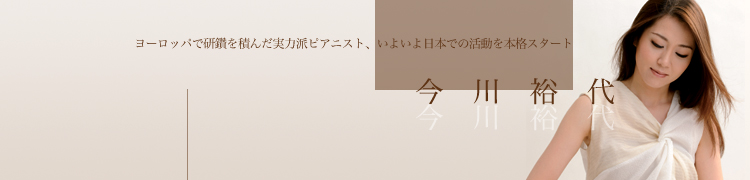
 ――つい最近までザルツブルクにお住まいだったんですよね。
――つい最近までザルツブルクにお住まいだったんですよね。
 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。