フジロック・フェスティバル'09での
JETのパフォーマンス(7月25日、GREEN STAGE)は熱かった! 肉感的で勢いあるロックンロールを4人は自信たっぷり胸を張って送り出し、観客もそれに真っ向から受け止め、熱烈に反応する。おお! そうした彼らのステージは鬼のように祝福されていると思わずにはいられなかったな。かように堂々メインストリームを闊歩するJETの面々はその翌日は韓国のロック・フェスに出演し、再び日本に戻ってきて、笑顔で山のような取材をこなしていった。新作
『シャカ・ロック』リリース直前の4人、ニック・セスター(g、vo)、キャメロン・マンシー(g、vo)、マーク・ウィルソン(b)、クリス・セスター(ds、vo)に話を訊いた。
――フジロックのステージは凄かったです。その様に触れながら、過去いろんなオーストラリアのバンドが紹介されてきたけど、これまでで一番日本人にライヴで熱く歓迎されたオーストラリアのバンドではないのか、なんて思ったりもしたんですが。
マーク 「7、8年前に初めてフジロックに呼ばれてライヴをやったときの会場はテントのRED MARQUEEだった。それで、そこでやるほかのバンドを観ていたら、アメリカのバンドだったんだけど会場の3分の1しか埋まっていなくて、俺たちのときもあまり埋まらないんだろうなと覚悟してステージに出たんだ。そしたら、もうものすごく満杯で、みんなダイブをしたりとか熱狂的に盛り上がってくれて。そのときから、日本の聴き手が自分たちのことを本当に親身に受け止めてくれていると感じているよ」
――オーストラリアのバンドである、という意識は強く持っているんですか。それとも、インターナショナルな存在になってしまったし、自分たちはコスモポリタンなバンドであるという気持ちが強いのでしょうか。
キャメロン 「両方の気持ちを持っている。もちろん、俺たちはオーストラリアから巣立ったバンドであることは変わらないんだけど、ここ数年はオーストラリアに住んでいないメンバーのほうが多いのでジプシーのようにあちこちを転々としているとも感じるし、その両方の気持ちを持っているな」
――今、マネージメントはアメリカの会社なんですよね?
クリス 「うん。それで、マークだけいまだオーストラリアに住んでいる」
――なぜ、マークだけはオーストラリアに住んでいるの?
マーク 「好きだからさ(笑)」
ニック 「俺たちもオーストラリアに戻るのが好きだし、オーストラリアでリハーサルをやったりもしているよ。俺は今年のアタマに1ヵ月ぐらい過ごしたりもした。俺たちの肉親も住んでいるし、やっぱりオーストラリアがホームだという意識は強いと思う。今晩(取材した日)、オーストラリアに戻るんだけど、それもうれしい。入国の際、“おかえりなさい”と言われると、ああ帰ってきたんだと安心を得るよね」
――メンバーが別れて住んでいると1人では成しえない広い世界に触れることができるし、多様性に繋がりますよね。
ニック 「俺も今回アルバムを作る前にオーストラリアから引っ越したんだけど、初めてメンバーがバラバラな所に住んでいて、皆で集まって作ったアルバムになった。その美点というのは、自分だけの時間を過ごすことで、自分を見直すことも出来たこと。とともに、バンドから離れたからこその経験やアイディアをバンドに持ち帰ってくることができて、それが新鮮だったな」
――今作はEMIを通してリリースされるわけですが、新たに自分たちのレコード会社を作ったわけですか。
マーク 「うん、そうだよ」
――それは、表現の自由を獲得するためですか。
マーク 「俺たちは2003年にエレクトラと契約をしたわけなんだけど、その1年半後にエレクトラはアトランティックに合併吸収されて、俺たちの知っていたスタッフがみんないなくなってしまったんだ。そんなわけで今回のアルバムを作る時点で知っている人が残っていなかったから、レーベルとの繋がりを感じることができなくなってね。それで、そうした状況で続けていくよりも、自分たちでもできるだろうし、独立したほうがいいと判断したんだ」
――2003年、2006年、そして今作は2009年のリリース。ちょうど3年おきにアルバムを出していますが、そのぐらいの間を空けるのがいいと考えていたりもするのですか。
キャメロン 「お、“3”が俺たちのラッキー・ナンバーなのかな(笑)?」
ニック 「べつに3年周期で出そうと思っているわけじゃないんだけどね。最初、
ファースト・アルバムがあそこまで成功するとは思っていなかった。それを受けてツアーがずっと続いて、自分たちとしてはツアーをしすぎと感じるぐらいだったんだ。やっとそれが終わった後に、2作目
『シャイン・オン』の曲作りを始めたところ、俺たち(セスター兄弟)の父が他界してしまったということもあり、肉体的にも精神的にも疲弊してしまったわけだね。そうしたなかロスに行ってレコーディングを始めたんだけど、かなり時間がかかってしまったんだ。それで、今作に関しては去年には完成していたんだけど、レコード会社やマネージメント会社の契約などといったビジネス面の問題で3年の間が空くことになったんだ」
――それで、今作を作るにあたって、どんなものにしたいと思ったのでしょう。
マーク 「俺たちは前もってこうしたいとか考えてスタジオに入ったりするバンドじゃないんだ。ただ1つだけ決めたことがあって、それはセルフ・プロデュースでアルバムを作ろうということ。でも、外の人間の客観的な意見も必要だということで、気持ちを許せる人を1人加えて作っていった。音楽的なコンセプトはあまり考えず、とりあえずやってみよう! それだね」
クリス 「大物プロデューサーを起用するのはやめにしたから、LAではなくテキサス州オースティンで録音したんた。そして、それは自由の獲得に繋がったはずだよ」
――もう少し、オースティンを録音地に選んだ理由を教えてもらえますか。
マーク 「(エンジニアで共同プロデューサーである)クリス・“フレンチー”・スミスのスタジオがそこにあったからさ。オースティンに革ジャンとか着て行ったら、めちゃくちゃ暑くてびっくり。でも、結果的にそれも良かった。45度ぐらいあってさ、そりゃスタジオにこもるしかないもん(笑)」
――どのぐらいの期間をかけて録ったんでしょう?
クリス 「3ヵ月と2日だよ」
――前作はお父さんの死などもあったためか、内省的な、メロウな仕上がりを示す部分もあったと思います。それが今作ではまた全面的に活気が出てきて、突出するような力が増しているように思いました。
ニック 「うん、そのとおりだね」
クリス 「今回は意識的にバラードは入れなかった。やはり、もっと活力のある、ロックンロールな作品を作りたかったから!」
――クリス・“フレンチー”・スミスの年齢はあなたたちと近いんですか。それとも、けっこう年長ですか。
キャメロン 「年上だけど、精神的には11歳だね(笑)」
――なぜ聞いたかというと、自分たちでドキドキしながら、楽しんで作っているのが分かるものになっていて、だから同年代の人間どうしで和気あいあいと録っていったのかなとも感じたんです。
キャメロン 「彼の人柄を紹介するなら、たとえばある日スタジオに来る前に、彼は凄い絵柄の靴下を俺たちに買ってきて、笑いを取ったりするんだ。そういう変わった人だね。3ヵ月の間、俺たちも楽しかったし、俺がギターを弾いている間も、彼はそこらへんで暴れているような人。いつも手にはレッド・ブルかコーヒーを持っていて、元気いっぱいなんだ」
――今回のフジロックでのパフォーマンスにしても、新作の内容にしても、ぼくはそれに触れてロックっていいなあと思わずにはいられなかったんです。なぜかと言えば、ストーンズが持っているような、ロックとして変わらなくていいもの、ずっと持ち続けるべきものをきっちり有して、それをあなたたちの姿勢や心持ちとともに“今”の迸るロックとして出せていたから。自分たちがやりたいようにやれば、絶対に新しさは出てくるし、今のバンドとしての輝きは出てくる、という自信はお持ちですよね。 クリス 「うん。オネスティ……、自分たちのありのままのものを表現すればそこからオリジナリティのあるものが生まれると思うな。同じ人間は2人といないわけだから、自分の心をちゃんと出せれば、いいものが生まれるという確信は持っている」
――どんどんビッグになっているのに自然体ですよね。偉ぶったりもしないし、メンバー間の横の繋がりも変わらず仲が良さそうだし。そういうところに、オーストラリア人らしさを覚えたりもしますが。
マーク 「ああ、そうだと思うよ。もちろん、俺たちも浮き沈みはあった。なんせ16歳のころから一緒にやってきているから、当然問題が起こったり、亀裂とか緊張が走ったことも普通にあった。だけど、そういうことはどんな関係性においてもあるもの。大切なのは、そういうことがあったとしても、みんなで1つのところに戻ってこれることなんだ」
キャメロン 「アルバムのレコーディングのときも白熱して、ケンカになったりする。でも、皆がそれだけ熱い気持ちを持っているということで、それはいいことだと思うな」
取材・文/佐藤英輔(2009年7月)

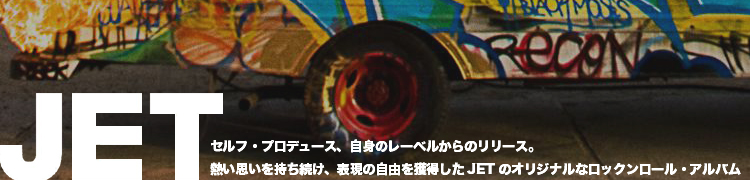



 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。