���ճ��Ȥ�פ���Τ�����
��ƣ�¼����ե롦����Х��ȯɽ����Τϡ�����̾���Ǥϼ¤�9ǯ�֤�������������
SPICY BOX�٤ޤ�4��������ߥˡ�����Х������ɤ�ơ��ޤ˿�����Ϣ���ʤɡ��ष������Ū�˺��ʤ�ȯɽ���Ƥ���������椨�ΡȰճ��ɤ��ʤ櫓���������������ݤäƤ����Τ���Ȥ��Ƥηи��ͤ�����10�ʤ�����ʥߥå���ʹ�����븣���ϤȤʤäƤ���ΤϤ��������˥塼������Х�Υ����ȥ�ϡ�
Ultra Worker�١���������ĥ�äƤ��뤹�٤Ƥο͡ɤ����ؤζ��������餷��ɽ��ȸ�����������
���ֺ���ϡ��ǽ餫��ơ��ޤ���ޤäƤ�����Ǥ����ͼ�������˻�������Ƥ�������ǡ����Ȥ��а����Ǥ��Ҥ�����ä����ꤹ����ǡȤ��줫����Фʤ�Ǥ��ɤȸ���줿�ꡣƯ���Ƥ��֤���Ƥ��������¿����Ǥ���͡����������Ư���͡ɤ�ơ��ޤˤ��ƺ��ʤ��줿��ʡ��Ȥ����פ����⤫��Ǥ�����Ǥ���������9ǯ�֤�Υե롦����Хࡣ���礤�����ä�������ޤ����͡�
��������Ͻв�äƤ����ե���������������ץ饹����ƣ�����Ȥ��֥쥤������ޤǤ������Ƥ�����ƣ����̴�äƤʤ���ä����ɤä��¤��������褦�ʤ͡�����ξ������蘆�ä��ơ��ޤ��ȡ����Ƥ�����Ǥ��礦����
����ξ�����ΤäƤ뤫�餳�����ʲλ줬�˽�����Ȼפ���Ǥ���͡�����Хࡦ�����ȥ�ʤΡ�Ultra Worker�Ӥˤ��Ƥ⡢���դ������Ȥ���˻����Ư���Ƥ�ͤߤ����ʥ���������뤱�ɡ���ultra�ɤˤϡ�Ķ�ۡɤȤ���Ķ���Ƥ����ɤȤ�����̣�⤢�롣��ʬ���Ȥ�Ķ���Ƥ�������ʬ�Τ�ꤿ�����ȡ�̴����ɸ�˸����ä��ͤ��ʤ��Ư���Ƥ���ͤ����Ȥ����������ơ����Υ����ȥ��Ĥ�����Ǥ���
����1���ܤΡ�HERO�פ⤫�ä������Ǥ���͡�80ǯ��������إ�����ˤ��̤��롢����äȤ�����ˤ⤭��Ӥ䤫���Τ��륢��ǡ�İ���Ƥ����ֲ��������롣 ���֤��ζ�̾�⡢ñ�ʤ륢�˥�������Τμ���Ȥ������ȤǤϤʤ��ơ�ï�⤬��ʬ�ο����ˤ����Ƥϼ���ʤ������ʬ���Ԥ�ƻ�ϡ���ʬ�ʳ����ʤ����������������������ƽ���Ǥ����Ϥ��ޤ���������ä����Ǥ�����ǡ�ï���ο����Υ��ݡ��ȡ��٤��ˤʤ�뤳�Ȥ��äƤ��뤫�⤷��ʤ����ͤ���ʬ�˸���ʹ�����Ƥ��뤳�ȤǤ⤢��ޤ��͡�����������å�������λ���硢���ʤ餺��ʬ�ȥ�����ƽƤ����Τǡ�
���������ǡ����դξ褻���ˤϡ������Υե�����������ޤ���͡�
���֥ǥ��İ���������ǡ������μ������ϴ����Ƥ��ޤ����������ߤ�����褦�������⤢�롣�����˥ơ��ޤȤ��Ƥ����ȥ���ȥ顦��������ɤ��������ˤϤɤ�����Ф����������ʤ��������餱�ʤ����դ��������ʸ��դ�褻�Ƥ������ȤϹͤ��ޤ����͡���������Ϥ�顢��ʬ����Ǥɤ�ɤ��äƤ��ä���
���������饹�⤴��ʬ�ǡ�
���֤Ϥ���
�����Ȣ�ĺ��ۤ��Ƥ椯����ɤΡ�ĺ��ɤȤ���ñ�켫�Ρ��������Υ꤬���������դ��ѥ��Ƥ���褦�ʡ����פ��Ť餵�줿�ʤȤ������ݤ�����ޤ���
���֡�ĺ��ɤȤ��Ⱦ徺�ɤȤ������ȡȸ³��ɡʾСˡ����ˤʤ��ߤ䤹�����դ����ޤ��Ϥޤä���Ǥ���͡�
�����ڤ���DzΤäƤ���Τ�����äƤ��롣
���ּ�ʬ�����������ŤͤƤ����Ǥ������ʤ餺�饤��������ʤ���쥳���ǥ������Ǥ����ɡ��ä˺���ϡ����Ҥ���������˲ΤäƤ����褦��ʷ�ϵ��DzΤ��ޤ�����
������Keep on going�ɤȤ����ե졼���ϡ��ǥ�λ����Ǥ��ä���Τʤ�Ǥ�����
���֤��䡢���äƤʤ��ä��Ǥ����̤θ��դ��ä��Ȥ�����äȹ礦�Ȼפ����Ѹ��ʬ��Ĵ�٤ơ����ƤƤޤ���
�����������⤷��ʤ����ɡ��ȴ�˾�ɤȤ�ʹ�����ޤ��ʾСˡ�
���֤ۤ�ȤǤ����ʾСˡ�����ϰռ����Ƥʤ��ä��ʾСˡ��Ǥ⡢���꤬�Ȥ��������ޤ���
�������ζʤˤ����餺���Υ��Ф��Τ����ߤˤʤäƤ����������ޤ�����
���ּ������Τ���ʤۤɡ��Τ����꤬���ˤʤ�Ȥ����ռ�Ū�ˡȶ����ɤ��Ȥˤ�äơ��ƥ�ݴ���Ĵ������褦�ˤϤ��Ƥ��ޤ�����ʬ�����Ϥ褤�Ȼפ���Ȥ��������������狼�äƤ��ޤ�����
����������̣�ǡ��Τ���Ȥ������Ϥ��Ƥ�����
���ֶʤؤ�����䡢�ž夬�ä����Υ���������ΤˤʤäƤ����Τ��礭���Ǥ��͡��Τϼ�ʬ�DzΤäƤƤ⡢�ɤ����������ˤʤ�Τ����狼��ʤ��ä�������夬�꤬�����Ǥ���褦�ˤʤäƤ������Ȥǡ��ޤ��ҤȤİ㤦���Фǡ��Τ˥��ץ������Ǥ���褦�ˤʤä���ʤ����Ȼפ��ޤ���
�����ʽ��פ��줿�Τ���ʤ��Ǥ�����
���֡�HERO�ӤϺǽ餫�Ǹ���Ȼפä���Ǥ����Ǥ⡢����ȥ���İ���Ⱥǽ餬�������ʤȡ���Ultra Worker�ӤϺǸ�˹ͤ�����Ǥ������쵤�ˤ����ǥ����Ȥ��Τ⤢�꤫�ʤȻפä����ǡ���L��P�ʥ롼�סˡӤ�Һ��ӡ�Calling Me�ӤϤ���äȽŤ��Τǡ����פ˻��äƤ��褦�ȡ�
������L��P�פ�����Ρ�SPICY BOX�٤˶ᤤ���������ǡ��ǥ����å�Ū�ʶʤǤ���͡�
���֤����Ǥ��͡�
���������ǡ��Ȥ�äȡ��ɤǻϤޤ�ե졼�����ߤ����Ƥ���������ʤɡ��λ�Ȥ������̤��⤤���ʤǤ⤢��ޤ���
���֡�L��P�Ӥϡ���ʬ���Ȥˤ⤳���������Ȥ����ä��ʤȻפ蘆�줿�ʤʤ�Ǥ��������餫���Ƥ��ܤ˿ʤ᤺�ˡ��ޤ�Ʊ��������äƤ����㤦��
����Ʋ���ᤰ�ꤷ�Ƥ��ޤ���
���ֵ�Ϥ������Ȥ��äȤ����ˤ��Ƥ��ޤ���Ǥ���͡��Ǥ⤽����֤��ˤäơ�ȴ���Ф��Ƥ���������ʿ����˿Ȥ��֤��ƲΤäƤ��ޤ����͡�
��������������̣�Ǥ⡢Ʊ���Ȥ�äȡ��ɤȤ���ñ����֤��Ƥ���褦�ǡ�
����Ʊ������ʤ���Ǥ����ͤ��Ƥ�ä��櫓�ǤϤʤ��ơ������ˤ����ʤäƤ��ä���Ǥ����ɡ��Ȥ�äȿ��ޤǼ�ͳ�ˡɡȤ�äȼ�ʬ�Τ���������ɡȤ�äȤ��ʤ������������ɡ��ҤȤĤҤȤĤ˰�̣������ɤ�äȡɤʤΤǡ�������Ʊ���ˤϤ������ʤ��Ȥ����Τ�����ޤ�����
������L��P�פΤ褦�ʥ������ʶʤ⡢�������ʤ�Ǥ��͡�
���ֹ����Ǥ����إ���á��ͼ��ȡ����ۤȷ�ɤΤ��Ȥ��Ǹ����ʤ顢�ȱơɤ���ʬ��¿���ȻפäƤ���Τǡ�
������Ultra Worker�פߤ����ʶʤȤ��жˤǤ����ɡ�
���֤��������Ȥ�����������ФƤ����ߤ����Ǥ���
���������Ҥ������Τ���ʾСˡ�
���֤Ǥ⡢������ޤ���ʬ�Τ褵���Ȼפ���Ǥ���ξ��ü��ɽ�����Ǥ���Ȥ����Τϡ����ߤˤʤ�Ȥ�פ������������ʶʤ�Τ����Ρȱơɤ���ʬ�äơ��饤����ɽ��������������������ʤ��Ǥ��������������ʤ����ȴ���ɤδ����DzΤä���ä����
�����ޤ���������֤��ޤ����͡ʾСˡ�
���֤ɤ���⼫ʬ����ˤ����Τ����餳����ɽ�����뤳�Ȥ��Ǥ��롣��ʬ����ˤޤä����ʤ���Τäơ�ɽ���Ǥ��ʤ��Τǡ�
���������Butterfly�פΤ褦�ʶʤ����äƤ뤳�Ȥ⡢�����ͤ���ȡ�ɬ���ɤȤ�������
���֡�Butterfly�Ӥȡ�BLUE MONDAY�ӤΤĤʤ��꤬���������褫�ä���Ǥ��衣����2�ʤ������¤Ӥˤ������Ȥ����Τ����ä�����BLUE MONDAY�Ӥϲλ������Ū�ˡ�����Х�Υ饹�Ȥˤդ��路���ʤȡ�����������ơ��������Ż����������ޤ��Ϥ�롣�Ǹ��İ���ơ��ޤ���������Ф����Ȼפ���褦���¤Ӥˤ������ä���Ǥ���
������BLUE MONDAY�פȸ��äƤ뤱�ɡ����ʤ餺����֥롼�ʤ�������ʤ���ȡ�
���֥֥롼�äƤ����ȡ��ɤ����Ƥ���ä�ɥ����������ޤ����ɡ��ͤˤȤäƤϡ��Ķ��ɤ˶ᤤ������䤫�ʸ��դǤ⤢���Ǥ��������Ǹ�Υ��Ӥβλ줬�����ޤ�ɽ�����Ƥ���Ȼפä��Τǡ�
�����ҤȤĤʤ���ȸ������祤�������Ǥ������ǽ��Butterfly�פ�İ�������ˤϤӤä��ꤷ�ޤ�����
���֥��������ƻ��ϤǤ�����͡ʾСˡ�
�������ʤ�EDM�ݤ��ơ�
���֥ǥ��İ���������Ǥϡ�����äȥ��ȥʤ������βΤ���ȻפäƤ�����Ǥ���Ư���Ƥ�Ф������������ͤäƤ������Ȥ�����������夬�äƤ��������ʤ�Ǥ��礦����ʬ����Υ�����������ä��Ѥ�äƤ��ޤäơ�
��������˻줬��ȯ���줿��
���֤���Ϥ���äȰ㤦�Ȼפä���������ɤ���������Ǥ�������������Τ��Ż��Ƥ���ͤ����˥��ݥåȤ����ƤƽƤߤ褦�ȡ�����γ������Ӳ��ij�ɤΥ���������ݥä��⤫��Ǥ�����Ǥ�������������ɤ�������̴���� �פ��Ф��ʤ��ɡ����뤳�Ȥ���������Ƥ�������������������ɡ������Ǥݤä���ȿ��˷꤬�����Ƥ����������̷��������������λ����DzΤ���λ줬�ФƤ�������ʬ�Ǥ�Ӥä��ꤷ�ޤ������ߤʤ���ˤ�Ӥä��ꤵ��ޤ������ɡʾСˡ�
�������������λ��Τ����ʤ���Ȥ����ϡ����ޤ��Ѥ�Ǥ��餷������и�����Τ���äƤ��뵤�⤷�ޤ���
���ֺ��ʤΥ�����������Ѥ��Ĥ���뤫�ɤ������Ȼפ��ޤ����ͤ������������餸���櫓�ǤϤʤ��Ǥ����ɡ��νб餷����
����ǥ��������٤Ȥ������ʤ�����ë�γ�������ˤ��Ƥ��������������ҥ�Ȥ����Ƥ��ޤ���
�����ǡ�³����BLUE MONDAY�פǡ�ī���ۤθ������äƤ��롣
���ֽ��������������Ǥ���͡��������饦�������ǥ��ء��ߤ����ʡ�
�������ΰ�̣�ǡ�1��1�ʡ��Τ���Ρȥɥ�ޡɤ������Ƥ�ä����櫓�Ǥ���͡����˳ڤ�����ΤǤ���������Ȥ⡢�����ޤ��ȻŻ��ɤ�Ϣ�ʤ��ΤǤ�����
�������ԤΤۤ����礭���Ǥ���
�����ڤ�����
���֤��������ǵ�ξ�硢���餸�뤳�Ȥdzڤ����������롣�������Τξ��ϡ��λ��ɤ���ʬ�������Ƥ���ɽ���Ǥ��뤫�����ܤϤ����ޤ��ʤ�����ɡ��ΤΤۤ��������ȼ�ʬ���ȡɤʤ�Ǥ���͡�
�����स�㤭����ʬ�����롣
���֤��٤ơ���ʬ�Ǥ������ˤ��뤳�Ȥ��Ǥ����Ǥ������ǵ�ξ�硢�������ʬ�Ǻ�äƤϤ���������ɡ���äѤ��вȤ����롣�����������¤���Ƥ�����Ǥ�ɽ���ʤ�Ǥ����Τ���Ǥϡ����������Ƥ��������ȸ����뤳�ȤϤʤ��Ǥ����顣�����ޤ��ͤ��ͤ����BLUE MONDAY�ӤǤ������Ǥ���
����100�ѡ�����ȡ���ʬ���ȤǤ������Ǥ��͡�
���֤�������äѤꤪ�⤷������Ǥ���
�������ڡ��������ޤ���͡�
���֤���⤦�����ڤ��ʤ��ȡġ�
������äƤ��ʤ��ʾСˡ�
���֤ȤޤǤϸ���ʤ��Ǥ����ɡʾСˡ��Ǥ⡢�����˼�ʬ��ɽ���Ǥ�����Ȥ����Τϡ���äѤ겻�ڤǤ��ꡢ��Ǥ�饤������ʬ���Ȥ��������������������Ƥ��ƴ����뤳�Ȥ�ɽ���Ǥ�����Ȥ����ΤϡȲ��ڡɤʤ�Ǥ������ǵ�Ǥϡ������ɽ���Ǥ��ʤ����쥳���ǥ��λ��⤽���ǡ������ȥ����뤷�ʤ���Τ����Ȥ���ȡ��ɤ����Ƥ�Ⱥ�ȡɤδ��Ф��������Ǥ��롣�����餳�����ȥ쥳���ǥ��ϥ饤���Ǥ���ɤȤ����ռ����ݤĤ��Ȥ����ڡ������פ��ʤ���Τ��褦�ˤ��Ƥ����Ǥ���
��ࡦʸ / ���ݤߤ椭��2018ǯ6���
2018ǯ7��28�����ڡ�
ʡ�� HMV&BOOKS HAKATA ���٥�ȥ��ڡ���
���� 16:30 / ���� 17:00
����������ŵ����ɬ�ס�
2018ǯ8��4�����ڡ�
���� ��顼���庴�� �̴� 1F ��顼����ץ饶
��14:30�� / ��16:30��
���ߥˡ��饤���ʴ���̵���� / ��������ŵ����ɬ�ס�
2018ǯ8��12��������
��� ������⡼���ڱ� ����Ź�� 1F �ֲФҤ���
��13:00�� / ��15:30��
���ߥˡ��饤���ʴ���̵���� / ��������ŵ����ɬ�ס�

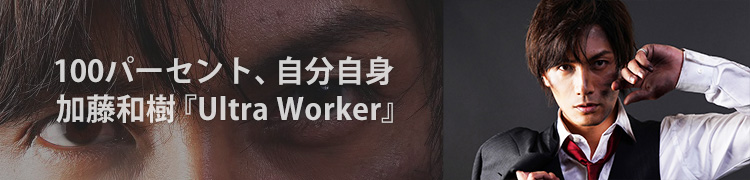
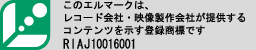
 ���ҥ����ȤǤϡ�CD��DVD���ڶʥ���������ɡ����å�������ϹԤäƤ���ޤ���
���ҥ����ȤǤϡ�CD��DVD���ڶʥ���������ɡ����å�������ϹԤäƤ���ޤ���