4週連続でお届けしている
リトル・クリーチャーズの20周年ヒストリー企画。高校の同級生だった
青柳拓次、
栗原務、
鈴木正人の3人がバンドを結成し、当時大人気を誇っていたバンド・オーディション番組『三宅裕司のいかすバンド天国』に出場したところ、あれよあれよという間にグランド・キングを獲得! 各社争奪戦の末、ついにメジャー・デビュー……といったところまでが前回のあらすじ。第2回目となる今回は、“恐るべき子供たち”として10代でデビューを飾った彼らが、90年代の音楽シーンにどんな形で影響を受け、バンドとしていかなる成長を遂げていったのか、当時の思い出を交えながら振り返ってもらいました。
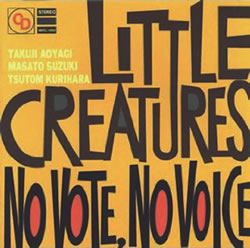
『NO VOTE, NO VOICE』(92年)
――第2回目のとなる今回は、リトル・クリーチャーズが90年代の音楽シーンからどのように影響を受け、それを作品化していったのか? そして、バンド・メンバー3人の世界が周りの人を巻き込んで、どのように広がっていったのかを検証したいと思います。1992年のリトル・クリーチャーズはと言えば、ロンドン録音の2ndアルバム
『NO VOTE, NO VOICE』という、スタジオ・ライヴ的に録った前作を完成度高くスタジオで発展させた成長著しい作品をリリースしていますよね。
栗原務(以下、栗原) 「最初のミニ・アルバムは、当時のプロデューサーに“イギリスでレコーディングしたい”って要望を伝えたんですけど、“イギリスは天気も悪いし、使える楽器も手に入りにくいから……”ってことで、気がついたらロスでレコーディングしていて(笑)。だから、2ndアルバムは念願叶ったロンドン録音だったんですけど、
U2や
ケイト・ブッシュなんかを手がけたケヴィン・キレンにプロデュースをお願いしたのはレコード会社のディレクターがファンだったんですよね(笑)」
鈴木正人(以下、鈴木) 「当時、栗原が東京、青柳がロンドン、俺がアメリカのマサチューセッツにいて、まぁ、レコード会社は大変だったんでしょうけど、本人たちは久々に会って、新鮮な気持ちで演奏できた作品ですね」
栗原 「前に会ったときよりやれることは増えてるし、作る楽曲も変わっていって驚きもあって、モチベーションは高かったんですよね」
青柳拓次(以下、青柳) 「あと、この頃のレコーディング感覚が板に付いたことによって、リリースの間隔が長くなった今、しばらく、会わなくても全然大丈夫っていう(笑)」
栗原 「個人的には、この作品から青柳が作ってくる曲はリズムが極端に変わったっていう印象があって。青柳から送ってもらったお気に入りの曲が入ったテープも、こっちでは誰も知らないような、ホントの意味での最新の音楽が入っていたんですよ」

95〜96年ごろのライヴ・ショット(会場不明)
青柳 「アシッド・ジャズみたいなクラブ・カルチャーだったり、レイヴだったり、当時の音楽体験が大きかったんですよね。それに日本と海外とでは今よりもタイムラグが大きかったし、浸透するまで時間がかかったしね。あと、それ以前、ジャマイカ音楽はすごく好きだったんですけど、そこからアフリカとかラテンに向かったのは、この頃ですよね。よく覚えているのは、
フェミ・クティのライヴで女性の黒人DJが
フェラ・クティの<ロフォロフォ・ファイト>って曲をかけてたこと。それまで4つ打ちっていうとディスコかハウス / テクノだったから、生演奏のすごくいい音で凝った4つ打ちのリズムを体験できたことは自分にとって大きかった」
鈴木 「そうかと思えば、アメリカの田舎は日本より輪をかけてひどくて、日本で聴けるものすらなくて、
マドンナと
マイケル・ジャクソンしかない、みたいな(笑)。その代わり、俺はバークリーでジャズの勉強をしていて、ベースと理論、あとは弦と管の編曲をやったりとか、セッションの日々ですね。よく道で演奏していたのを覚えてますね」

『NO VOTE, NO VOICE』発表時のアーティスト写真(92年)
――『NO VOTE, NO VOICE』に収録された「MURKY WAYERS」のアフロ的なリズムしかり、青柳さんがバンドに持ち込んだ新しい要素について、東京の栗原さん、アメリカの正人さんはどう思われたんでしょう?
栗原 「聴いたことがなかったし、すごい妙なリズムの曲を作ってきたなって。だから、プレイするのに必死でしたね(笑)」
鈴木 「ただ、咀嚼したアイディアを提示してくるから、“なるほど。この人はいつもおもしろいことを考えるな”って思いながら、よし、やってみよう!って(笑)。青柳は今もそういうところがあるんですけどね」
青柳 「最初のミニ・アルバム(
『Little Creatures』)とファースト・アルバム(
『VISITA』)には自分たちの理想とするものがあったと思うんですけど、この頃のリトル・クリーチャーズは何かを目指して音楽を作るんじゃなく、バンドそのものであればいいと思えるようになったからこそ、作ることができたアルバムですよね」
――それから、この作品のアルバム・タイトル『NO VOTE, NO VOICE』は、当時のイギリス総選挙の標語なんですよね? 90年代の日本の音楽シーンは政治とコミットしなかったとよく言われますが、93年にこのタイトルを付けたところが興味深いです。
青柳 「それは僕がイギリスにいたからかもしれないですね。かつて、
スタイル・カウンシルとか
ハウス・マーティンズはインタビューで左翼的な発言をしてましたし、音楽から政治をあえて切り離していることが僕にとってはいまだに不自然な感じがあって。もちろん、政治について、まったく考えてないんだったら繋げる必要はないんでしょうけど、考えているんだったら、それは自然に繋がってくるものでしょう? その点、イギリスでは音楽も政治もフラットで語られていて、そこに自由な空気を感じたんですね」
――留学を通じて、日本と海外の文化の違いを目の当たりにしたことで、音楽観やバンドのスタンスに変化はありましたか?
鈴木 「音楽のことを抜きにしたら、アメリカに住んでた実感として、日本はなんていい国なんだろうって思いましたけどね。とにかく安全だし、食べ物も美味いしね。それに当時のアメリカは景気が悪かったから、治安は悪いし、街のムードも暗かったしね」
青柳 「イギリスもそんな感じだったな」
栗原 「しかも、2人が景気よくないところから戻ってきたら、バブルが弾けてて、日本も景気よくなかったっていう(笑)」
鈴木 「音楽に関しては、向こうでジャズばっかりやってたんですけど、上手さのレベルが違うというか、これはもう、どう考えても勝負にならないなって(笑)。だから、ある時期からそういうことはいいから、もうちょっとアイディアとかアレンジで勝負しようって考えられるようになっていった」
青柳 「当時の体験は、今でこそソロなんかに活かされていますけど、この頃は本場の音楽を見聞きした経験を日本での活動にどうフィードバックさせるかがあまり分かっていませんでしたし、日本のシーンが特殊に見えていたこともあって、粛々と自分たちの活動を続けていこうと思ってましたね(笑)」
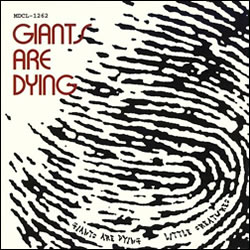
『GIANTS ARE DYING』(93年)
青柳 「この作品からセルフ・プロデュース度が高くなっていくんですけど、それ以前の作品では、いい音で録音してくれるエンジニアの方と仕事することができたものの、バンドとしては、もっとざらっとしていたり、もっとヴィンテージな鳴りを求めていたところがあったんですね」
鈴木 「ちょうどこの頃、オルタナティヴだったり、サンプリングのラフな質感を出すために、あえて、ローファイに録音する手法が注目を集めていて、それをなんとかバンドでやれないかなって思っていた気がします」
栗原 「あと、ジャズの偉人たちに捧げるとはいっても、この作品はいわゆるジャズ・アルバムではないんですよね。もちろん、上ものなんかにはジャズの要素があるんだけど、俺の中では、ジャズの人がやったアフロ・ミュージックだとか、ジャズが移行していくなかで、こんな音楽があったんじゃないかなっていう想像の音楽ですよね。あと、アナログ盤は最初の頃から出したかったんですけど、このミニ・アルバムで初めて夢が叶ったんですよね」
青柳 「DJを始める人やターンテーブルを買う人が増えたり、当時の状況的にもアナログを発表する意味が出てきたんでしょうね」
――そして、続く94年はリリースがなく、バンド活動は空白の時期になっていますが、その一方で93年3月から94年6月にかけて、下北沢のクラブ、スリッツで<BRILLIANT COLORS>というマンスリー・パーティを主宰されていましたよね。
青柳 「『NO VOTE, NO VOICE』の頃、フェラ・クティやカリプソがガンガンかかる現場を体験して、“じゃあ、世界中の音楽がかかるパーティをやろう”ってことで<BRILLIANT COLORS>を始めたものの、当時、それを面白いと思ってくれる人がなかなかいなくて、お客さんをどうやって集めるかが大変でしたね」
――当時、ワールド・ミュージックを意識的にプレイしていたDJは井上薫さんほか、数えるほどしかいなかったですもんね。
青柳 「そうそう。ワールド・ミュージックがそこまで注目されていない頃だったから、当時、かけてたレコードは全然売れないセール品のコーナーから探したりしてたし、パーティ当日もお客さんよりメンバーの方が多かったこともあったよね(笑)」
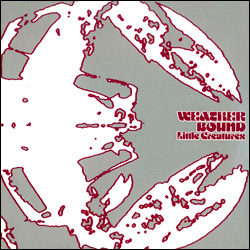
『WEATHER BOUND』(95年)
――そして、95年にはラテンやブラジリアンなど、当時吸収していたワールド・ミュージックの要素を溶かし込んで、またしてもミニ・アルバムである
『WEATHER BOUND』がリリースされます。
鈴木 「93年から95年にかけてミニ・アルバム2枚か。なんでだろうな(笑)?」
栗原 「でも、自分たちのなかでは『WEATHER BOUND』がミニ・アルバムって感覚ではなかったというか、普通にアルバム録ってるのと気持ちは変わってなかった。とはいえ、わざわざシンガポールまで行って、5曲しか録らなかったのか(笑)」

『WEATHER BOUND』のレコーディング・スタジオにて
@シンガポール(95年)
――すごい贅沢な話ですね。
栗原 「でも、シンガポールで録る方が予算的には安く済んだんですよ。あと、ワールド・ミュージックにハマっていた時期だったから、どこでレコーディングしようかって話になったとき、マネージャーを交えて、“アジア圏がいいんじゃない?”って。ここでも外的要因に流されまくってますね(笑)」
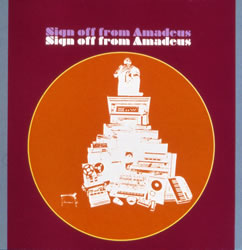
『Sign off from Amadeus』(96年)
――さらに同時期にインターネット・ブースが併設されていた渋谷のクラブ、Electronic Cafeにて、新たなパーティを主宰していましたよね?
青柳 「<Sign Off>ですね。そのパーティと同タイミングで周りにいろんなバンドが誕生してたので、ライヴで出てもらったんですけど、“このままアルバムになりそうだね”ってことで96年にコンピレーション・アルバム
『Sign off from Amadeus』を作るんです」
鈴木 「
Port Of Notesなんかはそれ以前にも別の名前でライヴはやってたんだけど、Port Of Notes名義になるのは、このアルバムからだった気がしますね」
――名前は正人さんが決められたとか。
鈴木 「そうなんですよ(笑)。(ギターの小島)大介はバークリーで知り合ったんですけど、彼が思いついた名前は“東京ソウル・マニアックス”とか、それはないんじゃないってものだったので、“例えばPort Of Notesとかさ……”って言ったら、それがグループ名になっちゃった(笑)」

『Little Creatures meets Future Aliens』(97年)
青柳 「当時、いろんなアーティストがこぞってリミックス作品をリリースしていた時代で、確かにリミックスは面白いんですけど、話を聞くと、仕事っぽくやり取りしている感じがして、いい印象がなかったんですよ。そんなこともありつつ、Electronic Cafeでサイレント・ポエッツの下田(法晴)くんとかがイギリスのバンド、
ムーンフラワーズをかけたりしていて、「ああ、いいバンドだな」って。だから、次のアルバムを作る時は好きな海外のバンドに参加してもらおうってことで、関係の深かった下北沢のレコードショップ、DISCSHOP ZEROの飯島直樹くんにムーンフラワーズを紹介してもらったんです」

シングル「barbarize」収録曲
「DRIFT」ミュージック・ビデオ撮影時のショット
@タイ(96年)
――ムーンフラワーズというのは、現代のジプシー・ミュージックというか、ヒッピー・トラベラー・バンドですよね。
青柳 「彼らはジャズとかプログレ、フォークロアな要素もあったり、ダブもやるし、そういう混ざり具合にシンパシーを感じて、きっと同じような音楽を聴いてきたんだろうなって思ってたら、実際に会ったとき、車の中で聴かせてもらった彼らのミックス・テープには僕らの好きな曲がたくさん入っていたり、そういうシンクロニシティがあったんです」
栗原 「あと、このアルバムでは自分たちによる録音にチャレンジしたんですよね」
鈴木 「当時、A-DATっていう安いデジタル・レコーダーが普及してきた頃だったので、YAMAHAのO2Rっていうデジタル・ミキサーを貸し別荘に持ち込んで」
栗原 「正人がミックスをやったり、ムーンフラワーズとか、参加してもらった海外組にもこっちで録った曲の素材を送って、向こうで組み立ててもらったんですよ」
青柳 「それで海外から戻ってきた素材を僕らが仕上げていったんです」
栗原 「作曲にしても、3人が入り乱れて、セッションから作り上げていったんですけど、スタジオでそれぞれの楽器をセッティングしたら、楽器を持ち替えて、それで曲が固まってきたら、ラジカセで録って、それをベースに膨らましていったりして。歌詞も途中まで俺が書いて、そこから正人の歌詞に替わったり。ただ、96年に出したシングル<barbarize>がループを組んで作ったのに対して、このアルバムは基本的に手弾きなんですよね」
鈴木 「つまり、このアルバムは、いわゆる素材をカットアップして構築していくDJっぽい作り方を作曲の段階からやってみたってことだったんですよね」

ビデオ作品『WORLD OF TOO MUCH SOUND』撮影時のショット@東京(98年)

『RADIO COLLECTIVE』(99年)
鈴木 「また出た! 何も出さなかった年(笑)。世の中、半年休業するだけでニュースになったりするのに、じゃあ、俺らはどうなるんだっていう(笑)」
栗原 「中山美穂さんのプロデュースは、彼女が『Little Creatures meets Future Aliens』を気に入ってくれたからっていう意外な展開ですよね」

中山美穂『manifesto』(99年)
――歌謡曲的な発想ではいろんなコラボレーターが参加するのが普通だと思うんですけど、この作品には、ひとつのバンドが丸々一枚手掛けることで生まれたトータリティがあって。リズムが変拍子だったり、いま聴いても大いに楽しめる一枚だと思います。
栗原 「気合いの生ドラムンベースとかやってるし(笑)、一緒にツアーまでやったり、結構がっつり組ませてもらいましたからね」
青柳 「好きにやってくださいっていう彼女のスタンスがあってこそ成立したプロジェクトですよね」
取材・文/小野田雄(2010年11月)
※次回の更新は12月15日を予定しています。
<LITTLE CREATURES 20th Anniversary LIVE>●日時:2010年12月17日(金)
●会場:ラフォーレミュージアム六本木
●開場 / 開演 18:00 / 19:00
●料金:¥3,900【サンキュー!!】(前売/自由席/整理番号付)
【チケット取扱】
チケットぴあ 0570-02-9999(P:117-084)
ローソンチケット 0570-08-4003(L:77334)
イープラス
※客席が出演者を360°囲むセンターステージで実施
※お問い合せ:SMASH 03-3444-6751
■リトル・クリーチャーズ オフィシャル・サイト
http://www.tone.jp/artists/littlecreatures/
![リトル・クリーチャーズ - ラヴ・トリオ [CD] リトル・クリーチャーズ - ラヴ・トリオ [CD]](/image/jacket/large/411010/4110101633.jpg)

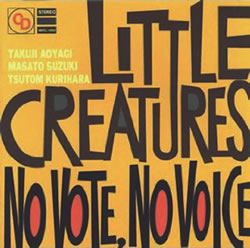


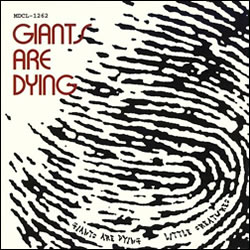
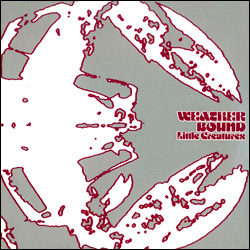

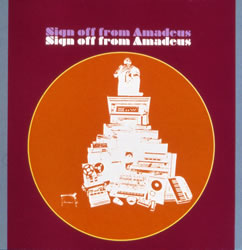







 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。