エレクトロニック・ミュージックにもアプローチするドラマーとして、つねにその動向に注目が集まってきたマーク・ジュリアナが、ひさびさにアコースティック主体のジャズ・カルテットでアルバム『ザ・サウンド・オブ・リスニング』をリリースする。長年活動をともにしてきたベースのクリス・モリッシーとサックスのジェイソン・リグビーに加え、ピアノのシャイ・マエストロも戻ってきた。それぞれがさまざまな楽器を演奏し、エレクトロニクスの要素も自然に取り込んで、次なる方向性を示している。新生ジャズ・カルテットの音楽について、マーク・ジュリアナに尋ねた。
――ジャズ・カルテットのアルバムとしては5年ぶりの新作になりますが、リリースの経緯から教えてください。
「ここまで間が空くはずではなかったんですが、コロナですべてが減速してしまったのです。2017年に出た『ジャージー』をレコーディングした後は、エレクトロニック・ミュージックのプロジェクト“BEAT MUSIC”に焦点を絞って『ビート・ミュージック!ビート・ミュージック!ビート・ミュージック!』を制作し、その後、2020年にこのアルバムに向けて曲作りを始め、2021年にレコーディングのはずが1年押してしまったわけです」
――ジャズ・カルテットにはどのようなコンセプトがあるのでしょうか?
「コンセプトは、僕が今までリーダーとして作ってきた諸々の音楽を受けてのものなんです。2015年ぐらいまでは、リーダーとしてレコーディングしたり作曲したりするのは、エレクトロニックな環境が多くて、アコースティック・ミュージックもジャズも大好きだけど、その文脈で音楽を作って作品として提示するのはちょっとしたチャレンジだと感じていたんです。サックス、ピアノ、ベース、ドラムは、もっとも頻繁に用いられる楽器編成のひとつだと思うし、ジョン・コルトレーンのカルテットはいちばん好きでよく聴いているグループのひとつなんですけどね。今回は、そういった影響を尊重しつつ、恐縮ながら、僕からもひとつ提示させてもらいます、という感じです」
――これまでと変化したこと、新たにチャレンジしたことはありますか?
「『ザ・サウンド・オブ・リスニング』は2作で1枚になっているところがあって、収録曲の半分は『ファミリー・ファースト』、『ジャージー』という僕らの前作から一貫したアプローチ、つまりスタジオに集まって準備したら録音ボタンを押して同じ部屋で一緒に演奏するやり方でした。それがこのバンドの真髄でした。収録曲のあとの半分は作曲された小作品と考えていて、テクスチャーを多めに活用しています。4人のみでありながら、ジェイソンがフルートやバスクラリネットを演奏したり、シャイがメロトロン他のキーボード類を演奏したり、僕がパーカッション的な要素を受け持ったりする場面があるのが、このアルバムに隠れているその他の要素ですね」
――アルバム・タイトルに込めたものを教えてください。
「“the sound of listening”というフレーズは、ティク・ナット・ハンの著書『Silence:The Power of Quiet in a World Full of Noise』(翻訳本は『沈黙:雑音まみれの世界のなかの静寂のちから』春秋社)で初めて知りました。彼はベトナムの禅僧で、その教えに多大なる影響を受けましたが、なかでもこの言葉が大好きで、沈黙のひとつの説明として聴くという音があるということ。彼は、互いに真摯に耳を傾けたり世界を観察するために、人がみな、自分の内面に持つべき沈黙について詳細を語っているので、それをアルバムに含めたいと思ったんです」
――『ファミリー・ファースト』に参加したシャイ・マエストロが戻ってきましたが、メロトロンやローズなど、ピアノ以外の鍵盤楽器も弾いていますね。
「シャイはこのアルバムでさまざまなキーボード系のテクスチャーを担当しています。彼とはベーシストのアヴィシャイ・コーエンとの仕事をきっかけに、これまでに何度も共演していて、すごくやりやすいんです。家で書きながらいろんなキーボードを使って録音していたので、そのテクスチャーを活かしてほしいと彼に頼んだんですが、やっぱりこのバンドのサウンドの幅を大きく広げていますね」
――クリス・モリッシーとジェイソン・リグビーはずっとジャズ・カルテットのメンバーですが、彼らとの関係性について訊かせてください。
「クリスもジェイソンも、音楽的力量はもちろんのこと、その友情も僕には頼りになるんです。長年一緒にたくさんの音楽を作ってきました。選択の余地さえあれば、まずは友だちと一緒に音楽を作りたいと考えているので、その絆が特別な音楽的モーメントを生み出すことに繋がっているのではないでしょうか」
VIDEO
――アルバム・タイトル曲の「the sound of listening」のみプログラミングされたビートですが、“BEAT MUSIC”のアプローチを取り入れたのですか?
「そのとおりです。この曲は少し“BEAT MUSIC”方面に踏み出していて、自宅で制作中にビートや808(ドラムマシンのTR-808)を使ってトラックの基盤を作るのがふさわしいと感じてたんです。カルテットが僕の脳みその片側に、“BEAT MUSIC”がもう片側にあって、この曲はカルテット側から始まったものの何歩か“BEAT MUSIC”側に歩を進めたってところでしょうか(笑)。カルテットも“BEAT MUSIC”もしっかり地に植え付けてきたので、今はそれぞれからの影響をブレンドする、あるいは自然と混ざっても良しとするようになったのかもしれないです」
――ほかの楽曲にも、“BEAT MUSIC”的なタイム感やテクスチャーを感じました。
「はい、“BEAT MUSIC”のテクスチャーが今まで以上に入り込んできていて、“BEAT MUSIC”的傾向や影響の一端がカルテットの音楽的風景に入り込むのを意識的に許していたんです」
――一方で、作曲面にもかなり力を注いでいるように感じられました。
「気づいてくれてありがとう。たしかに作曲により重きを置いています。ロックダウンがその機会を与えたんです。かなり内省的になって、作曲により時間をかけて探求するようになったので。今回の曲にはとても自信があるし、ミュージシャンがそれを演奏して、生き生きとした、僕の想像を超えた良いものにしてくれたんです」
――今年の初頭には、“BEAT MUSIC”的な『Music for Doing』のリリースもありましたね。
「あのアルバムは素晴らしい経験で、やはりロックダウンから生まれ、友人のピート・ミンと一緒に彼のロサンゼルスのスタジオで作業しました。スタジオで新しいテクスチャーを探求する良い機会で、音楽的に遠慮なく実験したってことですね。一緒に音楽の冒険をしてみようと思っていただけなのに、気が付いたらアルバムにできるだけのトラックができていたんです。あれを聴いてくれてありがとう」
――今回のリリース元のEditionは、現在のアメリカのジャズを紹介する良きプラットフォームとなっていると思いますが、あなたの見解を訊かせてください。
「Editionから出せたのはとても嬉しいです。レーベルのオーナー、デイヴ・ステイプルトンとはもう15年以上前からの知り合いで、彼はこういう音楽を紹介するうえで優れた仕事をしていると思います。伝えたいことが明瞭だし、創作上の自由をちゃんとくれて、作りたいアルバムをそのまま作らせてくれたんです。音楽のプラットフォームを提供してくれた彼に感謝しつつ、たくさんの人にぜひ、聴いてもらえるよう願っています」
取材・文/原 雅明

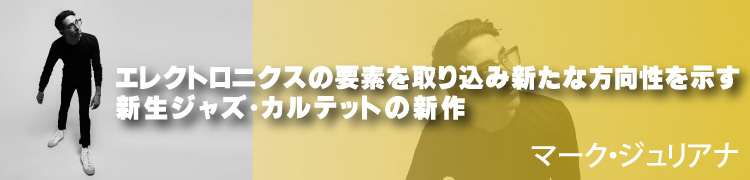


 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。