2007年のデビュー以来、クラシックとポップスというふたつのジャンルを横断して、真摯な演奏を重ねてきたヴァイオリニストの宮本笑里。その15周年を記念するアルバム『classique deux(クラシーク・ドゥ)』がリリースされた。ドビュッシー、ホルスト、ショパン、ファリャ、シューマン、フォーレ、ラヴェル、バッハなど、収められているのは、誰もが耳にしたことのあるクラシックの小品たち。楽曲を最大限リスペクトしつつ、心を込めた音色で、自分なりに紡いだストーリーを届ける──。そんな彼女の姿勢が、ストレートに伝わってくる仕上がりだ。「みんなが知っているスタンダードこそ、演奏家として人生が問われる」という宮本に、アルバムに込めた思いを聞いた。
――デビューから15年。振り返ってみて、どんな時間でしたか?
「長かったようで、あっという間だった気もするし(笑)。どちらの感慨もありますね。この15年間、クラシックにもポップスにも全力で取り組むという姿勢は変えずに活動してきて。一年一年、普通ではありえないほど濃密な人生を送らせていただきました。コロナ禍以降は、世の中に音楽って必要なんだろうかと落ち込む瞬間もあったけれど。それでも自分の演奏が何らかの励ましになればと、ライヴ配信に挑戦してみたり。本当にいろんな起伏があったなと、あらためて」
――2018年7月には、キャリア初となる全編クラシック小品集『classique』を発表されました。15周年記念アルバム『classique deux』はその第2弾ですね。
「ここ最近『Life』(2020年)、〈ララミディア〉(2021年)とポップス系が2枚続いていたので。自分にとってもうひとつの大事な柱を確認する意味でも、ちょうどいいのかなと。4年前に『classique』をレコーディングした際は、じつは不安も大きかったんですね。いつかはやろうと温めていた企画でしたが、いざ実行するとなるとやっぱりプレッシャーを感じましたし。ホール録音の場合、スタジオと違ってそう何度もリテイクできないので。それを必死で乗り切って、私なりに満足できるアルバムを作れた自信が今回に繋がった部分は大きかったです」
――第1弾に比べて、より自然体でレコーディングに臨めた?
「そうですね。たとえば準備の仕方にしても、やっぱり4年前の経験があるので。いろんな計算をしつつ、より細かく進められた気はします。ただ、それで楽になったかというと、そう単純な話でもなくて。ドビュッシーの〈亜麻色の髪の乙女〉など初めて演奏する楽曲も多かったですし。今回、ずっと弾きたかったけれど二の足を踏んでいた有名曲を、あえて選んだところもあった。なので本番2ヵ月前からは毎朝、寝起き状態でラヴェルの〈ツィガーヌ〉を弾いて、コンディションを作っていきました」
――へええ。いろんな収録曲ではなく、毎朝かならずラヴェルを?
「はい。〈ツィガーヌ〉って、ヴァイオリニストにとっては避けて通れない道というか。演奏テクニックはもちろん、譜面の理解度から音楽と向き合う姿勢まで、すべて晒されてしまう曲だと思うんですね。完全無伴奏パートも長いので、集中力を持続させるのが大変だし。朝イチの起き抜けで弾きこなすのはけっこう難しい。だからこそ、自分の状態を把握するにはいいのかなと」
――レコーディングに向けての定点観測ですね。アーティストとしての姿勢を問われるというのは、もう少し具体的にはどういうことでしょう?
「これは私個人の感覚ですが、少しでも緊張が途切れて弱みを見せると、曲に飲み込まれそうになる。そういう深さや怖さが〈ツィガーヌ〉という小品にはある気がするんです。たとえば“♪タタ〜ッ、タ〜ラララ〜”で始まる導入部に顕著ですが、演奏の端々に、ほんの一瞬の無音が挟まるでしょう。ひとつの音を奏でてから次に移るまでの、ゼロコンマ何秒の間を、演奏者がみずから創らないといけない。〈ツィガーヌ〉にはそういうポイントが無数にあって、そこにこそアーティストの音楽観や息遣いが出ますし。聴き手からすると、先の読めない面白さがあると思うんですね。でも、こちらの気持ちが負けているときは、その一瞬のタメが利かないというか……」
――なるほど。
「どんどん先を急いでしまう。そうなると演奏全体が平板になって説得力も失われるし。楽曲の持つストーリー性も伝わらない」
――落語家さんは、練習が足りない大ネタほど口調が早口になり、客席の気持ちが離れてしまうそうです。そうならないためには、とにかく稽古を重ねて、身体の中に噺を入れるしかない。今の宮本さんの話から、そんな関係ないエピソードを思い出しました。
「すごく似ている気がします。私はデビュー以来ずっと、ポップスもクラシックもただ演奏するだけじゃなくて、まずは自分なりのストーリーに落とし込むことを重視してきました。その上でのストーリーをどうメロディで奏でるか模索する。そこに辿りつくまでのプロセスを何より大事にしなさいというのが、父(元オーボエ奏者の宮本文昭)の教えだったんです。それについてはデビューから15年たって、やっと少しずつ、納得できる演奏に近付けたのかなと」

Photo by Akinori Ito
――「ツィガーヌ」以外で印象的だった楽曲はありますか?
「ショパンの〈ノクターン(夜想曲第20番嬰ハ短調)〉なども、当初かなり苦しみましたね。誰もが耳にしたことのある名曲で、私も大好きですが、やっぱりピアノのイメージが強烈じゃないですか。今回は、ヴァイオリニストのミルシテインが編曲した定番の譜面を使ったんですが、心のどこかでピアノの記憶を追い求めている自分がいて。なかなかうまくいかなかった。“これじゃダメだ、ヴァイオリン用の小品として真っ白な気持ちで向き合わなきゃ”と気持ちを切り替えたのが、レコーディングの2〜3日前かな。そこから強弱の付け方とか、音色の奏で方なども大きく変わって。何とか納得できる音の運びが見つかった。本当にギリギリ間に合った感じです(笑)」
――1曲目、ドビュッシーの「亜麻色の髪の乙女」も素晴らしかったです。レコーディング会場のHakuju Hallという場の空気感、奥行きがリアルに感じられる演奏ですね。とくに前半部、たゆたうように変化する音の強弱が、何度聴いても美しい。
「ありがとうございます。この楽曲はとにかく、歌い込みすぎないことを意識しました。あえて輪郭を定めず、ぼんやりした色彩を保つ感覚っていうのかな。私は絵画を見るのも好きなんですが、モネやルノワールなどフランス印象派の画家たちは、光そのものをどうキャンバスに再現するかを追究していたでしょう。同時代を生きたドビュッシーもきっと似ていて。輪郭のはっきりしたメロディではなく、いろんなハーモニーや音の色彩感で世界観を創っていく。その感覚を自分なりに共有できればいいなと」
――ピアニストは前作から引き続き佐藤卓史さん。さらに本作『classique deux』では楽曲によって豪華なゲストも迎えています。ホルスト「木星」は、世界的なホルン奏者・福川伸陽さんとの共演曲ですね。
「福川さんとは最初、Hakuju Hallの原(浩之)支配人経由でお目にかかったんです。その後、コロナ禍になってからは、私がSNSで発信した動画に福川さんがメロディを乗せてくださって。今回のアルバムを作るにあたっては、ぜひリアル共演できればと思い、お声がけさせていただきました。〈木星〉は福川さんのアイディア。私はこれまでオケでも弾いた経験がなく、けっこう冒険だとは思いましたが、大好きな歌手の平原綾香ちゃんの代表曲でもあるし。がんばって挑戦してみようと」
――ヴァイオリン、ホルン、ピアノという小編成ながら、厚みがあってシンフォニックな仕上がりが印象的でした。
「基本はオーケストラの譜面をベースにしつつ、リハーサルで細部を詰めていきました。原曲の持つ壮大なスケール感が出せたのは、おふたりの力ですね。今回、パートによっては同じフレーズを何度も繰り返すんですが、オケの経験の少ない私はそれも勉強しつつ……。最後はあのサビのメロディを、歌える喜びをかみ締めながら奏でています」

Photo by Akinori Ito
――そこに到るまでの展開が波瀾万丈なだけに、カタルシスがありますよね。モンティの「チャールダーシュ」はエモーショナルで楽しい雰囲気の一曲。チェリストの新倉瞳さんが参加されています。
「瞳ちゃんとは数年前に『ららら♪クラシックコンサート』でご一緒する機会があって。そこでこの曲を演奏しました。とくに決め事もせず、かなり即興的な感じだったんですが、気持ちいいくらい息が合った。今回のレコーディングもただただ楽しかったです(笑)。もともとこの楽曲って、ミュージシャンがバーでお酒を飲みながら腕比べをしてるような華やかさがあるじゃないですか」
――わかります。酔いが回って、どんどん超絶技巧が加速していく感じ。
「そうそう(笑)。そうやって盛り上がっていく面白さを、あまり張り詰めることなく、ヴァイオリン、チェロ、ピアノの3人で表現できたらいいなと。本来、チェロで弾くのは大変なフレーズもいっぱい出てきますが、瞳ちゃんはそういった速いテンポ感にも見事に応えてくれて。素晴らしかったです」
――ゲーゼの「ジェラシー」、ガルデルの「首の差で」、ピアソラの「リベルタンゴ」と続く後半のタンゴ・メドレーは本作のクライマックスです。ヴィオラ奏者の川本嘉子さんとの共演。2本の響きの違いも際立って引き込まれました。
「川本さんとも去年、Hakuju Hallで初めて共演させていただいて。そこで演奏したのが今回のメドレー3曲。あまりにもかっこいいアレンジだったので、会場に来られなかった方々にも届けたくて収録しました。タンゴって、人間の陽気な部分やドロッとした部分がいろいろ詰まっていて。何とも言えない色気がある。リズムにも微妙な揺らぎがあって、独特なんですよね。今回のヴァージョンでは本来の泥臭い魅力とはまた違った、クラシック演奏家から見たタンゴというものを、うまく出せたのかなと」
――日本を代表するヴィオラ奏者と共演してみて、いかがでしたか?
「演奏家として心から尊敬していますし、とにかく私は川本さんの奏でる音色が大好きなんですね。横で聴いていると胸がギュッと締め付けられて、涙が出てきちゃうくらい。人柄も本当に素敵で。今回の共演でも、本来なら私が合わせるところをパッと察知して、支えてくださった瞬間が何度もありました。川本さんのヴィオラを聴いていると、楽器の音色には演奏する人のすべてが出るんだなって、あらためて感じます。そんな深い音を、こういう形で収録できて本当に嬉しい。私にとっては、15周年の宝物です」
取材・文/大谷隆之

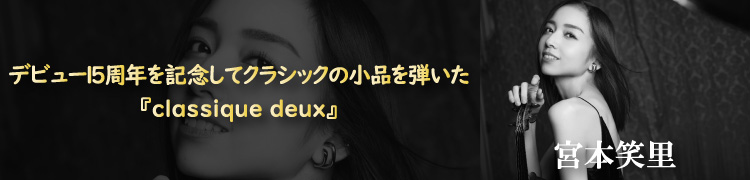



 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。