10周年特別企画の第3週目はジャズです。ジャズ界のこの10年といえば、
ノラ・ジョーンズや
上原ひろみの世界的なブレイクをはじめ、女性ミュージシャンの活躍が顕著だったように思います。そこで、日本ではジャズ・オーケストラを率いる数少ない女性ピアニスト、
守屋純子さんと、2003年に16歳で鮮烈なデビューを飾ったアルト・サックス奏者の
矢野沙織さんの対談を決行! お二人に“この10年のジャズ界と女性ミュージシャンの関係”について、実際に感じたことを自由に語っていただきました。

矢野沙織(左) 守屋純子(右)
「服装や生き方のかっこよさは、そのまま音楽のかっこよさにつながってる」(矢野)
守屋純子 「沙織ちゃんと初めて会ったのは、ちょうど10年くらい前かな。当時、私が最初のアルバム『My Favorite Colors』を作った頃で、懇意にしていただいていた
高橋達也さん(故人、
東京ユニオンを率い、ビッグバンド・ジャズの振興に力を注いだ)のイベントで会ったんだよね」
矢野沙織 「そうですね。あれは小学6年生の時でした。子供のジャズ・バンドに入ってたんですが、その先生が高橋さんとご縁があって、連れて行ってもらったんです」
守屋 「それで高橋さんに促されて沙織ちゃんがお客さんの前で吹いたんだけど、もうびっくり。〈ストレート・ノー・チェイサー〉だったかな。あとでまた呼ばれて〈ドナ・リー〉を吹いたよね。何が驚いたかと言うと、もちろんサックスのうまさもなんだけど、それ以上に人前で物怖じしない。この子はすごい! と思った」
矢野 「じつは、私は内向的な性格なんですけど、その頃から身長も結構あったから、なんか堂々とした態度のように見えたんですよ」
守屋 「それもよく分かるけど、ミュージシャンというのは、人前でやってこそナンボの世界なわけで、それができるかできないかで、うまいヘタとは違った、向き、不向きがある気がする。日本人では珍しいと思ったし、この子は素質があると思った。だから、あとで有名になっても驚かなかった。むしろ、当然だと。高橋さんもあの時、“この子は必ず成功する”とおっしゃってましたけど、同じことを感じたんだと思う」
矢野 「ありがとうございます。その頃、目上の女性と接すると、たいてい“かわいいわね”とか“まぁ、女の子なのに”なんて言われてたんですけど、守屋さんはそういうのとは関係なく、“音楽をやる人”としてわりと対等に見てくださってたというか」
守屋 「たしかにそうですね。ただ、一般的には、“美人シンガー”とか“美人ピアニスト”だとか、昔から数少ない女性ジャズ・ミュージシャンにはつきものの言葉ですよね。女性を立ててくれる言葉として受け止めてますけど、でも、そのイメージから入るというのはなくならないどころか、むしろ、最近は、より容貌を重視する傾向があるんじゃないかな。ジャズ界にも“イケメン・ミュージシャン”という言葉が出てきてるように」
 矢野
矢野 「それはありますね。ジャズにおいての一般的な女性らしい表現というのは、私はよくわからないんですけど、唯一私が思う女性らしさって、ミニスカートをはいたり、大きく胸の開いた服を着てステージに出ることなんです。もちろんそういうファッションが好きってこともありますけど、そのほうが自分も楽しいし、お客さんも喜んでくれるし」
守屋 「よく言った! 普通はそんな風に思ってても、絶対口に出して言えないからね。やっぱり矢野沙織はすごい(笑)。仮に私が男性だったとしたら、そっちのほうがいいと素直に思うよ。スウィングの楽しさも増すに決まってる。それが自然なジャズなんだと思う」
矢野 「初めて
キャンディー・ダルファーを見たとき、“何てかっこいいんだろう!”と思ったんですよ。金髪で胸を出しておヘソを出して、っていうあの姿に憧れたんです」
守屋 「そこを日本人は否定しがちなんだよね。逆に素直じゃなくなってる。ジャズって昔からかっこいいものだったでしょう?
マイルス・デイヴィスにしても
ジョン・コルトレーンにしても、あの人たちは服装も自由でおしゃれだった。根にそういうものがあるからこそ人を夢中にさせる。自然に生きて、何も隠さない。好きなことをやり、それが音楽に出る。これはメンタリティにも関係するんだけど」
矢野 「そうですよね。日本だったら、
日野皓正さんなんかかっこいいですよね。日野さんのかっこよさは、そのまま音楽のかっこよさにつながってる」
「ジャズを“らしさ”で決め付けてる。“女性らしさ”も同じ。個性なんて自然に音楽に反映されることだと思う」(守屋)
守屋 「やっぱりジャズはこうだと決め付けてはいけないと思うんだ。人それぞれ、いろんな個性があっていい。それに個性は真似なんてできないし、自然に暮らしていれば、誰だってそれなりに自然に生まれるものでしょう。有名なミュージシャンの誰かみたいに“個性を作れ”とよく言われるけれど、それは結局他人の真似をしろということに近いものね」
矢野 「私も昔、“ちょっと遅れた感じにすると、もっとジャズらしくなるよ”とか人によく言われたけれど、それは違うなと。そのもたっとした感じは、私はジャズじゃないとずっと思ってました」
 守屋
守屋 「それってよく言われるけど、結局ジャズを、“らしさ”で決め付けてるわけ。“女性らしさ”も同じで、私なんか、音楽においては自分が女性であるということを一度も考えたことがない。そんなことはほっといても自然に音楽に反映されることだと思う」
矢野 「私がサックス吹きということで、女性らしくないと言われたこともあったけど、これも自然な選択だったんですよね。ブラス・バンドで、単に楽器選びのじゃんけんに負けたからという(笑)。本当は女の子らしくフルートを吹きたかったけど、やむなくサックスに決まった。それまでサックスは見たこともなかったんですよ」
守屋 「女性は、ヴォーカルかピアノかフルートというのがこれまでの常識で、ドラムとか管楽器は無理だろうとなってたわけだけど、それはそう思い込まされていたに過ぎない。やってみたら十分できる。男性よりもうまく吹ける女性も出てきて、そんな常識は過去のものになった。そういう意味で矢野沙織の出現は衝撃的だったな」
矢野 「私は、ただぼーっとしてただけなんですけどね(笑)。小学生からサックスを吹いていて、中学生になった時、さて、この先どうしようと思ったんです。そこでやれることを考えた結果が、ジャズ雑誌にあったライヴ・ハウスのリストを頼りに、一軒一軒何とかやとってくれませんか? と電話をかけることだったんです」
守屋 「そこがすごいよね。しかも中学生がそれを実行するなんて」
矢野 「いやいや、今は中学生にそんなこと絶対に薦めませんよ(笑)。でも、それがきっかけで後押ししてくれる人に出会ったり、そして、幸運にもレコード会社の人の目に留まってレコード制作ができたわけです。ラッキーだったのはデビューの直後に映画の『スウィングガールズ』がヒットして、話題になったことと、そして
小林香織さんや
市原ひかりさんが次々デビューし一緒になって話題になったことです。一人だったら、こうはならなかったと思います」
守屋 「そんなことはないと思うよ。自信なさそうに言うけど、これは時代の流れだと思う。女性がジャズの世界に進出するのは自然なことで、今までの常識がおかしかった。人それぞれ個性が自然に備わっていて、それをジャズの中で表現するのは、当たり前のことだと思う。男女同権ということで言うと、これまではかわいいからいいとか、若いからいいといったことではなくて、明らかにうまいとかしっかりした個性、実力を持った魅力的な女性ジャズ・ミュージシャンが出てきたということが重要で、そういう意味では、たぶんピアノの
大西順子さんが登場したとき(90年初頭)が時代の分かれ目だったと思う。そして、管楽器では矢野沙織という開拓者が登場した――」
矢野 「私は男女同権とか声高に叫ぶ必要は全然ないと思ってるんですけど、女性らしさ、男性らしさはとても大切だと思うんですよね。アメリカのように何でも同じというのは違うと思う。女性は女性、男性は男性それぞれの役割はやはりあると思います」
守屋 「そう。いくら日本がアメリカの後を追おうとしても、それはできないと思う。文化もそれぞれ個性があるわけで、簡単なことではないから」
矢野 「そもそも私は、男性になりたいとは思わないですし」
守屋 「私も。とくに今の日本の男性は、いろいろとたいへんですよね。生きるためにしんどい仕事をやらなければいけない(笑)」
矢野 「自然に生きられなくなってるというか。音楽にしても自然体じゃないといいものが生まれないと思います」
守屋 「最近、大西順子さんや上原ひろみさんたちのように、今までにない強烈な個性を持った表現者が登場して、女性ジャズ・ミュージシャンがいろいろ話題になってるけれど、それは女性が強くなったというんじゃなくて、もしかすると男性が弱くなったんじゃないかとも思うんですけどね」
取材・文/青木和富(2010年6月)
撮影/土居政則
【Profile】 ■守屋純子
■守屋純子5歳よりピアノを習い、早稲田大学で“ハイソサエティーオーケストラ”に所属し、ジャズを始める。卒業後、ニューヨークのマンハッタン音楽院の大学院に留学。帰国後、97年にアルバム『My Favorite Colors』でデビュー。2005年、セロニアス・モンク・コンペティション作曲部門で優勝し、アジア人初、女性初の受賞という快挙を成し遂げた。最新作はトリオ作『THREE AND FOUR』。現在はジャズクラブやフェスティヴァル、FM番組などで活躍しているほか、大学などで後進指導も行なっている。
■矢野沙織1986年、東京生まれ。小学4年の時、ブラス・バンドでアルト・サックスを始める。その後チャーリー・パーカーを聴いて衝撃を受け、ジャズに傾倒。14歳から自らジャズ・クラブに出演交渉を行ないライヴ活動を開始する。2003年に名門SAVOYレーベルからアルバム『YANO SAORI』でデビュー。モダン・ジャズの起源であるビ・バップに真摯に取り組む姿やその実力が高い評価を受ける。2010年1月、早くも通算9枚目となるアルバム『BeBoP at The SAVOY』をリリースした。

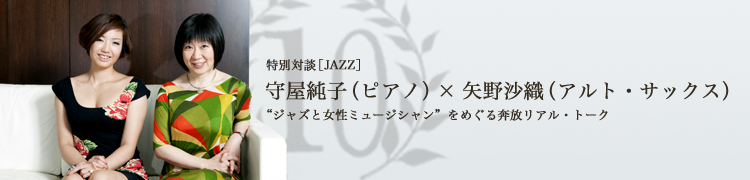

 矢野 「それはありますね。ジャズにおいての一般的な女性らしい表現というのは、私はよくわからないんですけど、唯一私が思う女性らしさって、ミニスカートをはいたり、大きく胸の開いた服を着てステージに出ることなんです。もちろんそういうファッションが好きってこともありますけど、そのほうが自分も楽しいし、お客さんも喜んでくれるし」
矢野 「それはありますね。ジャズにおいての一般的な女性らしい表現というのは、私はよくわからないんですけど、唯一私が思う女性らしさって、ミニスカートをはいたり、大きく胸の開いた服を着てステージに出ることなんです。もちろんそういうファッションが好きってこともありますけど、そのほうが自分も楽しいし、お客さんも喜んでくれるし」
 守屋 「それってよく言われるけど、結局ジャズを、“らしさ”で決め付けてるわけ。“女性らしさ”も同じで、私なんか、音楽においては自分が女性であるということを一度も考えたことがない。そんなことはほっといても自然に音楽に反映されることだと思う」
守屋 「それってよく言われるけど、結局ジャズを、“らしさ”で決め付けてるわけ。“女性らしさ”も同じで、私なんか、音楽においては自分が女性であるということを一度も考えたことがない。そんなことはほっといても自然に音楽に反映されることだと思う」 ■守屋純子
■守屋純子
 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。