“歌は世につれ、世は歌につれ”なんていうけれど、時代性にとらわれない、普遍的な輝きをたたえた歌を届けてくれる歌い手さんというのは、いつの世にも存在するもので。今回の特集では、目まぐるしくトレンドが移り変わる昨今の音楽シーンにおいて、自らのペースやスタンスを変えることなく、常に良質な“歌”を届けてくれる、
おおはた雄一、
イノトモ、
ハンバート ハンバートという3組のアーティストをご紹介します。過剰なまでに装飾された大味な音楽に食傷気味なあなたにこそ味わっていただきたい、シンプルながらも豊穣な味わいを持つ彼らの歌世界。僕たちの日常にさりげなく溶け込み、ささやかながらも、幸せなひとときを運んでくれるグッド・タイム・ミュージック。願わくばコーヒーでも飲みながら、ごゆるりと、味わっていただければ、と。
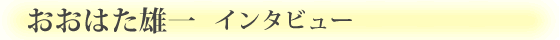

古き良きあの時代の空気を再び──といった懐古的なムードとはまったく関係ないところで、常に瑞々しい光を放ち続ける歌がある。時代という名の酸性雨をものともせず、決して輝きを失うことのない、それら名曲の数々は、まさしく、その素晴らしさがゆえに、心ある歌い手たちによって、これまで長きにわたり歌い継がれてきた。先ごろ初のカヴァー・アルバム
『SMALL TOWN TALK』を発表した、おおはた雄一も、そんな心ある歌い手のうちの一人だ。
レッドベリーの「GOODNIGHT,IRENE」や
ボブ・ディランの「Don’t Think Twice It’s All Right」といったライヴでもお馴染みの楽曲に加え、エリック・ジャスティン・カズの「If You’re Lonely」、
かまやつひろしの「ゴロワーズを吸ったことがあるかい」など、1970年前後の洋邦の名曲を中心に選曲した今作において、彼は得意の弾き語りを中心にした簡素なサウンド・アプローチで原曲が持つ普遍的な輝きを見事に際立たせている。
「今回は、実際に収録されている倍以上の曲数をレコーディングしたんですけど、最終的に残ったのは、本当に思い入れのある曲ばかり。たとえばB.J.トーマスの〈Raindrops Keep Fallin’ On My Head〉とかプラターズの〈ONLY YOU〉は、アマチュアの頃にバーで演奏してた曲だし」 
セルフ・プロデュースで制作が進められた今作で、彼がもっとも心がけたのは、客観性を保ちながら、いかにして楽曲そのものの魅力を引き出すかということだった。
「意識しなくても、自分の色みたいなものって、自然と演奏に出てしまうものだと思うので、今回は “自分らしい演奏”を、あえて意識しないようにしたんです。いかに自分を空っぽにして、肩の力を抜いて演奏できるかっていう。実際、やってみると難しかったですけどね。“さぁ空っぽになるぞ”と思ってもなかなか、なれるものじゃないし(笑)。目指すはジョアン・ジルベルト。あんな風に肩の力を抜いて、自然な姿勢で音楽と同化できたらいいなと思います」
ニュートラルなスタンスで楽曲に向き合うことで、結果的に「今までの作品の中で、自分の色が、いちばん自然に出せた気がする」という今作。
高田漣や
塚本功(
SLY MONGOOSE)といった、彼がシンパシーを抱くギター・プレイヤーとの共演も大きな聴きどころのひとつだ。
「漣くんは、自分が音楽を作るうえで、もはや欠かせない存在になっているような気がします。二人で演奏しているときの自由な感覚は、ちょっと他の人では味わえないんじゃないかと思うんです。塚本さんは、個人的に昔から大ファンだったんです。特に1stソロ・アルバム『Electric Spanish-175』で一気にヤラれちゃって。今回も、最初は自分でエレキを弾こうと思ったんですけど、どうしても“匂い”のあるギターを入れたいと思って。それで塚本さんにお願いすることにしたんです」 めまぐるしくテクノロジーが進化を遂げる一方、人肌の温もりを感じさせるアコースティック・サウンドに再び注目が集まり始めている昨今。活動当初より生音の響きにこだわり続けている、おおはた雄一は、自らが惹かれるアコースティック・サウンドについて次のように語る。
「生楽器に対するこだわりというよりも、弾いている人の存在みたいなものを感じられるような音楽が好きなんです。たとえばエレキ・ギターを使っていても、塚本さんの弾くギターからは、独自の存在感が生々しく漂ってくるから、僕にとっては、すごくアコースティックに感じられるんですね。その反面、いくらアコースティック楽器を使っていても、まったくアコースティックに感じられないような音楽もいっぱいあるし。演奏者の人柄が生々しく音に滲み出ているようなものに、どうしても惹かれてしまいますね。特に生楽器の響きからは、そういう感覚が、はっきりと伝わってくるから」
取材・文/望月 哲(2008年5月)
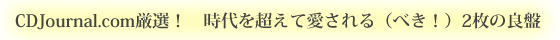
昨年から静かな反響を呼び、グラミー賞歌曲賞まで受賞したアイルランドの音楽映画
『once ダブリンの街角で』。主演の男女ミュージシャン2人による素のままの楽曲は、歌がもたらす本来の感動について改めて気づかせてくれた。そんな矢先に届いたハンバート ハンバートの
新作。こちらの2人が織り成す調べにも、どこか共通するものがある。会得したフォーク・ミュージックの深い懐の中で、一途に曲を作りギターを弾きフィドルを奏でる佐藤良成。今回は表題や1曲目「バビロン」にも明らかなように、度々アコギをエレキに持ち替えながら赤裸々な青春残酷物語まで盛り込んできた。それを澄んだせせらぎのような歌声で表わす佐野遊穂。すると、はびこる闇はみるみる浄化され一面に蒼々たる景色が広がっていく。そんな掛け合いはかつての
リチャード&
リンダ・トンプソンにも通じる武骨な優しさのよう。気高く生きるためのお伽噺として心して噛みしめたい。
(除川哲朗)
デビュー10周年を記念してのワンマン・ライヴは
フェアグラウンド・アトラクションのカヴァー「ハレルヤ」で幕を開けた。若草声が気持ち良さそうにメロディーと溶け合う瞬間、もはや彼女はその歌の住人であることを実感した次第。古きを訪ねて新しきを知るには、やはりこのくらいの月日が必要なのかもしれない。そして訪れる豊潤の季節。ベストCMTVワークス
『真昼の月』に続いてリリースされるオリジナル新作
『夜明けの星』は、そんな節目の作として申し分ない出来で、ますますシンプルに核心を突いている。工房感覚の手作りアコースティック。ただし調度品というよりも、椅子とか机、その上に乗る熟成されたパンのような日々の暮らしに欠かせない類だから味わいも一塩。岸田繁、塚本功、高田漣といった職人たちを招いての瑞々しい彩りも要所に、ささやかだけど確かなものを実感出来る至福の時を与えてくれる。まさにグッド・タイム・ミュージック。
(除川哲朗)

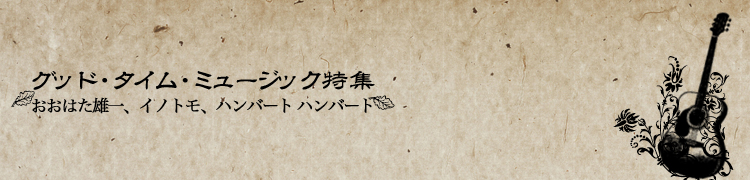
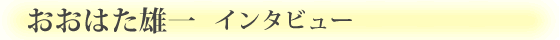

 セルフ・プロデュースで制作が進められた今作で、彼がもっとも心がけたのは、客観性を保ちながら、いかにして楽曲そのものの魅力を引き出すかということだった。
セルフ・プロデュースで制作が進められた今作で、彼がもっとも心がけたのは、客観性を保ちながら、いかにして楽曲そのものの魅力を引き出すかということだった。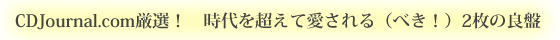



 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。