去る10月10日、
illmore や
ケンチンミン らが所属する新興レーベル
Chilly Source から、フィメール・ラッパー
pinok oがミニ・アルバム『
Hotel 』でデビューした。恋愛にとどまらない20代半ばの女性の光と影をせつなく、やるせなく歌う。キャリアはわずか3年弱だそうだが、ラップと歌を自在に行き来するパフォーマンスは堂に入ったものだ。
この日は彼女にとって人生初のインタビューだったそうで、終わったとき“すごく緊張しました”と言っていたが、社会人経験もあるためか受け答えも落ち着いていて、しっかり者という印象。……というだけでは終わらない、それなりに波瀾万丈の人生を送ってきたことが話すうちにわかってくるのだが、アルバム収録曲「where r u going?」にも示唆されている通り、街ですれ違う若い女性たちも似たようなものなのかもしれない。
――この時間(夜7時)取材スタートということは、昼間のお仕事をなさっている?
「はい。職種は内緒ですけど」
――職場の方たちはpinokoさんがラップをしているのはご存じなんですか?
「“Yo, yo, チェケラッチョって言ってます”って言って笑われてます(笑)。自分の音楽性を説明しても、詳しくない方だと理解できないかなと思って」
――pinokoというお名前で活動を始めたのはいつごろですか?
「えーと、この12月で3年です」
――pinokoを名乗ることにした理由は?
「23歳のとき病気になったんです。大きいのと軽いのといくつか見つかったんですけど、そのひとつが『ブラック・ジャック』のピノコが生まれたきっかけと同じ病気だったんです。卵巣嚢腫。それを友達に言ったら“MCネーム、ピノコにしなよ”って言われて、たしかにその名前だったらぐちゃぐちゃした気持ちを全部一緒にして曲にするみたいなイメージもあるな、って思って」
――『ブラック・ジャック』を読んだことは?
「ないです(笑)。いまようやく読み始めました。“好きなんですか?”って訊かれたりするので。去年、
手塚治虫 さんと
初音ミク がコラボした〈
全ての手塚作品へ敬意を。初音ミクより、ラップに乗せて 〉という企画に楽曲提供したんですけど、その曲が“手塚さんの88作品のタイトルを全部入れて韻を踏んでください”っていうリクエストで、すごい作品数だと思いました」
VIDEO
――プロフィールを拝見すると“15歳から路上ライヴを開始”とありますが、そのときはラップではなかったんですね。
「フォーク・デュオみたいな感じでした。ギターを弾いてくれる人がいて、わたしが歌って、ピアニカを吹いて」
――ピアノと和太鼓、あと篠笛も習っていたそうで。
「ピアノは4歳からやってました。母に“ピアノを始めてくれたらお菓子買ってあげる”とだまされて“やる”って(笑)。和太鼓も小学校の低学年から始めて、千葉県のジュニア大会みたいなので2位になったりしました」
――すごい。何か始めたらまじめにコツコツやるタイプですか?
「好きなことなので楽しんでやってて、努力してる感覚はないんですけどね。途中で飽きちゃうんですけど、基本はやり遂げる感じです」
――ラップを始めてわずか3年弱でこれだけの技術を身につけたのも納得です。
「ヒップホップはすごく長く聴いていたんです、そうとは知らずに。年齢がバラバラの家族で生活していたので、子供のころからクルマに乗るといろんなジャンルの曲が流れてきてて。
美空ひばり がかかったかと思えば
カーペンターズ が流れて、次は
B'z 、そして
長渕 剛 、みたいな。だからジャンルとかはわからないまま二十歳ぐらいまできてて、大学に入ったときサークルの友達に“俺らヒップホップしか聴かねえから”って言われて、“わたしヒップホップって知らない”“じゃあ俺らのカラオケ聴いてよ”って言うんで聴いたら“これ知ってる!”って(笑)」
――当時流行っていたのは?
――けっこうハーコーですね!
「いわゆる飲みサーだったんですけど、飲み曲が
鬼 さんの〈小名浜〉とか
キングギドラ の〈公開処刑〉でした(笑)」
――大学時代には音楽活動はしていましたか?
「全然。高校に入ってグレてしまって、学校に行かなくなって。テクノとかサイケが好きでクラブには行ってましたけど、自分がやることからは離れてました」
VIDEO
――23歳のときにご病気をなさったのがきっかけでラップを始めたそうですけど。
「手術をするとき病院のベッドで、もしかしたら二度と目が覚めないかもしれない、わたし死ぬのかな、って思って、やり残したことはなんだったろうって考えたんです。そしたら、サークルの人たちとカラオケに行ったときにマイクを回してサイファーみたいなことをやったときに“わたしできないから”ってやらなかったことがすごく悔やまれて……」
――そこなんですね(笑)。
「なんでやらなかったんだろう、やればできたかもしれないじゃん、って思って。頭には言いたいことも伝えたいこともあったのに、言ったらみんなにも伝わったかもしれないのに……って思ったら、これはすぐに始めないといけないと思って、手術が終わって退院したらすぐにラップを始めました」
――最初はどんなスタイルでやっていたんですか?
「最初に書いたのが〈たばこ〉です」
――あ、初めからいまのスタイルなんですね。
「そうですね。いろいろやってみたんですけど、これだったら他の人でもできるんじゃないかと思って、自分でないとできないスタイルってなんだろうって考えたんです。声が特徴的だねって言われることが多いので、それを生かして、昔は歌もうたっていたので、歌いながらやるのってなかなかみんなができることじゃないのかなって思って」
――やってみてどうでした?
「最初は思ったようにできなかったんです。考えてる内容と口に出ることが全然違っちゃったりして、みんなこんな難しいことしてたんだな、ってすごく思いました。でもだんだんと楽しくなって、やっぱやればできるんじゃん!って(笑)」
VIDEO
――始めてからChilly Sourceに入るまでの時間はどれくらい?
「入ったのが1年半ほど前で、レーベルができて半年後くらいなので早いほうだと思うんですけど、約1年半はひとりでやってました」
――当時はどうやって楽曲を発表していたんですか?
「音楽SNSを謳ったnanaっていうアプリですね。1分半が上限なんですけど、オケがいっぱい上がってて、そこに歌を乗せていくんです。それを毎日上げ続けていました。そこから現場に行ってみたいなと思ってイベントに行って、お友達ができて、“やってるの?”って言われて、聴かせたら“うちで宅録できるからやってみない?”って言われて、SoundCloudに上げ始めて、EPを出して、Chilly Sourceに加入、という流れですね」
――Chilly Sourceの人が最初のEPを聴いて誘ってくれたとか?
「去年の3月に出して7月に入ったんですけど、きっかけは全然違うんですよ。Chilly Sourceを主宰してる
DJ KRO さんがツイッターで企画をやってて、曲を送ってください、僕たちが気に入ったら無料でMVを作ります、みたいな。それに応募したらすぐに“ぜひ撮りたい”って言ってくださって、会いに行って話していたら“(君は)すごいChilly Sourceじゃない? 入ってよ!”みたいに言われて、そこで決めました」
――過ごしやすいですか?
「はい。みんなとっても温かいですし、価値観が合うんです。わたし自身もクラブは好きなんですけど、朝まで飲んで帰るときに虚しい気持ちになって疲労感がすごくて、“何やってんだろわたし……”って思うときがよくあるんです。Chilly Sourceの人たちとはその感覚を共有できて、翌日のお昼ごろにチルしながらカフェとかで話しながら聴ける音楽を目指したいね、って言ってやってるので」
「初めて会ったときに“あ、おんなじ!”って思いました。話すのが好きな人が多いですね」
VIDEO
――アルバム『Hotel』にはこの3年弱で作りためてきた曲が入っている?
「はい。他にもあるんですけど、本当に思い入れが強い曲を入れました。あとはDJ KROさんとかに“これ、俺好きだから”とか言われた曲と」
――特に思い入れが強いのは?
「全部そうなんですけど、気に入ってるのは〈すいみんやく〉ですね。いちばんわたしの黒いものが出てる曲です。一時期ほんとに眠れなくて、睡眠薬を飲んで寝ていた時期があって。歌詞にOD(過剰摂取)って出てきますけど、実際に飲みすぎちゃったりとか、もう起きなくていいやって思ったときもあるんですけど、目が覚めて朝になってたら“今日もがんばってみるか……”みたいな気持ちになったりして。こういう人っていっぱいいるんじゃないかと思うので、睡眠薬代わりに聴いてもらえればって書いた曲です。そして朝、起きたときに楽しいことが一個でもあったら生きていけるんじゃないかなと思って。ネガティヴなことを題材にはしてますけど、自分が元気になりたいから作ってる部分もあるので、少し希望を入れるようにしてて。それが伝わったらうれしいです」
――「Skit」がインストなのがユニークですね。
「アルバムの最後の8、9曲目にこれと〈after pills〉のリミックスが入ってるんですけど、〈where r u going?(sugarloaf remix)〉で始まって〈where r u going?(Original)〉で終わるイメージなんです。最初に“どこへ行くの?”って提示して、ここだよ、ここだよっていろんな曲を並べて、最後にもう一度問いかけをしていったんこのミニ・アルバムは終わっていて、〈Skit〉はエンドロールとして入れた感じです」
――僕が聴いていて印象的だったのは比喩でした。例えば「after pills」は記憶をチャラにするものの喩えですよね。「たばこ」はだんだんと短くなっていくものの喩え。
「それは自分でもすごく気にして書いてます。自分のことをちょっと客観視したいというか、自分目線で書いちゃうとほんとに黒いぐちゃぐちゃした気持ちしか書けないので、自分をものに喩えて視点を変えると、これにもいいところがあるんじゃないかなって思ったりするので」
――ほんとのドロドロにはしたくない?
「ドロドロにしてもいいと思うんですけど、自分のこと嫌いになっちゃいそうで(笑)。かといって距離をとりすぎると他人事みたいになっちゃいますし」
――さじ加減は難しいですね。僕も文章を書いていて、少しだけ筆が滑ったくらいがほめられたりするんですけど、意識的に同じくらいの調子にチューニングするのはなかなかできない。
「文章を書く方はすごいです。わたしの勤め先も文書をたくさん扱うんですけど、みんなたったひとことをすごく大事にしてて、自分のやってることと通じるところがあるなと思うんです。自分で文章を作って見てもらうと、“ここは相手に伝わるときにニュアンスが変わってしまう”とか言われたりして。指示代名詞が“それ”か“これ”かっていうところまでこだわるんですよ」
――そこに反応するpinokoさんも文章がお得意なのでは?
「もともと読むのが好きなんです。中学のときは全然学校に行ってなかったんですけど、図書館に入り浸って気になる本を全部借りて読んでました。この表現からは風景が浮かんでくるなとか、このひとことがすごく素敵だとか、そういうところに着目して物事を見てきたと思います。中高時代はすごいギャルだったんですけど、
村上春樹 とか読んでて」
――読書家のギャル。ギャップがあっていいですね。
「電車の中でうつむいて読んでたら、前に立ってる人にパン!って叩き落とされたりしてました(笑)。おまえみたいな格好したやつが本なんか読んでんじゃねえ、みたいな」
――“何すんだよ!”って凄んだりは?
「黙って拾ってました」
――見た目はイカツいけど怖い子ではなかったんですね。
「電車でおばあちゃんに席を譲ると全員びっくりみたいな(笑)」
――いまの落ち着いた物腰からは想像もつきませんが、どうしてグレたんですか?
「やっぱり家庭環境にすごく恵まれていたわけではないので……。両親とも不妊症で、12年ぐらいできなくて、やっとわたしが生まれたら1歳のときに父が亡くなってしまって。だから母には溺愛されてました。まわりもすごく優しくしてくれるんですけど、わたしの顔を見て泣き出したりするので“わたしってかわいそうな子なのかな”って思ったりしました。母は昼も夜もなく働いていたので、幼稚園のときから夜はひとりで過ごしたりしてて、寂しい気持ちもあったし。“母子家庭だからってバカにされたくない”と母が気を張っていたのもプレッシャーになってしまって、中学ぐらいになるとわたしの反抗期とお母さんの更年期が重なって(笑)、家出を繰り返したりしてました」
――いまはお母さんとは?
「仲よしです」
――よかった。お母さんは朝から晩まで働きながら習いごともさせてくれて、大事にされて育ったのは間違いないですものね。
「“ものはなくなっちゃうから買ってあげられないけど、身についたものは一生あなたの中にあって、誰にも取ることができない。そういうものにはお金をかけてあげられる”って言われて。勉強しなさいとかは言わない母でした」
――今後こんな活動をしていきたい、みたいな目標はありますか?
「まずはこのCDがみんなの手に渡ってくれるとうれしいですね。立ち止まらずに曲も作り続けたいですし。今回のアルバムは恋愛のことを歌った曲が多かったんですけど、集めたら恋愛が多くなっちゃっただけで、わたしはわりと“人生とは不条理なものである”みたいな考え方が強いので、そういう感じの曲も書いていきたいです。あと、もっと長期的な目標でいうと、いまで言うと
chelmico さんとか
iri さんとか、女性ラッパー / シンガーでうまくいってる方たちみたいになりたいの?ってよく訊かれるんですけど、あんまりそこは目指してなくて。わたし、
いとうせいこう さんになりたいんです」
――それはまた意外な名前が……(笑)。
「バラエティにも情報番組にもCMにも出られて、本も書いていらっしゃるじゃないですか。ああいうマルチな人になりたくて。もちろん音楽も作っていきたいですけど、もっともっといろんなことをやっていきたいなって思います」
取材・文 / 高岡洋詞(2018年10月)

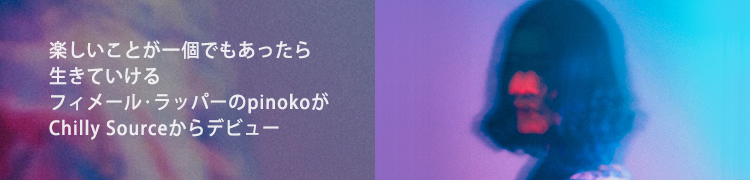

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。