俳優の佐藤浩市が、歌手としての初めて本格的なアルバム『役者唄 60 ALIVE』をリリースした。もともと彼は同じく俳優で歌手の原田芳雄の影響によって以前からライヴで歌うことを重ねてきており、それがこのアルバムにつながっていて、原田のレパートリーだった曲のカヴァーを中心としたブルース・アルバムになっている。存在感たっぷりなダンディズムあふれる声で、メロディ・ラインにとらわれずに自在性の高い歌声を聴かせ、それはまさに演技をするような表現であり、役者ならではの歌といえるだろう。原田の魂が乗り移ったような歌でありつつ、原田とは異なる今の時代のブルースとしても捉えられる力作だ。佐藤に話を聞いた。
――佐藤さんが歌うことになったきっかけって、どういうものだったんですか。
「20代の時に松田優作さんや原田芳雄さんがやっていたライヴに1、2度顔を出したことがありました。その後、芳雄さんと姻戚関係になり、彼のライヴでステージに上がって1曲歌わされたりしたことも。でもちゃんと歌うようになったのは芳雄さんの追悼ライヴを毎年、赤坂BLITZや下北沢のGardenでやっていた頃に年に数回、ステージに立たせていただいてからです」
――そういう機会を重ねて、佐藤さんの中で歌うことの醍醐味を感じるようになっていたんでしょうか。
「醍醐味なのかな。僕の中では正直言ってそのへんのところはまだわかりません。自分が今までまったくしたことがない経験をしているというか。今もそうですけどヘタクソなわけですよ。そのくやしさもあるし、来年はもうちょっとマシになろうという思いです。今でもよく覚えているのは、芳雄さんが“年取るとな、低いのが出ねえんだよ、上じゃねえんだ、下が出ねえんだよ”って言ってて。へえーって。そういうことが新鮮でした。実際に60歳を過ぎてみると、確かにそうだな、下が出なくなるな、響かせにくくなってきてるなって思う。自分たちで作った〈Life is too short〉(佐藤が作詞を手がけた新曲)も、3、4年前に作った時は下がきれいに響いていたのに、今歌うと下がきついなって思うようになったり」
VIDEO
――では今回のアルバムを作ることになったのは?
「2年以上前に、60歳の記念にアルバムを作ってみないかと提案されたのですが、ずっと返事を曖昧にしていました。そうしたらコロナになって、田舎に帰っていくスタッフたちや、いろんな連中の苦労を見ていて、自分たちの本業の世界がこういう中で、自分が歌を歌うということに対してモチベーションがまったく上がらなかった。だから申し訳ないけど今回は……って返事をしました。でもそれから1年弱経ってから、“芳雄さんの楽曲を中心に歌うのはどうですか?”って再度ボールを投げていただいて、芳雄さんの曲中心ならと思って。そこで意味合いが変わるわけではないけど、自分の中で“それだったらやってみようかな”っていう気持ちになりました」
――原田さんの曲を歌い継ぐことに意義がある、ということですか。
「意義ではないです。ただ、芳雄さんの曲を今こういった形で、記録として残せるのならと思いました。それと“ライヴで一発録りしませんか?”と言われて、それならやれるかなと思いました。(無観客ライヴの会場となった)ブルーノート東京も、リハも含めて数日間空けてくださいました」
――ライヴ・レコーディングのほうがやりやすかったということですか。
「スタジオのレコーディングをあまり経験したことがないし、何回も録音するっていうより、勢いでやったほうが役者の自分には合っているんじゃないかと思いました。プロの歌手の方は、ライヴ・レコーディングをやりますよとなったら、怖さを知っているから大変だと思うのですが、僕の場合は怖さを知らないので」
――そういう役者さんならではの歌、というのはすごく思ったんですけど、メロディ・ラインに縛られないで自由に歌っていますよね。とくに「ブルースで死にな」「横浜ホンキー・トンク・ブルース」などは語りかけるように歌っています。
「ブルースっぽいブルースだと多少遅れてもいいだろうって(笑)。だから芳雄さんや優作さんのような昔の役者はみんなブルースを歌っていたのかなとも思いました。ちょっと遅れても合うっていうか、それもひとつの形ですよね」
――原田芳雄さんの曲のカヴァーが中心なわけですけど、選曲は佐藤さんが歌い慣れている曲ということですか。
「そうです。〈ONLY MY SONG〉と〈DON'T YOU FEEL LONELY?〉はステージで毎回やっていた曲ですし、〈朝日のあたる家〉や〈ブルースで死にな〉も最初から歌っていました。〈LAZY DAY(OVER AND OVER AGAIN)〉だけ、今回初めて歌った曲です。これは〈Life is too short〉と同じで、喪失感がテーマ。喪失感を老犬にたとえた歌なので、これはぜひ入れたいと思いました」
――その選曲というところで、孤独感のある曲が多いですよね。「LAZY DAY」の“俺は今夜も独りで眠る”とか、「横浜ホンキー・トンク・ブルース」の“ひとり飲む酒わびしくて”とか、一人の情景を歌った曲が多くて、それが今の佐藤さんが歌うとすごくしっくりきて、孤独な男っぽいイメージが浮かび上がるんですよね。
「僕というよりは、ブルース、役者が歌う歌、原田芳雄、それらが三位一体となっているということだと思います。“ひとり飲む酒”は作詞が藤竜也さんですしね」
――佐藤さん自身がそういう曲を好む、というのはあると思いますか。
「必然的にそっちに寄ったと思います。最初からそう思っていたわけではなくて、僕が歌いたい曲を選んだらそういう曲だったということ。だから結果からするとそういうところがあるのかもしれません。その時の時代性からいってもそうなんでしょうね。あきらかに今の子たちが書く曲ではない。〈ブルースで死にな〉の“春は嫌だね、しんと寒いよ”“秋は辛いね、じんとこたえる”“酒と男が仕事のおまえ”とか、今の子たちは絶対に書かないでしょう(笑)。でも僕らの中では、人生を何十年か経過した中で聴くと、響くものがある。やっぱり僕らにとってはこういうことなんだなって思うなにかが、演歌であるしブルースであると思う。僕は日本のブルースは完璧に演歌だと思います。演歌の歌詞もブルースだと思うし」
――役者が歌ってこそいっそう生きる言葉、って感じはしますよね。
「今回のテーマが“役者唄”ということで、役者が歌う以上、どういう言葉を大事にするか。〈ブルースで死にな〉の“酒と男が仕事のおまえ”なんて言葉が、どんな風に相手に刺さってくれるか。そういう、役者が大事にする言葉のなにかっていう、それが歪みであったり重さであったり、そういうことを表現できないかなっていうのが、“役者唄”の発端でした。若い頃からミュージシャンの方とお芝居をすることがあって、音楽をやっている人は、僕らとは違うなにかがある。独特のリズム感だったりテンポだったり、所作が役者とは違うけど、それが上手い具合にしっくりとくる。そのおもしろさがあるように、もしかしたら、役者が歌った場合にも、歌手にはないなにかが、出てくるんじゃないかと思って、“役者唄”を始めました。今回、実際出ているかどうかはわかりません。わからないけど、歌い手の人にはない、役者が歌う言葉の独特な伝わり方が出せていたらいいと思います」
――佐藤さんにとって歌うということは、役者の時に演技をしてセリフを言うことに近いんでしょうか。
「全然違います。全然違うけど、近づけたいとは思います。だから譜面を無視していることはかなりありますし、〈横浜ホンキー・トンク・ブルース〉なんてまったく僕のアレンジ。それが僕のアプローチの仕方です」
――じゃあ、歌と芝居の違いってなんだと思いますか。
「なんだろうな。難しいですね。届く側にとっては一緒かもしれません。芝居も、表現として、刺さり方であったりとか。本質的には違うんだけど、その時々の瞬間的に拘束するなにかっていうのは絶対にある。そこがおもしろい。自分でやってやった!っていうなにかがあれば、僕は絶対的におもしろいと思う。それが原田芳雄の歌にもあったという気がします」
――原田さんの影響は、今でも相当にあるんですね。
「ありますね。〈愛の讃歌〉を芳雄さんが歌っていて、(本作のサウンド・プロデュースを手がけた原田)喧太からも“〈愛の讃歌〉やってみない?”って提案がありましたが、それは勘弁してほしいと言いました。僕にとってはまだアンタッチャブル。畏怖心もあれば、もちろんやりたい気持ちもありますが。映画のラスト・シーン(『寝取られ宗介』)でも芳雄さんは歌っているんですよ。女の心情を歌っていて、そこで毎回涙が出る。役者やミュージシャンというのとは違ったところに存在するなにかだったんじゃないのかな。僕はまだその域にいけていない。でもいつかは〈愛の讃歌〉が歌えたらいいなとは思います」
――佐藤さん自身で歌詞を書いた「Life is too short」は、先ほど喪失感がテーマと言っていましたが、相手がいなくなってしまうという、これも孤独感のある曲ですね。
「この曲は3、4年前、よく行くバーで、マスターの知り合いで今回作曲をやっている(田内)洵也がギターを持ってきて、夜中にブルース・コードを弾いて、それに合わせてアドリブで歌ったりして遊んでいたんですよ。たまたまその時、オリジナルを作らないかとなって30分くらいで作った曲です」
――この曲はヴォーカルがすごく丁寧に、やさしく歌われていますね。
「曲の感じがほかの曲とはまったく違いますよね。ブルースでもない。なんで人って、失うまで気づかないんだろうねという歌で、だからやさしく歌えたんだと思います。失うと相手の大切さをこんなに感じるのに、もっとやさしくしてあげればよかったって、相手を失った時にそう思う。本当はそうなる前に気づけばいいんだけど、なかなか気づけない。それを歌にした曲です」
VIDEO
――もうひとつ、今ってかつての原田芳雄さんとか松田優作さんとか、あるいは萩原健一さんのような、役者だからこその凄味のある歌を歌う人ってほとんどいないと思うんですけど、そういう意味で佐藤さんが歌うのはシーン的に大事なこととも思えるんですよね。
「人生の酸いも甘いもある程度通過した人間が歌を歌ったらどうなるのかなという、それも異業種の役者が。そういう意味で言うと、すごくナローなジャンルだと思います。70〜80年代にはあったけど、今はもうほとんど存在していない。だけどこんなジャンルがこれからも生き延びていっても、もしかしたらおもしろいんじゃないのかなという可能性は感じます」
――じゃあ、またライヴをやってみたいと思いますか。
「そうですね。ワンマンはプレッシャーがかかるけど、またみんなとやりたいし、“役者唄”というテーマで、役者みんなが集まって、自分たちが好きな歌を歌って、それがプロが歌うものとは違うなにかが届けられれば、それはそれでおもしろいと思う。狭いジャンルだけど、やっていける可能性はあると思います。今でも気持ちはアマチュア。昔、親父に言われたんです。“プロの鎧を着たアマチュアであれ”って。その気持ちが自分の中でずっとあります」
取材・文/小山 守

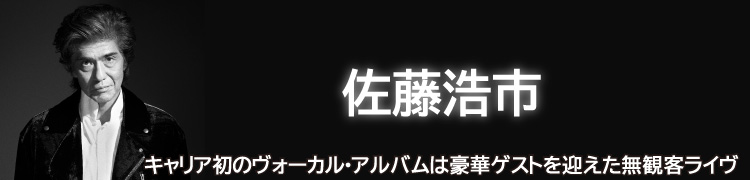


 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。