弾き語り、バンド、アイドルとシーンの壁を越えた活動を繰り広げている20歳のアーティスト、シバノソウが1stフル・アルバム『あこがれ』を発表。80年代〜90年代のオルタナ、シューゲイザーを昇華したバンド・サウンド、生きづらさを抱えながらも、“あこがれの先”へと向かう意思を反映せた歌が一つになった本作は、彼女自身の独創的な音楽性とリアルな生き様が強く刻まれている。アルバム『あこがれ』にまつわるインタビューを通し、さまざまなコンプレックスを抱えた10代の少女が、ナンバーガールやスーパーカーと出会い、心から好きだと思える音楽を掴み取るまでのストーリーを追体験してほしい。
――1stフル・アルバム『あこがれ』、素晴らしいですね。90年代のオルタナやシューゲイザーを強く感じさせるサウンド、シバノソウさん自身の生々しい感情が真っ直ぐに伝わってきます。
「ありがとうございます。“圧が強い”という評価を受けたんですよ(笑)。自分でも“確かに熱量が高いかも”と思います。リード曲の〈あの夏の少女〉を録ったときに“このアルバム、売れないと困るんです!”ってレコーディング・スタジオで絶叫してたら、“その調子でやってみましょう”と言われて、叫ぶような感じで歌いました。そういう熱量や焦燥感、切羽詰まってる感じが入ってるのかな」
――“売れないとヤバイ”という焦りはレコーディング中、ずっと感じてたんですか?
「そうですね。1年くらい前に入っていた事務所を辞めて、CDを出せない期間があったんです。今回のレコーディングは自分でお金を工面して、バンド・メンバーも自分で集めて、いろいろ焦っていて。私、だいぶ生き急いでると言われるんです。映画監督の山中瑶子さんにコメントをいただいたんですけど、そこにも“きっと人生の長さに絶望しているのでしょうけど”と書いてあって、“そうなんです”と思いました。高校生から活動しているんですけど、そろそろ結果を出さないといけないと思ってたし、(制作期間の)去年の夏の暑さもあいまって、熱量の高いアルバムになったのかもしれないです」
――事務所を辞めて、すぐに一人でやろうと決めたんですか?
「辞めた直後は落ち込んでたんですけど、そこから立ち上がるときに“版権死守だ!”と思って、それが座右の銘になってます(真顔)。あと、音楽家というよりも、プロデューサー的なことに興味があるというか、“この人にこれをお願いしたい”ということをやってみたくて。それを実行するためには、一人で活動したほうがいいのかなって」
――なるほど。活動全体のビジョンは、どう描いていたんですか?
「もともと高校生の時は最短ルートで売れようと思っていたんです(笑)。アイドルともよく対バンしていたし、シンガー・ソングライターやバンド形態でも活動していて、それぞれに認知されたらいいなと。でも最近、そういうことは重要じゃないと思うようになって。それよりも生きづらさみたいなものを共有したり、見守ったり、思い出してもらえたらいいなって。それを意図的に曲にしているわけではないんですけど。それをやったら見透かされるので。でも、自分のなかに起きていることは変化を感じてもらって、生きづらさを抱えている人、いまは“ちょっと大人になったな”という気分の人に刺さってくれたらと思ってます」
――シバノソウさん自身も、同じような体験があるんですか? 音楽を聴くことで、自分の生きづらさを昇華するというか……。
「そうですね。私、きのこ帝国が大好きなんです。中学生のときは感情移入しながら聴いていたし、いま聴いてもやっぱり良いんです。そういう感じで聴いてもらいたいんですよね、私の音楽も。日記を書くような感じで曲を作ってるので、それをのぞき見するようにして聴いてもらいたい。全員に伝わらなくても、沁みる人に沁みればいいという気持ちもあります。事務所を辞めたときに“私はメジャーの人間じゃない”とわかったので(笑)、そこは意識しないで、自分が好きな感じにしたいなと。レコーディングのメンバーも自分で選ばせてもらって、“こういう音にしてください”と要望を出させてもらって。私以外にプロデューサー的な人が入ると、どうしても純度が落ちてしまう気がしたんですよね。それはつらいので、今回は好きな人たちと一緒にやりたかったんです」
――セルフ・プロデュースに近い形で制作することで、イメージ通りの音になったと。オルタナ、シューゲイザーのテイストが強く反映されていますが、こういうジャンルの音楽を聴き始めたのはいつ頃ですか?
「中2くらいですね。塾の先輩にSAKANAMONを教えてもらったんですが、YouTubeで動画を見ていたら、関連動画にナンバーガールの〈鉄風 鋭くなって〉やスーパーカーが出てきて、“すごい!”と思って。あとは学校の先輩に、きのこ帝国やPOLYSICSを教えてもらったりしてCDを買ってました。とくにナンバーガールは衝撃でしたね。“最近にはない感じだ”と思ったし、すでに解散してたので“もう見られない”というノスタルジーもありました」
――ナンバーガール、再結成しましたね。
「2回ライヴを観ました! チケット当たるように、毎日お祈りしたんですよ! 豊洲と日比谷(野外音楽堂)で観たんですけど、すごかったです」
――20歳くらいのリスナーにも支持されてるんですね。
「好きな人は多いと思います。BiSHのアユニ・Dさんのバンド(PEDRO)に田渕ひさ子さんが参加していて、それをきっかけに知った人もいるみたいで若い人も多かったですよ。私は向井秀徳さんが好きで。ふだんは“シュートク(秀徳)”って呼んでるんですけど(笑)、シュートクに曲を書いてもらうのが目標です」
――『あこがれ』というアルバム・タイトルについては?
「最初は『ティーンエイジ・サマードリーム』というタイトルにしようと思っていたんです。“10代の夏の夢”ということなんですけど、ちょっとわかりにくいかなと思って。さっきも言いましたけど、私はずっと生き急いできて、“20代で死のう”みたいな感じだったんです。高校3年のときにWWWでワンマンをやって、“ここからどんどん売れていこう”と思ってたら事務所とうまくいかなくて、意気消沈して。でも20歳になっても死ななかったし、どうやらこれからも生きていくらしい……という曲が〈あこがれの先へ〉なんです」
――“あこがれ”というワードに対してはどんな思いがあるんですか?
「10代のときは、“高校の同級生とうまく付き合えなかった”“軽音楽部に入れなかった”“バンドを組めなかった”“アイドルみたいにかわいくなれない”とか、嫉妬や憎しみを抱えることが多かったんです。でも、今は一緒にレコーディングしてくれるメンバーもいるし、成人式で同級生に会ったときも、わりと普通に話ができて、ちょっとずつ気持ちがフラットになってるんです。“今からでもやりたいこと、憧れていたことはできるかもしれない”というモードになってるというか。16歳のときに出した最初のCDが〈愛憎?〉で、20代になって最初に出すCDのタイトルが『あこがれ』というのは、それだけ成長したのかもしれないです」
――“愛憎”から脱して、フラットな状態になれたのはどうしてだと思いますか?
「アルバムを出せることが決まったからですね。あと、人と関わるようになったのが大きいと思います。今までは誰にも頼まず、“一人でやれるんで!”って意固地になっていたんです。周りに才能がある人が多かったから、“一人でやれることを増やして、自分で提示できないと”という気持ちもあったし。でも、今回のアルバムの制作では“こういう曲をやりたいので力を貸してください”といろいろ話して。それで思い通りのものが作れたことがすごくよかったなって思います」
――好きなサウンドを共有し合えるミュージシャンとの出会いも大きいですよね。
「そうですね。アルバムに参加してくれたミュージシャンは全員20代で、インディ・ロックのシーンで活動している人が多くて。前は40代くらいの人たちとやることが多かったんですけど、意思の疎通が難しい部分も多かったというか……(笑)。たとえば“マイブラ(マイ・ブラッディ・バレンタイン)みたいな感じでやりたい”と言っても、マイブラの解釈がちょっと違ってたり」
――なるほど(笑)。わかる気がします。
「“そこまで太い音じゃなくて、もっと今っぽい浮遊感がほしくて……”みたいなことを伝えても、なかなかそうならなくて。それも楽しかったんですけど、今一緒にやってる人たちは、“こういう感じだよね?”“それ!”とすぐに通じ合えるんです」
――アルバムの最後に入っている「モラトリアム・ナインティーン」についても聞かせてください。“鬱屈した感情を解き放ちたい”という思いが真っ直ぐ伝わってくる曲ですね。
「アルバムをきれいに終わらせたくなかったんです(笑)。“いつになれば人間になれるのかな”って歌ってるんですけど、“結局、まだ人間にもなれてない。ムリ”という開き直りだったり、ヤケになってる歌です。間奏でメチャクチャにギターを弾いてもらってるんですけど、録ってるとき“もっと狂って! 中学生の時の自分を思い出して!”ってみんなに言って(笑)」
――“中学生のときの自分”がキーワード?
「その頃の自分が常にそばにいるんですよ。すぐ近くにいて……バンドを組んだり、ちょっと楽しいことがあると、“おまえ、変わっちまったな”って話しかけてくるんです(笑)。そのたびに“そんなことないよ!”って自問自答してます」
――『あこがれ』とともに20代のシバノソウが始まります。次の展開はどうなりそうですか?
「ほかのアーティストに楽曲提供をしていただきたいし、幅を広げたいと思ってます。自分が好きな方にお願いしたいし、こちらの意図をお伝えしつつ、全面的にお任せしてみたい。そういう音楽が好きだった自分の思いも報われると思うんです」
――オリジナル曲にはこだわらない、と。
「そこはぜんぜんこだわってないです。自分のエッセンスが入っていれば歌う意味があると思うし、私の意図と作ってる方の意図を合わせてながら作ってみたい。もちろんCDも作りたいし、映画にも関わりたいと思っていて。私がいいなと思っている人と一緒に何かをやりたいんですよ。今回のアルバムで、その土台ができたかなと」
――すごく閉じこもってるところもあれば、積極的に他者と関わりたい願望もありますよね。
「ははは(笑)。関りたい人には勢いよくバーッといくんですけど、上手くいかないことも当然あって。そこもずっと自問自答してますね(笑)」
取材・文/森 朋之

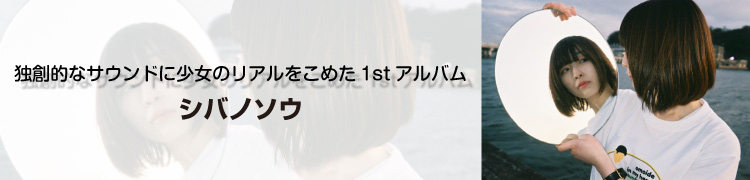



 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。