理想的なバンドだ。バンドはこういうものだといった概念にとらわれることなく、4人のメンバーでじっくり年輪を重ねてきたことが、約3年半ぶりとなる2ndアルバム
『たからじま』からは確かに感じられる。原点にあるのは「なんだかやれそう」という根拠のない想いと、この4人の信頼関係だ。音楽性が先立つのではなく、この4人が揃っているからこそ、
シャムキャッツという音楽が生まれている。感覚はそのままに、バンドとしての芯が太くなった彼らに話を訊いた。

――シャムキャッツのみなさんは、音楽誌で語られているような系統に従って音楽を聴くというより、感覚に従って音楽を聴いているような印象がありますよね。
夏目知幸(以下、夏目) 「うん、全員が直感で聴いていると思います。もちろん音源を作るときに、ドラムやギターの音、ミックスの感じとかを参考にするためにジャンルやアーティストを絞って音楽を共有することはあるんですけど、そういう系譜の中にバンドの音を求めようっていう考えはないです。いま生きている4人から自然に出てきたものをやる、自分たちの気にいった形にするために参考にするっていうのが根本ですね」
菅原慎一(以下、菅原) 「ただ、今回は、個人的に日本の70年代とかのポップスを意識的に聴いてましたね。こういう感じの曲に仕立てたいなっていう資料集め的な感覚で」
――夏目くんは、資料的に聴くってことはあるんですか。
夏目 「一人でやる曲作りに関しては僕は全然ないかも。何となくインスパイアされることはありますけど。自然に出てきたものに対する肉付けのために資料的に聴くことはあります。真似るってことがすごく苦手なバンドなので、雰囲気を共有するくらいのものにしかなんないですが(笑)」
――でも、バンドを始めた頃は、誰かしらのコピーをして楽器を練習していたわけですよね?
夏目 「菅原はしてないよね」
菅原 「僕はシャムキャッツで、初めてエレキ・ギターを弾いたので、何もコピーをしたことがないんですよ。教科書通りに弾こうと思ったことはなくて。でも楽器を触っていると、何となく音のアリ/ナシに気づくじゃないですか?」
夏目 「あはは。気づきね」
――かなり感覚的なんですね。他の三人は、そうした菅原くんの音の探り方をどう感じてるんですか。音を合わせると、ばちっとハマる?
夏目 「ハマりますね。僕は、そこのバランスを見ているところもあって、わりと全体を把握しているつもりです。菅原が“何々系”って名付けずらいギター・プレイをするでしょ? あれ、バンドの武器だと思うんですけどそれを菅原が繰り出したときは僕が暴れちゃうと収集つかなくなるんで、僕はまあ普通にやっとくかな、とか。菅原が引き気味だったらちょっと前出ておくかな、とか」
――シャムキャッツは地元が一緒とはいえ、結成当時からメンバーも変わっていないし、本当に結びつきが強いですよね。それは本人達としても感じますか。
夏目 「強いと思いますよ」
――なんで、この4人だったんでしょうね。
夏目 「それが不思議なんですよね。大学を卒業するときにバンドをやるって決めたんですけど、そのときバンドはちゃんと動いていなかったので、やっていけるなんて確証は全然なくて。ただ、この4人だったら、いけそうだったので踏み切ったんです」
藤村頼正(以下、藤村) 「いけそう感はすごいあったよね」
夏目 「それでバンドが始まったんですよ。バンビ(大塚)以外は楽器もろくに弾けないのに(笑)」
藤村 「いやいや楽器じゃないだろう、ソウルだろう! って言ってね(笑)」
――あははは。それって、1曲目の「なんだかやれそう」にも繋がる感覚ですか?
夏目 「ほとんど一緒かもね。そういえば、ずっと思っているよね。なんだかやれそうっていう感覚を」
藤村 「そう思っているバンドは多いと思いますよ」
夏目 「じゃないと、続けられないよね」
大塚智之(以下、大塚) 「そこに関しては1回もネガティブになったことはないよね」
一同 「ない」
夏目 「多分、なんだかやれなそうになると、ダメなんだよね」
――でも、さすがに東日本大震災のあとは落ちこんだんじゃないですか。バンドを続けるのかって悩んだりしなかったのかなって。
夏目 「むしろ4人の結束みたいなものが強くなったよね」
藤村 「そうだね。拠り所じゃないですけど」
夏目 「よく覚えているのが、下北沢シェルターでアコースティック・ライヴをやったときのことなんですけど、4人いることで自由に遊べるんだなと思ったんですよ。電気を使わず盛り上げられたし、楽しさを出せたし、バンドの強さを感じました」
藤村 「本当に貴重だなって感じましたね」
夏目 「一人で出て行って歌う人たちもよかったけど、ああいう状況で、4人が集まって“いくぞ!”ってなったら楽しくないですか? やっぱりバンドっていいなって実感したし」
藤村 「あと、思春期をともにしているのは大きいかもね」
夏目 「そうね。大学を出るとき、4人全員がこのバンドやるために就職しないってなれてよかったよね。音楽で生きていくためにバンドがあるってわけじゃなくて、バンドをやるために大学を出て勝手に過ごしているから。そこらへんは揺れないよね」
――あの……僕もそのなんだかやれそう感が欲しいです。
一同 「(笑)」
夏目 「僕もライターさんみたいにひとりでやらなきゃいけない仕事ならダメだったかも。他のメンバーがいるから保てるってところがすごくあって。1人だと負けちゃうんですよ。だから、“本当にラッキーだな、俺”って思います。極端な話、バンドの中で誰かひとりダメダメになっても他の3人がしっかりしてればなんとなく事は進んでいくし、それに乗ってればダメダメなひとりも、なんとなくいい感じに乗れていくと思うんで、まあ気の合う奴が近くにいて、ラッキーだなと思います」
――大学を卒業したてだったら、まだそういう感覚ってあると思うんですけど、20代後半になっても、そういう繋がりを持てているのがいいなって。
夏目 「僕たちのやっている部分って、遊びの楽しさじゃないけど、そういう感覚でやりたいっていうのが強いんですよね。ライヴが終わって一番嬉しい感想は、“バンドやりたくなりました”っていう言葉。『たからじま』はバンドにこだわりました。
『GUM』もそうなので、“続”って感じですね。DJに言われると嬉しいですね。“だろ?”って言いたくなりますもん(笑)。もちろんDJっていう文化も素晴らしいと思ってます。けど、やっぱ“バンドでしょ〜”って思ってます!」
――たしかにバンド感が強く感じられる作品だと思います。今作では、菅原くんの作詞作曲した楽曲が収められているのも一つのトピックですよね。宿題的な感じで、作ることを課して、それに向かって作ったんですか?
菅原 「完全にそうですね(笑)。シャムキャッツには夏目というソングライターがいるから、自分の曲は必要ないよなぁって思ってましたから。でも今回からはよし!という感じで。バンドの作業として、自分の中では新しいことばかりでした。簡単なうたとコードを作って聞かせるっていう感じで」
――その曲をどうやって膨らませていったんですか。
菅原 「夏目と2人で阿佐ヶ谷のスタジオに入ったんですけど、まともに自分の曲を披露するのは初めてなので、緊張するんですよ。この曲はあれだけど、こっちはいけそうだなって感じで進めていって」
夏目 「初めてだったので緊張しましたけど、けっこうすんなりいけました」
菅原 「センスがあまり違わないというか、夏目とは幼稚園からずっと一緒だし、聴いてきた音楽も似てるから、これはOKでこれはダメというラインも近いところにあって、拒絶とかは特になかったよね」
夏目 「ないないない」
菅原 「ただ、僕がシャムキャッツのソングライティングに関わる以上は、夏目とは違う自分のよさを出さなくちゃいけないと思ったので、曲ごとにセレクトの基準がありましたけども」
夏目 「いろいろな方向が見えましたよ。追い込まれてできた曲もあるし、自然に出来た曲もあるし、菅原がやったのもあるし、ふたりで合わせてできた曲もあるし」
藤村 「〈スピークアウト〉とかは4人でジャムってできたし」
夏目 「そうだね。アウトプットまでの過程のスタイルがいろいろ見えたから、遊べそうだなと。「本当の人」とか、1回菅原が弾いたんですけど、Aメロもコードがガタついてるところがあったから、話しあって進めていって。理想的なソングライターがふたりいるみたいなソングライター同士としての菅原との会話が新鮮で、、バンドとしては理想的なカタチだなあと感じました。すごい楽しかったです」
――夏目くんにとってソングライターがふたりになるというのはどういう感じなんですか。
夏目 「今まではメロディはほとんど自分で考えて、バンドのアンサンブルをみんなで自由にやっていたんですけど、メロディの部分も俺だけが考えなくていいわけじゃないですか。そこでまた曲のおもしろさの幅が広がったので、これからが楽しみですけどね。要はバリエーションが増えるというか」
――リズム隊の藤村くん大塚くんは、ソングライターがふたりになったことで、何かしら変化はありました?
藤村 「ふたりはキャラクターが似ているようで違うので、菅原くんが曲を作って合わせるときは、普段と違う合わせ方に自然となるんですよね。菅原くんのは最初、ぼんやりといいものを提示してくれるというか」
夏目 「菅原の曲は最初ぼんやりとしているけど、曲の全体像は見えるんですよ。要は画用紙を用意して、ここに家があって風景山があって、っていう全体の感じはわかるんですよね。僕の場合は絶対にここに赤い家が必要だ! みたいなところから始まることが多いんですよ。全体像はあまり見えないというか、点々のおもしろさでやっていくことが多いので、多分その作り方の違いでプレイヤーは身の振り方が変わってくるんです」
菅原 「それによって、4人の立ち位置が変わってくるからおもしろいよね。夏目の作った曲の場合、ふじまん(藤村)は特攻したりするけど、僕のときは後ろで守るように叩いてくれたり。夏目ではなく僕がリズム・ギターを弾くと、いつもとタイム感が変わって、そこでまた化学変化も生まれてきて」
夏目 「それはすごく感じました。やったことがないことだから、全然違うよね。フォーメーションが変わってくるからグルーヴも変わってくるんですよね」
大塚 「意外かもしれないですけど、菅原くんのやり方のほうが、王道というかオーソドックスだから、むしろやりやすかったです」
藤村 「そうそう、やりやすかった」
大塚 「先にへんてこなほうやっておいてよかったなって(笑)」
一同 「(笑)」
菅原 「俺もすげえそう思った。普通にコード弾いているだけでいいんだって」
大塚 「それも今だからこそできたのかなって」
藤村 「それがスタートだったらよくなかったんだろうなってのはあるよね」
夏目 「俺もリード・ギターを弾く楽しさがすごくて。ずっと歌いながらやっていなきゃいけなかったんですけど、(菅原が)歌ってリズム・ギターをやってくれるじゃないですか。そしたら、俺動けるぜー! と思って、楽しくて」
――じゃあ、今後はリズム隊の2人が作詞作曲して、それぞれの曲を歌う可能性もあるかもしれないですね。
夏目 「藤村がリンゴ・スター的な感じで、歌ってもいいんじゃないですか(笑)」
大塚 「サザンオールスターズの〈松田の子守歌〉みたいなのもね」
――非常に状態がいいシャムキャッツですが、ゴールというか目標みたいなものは見据えているんですか。
大塚 「変に括られてないからこそ、自分たちができることはこうだってのがはっきり見えてきているというか。アイデンティティが発見されていくので、そういう意味で自分たちの進む方向はこっちかなってのは見えますよね」
――4人ありきで進んでいくということは変わらなそうですね。
夏目 「そうですね。これからも何をやったらおもしろいか、格好いいかとかを考えてやっていこうと思います」
取材・文/西澤裕郎(2012年11月)



 ――シャムキャッツのみなさんは、音楽誌で語られているような系統に従って音楽を聴くというより、感覚に従って音楽を聴いているような印象がありますよね。
――シャムキャッツのみなさんは、音楽誌で語られているような系統に従って音楽を聴くというより、感覚に従って音楽を聴いているような印象がありますよね。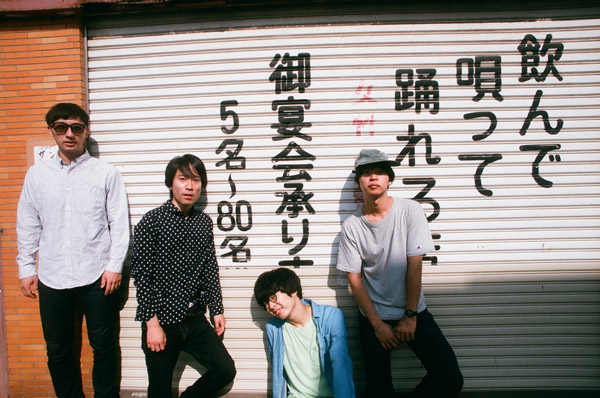

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。