――1年半ぶりの作品が3作連続リリースということで結構な量があるわけですけど、スパングルは逆にデビュー時から比べるとどんどん軽やかになってる印象を受けます。
藤枝憲(以下、同) 「いま、バンド内は何やってもオッケーな状態、いろんなことをひっくるめて、バンドが一周した感じがあるんですよ。スパングルを始めた頃は、知り合いのデザイナーとかカメラマン、モデルとか編集者でもいいんだけど、そういう人たちに“僕、バンドやってるんですよ”ってCD持っていくのは恥ずかしいっていうか、スゴいヤだなって(笑)。そんなの絶対いいはずがないっていうか、自分が渡されても絶対聴かないですもん。だから、最初の5、6年は自分たちからバンドの話はしないし、音源も渡さないようにしようって。でも、さすがに10年もバンドをやってると、どんなに趣味ですって言ってても、デビュー1、2年のメジャー・バンドよりはプロっぽくなっちゃうっていうか、そういう意味での開き直りがちょっと出てきたし、もう許してくれって思ったりもしつつ(笑)。2008年の結成10周年で出した『ISOLATION』と『PURPLE』は何度目かのECMブームが来たこともあるし、部屋で流したまま仕事ができるアルバムっていうか、自分たちのやりたいことをやって、ファン・サービスをしなかったので、今回は逆にそういう作品を出したかったんですよ」
――だからこそ、今回のシングル「dreamer」とアルバム『VIEW』は前2作とは真逆にポップ・サイドへ振ってみたっていう?
「そうそう。ホントにそういうバランスだけでやってますって感じなので、こういう取材ではバンドのアティテュードや作品に関して話してるのはフレームだけ、中身に関してはほとんど話すことがないっていう」
――構造主義というか、ニューウェイヴ的というか。ナラティブやメッセージと距離を置いているという意味でスパングルの表現はサウンド・アートにも近い気もします。
「リスナーとしての自分は
サニーデイ・サービスや
空気公団みたいに街の風景を情緒的に切り取った音楽も好きなんですけど、自分がやるとなるとまた違って。人間、変わっていくし、35歳になって、20歳の時に考えてたことって恥ずかしいことがいっぱいあるから、逆にメッセージがないスパングルの音楽は10年経っても歌えるんですよ。それにメンバー間でのメッセージ的な接点はまったくないというか、逆にデザインだったり、バランスみたいなところにしか共通項がないんですよ」
――「dreamer」の共同プロデュースを担当した永井聖一さんがやってる相対性理論もそういうグループだと思うんですけど、大坪さんの歌詞が意味性よりも音声的な響きを重んじているのに対して、今回、永井さんが提供した歌詞はシングルということを踏まえて、もう少し意味性を持たせていますよね。 「そうですね。相対性理論は音楽もそうだし、それ以外のジャンルや年代の縦と横の軸のバランス感覚や距離の取り方も上手くて、メンバーみんなが歌詞の添削をしているみたいだし、唯一、歌詞を頼んでもいいかなって思うグループだったんですけど、シングルであることも踏まえて、うちらの微妙なニュアンスも汲み取ってくれたんですね。今回、永井くんには、ヴォーカルのディレクションもお願いしたんですけど、彼はギタリストなんで、歌詞も頼むんだったら、うちらギター2人も弾かないくらいやらないと面白くないから、ギターも委ねることにしたんです」
――そして、前2作の反動で、ポップな反転をシングル「dreamer」に象徴させた後、ROVOの益子樹さんと再び組んだ『VIEW』はスパングルのポップス・アルバムですよね? 「そう。そういう『VIEW』が作りたかったから、その前に<dreamer>を置いたんですけど、『VIEW』は時間と経験を経たからこそ作ることができたセルフ・パロディ。過去の作品で一番売れた
『Nanae』をプロデュースしてくれた益子さんとそこに
『Trace』のポップ感を加えて作り上げたアルバムですよね。このアルバムには、10年前にバンドでほぼ初めてレコーディングしたもののお蔵入りになってた<泣いたり>をリメイクした<rara>、それから『PURPLE』の<rio>と『ISOLATION』の<roam in octave>をリメイクした<rio the other>も収録したんですけど、そういう意味ではベタなスパングルの素材を集めて作ったものというか」
――そして、具象を極めたアルバム『VIEW』からtoeの美濃隆章さんが共同プロデュースのさらなる新作アルバム『forest at the head of a river』の抽象へ。 「今回の3枚の構想は作る前にあったというか、そういうものがないと分かりにくいですし、この後も続いていくという意味で現状の最新作は抽象的な作品にしておきたかったんです。ただ、ここ2、3年でみんなパソコンでデモを作るようになって、そうすると完成形が見えちゃうんですよね。だから、もうちょっと抽象的なものを作るにはスタジオであうんの呼吸でやってみるとか、ひたすら長く演奏して、よかった部分をピック・アップする作り方でもしないとなっていうことでセッションをもとにした作品になってますね」
――この作品は意味性よりも音声的な響きを重んじた大坪さんのアブストラクトな歌詞と歌唱法、ここ10年では傑出した才能だと個人的には思っているんですけど、その魅力が抽象的な音の流れのなかで映えますよね。
「僕もそう思っているんですけど、誰も評価してくれないんですよ(笑)。日本語の歌詞って、まだ、そんなに荒らされていない領域だと思っているんですけど、日本語の歌詞でここまでアップデートしたことをやってる人はそんなにいないんじゃないかって。本人は彫刻を彫るように作ってるって言ってるんですけど、感情とか情景だけじゃなく、字画の濃さとか音声とか、そういう不思議なバランスで成り立ってるんですよね。これが凡人の僕とか笹原くんだったら、もうちょっと狙っちゃうんですけど、そういう意味で彼女はアーティストだと思うし、作品を作り終えると僕らはすぐ次の作品を作りたくなるのに対して、彼女が燃え尽きてしまうのも分かるというか」
――そんなメンバー間の絶妙なバランスを保ちつつ、今回の3枚を含め、12年でアルバム9枚。スパングルはそこまで精力的に活動している印象はないんですけど、バンドの熟成された歴史を感じますね。
「そうなんですよね。僕ら、活動してませんって言いつつ、この12年で9枚出しているのでコンスタントには活動している方だと思うんですけどね。ただ、音楽は副業ですって言い続けている言葉は変わらないですよ(笑)。デザイナーとして自分が好きなバンドのジャケット制作に携わってきた経験から、僕らがそういう正攻法のバンドを越えられるかっていったら、ちょっと甘いなって思うし、そのことを踏まえたうえでどういう活動をするか。だからこそ、無理なくやれることをやる。ただ、これだけ音楽産業が疲弊しているのを肌身で分かったうえで今も副業で音楽を作り続けてるというのは、我ながらタフだし、ピュアだなっていうことを改めて再確認しましたね」
取材・文/小野田雄(2010年5月)

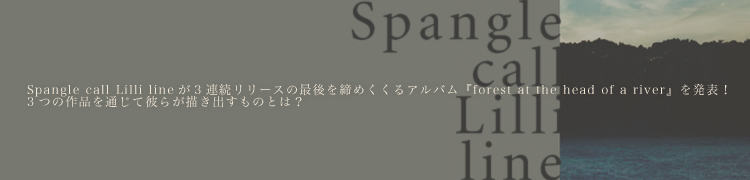




 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。