切った張ったのセッションあれば、北だろうが南だろうが駆けつけばっさりと斬りつけ、なんでもアリの自由と洒落を謳歌する。だが、1974年生まれなのに、クラブ音楽には流れず。そんな、ばりばり硬派なかっとびジャズ・ピアニストが
スガダイローだ。その勇姿は
鈴木勲OMA SOUND(現在は脱退)や、
渋さ知らズなどでもチェックすることができるが、やはり彼の本懐はそのリーダー作でこそ輝く。
いろんな編成の演奏が収められた
『スガダイローの肖像』に続く、ソロ第2作
『坂本龍馬の拳銃〜須賀大郎短編集〜(上)』はトリオによるもの。そこで彼は気心知れたリズム隊とともに、嵐のような気持ちと美意識あふれる冒険ピアノ・トリオ表現を悠々と展開する。そして、その奥から浮かび上がるのは、“ソレデイイノ?”という、澄んだバカヤロー精神だ。
スガダイロー(以下、同) 「ま、流れ的に。もう、退くに退けない(笑)。今回一番のお手柄が、この坂本龍馬ジャケかも」
――今回は“須賀大郎”と、アーティスト表記が漢字になっていますが。
「そうですね、小説っぽく。単行本みたいに」
――小さい頃からずっとピアノ少年ですか。
「最初はクラシックです。高校で一回やめて、大学は最初、生物学専攻で入学して、その後に音大に入り直しました」
――理系でもあったわけですか。それって、音楽に活かされている部分あります?
「ありますね。作曲とかで」
「あー。そこまで数学を使おうとは思ってないけど、コンセプト的にはそうです。一つアイディアを作って、そこから1+1は2だったら、次は1+2は3だろみたいな感じで、自動的に進んでいくように曲を作ったり、演奏したりしている」
――音大に入り直したのは、クラシックではなくジャズをやりたくてですよね。ジャズはいつ頃から聴いているんですか。
「ジャズは中学ぐらいからで、ロックは通ってないです。好きだったのは、
ジョン・ルイス(モダン・ジャズ・カルテットのピアニスト)。彼はちょっと変態ですね、あの人はなんか異様な空気が流れていた」
――それで、日本の音大の後、バークリー音楽大学に行ったんですね。
「強い気持ちを持っていたわけではないけど、ちゃんと4年間いて卒業しました。専攻はパフォーマンスで、演奏技術を上げることを目的とするもの。バークリーに行って、自分が日本人である、それをちゃんと主張しなきゃと思うようになりました」
――それから日本に戻ってきて、渋さ知らズに関与したという感じですか。
「そうですね。その前はわりとちゃんとジャズを演奏していましたね。そうしなきゃヤバいんじゃないか、みたいな空気があった。でも半年ぐらいで“アメリカまで行ってこれでは駄目でしょ”となって、好き勝手いくことにしました。それで1年間ぐらい仕事がなくなって、馬鹿にされて。でも、そうすると寄ってくる人もいて(笑)」
―― 一緒に演奏してきた人って、傾向はありますか。
「だいたい可愛がってくれる人はドラムかベースですね。フロントの楽器から呼ばれるということはないです」
――そして昨年『スガダイローの肖像』を出しましたが、今振り返ると前作はどんなアルバムだと思っています?
「祭り、ですね。方向も決めてないのに“じゃ、出すか”というノリだったので。とっちらかってはいるけど、言いたいことは言えているな」
――続く今作は、トリオでレコーディングしています。トリオは自分を出しやすい器ではあるんですか。
「そういうわけではないですね。たまたま今回はコレという感じかな。このメンバーになった時点で“これはいけるな”と思った。ベースはバークリーでの仲間。ドラムは僕が最初に入った東京農工大学のジャズ研の仲間です」
――けっこう、古い付き合いですね。
「はい、古い仲ですね」

―― 一緒にやる人を選ぶときに、音楽的なこととともに、何かが通じ合わなきゃ駄目とかというのはあります?
「そうですね、僕はけっこうそれを大事にする。要は、自分たちの共同意識みたいなのがあれば一緒にできる。ジャズのいいところは、知らない人とやってもできちゃうところ。でも、それは表面的なところにおいてで、阿吽の呼吸で深いことをやるには数年かかる」
――今作ではオリジナルとともに、「ハイフライ」や「チェロキー」など有名曲も取り上げています。“オリジナルをやってこそ自分のジャズができる”と考える今のジャズ・マンもいますが。
「僕はそうでもない。昔はそう思っていたこともあって、アメリカから帰ってきた後、数年間はスタンダードはやめていたけど。『ジャズ・テロリズム』をやったぐらいからかなあ、スタンダードもいいじゃんと思えてきた(笑)。あと、自分の作った曲は好きなんだけど、それより優れた曲はあるし、〈ハイフライ〉ぐらい素晴らしい曲はなかなかできない。だったら、その曲を演奏するほうがいいと思う」
――オープナーの「スピーク・ロウ」とかは、ベースが弓弾きもしていたりして、かなり構成に凝っていますよね。
「意外に、そこらへんは綿密なアンサンブルを取っています。ベースとドラムが違うリズムを出していて、ピアノも違うみたいな……そういうことをやるのは面白い。〈スピーク・ロウ〉はかなり作り上げているけど、ゆくゆくはそういうことを即興でできるようになれば。そういうシステムをこのトリオで作り上げたい」
――“短編集”となっていますが、短めにしようという意図はあったんですか。
「曲は短くしようとしました。ちゃんとアンサンブルのシステムが機能して、デフォルメする要素――ギャグのようなもの――がちゃんとあれば、長い必要はないから。あるがままの状態が収められるなら、このトリオは2、3分でもいいと思う」
――それで、第2集も出るんですか。
「次作は『坂本龍馬の革靴』というタイトルになると思います。坂本龍馬は中学生ぐらいから好き。ここのところ、子供のころの記憶を辿っていますね。自分が何を好きなのか忘れがちだから。最初に
チャーリー・パーカーを聴いたときの驚き、“なんだこの滅茶苦茶は!”という驚きを表現したいんです」
取材・文/佐藤英輔(2009年6月)

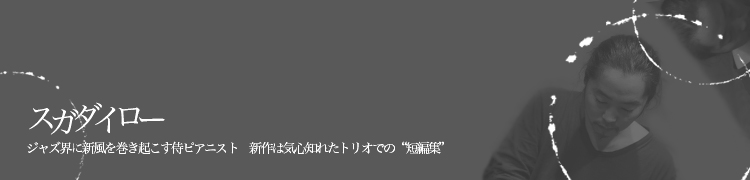



 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。