オアシスらを手掛けるオーウェン・モリスをプロデューサーに起用したデビュー・アルバム
『Hats Off To The Buskers』で、全英アルバム・チャート初登場1位という記録を打ち立て、UKロック・シーンに鮮烈なインパクトを与えたバンド、
ザ・ヴュー。彼らの2ndアルバム
『フィッチ・ビッチ?』が2月にリリース。本作は、数々の大物アーティストの名作が生まれたウェールズのモノウ・ヴァレー・スタジオでレコーディングされ、彼ら特有のメロディアスなロック・チューンだけでなく、ストリングスを取り入れた楽曲や、パウロ・ヌティーニをゲスト・ヴォーカルに迎えた楽曲なども収録。バンドとしての進化が窺える一枚に仕上がっている。
ロック・バンドには、二種類ある。変化することに恐れを感じつつ自分を奮い立たせるタイプと、変化を“当然”だと感じるタイプだ。デビュー当時はパンクの系譜を濃厚に宿した初期衝動とともに、ケルティックならではの美メロを絡ませていたザ・ヴューが、まさかこれほど後者型だったとは、いったい誰が想像しただろう。彼らの2ndアルバム『フィッチ・ビッチ?』は、当たり前のようにストリングスやブラスを導入し、当たり前のようにフォークやトラディショナル音楽を消化し、そしてラップまで披露したりと、小気味いいほど新たなステップを軽やかに踏むバンドの姿が印象的だ。
「僕らとしては、フツーにヴァースがあってコーラスが来て、またヴァースが来てコーラスに行って……っていうのとは、違う展開を考えたかったんだ。もっと、興味深い展開っていうのかな。そうすることで、前作からまた前に進みたかった。それにアレンジに関しては、前のアルバムでも今回みたいな音ができたはずなのにっていう気持ちがあったし」

そう話すのは、取材に答えてくれたキーレン・ウェブスター。もっとも、レコーディング中は相変わらず大騒ぎだった模様だ。録音初日に酔っ払っている様子は、プロデューサーのオーウェン・モリス(これまでに初期のオアシスなどを担当)の手できっちりレコーディングされ、本作の冒頭と最後に織り込まれている。肩に力を入れすぎずに、より豊饒に、より深みのある曲を生み出そうとしたバンドの姿が目に浮かぶかのようだ。まるで、俺たちゃスコットランドのダンディー出身、頭でっかちのコンセプトなぞ不要で、自然にこういう進化を遂げただけさ、と言わんばかりに。
「カイル(・ファルコナー/vo、g)はクラシックを積極的に聴いてたね。もちろん、カイルが聴いてたから僕も聴いてたことになるけど。まあ、どんな音楽からでもインスピレーションを受けると思う。今は主にフォーク・ミュージックをよく聴いてるんだ。アイリッシュ・フォーク・ミュージックが多いかな。あと〈ディスタント・ダブロン〉はカイルが1人で書いて僕がちょっと手伝った曲なんだけど、あいつ、あの曲は『宝島』を踏まえて書いたって言ってたよ。『宝島』って知ってる? ジョン・ロング・シルヴァーの」
本なんか読みそうにないタイプなのに、と言うなかれ。こんな話を聴いていると、自分の町にライヴに来た
ピート・ドハーティの楽屋に押し掛けデモ・テープを渡した片田舎の4人が、才能のある音楽好きの悪ガキから成長し、今はミュージシャンとしての充実を促すインスピレーションに貪欲になっていることがわかる。
ちなみにカイルはプロデュースにも参加した。
「今度のアルバムでは、カイルに何度も驚かされたよ……向こうも僕に驚かされてることを祈るけど。僕は、他のメンバーより先にあいつに呼ばれてアイディアを聴かされて、相談されることが多いんだけど、その段階では全然スゴいと思えないこともよくある。それが、形になっていくにつれ“なるほど、こういうイメージだったのか”って驚かされるんだ。これからも、お互いを驚かすことでクオリティを高く保っていけたらいいなと思うね」
新作でのステップ・アップも、きっと更なる自信に繋がるはず。こいつらがこの先何を生み出すか、さらに目が離せなくなってきた。
取材・文/妹沢奈美(2008年12月)

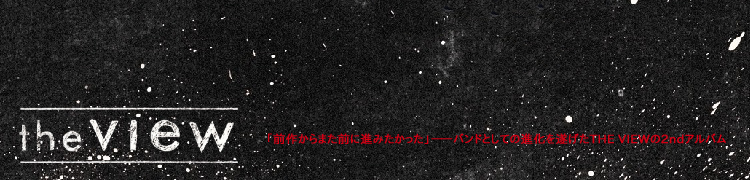



 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。