管楽器奏者の宝庫たるニューオーリンズが生んだ、怪傑かっとびトロンボーン奏者が
トロンボーン・ショーティ(本名:トロイ・アンドリュース)だ。1986年生まれ、誰もがブライテスト・ホープと認める彼は、ついにメジャーからワールドワイドな新作
『バッカタウン』をリリース。そして、その新作を携え、フジロックフェスティバルに出演(門外漢からも大好評であったよう)をした。以下は、フェス現地で行なった質疑応答である。
 ――今もニューオーリンズに住んでいるんですか?
――今もニューオーリンズに住んでいるんですか? トロンボーン・ショーティ(以下、同)「うん。でも、ツアーが多いので、“ツアーに住んでいる”と言ったほうがいいかもね(笑)。だけど、俺のココロはいつもニューオーリンズにある。ニューオーリンズがなかったら、今の俺はないしね」
「俺は音楽に満ちあふれたトレメ地区で生まれ、小さい頃からコミュニティの中で楽器を教わって、現在があるんだ。それで、俺の場合は兄がすでにトランペットを吹いていた。だから、一緒にバンドをやるためには、別の楽器を吹くしかなかったわけさ。トロンボーンを手にしたのは4歳のとき。それ以降、俺はブラス・バンドで吹き続けてきている。もう生演奏とセカンド・ライン(注1)は生活の横にあるものさ」
――2007年にニューオーリンズに行っていろいろなライヴを観たことがあったんですが、そのとき感じたのは、“より派手でデカい音を出せる管楽器奏者が偉い”みたいな価値観がニューオーリンズにはあると感じたんですが。
「まさしく、その通り!」
――それで、日本は今回が初めてになるんですか?
「ああ、これまでも何度か話はあったんだけど、今回が初来日。バンドの面々ともども、とっても高揚しているよ」
――日本初の実演の場がフジロックという大きなロック・フェスなんですが、米英でもそういうフェス出演はしているんですか?
「たくさん出ているよ。でも、観客の数なんか関係ない。とにかく、人の前で演奏するということに価値があるのであって、それを通して聴き手が俺の音楽に興味を持ってくれたなら最高さ」
――やはり、ライヴが自分の持ち味を出せる一番の場であると考えていますか?
「うん。でも、ライヴだけではなく、テレビやラジオも重視している。まあ、ライヴは聴き手を魅了するにはてっとり早い手段だけど、CDだって負けちゃいないと思う」
――では、新作のことをお聞きします。ジェームス・ブラウンっぽいファンクもあればロックっぽいものもあるなど、とても幅の広い仕上がりになっていると思います。ながら、随所にニューオーリンズっぽさも息づいています。あなたとしては、あなたなりのニューオーリンズ・ミュージックを作っているという気持ちなんでしょうか。 「自分の色が出た、ニューオーリンズで育った“俺の音楽”になっていると思う。まあ、“ガンボ”(同地周辺で愛されるごった煮スープ)だな。いろんなものが入っているけど、それは俺というフィルターを通した末のガンボなんだ」
――今作はメジャーからの発売ということで、より広い層に届くものにしたいと思ったりはしました?
「そりゃあ、ね。ニューオーリンズの音楽にこだわっていない人でも、気分よく聴くことができるようなものにしたかった。でも、そうであっても、自分はなくさずきっちり残したつもりさ」
――アルバムの参加者と今回の来日メンバーは重なりますが、彼らはニューオーリンズの仲間なんですか。
「うん、地元のアート・スクールがあって、そこで知り合った仲間たちさ」
――あなたは歌も歌っています。歌うこととトロンボーンを吹くことは、あなたの中では等価値にあるものなんでしょうか?
「歌うというのは、昔から俺のパフォーマンスにあるもの。
ルイ・アームストロングがそうであるようにね。僕はずっと歌ってもきているよ」
――アルバムにおけるゲストが興味深かったです。ある曲ではニューオーリンズの大御所アラン・トゥーサンを入れ、もう一方では広がりを代表させるかのようにレニー・クラヴィッツを迎えています。これは、あなたの音楽に対する姿勢を表わしていると思いました。 「ありがとう。俺がレニーのバンドに入っているときにハリケーン・カトリーナ被災があった。だけど、俺は彼から得たギャラで家族の面倒を見ることができたわけで、彼に入ってもらうのは自然な流れだった。これからもいろんな人と絡んでみたい、
スティーヴィー・ワンダーとか
ジェイ・Zとできたらいいな」
注1)ブラス・バンドを伴ったニューオーリンズの伝統的なパレード
取材・文/佐藤英輔(2010年7月)
トロンボーン・ショーティの紹介フィルム『Trombone Shorty reel 2010』

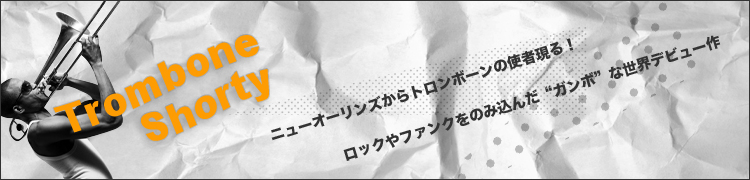

 ――今もニューオーリンズに住んでいるんですか?
――今もニューオーリンズに住んでいるんですか?

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。