ウィルコ(Wilco)は昨年の7年ぶりのツアー、今年のフジロック出演と2年連続の来日を果たし、本国アメリカとは隔たりのあった日本での人気と評価も急上昇している。そんな絶好のタイミングで届いた通算8作目のアルバム
『ザ・ホール・ラヴ』は彼ら自身のレーベル〈dBpm〉からの第1弾でもある。ポップな曲からフォーキーな曲、そして実験的な曲まで、彼らのさまざまな面が表われた収録曲は粒揃いで、日本でのウィルコの地位を確固たるものにするはずだ。リーダーでソングライターの
ジェフ・トゥイーディ(vo、g)と共に、創立メンバーとしてバンドを支えるベーシストの
ジョン・スティラットに電話で話を聞いた。
――あなたとジェフのつきあいは前身バンドのアンクル・テュペロ以来の20年近くという長い年月となります。彼の作る曲に今も驚かされますか? ジョン・スティラット(b/以下同)「うん。ジェフはある種の自信を得たと思う。彼は長い間それほど強い自信を持っていなかったんだけど、今では自分の場所を見つけたという感じだね。彼の強みは
ディラン的な曲を書くこともできる一方で、攻撃的な大胆さも持っているところだ。本物のロックンロールの態度を持っていて、〈アイ・マイト〉が良い例だけど、このアルバムではウィルコとしてその部分が表われているのが興味深いと思う、僕はジェフのことを今もアンクル・テュペロの頃のとても生意気なロッカーといった感じの奴だと思っている。彼にはいろいろな面があって、ウィルコのアルバムはそれらを合体させたものなんだ」
――新作は実験的な面を見せた7分の「アート・オブ・オールモスト」で幕を開け、私的な物語を歌うアコースティックでフォーキーな12分の「ワン・サンデー・モーニング」で締め括られますが、その間の10曲は3分台の曲ばかりがずらりと並んでいますね。
「大半の曲は僕らの思ったよりもずっと短く仕上がった。でも、早い段階から長い2曲でブックエンドにすべきだとわかっていた。それは主題にも関係した案で、最もハードにドライヴする曲で始めて、最後はオーガニックな曲で終わる。それは僕らがレコーディングで辿った旅でもある。伝統的なフォーク音楽もあれば、革新的なエレクトロニック音楽のようなものもあって、このレコードはそれらを共存させようとする取り組みと言えるからね」
――アルバム制作開始前のインタヴューで、あなたは“前作はもっと荒々しくできたかもしれない。次作はもっと耳障りなものになるよ”と話していました。
「それがこのレコードに僕が最も望んだことだ。前2作に欠けていた、ある種のロック的な態度のようなもの、それは僕らがグループとしても間違いなく持っているけど、特にジェフがメンバーの誰よりも持っているものだ。その特性はそれらのレコードになかったね。でも、今回はジェフが〈アイ・マイト〉を持ち込んだときから、僕は“よし、これが僕の求めていたものだぜ!”と思ったんだ。その大胆不敵さだね」

2011.7.31@FUJIROCK FESTIVAL'11
(C)Mitch Ikeda
――ジャンルをまたいでほかのプロジェクトでも活躍するギターのネルス・クラインやドラマーのグレン・コッチェ、本作では共同プロデューサーも務めたマルチ奏者のパトリック・サンソンなど、最強と呼べる現在の顔ぶれとなって今年で7年目です。 「このレコードは僕らの作ってきたどのレコードよりも全員の個性を反映していると思う。6人もメンバーがいると、全体の音響空間の中で自分の空間をたくさん取るのはむずかしい。でも、このレコードでは全員が自分のサウンドを主張している。僕らにはネルス、マイク(マイケル・ヨルゲンセン/key)、パトリックとそれぞれ異なった個性的なプレイヤーがいて、彼らがリズムセクションの上で素晴らしく絡み合っているんだ。3枚のアルバムを経て、それがもっとたやすく、もっとうまくできるようになった」
――常に変化を続けてきたウィルコですが、進化を続ける余地はまだあるでしょうか?
「そう思うよ。レコードを作り終えるたびに、僕らの最高のアルバムはまだ先にあると感じる。僕らにはいろんなことをやり続けていく余地がたっぷりあると思う。プレイヤーとして、バンドとして、可能性はまだまだあると思うんだ」
取材・文/五十嵐 正(2011年9月)

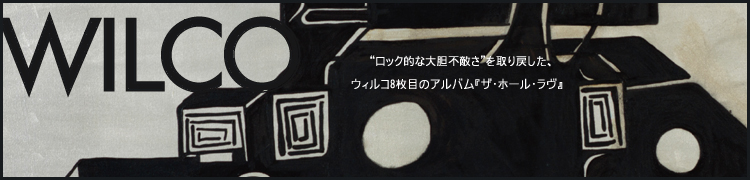




 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。