 浦沢直樹
浦沢直樹と
和久井光司による対談を中心にした単行本『ディランを語ろう』(小学館=刊)が、11月末に発売された。これは和久井が『週刊ビッグコミックスピリッツ』に連載してきた対談(
ザ・クロマニヨンズ、
サンボマスター、
岡林信康、
PANTA、ジョン・ウェズリー・ハーディングがゲストとして登場)や、浦沢が描き下ろしたイラスト・ストーリー「ボブ・ディランの大冒険」を含むもので、ディランを軸に20世紀後半のポップ・カルチャーを見つめ直した画期的な一冊だ。さらに、和久井は
ボブ・ディラン公認の日本語カヴァー集
『ディランを唄う』と、和久井光司&セルロイド・ヒーローズ名義でのオリジナル・アルバム
『愛と性のクーデター』という、近年の音楽活動の充実ぶりを窺わせるCDを2枚同時に発表した。そこで、新作の聴きどころとともに、彼のルーツでもあるディランの魅力を聞いてみた。
「ボブ・ディランって、やりたい放題で当たりハズレも激しければ、説明もないし、平気で前言を覆したりする(笑)。実像も作品の意味もよく分からないから、みんなが勝手にディラン像を描いているんですよ。でも、音楽的な“核”となっている部分の重みは、誰よりもすごいミュージシャンだと思う。だから、それぞれの歌の“核”をどう捉え、音楽的にどう脚色していくかってことが、『ディランを唄う』のテーマになりましたね。たとえば、
ポール・マッカートニーの曲だったら、トラディショナル・フォーク、ロックンロール、R&B、ソウル、レゲエ……と、その曲の“核”になる要素を断定できる。だけどディランの場合は、ブルースの3コードで出来ている曲でも、“核”はブルースなのかといえば、そうでもない。おそらくディランは、詞を乗せる段階でいろいろな音楽を混ぜちゃうんですよ。“ディラン色”の変なものにしちゃう。じゃあ、ディランの音楽の“核”にあたる部分が純然たる彼の“オリジナル”なのかといえば、それもまた違う。ルーツは常に匂わせてますからね。だから、音楽的な分析は非常に難しい人なの。“オリジナルは詩魂”と言ってしまえばそれまでなのかもしれないけど。ただ、いろいろなことに対して目配せすることを忘れない人なんで、詩人としての魂とポップ音楽の要素の融合はうまい。で、その図式を探るには、実際に彼の曲をやってみるのが一番早道だったんですよ」
――では、アルバムを作ってみて分かったことは?

「うーん。日本語詞をつけるにしても、もともとはディランのものでしょ。あれだけ長い歌詞を唄うには、高い緊張感を維持しなくちゃいけない。それをやりながら、日本語で唄うからこその抑揚もつけていくというのは、高度なことなんです。シンガーとしての力量を試されてるな、って思いましたね。言葉を人の心に投げ込むことの重要さを痛感したか。とはいうものの、ディランって力の抜けた人で、完成形に達してないようなレコーディングでも発表しちゃう。でも、良くないオリジナル・ヴァージョンにも、曲の“核”は刻まれているわけで、実際に取り組んでみると、その時は“核”となる部分だけをレコードに投げ込みたかったんだな、って気づかされたりもした。そういう人のものだから、
ビートルズみたいな完成された音楽をカヴァーするのとは違って、ディラン自身のヴァージョンも目標にならない。彼は“せーの”で音を出してみて、当たりなら当たり、ハズレならハズレの人なんでね(笑)。だから『ディランを唄う』は、ディラン作品をいかに自分流に作り替えられるかってことがポイントになりましたね」
――なるほど。『ディランを唄う』がご自身のルーツを再確認する作品だとしたら、『愛と性のクーデター』は“今”を示す作品と言えそうですね。

「いや、あまり差異はないですよ(笑)。それは音楽に限らず、文章を書いたり、本を作ることにしてもそう。あとから2007年度の仕事を振り返ったときに、自分でも“その年にやったんだな”って思えることをどこかに刻んでおきたい。『愛と性のクーデター』にはここ数年のライヴでやってきた曲を入れたんですけど、2007年の“ディス・イヤーズ・モデル”な感じにはこだわりました。ここ1年でドラマーが代わったこともあって、もともとのアレンジとは気持ちが変わった部分もある。だから、なかにはレコーディングしたあとに、切り貼りで強引にアレンジを変えた曲もあるし、“2007年夏のセルロイド・ヒーローズ”でしかありえなかったアルバムになってると思います。ライヴではすでにCDのアレンジでやってない曲もあるぐらいですからね。自分の意識はどんどん変わっていっちゃうんで、ディランのカヴァーだから、オリジナル・アルバムだからって差異なんかにこだわってるヒマはない。実際、レコーディングも同時進行でやってましたから、メンバーやエンジニアはどっちのアルバムに入る曲なのかも分からなかったりしてね。〈コールド・アイアンズ・バウンド〉が〈冷たい鋼鉄の境界線〉になってれば、無理ないでしょ(笑)。ま、ディランの曲だからといって演奏する気持ちを変えてはいけないわけだから、それでよかったと思うし、スタジオでみんなが“これ、どっち用?”なんて言ってる状況は面白かったですね」
――“自分の意識も変わっていく”とおっしゃいましたが、それって“核”があるから変わっていけるのかもしれないですね。
「そうですね。だから、アレンジがどうだろうと、メンバーが誰だろうと、ぼくの音楽が大きく変わることはないと思う。セルロイド・ヒーローズもメンバーは必然的に変わっていくものだと思ってるし。これがパーマネントなバンドだって決めちゃうと、“この曲とこの曲だったらリハーサルなしでできちゃうね”ってなりがちだし、そうなるとステージからスリルが消えていく。だから、いまも〈サティスファクション〉を新鮮な気持ちでプレイしてる
ストーンズは凄いですよ」
――歌詞は50歳手前の男のさまざまな想いを、女性が“ふん”と言いそうなダンディズムやユーモアを交えながら綴っていますよね。
「この歳の男が普通のラヴ・ソングを書いたところで、どれだけリアリティがあるかってことなんですよ。この歳で唄うラヴ・ソングっていうのは、えげつないセックスや不倫の歌なんじゃないかって(笑)。で、そういった歌を書くと、幸せな家庭を持ちながらもスケベ心を持ってる正直な人たちが味方になってくれる(笑)。でも、タテマエで生きてる人たちは“良識に反する”って思うでしょうね。ぼく自身は、そういう人たちは感覚が違うんだなって思うし、タテマエを重んじるような人に分かってもらわなくてもいい。誰に、何を言いたいのかってことが明確なほうが、鋭いリズムが沸き上がってくるものなんで、ロックに向かう気持ちが過激な表現を必要とすれば、ぼくは迷わずそっちに行きますよ。根はパンクなんでね(笑)」
取材・文/兒玉常利
■KOJI WAKUI'S OFFICIAL WEB SITE

※ 関連作品 ※
小学館=刊
ISBN: 9784093592024 / \1,980(税込)
浦沢直樹、和久井光司=著

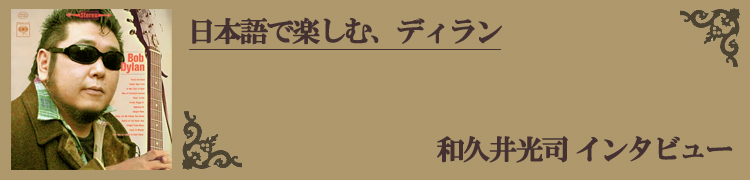
 浦沢直樹と和久井光司による対談を中心にした単行本『ディランを語ろう』(小学館=刊)が、11月末に発売された。これは和久井が『週刊ビッグコミックスピリッツ』に連載してきた対談(ザ・クロマニヨンズ、サンボマスター、岡林信康、PANTA、ジョン・ウェズリー・ハーディングがゲストとして登場)や、浦沢が描き下ろしたイラスト・ストーリー「ボブ・ディランの大冒険」を含むもので、ディランを軸に20世紀後半のポップ・カルチャーを見つめ直した画期的な一冊だ。さらに、和久井はボブ・ディラン公認の日本語カヴァー集『ディランを唄う』と、和久井光司&セルロイド・ヒーローズ名義でのオリジナル・アルバム『愛と性のクーデター』という、近年の音楽活動の充実ぶりを窺わせるCDを2枚同時に発表した。そこで、新作の聴きどころとともに、彼のルーツでもあるディランの魅力を聞いてみた。
浦沢直樹と和久井光司による対談を中心にした単行本『ディランを語ろう』(小学館=刊)が、11月末に発売された。これは和久井が『週刊ビッグコミックスピリッツ』に連載してきた対談(ザ・クロマニヨンズ、サンボマスター、岡林信康、PANTA、ジョン・ウェズリー・ハーディングがゲストとして登場)や、浦沢が描き下ろしたイラスト・ストーリー「ボブ・ディランの大冒険」を含むもので、ディランを軸に20世紀後半のポップ・カルチャーを見つめ直した画期的な一冊だ。さらに、和久井はボブ・ディラン公認の日本語カヴァー集『ディランを唄う』と、和久井光司&セルロイド・ヒーローズ名義でのオリジナル・アルバム『愛と性のクーデター』という、近年の音楽活動の充実ぶりを窺わせるCDを2枚同時に発表した。そこで、新作の聴きどころとともに、彼のルーツでもあるディランの魅力を聞いてみた。
 「うーん。日本語詞をつけるにしても、もともとはディランのものでしょ。あれだけ長い歌詞を唄うには、高い緊張感を維持しなくちゃいけない。それをやりながら、日本語で唄うからこその抑揚もつけていくというのは、高度なことなんです。シンガーとしての力量を試されてるな、って思いましたね。言葉を人の心に投げ込むことの重要さを痛感したか。とはいうものの、ディランって力の抜けた人で、完成形に達してないようなレコーディングでも発表しちゃう。でも、良くないオリジナル・ヴァージョンにも、曲の“核”は刻まれているわけで、実際に取り組んでみると、その時は“核”となる部分だけをレコードに投げ込みたかったんだな、って気づかされたりもした。そういう人のものだから、ビートルズみたいな完成された音楽をカヴァーするのとは違って、ディラン自身のヴァージョンも目標にならない。彼は“せーの”で音を出してみて、当たりなら当たり、ハズレならハズレの人なんでね(笑)。だから『ディランを唄う』は、ディラン作品をいかに自分流に作り替えられるかってことがポイントになりましたね」
「うーん。日本語詞をつけるにしても、もともとはディランのものでしょ。あれだけ長い歌詞を唄うには、高い緊張感を維持しなくちゃいけない。それをやりながら、日本語で唄うからこその抑揚もつけていくというのは、高度なことなんです。シンガーとしての力量を試されてるな、って思いましたね。言葉を人の心に投げ込むことの重要さを痛感したか。とはいうものの、ディランって力の抜けた人で、完成形に達してないようなレコーディングでも発表しちゃう。でも、良くないオリジナル・ヴァージョンにも、曲の“核”は刻まれているわけで、実際に取り組んでみると、その時は“核”となる部分だけをレコードに投げ込みたかったんだな、って気づかされたりもした。そういう人のものだから、ビートルズみたいな完成された音楽をカヴァーするのとは違って、ディラン自身のヴァージョンも目標にならない。彼は“せーの”で音を出してみて、当たりなら当たり、ハズレならハズレの人なんでね(笑)。だから『ディランを唄う』は、ディラン作品をいかに自分流に作り替えられるかってことがポイントになりましたね」 「いや、あまり差異はないですよ(笑)。それは音楽に限らず、文章を書いたり、本を作ることにしてもそう。あとから2007年度の仕事を振り返ったときに、自分でも“その年にやったんだな”って思えることをどこかに刻んでおきたい。『愛と性のクーデター』にはここ数年のライヴでやってきた曲を入れたんですけど、2007年の“ディス・イヤーズ・モデル”な感じにはこだわりました。ここ1年でドラマーが代わったこともあって、もともとのアレンジとは気持ちが変わった部分もある。だから、なかにはレコーディングしたあとに、切り貼りで強引にアレンジを変えた曲もあるし、“2007年夏のセルロイド・ヒーローズ”でしかありえなかったアルバムになってると思います。ライヴではすでにCDのアレンジでやってない曲もあるぐらいですからね。自分の意識はどんどん変わっていっちゃうんで、ディランのカヴァーだから、オリジナル・アルバムだからって差異なんかにこだわってるヒマはない。実際、レコーディングも同時進行でやってましたから、メンバーやエンジニアはどっちのアルバムに入る曲なのかも分からなかったりしてね。〈コールド・アイアンズ・バウンド〉が〈冷たい鋼鉄の境界線〉になってれば、無理ないでしょ(笑)。ま、ディランの曲だからといって演奏する気持ちを変えてはいけないわけだから、それでよかったと思うし、スタジオでみんなが“これ、どっち用?”なんて言ってる状況は面白かったですね」
「いや、あまり差異はないですよ(笑)。それは音楽に限らず、文章を書いたり、本を作ることにしてもそう。あとから2007年度の仕事を振り返ったときに、自分でも“その年にやったんだな”って思えることをどこかに刻んでおきたい。『愛と性のクーデター』にはここ数年のライヴでやってきた曲を入れたんですけど、2007年の“ディス・イヤーズ・モデル”な感じにはこだわりました。ここ1年でドラマーが代わったこともあって、もともとのアレンジとは気持ちが変わった部分もある。だから、なかにはレコーディングしたあとに、切り貼りで強引にアレンジを変えた曲もあるし、“2007年夏のセルロイド・ヒーローズ”でしかありえなかったアルバムになってると思います。ライヴではすでにCDのアレンジでやってない曲もあるぐらいですからね。自分の意識はどんどん変わっていっちゃうんで、ディランのカヴァーだから、オリジナル・アルバムだからって差異なんかにこだわってるヒマはない。実際、レコーディングも同時進行でやってましたから、メンバーやエンジニアはどっちのアルバムに入る曲なのかも分からなかったりしてね。〈コールド・アイアンズ・バウンド〉が〈冷たい鋼鉄の境界線〉になってれば、無理ないでしょ(笑)。ま、ディランの曲だからといって演奏する気持ちを変えてはいけないわけだから、それでよかったと思うし、スタジオでみんなが“これ、どっち用?”なんて言ってる状況は面白かったですね」
 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。