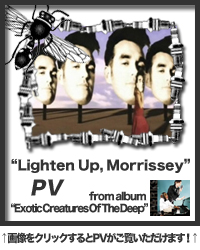
2008年、最新アルバム
『エキゾチック・クリーチャーズ・オブ・ザ・ディープ』の発表、FUJI ROCK FESTIVAL'08への出演で注目を集めた
スパークスが、早くも今年4月に再来日を果たした。最新作と旧作から楽曲を披露した東京・大阪の3公演は大好評のうちに終了。本稿では、2009枚の限定盤、初の紙ジャケット、メンバー監修のデジタル・リマスタリング、各アルバムにボーナス・トラックを3曲追加、メンバー本人によるボーナス・トラックの解説(翻訳)付きのSHM-CD仕様(!)で2月に再発された6作品をあらためて聴きながら、ユニークな音楽性を作り上げた彼らの軌跡をたどってみたい。

フジロック来日から一年。今度は東京2デイズ&大阪1日と単独公演を果たし、ますます親日度が高まるスパークス。とりわけ今回の来日は、2月に旧作6タイトルが紙ジャケ/リマスタリング、そしてボートラ付きで再発されたことを受けてのことだけに、ただの来日公演とはひと味違う。最新作『エキゾチック・クリーチャーズ・オブ・ザ・ディープ』を中心に、過去のナンバーもたっぷり披露。東京では4月23日が
『キモノ・マイ・ハウス』、24日が
『No.1 イン・ヘブン』を全曲演奏するというファンには嬉しい企画だった。

さて、そんなスペシャルなツアーのきっかけとなった今回の再発。グラム期以降、スパークスのサウンドが次々とモデル・チェンジしていく時期だけに、どのアルバムをとってもピカピカのスパークスがいる。まず、イギリスから帰国して故郷のLAでレコーディングした
『イントロデューシング・スパークス』(77年)は、参加ミュージシャンが豪華。
デヴィッド・フォスター、
リー・リトナー、
デヴィッド・ペイチなどアメリカ西海岸の腕利きミュージシャンが顔を揃えた本作は、滑らかなバンド・サウンドに毒気もしっかりと織り込まれている。
ビーチ・ボーイズ風のコーラスが飛び出す「オーバー・ザ・サマー」なんて、彼らなりのLA讃歌なのかもしれない。


地元に錦を飾ったスパークスが次に興味を持ったのが、
ドナ・サマーのヒット曲「アイ・フィール・ラヴ」だった。プロデュースを手掛けた
ジョルジオ・モロダーを訪ねて、二人は早速ミュンヘンへ。そして、生まれたのが『No.1 イン・ヘブン』(79年)だ。本作ではキラびやかなディスコ・サウンドを着こなして、スパークスのモダン・ポップなセンスが爆発! ロンの弾く骨太なシンセの音色と、ラッセルのアリアのような美しい歌声が溶け合って、まるでテクノ・ポップの聖歌のようなサウンドを作り上げた。本作の仕上がりに手応えを感じた二人は、次作
『ターミナル・ジャイヴ』(80年)もジョルジオ・モロダーのプロデュースで制作。「ロックンロール・ピープル・イン・ア・ディスコ・ワールド」なんて曲名が当時の世相を物語っているが、このあたりから“ニューウェイヴの元祖”として新世代バンドからリスペクトされるようになっていった。


そんななか、スパークスは地元LAのバンド、ベイツ・モーテルをバックに従えて
『弱い者いじめ』(81年)をレコーディング。本作からシンセ・サウンドとバンド・サウンドを融合したスタイルへと移行するが、そのアプローチは
『アンガスト・イン・マイ・パンツ』(82年)で完成した。一見、エレ・ポップのようでいて、その中身は強固なバンド・サウンドが尻尾の先までギッシリと。だからこそ、若手ニューウェイヴ・バンドにありがちなひ弱さはなく、足腰がしっかりしているのだ。

初のセルフ・プロデュースとなった
『イン・アウター・スペース』(83年)では、スパークスのファン・クラブに入っていた
ゴーゴーズの
ジェーン・ウィードリンが参加。エレクトロニックな度合いは強くなっているものの、やはりグルーヴはオーガニックで逞しい。オールド・ウェイヴからニューウェイヴへ、そんなロックの革命期のなか、見事な身のこなしで独自のスタイルを極めていったスパークス。今回、再発された6作品を通じて、スパークスのユニークな音楽性を再発見できるはずだ。
文/村尾泰郎

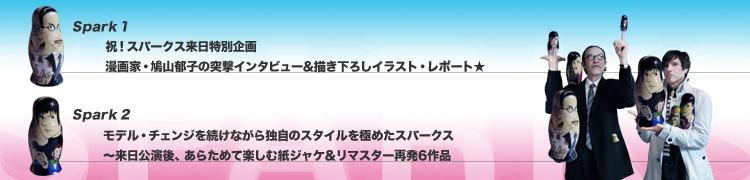
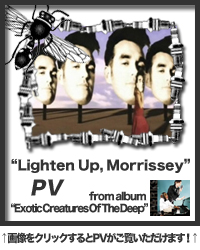
 フジロック来日から一年。今度は東京2デイズ&大阪1日と単独公演を果たし、ますます親日度が高まるスパークス。とりわけ今回の来日は、2月に旧作6タイトルが紙ジャケ/リマスタリング、そしてボートラ付きで再発されたことを受けてのことだけに、ただの来日公演とはひと味違う。最新作『エキゾチック・クリーチャーズ・オブ・ザ・ディープ』を中心に、過去のナンバーもたっぷり披露。東京では4月23日が『キモノ・マイ・ハウス』、24日が『No.1 イン・ヘブン』を全曲演奏するというファンには嬉しい企画だった。
フジロック来日から一年。今度は東京2デイズ&大阪1日と単独公演を果たし、ますます親日度が高まるスパークス。とりわけ今回の来日は、2月に旧作6タイトルが紙ジャケ/リマスタリング、そしてボートラ付きで再発されたことを受けてのことだけに、ただの来日公演とはひと味違う。最新作『エキゾチック・クリーチャーズ・オブ・ザ・ディープ』を中心に、過去のナンバーもたっぷり披露。東京では4月23日が『キモノ・マイ・ハウス』、24日が『No.1 イン・ヘブン』を全曲演奏するというファンには嬉しい企画だった。 さて、そんなスペシャルなツアーのきっかけとなった今回の再発。グラム期以降、スパークスのサウンドが次々とモデル・チェンジしていく時期だけに、どのアルバムをとってもピカピカのスパークスがいる。まず、イギリスから帰国して故郷のLAでレコーディングした『イントロデューシング・スパークス』(77年)は、参加ミュージシャンが豪華。デヴィッド・フォスター、リー・リトナー、デヴィッド・ペイチなどアメリカ西海岸の腕利きミュージシャンが顔を揃えた本作は、滑らかなバンド・サウンドに毒気もしっかりと織り込まれている。ビーチ・ボーイズ風のコーラスが飛び出す「オーバー・ザ・サマー」なんて、彼らなりのLA讃歌なのかもしれない。
さて、そんなスペシャルなツアーのきっかけとなった今回の再発。グラム期以降、スパークスのサウンドが次々とモデル・チェンジしていく時期だけに、どのアルバムをとってもピカピカのスパークスがいる。まず、イギリスから帰国して故郷のLAでレコーディングした『イントロデューシング・スパークス』(77年)は、参加ミュージシャンが豪華。デヴィッド・フォスター、リー・リトナー、デヴィッド・ペイチなどアメリカ西海岸の腕利きミュージシャンが顔を揃えた本作は、滑らかなバンド・サウンドに毒気もしっかりと織り込まれている。ビーチ・ボーイズ風のコーラスが飛び出す「オーバー・ザ・サマー」なんて、彼らなりのLA讃歌なのかもしれない。
 地元に錦を飾ったスパークスが次に興味を持ったのが、ドナ・サマーのヒット曲「アイ・フィール・ラヴ」だった。プロデュースを手掛けたジョルジオ・モロダーを訪ねて、二人は早速ミュンヘンへ。そして、生まれたのが『No.1 イン・ヘブン』(79年)だ。本作ではキラびやかなディスコ・サウンドを着こなして、スパークスのモダン・ポップなセンスが爆発! ロンの弾く骨太なシンセの音色と、ラッセルのアリアのような美しい歌声が溶け合って、まるでテクノ・ポップの聖歌のようなサウンドを作り上げた。本作の仕上がりに手応えを感じた二人は、次作『ターミナル・ジャイヴ』(80年)もジョルジオ・モロダーのプロデュースで制作。「ロックンロール・ピープル・イン・ア・ディスコ・ワールド」なんて曲名が当時の世相を物語っているが、このあたりから“ニューウェイヴの元祖”として新世代バンドからリスペクトされるようになっていった。
地元に錦を飾ったスパークスが次に興味を持ったのが、ドナ・サマーのヒット曲「アイ・フィール・ラヴ」だった。プロデュースを手掛けたジョルジオ・モロダーを訪ねて、二人は早速ミュンヘンへ。そして、生まれたのが『No.1 イン・ヘブン』(79年)だ。本作ではキラびやかなディスコ・サウンドを着こなして、スパークスのモダン・ポップなセンスが爆発! ロンの弾く骨太なシンセの音色と、ラッセルのアリアのような美しい歌声が溶け合って、まるでテクノ・ポップの聖歌のようなサウンドを作り上げた。本作の仕上がりに手応えを感じた二人は、次作『ターミナル・ジャイヴ』(80年)もジョルジオ・モロダーのプロデュースで制作。「ロックンロール・ピープル・イン・ア・ディスコ・ワールド」なんて曲名が当時の世相を物語っているが、このあたりから“ニューウェイヴの元祖”として新世代バンドからリスペクトされるようになっていった。
 そんななか、スパークスは地元LAのバンド、ベイツ・モーテルをバックに従えて『弱い者いじめ』(81年)をレコーディング。本作からシンセ・サウンドとバンド・サウンドを融合したスタイルへと移行するが、そのアプローチは『アンガスト・イン・マイ・パンツ』(82年)で完成した。一見、エレ・ポップのようでいて、その中身は強固なバンド・サウンドが尻尾の先までギッシリと。だからこそ、若手ニューウェイヴ・バンドにありがちなひ弱さはなく、足腰がしっかりしているのだ。
そんななか、スパークスは地元LAのバンド、ベイツ・モーテルをバックに従えて『弱い者いじめ』(81年)をレコーディング。本作からシンセ・サウンドとバンド・サウンドを融合したスタイルへと移行するが、そのアプローチは『アンガスト・イン・マイ・パンツ』(82年)で完成した。一見、エレ・ポップのようでいて、その中身は強固なバンド・サウンドが尻尾の先までギッシリと。だからこそ、若手ニューウェイヴ・バンドにありがちなひ弱さはなく、足腰がしっかりしているのだ。 初のセルフ・プロデュースとなった『イン・アウター・スペース』(83年)では、スパークスのファン・クラブに入っていたゴーゴーズのジェーン・ウィードリンが参加。エレクトロニックな度合いは強くなっているものの、やはりグルーヴはオーガニックで逞しい。オールド・ウェイヴからニューウェイヴへ、そんなロックの革命期のなか、見事な身のこなしで独自のスタイルを極めていったスパークス。今回、再発された6作品を通じて、スパークスのユニークな音楽性を再発見できるはずだ。
初のセルフ・プロデュースとなった『イン・アウター・スペース』(83年)では、スパークスのファン・クラブに入っていたゴーゴーズのジェーン・ウィードリンが参加。エレクトロニックな度合いは強くなっているものの、やはりグルーヴはオーガニックで逞しい。オールド・ウェイヴからニューウェイヴへ、そんなロックの革命期のなか、見事な身のこなしで独自のスタイルを極めていったスパークス。今回、再発された6作品を通じて、スパークスのユニークな音楽性を再発見できるはずだ。
 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。