昨年12月の1stアルバム
『anew』発表以降、
andropに対する評価と期待はさらに大きく膨らんでいる。J-WAVEのラジオ番組「TOKOYO REAL-EYES」で楽曲が30週以上にも渡ってオンエアされ、「TOKIO HOT 100」では最高13位にランクイン。さらにMySpaceでの楽曲プレビューは58万を突破。相変わらずアーティスト・プロフィールは一切公表されてないにも関わらず、彼らの存在は――純粋に楽曲の力によって――さまざまなメディアとシュアな耳を持つリスナーによって拡大し続けているのだ。
単発的に行なわれているライヴ活動でも、既存のバンド・フォーマットには捉われないパフォーマンスを披露している。3月22日には、フォトグラファーの橋本塁氏がオーガナイズするイベント“SOUND SHOOTER Vol.5”(新木場 STUDIO COAST)に出演。楽曲ごとにコンセプトの異なる映像を使用、イマジネーション豊かなライティングとともに、とても新人とは思えない完成度を体現していた(個人的な感想ではあるが、
コーネリアスのライヴにも似た手触りを覚えた)。andropの楽曲アレンジは非常に高度であり、ときに抽象的な表現も伴うので、音源を聴いたときに“これ、ライヴではどうなるんだろう?”なんて思ってしまったのだが、その演奏能力にも注目すべきものがあり、楽曲の世界観とメッセージをしっかりと描き出していた。ロック・バンドに不可欠な肉体的ダイナミズムも十分に感じられ、ライヴ・バンドとしてのポテンシャルも相当に高いようだ。4月17日に行なわれるワンマン・ライヴ<angstrom 0.1pm>(代官山UNIT)も当然のようにソールド・アウト。いまのところステージ以外で彼らの姿を見る機会がないため(ホームページにもメンバーの写真は載っていない)、andropのライヴには今後さらに大きな注目が集まることになるだろう。
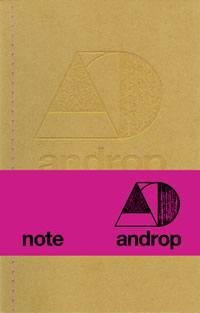
爆発的ブレイク前夜とでもいうべき状況のなか、andropは2ndアルバム
『note』をリリースする。前作からわずか4ヵ月というスピードで届けられた本作からは、このバンドが持つ未知数の、そして、無限の音楽的可能性が(前作以上の濃度・強度で)伝わってくる。収録されているのは5曲。じつに多彩な魅力を持った楽曲について、ひとつひとつ紹介していきたい。
まずはオープニング・ナンバーの「Colorful」。“透明なボール、きれいなボール。青に白にそれから緑”という、色とりどりの映像を想起させる歌詞を響かせるヴォーカル〜シャープな切れ味を持つギター〜刺激的なビートを放出するドラム〜ヘヴィにしてしなやかなグルーヴを備えたベース。ファンクとロックとポップスを絶妙のバランスで融合させたこの楽曲は、andropの急激な進化をはっきりと示していると思う。
「Colorful」とは対照的に、2曲目の「Glider」はバンド全体が完全にひとつになったロック・チューン。鋭く空間を切り裂いていくリズム、ドラマティックに展開していく楽曲構成のなかで、美しくもノスタルジックなメロディが広がっていく。そこに出現する圧倒緒的な気持ちよさをぜひ、体感してほしい。“悲しみを目に映したグライダー”をモチーフにしたリリックも秀逸だ。
そして「男は旅の途中です」というフレーズから始まる「Traveler」。この曲には彼らが持つ、ストーリーテラーとしての才能が刻み込まれている。基本的なモチーフは、人間の一生。神話的と言えるほどのスケールを感じさせながら、しかし、決して日常的なリアリティを失うことなく、聴き終わったあとには”ここからまた、がんばって生きてみよう”というナチュラルなポジティヴ感を与えてくれる。また、物語の展開としっかり重なりながら、楽曲に奥行きを与えるアレンジメントも素晴らしい。
個人的にもっともグッと来たのが、4曲目の「Merrow」。軽やかに飛び跳ねるようなベース・ライン、浮遊感のあるギター・フレーズ、クルクルと表情を変えていくドラム、そして、“悲しい海”“優しい風”“君想う未来”といった印象的な言葉たち。それらのエレメンツがゆったりと重なりながら、ひとつの真実に触れてしまいそうな“歌”を紡ぎ出していく。この表現方式もまた、andropの大きな特徴だと思う。
シンプルなギター・ロックのスタイルを用いた「Meme」からは、彼らの音楽的スタンスが感じられて興味深い。「君の遺伝子になるよ/知らないコードが今日も/君の胸で泣いてるよ」というラインからは彼らのモチベーションの在り処を想像させるし、「未来の下でいつかは出会いたい/問題ない様に光るよ」にはこのバンドの健康的な上昇志向を感じてしまうのだ。
最後に強調しておきたいのは、“解説”や“情報”だけでは『note』の世界観は絶対に捉えられないということだ。andropの音楽はおそらく、聴く人の状況、精神状態などによって、カラフルに表情を変えていく。それはつまり、何度聴いても、いつ聴いても新鮮な魅力を失わないということに他ならない。まだ彼らの音楽を経験してない人はぜひ、このアルバムに触れてみてほしい。そこには音楽だけが持ちえる、豊かで奥深い世界が広がっているはずだ。
文/森 朋之

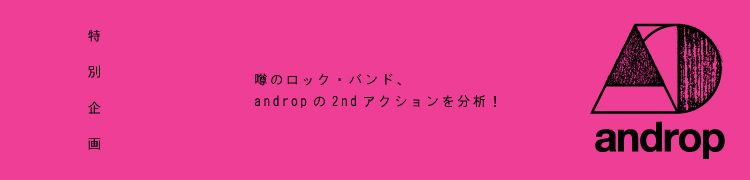
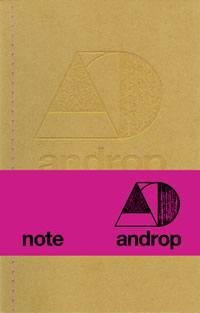 爆発的ブレイク前夜とでもいうべき状況のなか、andropは2ndアルバム『note』をリリースする。前作からわずか4ヵ月というスピードで届けられた本作からは、このバンドが持つ未知数の、そして、無限の音楽的可能性が(前作以上の濃度・強度で)伝わってくる。収録されているのは5曲。じつに多彩な魅力を持った楽曲について、ひとつひとつ紹介していきたい。
爆発的ブレイク前夜とでもいうべき状況のなか、andropは2ndアルバム『note』をリリースする。前作からわずか4ヵ月というスピードで届けられた本作からは、このバンドが持つ未知数の、そして、無限の音楽的可能性が(前作以上の濃度・強度で)伝わってくる。収録されているのは5曲。じつに多彩な魅力を持った楽曲について、ひとつひとつ紹介していきたい。
 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。