透明感のある声、卓越した技術、深い情感を併せもつシンガーであり、歌うべきことと真摯に向き合うソングライターであり、時流を追う制作ではなく、音楽本位の創作を志向するプロデューサーでもある
KOKIA。5月18日にリリースされる
『moment』は、彼女がその才能をフルに発揮したアルバムだ。レコーディングは3月8日、9日の2日間、東京・草月ホールにオーディエンスを招き、プロセスを公開するという異例の方法で行なわれている。通常のレコーディングとは違うために準備段階から困難もあったようだが、KOKIAとミュージシャン、スタッフのチームは“オーディエンスと同じ空間にいるからこそ、音に命が吹き込まれる”というコンセプトを共有し、素晴らしい作品をつくりあげた。(文中のコメントはすべて関係者のメール・インタビューでの回答)
“音楽が生まれる瞬間−moment”を共有する
貴重な公開レコーディング
3月8日、午後1時20分。画期的なステージ・レコーディングのスタートを目前にした草月ホールは静けさに包まれていた。実際はステージを歩くスタッフの足音や、打ち合わせの声、オーディエンス同士の会話、さらにはMCによる前説なども聞こえてくるのだが、それらが静けさを強調しているように感じられるのだ。これからどんなことが行なわれるのか、明確にわかっているオーディエンスはいない。進行を理解しているスタッフも、実際にどんなことが起きるのかはわからない。そんな期待と緊張が入り混じり、ホールの空気を支配しているのだろう。
予定時刻の1時30分をわずかに過ぎて、KOKIAとミュージシャンがステージに登場。KOKIAがオーディエンスに挨拶をし、笑顔を見せると、少し空気が緩んだように感じられた。ミュージシャンのまとめ役を担うピアニストの浦清英が「それじゃあ、いってみましょうか?」と声をかける。
1曲目は「本当の音」。ピアノのイントロがホールに響く。KOKIAはステージ奥のピアノを見る形でマイクに向かうので、オーディエンスには背を向けている。今回のレコーディングがライヴとはまったく違うものであることを象徴しているかのようだ。しかし、ライヴとの決定的な違いは、KOKIAが歌い始めたときに知ることとなった。PAを通さないので、通常のバランスではないのだ。演奏にベース、ギター、パーカッション、ストリングスが加わると、抑えて歌う部分などはヴォーカルが聴き取りにくくなるが、ステージ上の一体感は伝わってくる。

テイク1を完奏するとすぐにプレイバック。メンバー全員が調整卓の両側に置かれたモニタースピーカーの前に集まり、各自のパートをチェックする。パーカッションは音色を変えるために、別のマイクで録ることにした。
演奏の途中でミスが出ることもあり、テイクを重ねていく。ヴォーカルも含めて全員が揃って演奏する同録であり、しかも、各楽器の音の“かぶり”を避けられない状況でのレコーディングだけに、一人のミスも許されない。息を潜めてステージに注目している筆者も、“うまくいってほしい”と祈るような気持ちになる。
最終的にはテイク5がOKとなった。オーディエンスにも十分な音量で聴いてもらえるように、ステージ前のラージモニターでプレイバックする。深い森の清涼な空気を思わせる演奏をバックにしたKOKIAのヴォーカルは、強弱の振幅が大きく、ニュアンスに富んでいる。音楽の全貌がオーディエンスに初めて明かされ、ホールにいるすべての人が“音楽が生まれる瞬間−moment”を共有した。
「公開録音で最も興味があったのは、聴衆を前にした演奏者がテイクを重ねていくとどんなことが起こるのかということに尽きます。スタジオ録音のディレクションで最も大事なのは何時、何処で最良のテイクが生まれるかを見極める作業であると考えています。気心の知れた演奏者とスタジオという密室空間で作業をしていると、先の“何時、何処で”が完全ではないまでもわかるようになってきます。相撲における立ち会いの如く合図もなく各々の間合いがすっと整うのが、啓示のように降りてくる。しかしながらそれはあくまでも気心の知れた仲間と密室空間でのこと。聴衆を前にした我々は全体どんな演奏をするのか、もう少しいえば聴衆を前にしたテイク2、テイク3はどんな演奏になるのか、これに非常に興味を持ちました」
(ピアノ+編曲・浦清英)
プロフェッショナルな音への追求
3曲目の「大丈夫 だいじょうぶ」では思わぬトラブルがあった。レコーディングが中断し、ステージ上が慌ただしくなったのだ。“どうしたのだろう?”と筆者には不安がよぎり、オーディエンスも同じだったと思うが、“ペダル・スティール・ギターの音が歪むために、解消する方法を探っている”というMCの的確な説明によって、状況を把握することができた。このときに限らず、専門的なことを解説したり、会場を和ませたりと、今回の特殊なレコーディングにおいてはMCの存在が重要だったと感じる。
「いま何が行なわれているのか? これを一般の方にどうわかりやすく説明できるかに命を懸けました。どれだけたくさんの“へえ〜!”“なるほど! こうなってんのか!”をお持ち帰りいただけるかが、今回の企画の成功を左右すると思っていたので。あとは、MCでも言いましたが、客席の皆さん全員がディレクターだと想定し、僕もお客さんと同じ目線でステージを捉える。そこで受けた印象は全員共有しているはずだから、それをうまく代弁し言語化することで、ステージと客席をブースとコントロール・ルームの関係に置き換えていけるんじゃないかと考えました。MCっていうより通訳っていうイメージで臨んだつもりです。何が起きるか分からないから、ホントに同時通訳の心境。パフォーマンスとMCの間合いは、最初は難しいかな?って思いましたけど、実はスタジオでの間合いとそう変わらなかったです。でも一番注意したのは、とにかくオーディエンスの皆さんを固くさせず・飽きさせず、かなあ」
(ビクターエンタテインメント A&R・助川 仁)
前例のないレコーディングにおいて、準備がいかに大切だったかは容易に想像できる。すべて新曲の11曲を2日間でしっかりと録り終えることができたのは、万全の態勢で臨んだからこそだろう。

「今回の発想がKOKIAから出た時に、“面白い”と同時にKOKIAならできると最初は簡単に思ってましたね。でも今までのDVD用のコンサート収録や、スタジオでの同録と、どう違うのかをスタッフ、オーディエンス共に説明するのが大変だなと頭を悩ませてました。オーディエンスが居るという緊張感はありつつ、レコーディングのやりやすさを考えるのが、場所やシステムや時間も含めて考えどころでしたね。いざ曲数が決まりシステムを構築し始めると障害が多々あって……でも“チームKOKIA”のみんなのお陰で無事にできたと思ってます。ミュージシャンにレコーディング以上のパフォーマンスを発揮してもらいつつ、良い(音の)環境で演奏するにはどうするか。ホール(ステージ)という場所でもスタジオ並みのクオリティでレコーディングするにはどうするか。普段では聴けないような状況の音をどうやってオーディエンスに聴いてもらうのか。どれも今回の主旨では犠牲にできない部分なのでコンセンサスをとるのは大変でしたが、固唾をのんで見守っていたオーディエンスも含めてみなさん最高でした!」
(anco & co. ディレクター・平野重之)
初日の4曲目「愛と平和と音楽と」は中盤からドラムスとともに別のスネアも加わり、マーチング・バンドのリズムを刻む音圧のある曲。通常のスタジオ・レコーディングではそれぞれの楽器をブースに収めて、音がかぶらないようにするが、今回はステージということで完全な分離は不可能だ。そうしたなかで、いかに音楽としてまとまりのある音に録るかはエンジニアにとって腕の見せどころである。ラージ・モニターで聴いたOKテイクのテイク3は、穏やかな序盤と力強い中盤以降の対比が鮮やかな、スケールの大きい音だった。

「今回の仕事を依頼されて、まず考えたのはどの音像、質感に収めるかということです。それは、スタジオ録音のように、できる限り個々の音をクリアに録音して聴かせるのか、それよりは、ライヴよりの音像で個々の音よりは全体感で聴かせるのかということですね。この方向性をどうするかで全てが決定されるので、平野さん、浦君とは、かなり話し合いをしました。一番悩んだのは何もない場所での録音ということで機材の選択ですね。録音するレコーダーはPro Toolsに決定していたので、そこに送るまでのMic PreやCompのセレクトです。最初の段階ではVenueというデジタルコンソールで全てを完結する予定でしたが、リハ1週間位にこのシステムは基本がPA用のため、このままでは録音はできてもダビングはできないということが発覚、急遽フルアナログでのシステムの再構築となりました。結果的にはフルアナログに移行したことが音的に良い方向に行きましたね。次に悩んだのはマイクのセレクトです。これはどこまでスタジオ寄りの音質にするかということと同じことなんですが、スタジオで使用しているマイクは音質はいいけど他の音のかぶりが多くてMix時にどこまで音をコントロールできるのか解らない。とはいってもライヴで使用しているマイクはかぶりが少ないけど音質が……ということで、リハでいろいろ試して何とか本番を迎えられました。今回KOKIAが使用したマイクは、通常スタジオで使用している真空管マイクだったのでかなりの冒険でしたけど。レコーディングをして感じたのは、音楽を表現する上での全員の一体感ですね。スタジオでも同時に録音すれば同じだと思われるかもしれません。しかし、スタジオの場合は各自ブースに入っているので人のプレイはヘッドホンを通して聴こえるのみなのに対し、今回のステージ・レコーディングの場合は、ドラム、パーカッションの前にパーテイションはあるものの、目の前で全員がプレイをして人の音を肌で感じてプレイしています。歌に対する一体感が凄いですね」
(レコーディング&ミキシングエンジニア・笹原与志一)
KOKIAのヴォーカリストとしての力
レコーディングの場にいて、最も印象に残ったのはKOKIAの圧倒的な力量である。2日目は、初日と同じく、最後に「もう一度…」を歌った。ピアノとのデュオ。語りかけるように表現される歌詞の一語一語が胸に染みる。オーディエンスと“moment”を共有したことが、音楽にただならぬ説得力をもたらしているのだろう。
「今回の件を始め、その企画力は凄まじいといっていいほどであります。その閃きの力強さに僕は飲まれ、這い出す力が僕の仕事を前に進めてくれる。これまた希有なプロデューサーであると考えます。聴衆を前にしたテイク2、テイク3は実に得難い経験でありました。使っても使っても擦り減らない“やすり”のように、テイク毎に増していく集中力。しかもお互いのそれをステージの上の全員が五感で感じていく、これ以上に素敵な体験があり得ますでしょうか。シンガーとしてはコントロールしている自分、コントロールしていない自分、その2つをさらにその上からの視点でコントロールしている。実に希有なシンガーであります。震えました」
(浦)
現在は当たり前になっているヴォーカルや演奏の差し替えは一切なし。『moment』はそうした点でも純度の高い作品といえる。

「音楽の原点が全曲溢れていると思います。KOKIAは、“私たちミュージシャンの瞬間芸”と上手いこと言ってましたが、まさにその通り。ワン&オンリーの瞬間を記録しながら、いや、だからこそかな、何度でも感動を味わえる。そんなニュー・アルバムです。当日会場にいらっしゃれなかった多くの方にこそ、その素晴らしさが感じ取っていただける。そんな音楽が詰まっています。ミックスは確かに重要なんですが、もともと何が録れているかで、同じミックスでも意味合いが180度違ってくると思います。と、エンジニアの笹原師匠にプレッシャーをかけつつ(笑)。でもKOKIAの真骨頂、一瞬一瞬の集中した歌声をこれほどの密度で収めた、という意味ではキャリア最高の作品になるでしょう」
(助川)
アルバム・ジャケットはKOKIA自身が撮影した青空の写真に、アーティスト名とタイトルを配したシンプルなデザイン。音楽にぴったりだと思う。

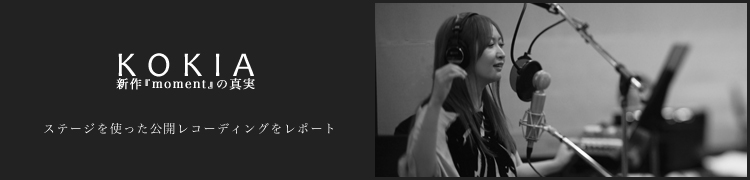

 3月8日、午後1時20分。画期的なステージ・レコーディングのスタートを目前にした草月ホールは静けさに包まれていた。実際はステージを歩くスタッフの足音や、打ち合わせの声、オーディエンス同士の会話、さらにはMCによる前説なども聞こえてくるのだが、それらが静けさを強調しているように感じられるのだ。これからどんなことが行なわれるのか、明確にわかっているオーディエンスはいない。進行を理解しているスタッフも、実際にどんなことが起きるのかはわからない。そんな期待と緊張が入り混じり、ホールの空気を支配しているのだろう。
3月8日、午後1時20分。画期的なステージ・レコーディングのスタートを目前にした草月ホールは静けさに包まれていた。実際はステージを歩くスタッフの足音や、打ち合わせの声、オーディエンス同士の会話、さらにはMCによる前説なども聞こえてくるのだが、それらが静けさを強調しているように感じられるのだ。これからどんなことが行なわれるのか、明確にわかっているオーディエンスはいない。進行を理解しているスタッフも、実際にどんなことが起きるのかはわからない。そんな期待と緊張が入り混じり、ホールの空気を支配しているのだろう。 テイク1を完奏するとすぐにプレイバック。メンバー全員が調整卓の両側に置かれたモニタースピーカーの前に集まり、各自のパートをチェックする。パーカッションは音色を変えるために、別のマイクで録ることにした。
テイク1を完奏するとすぐにプレイバック。メンバー全員が調整卓の両側に置かれたモニタースピーカーの前に集まり、各自のパートをチェックする。パーカッションは音色を変えるために、別のマイクで録ることにした。 3曲目の「大丈夫 だいじょうぶ」では思わぬトラブルがあった。レコーディングが中断し、ステージ上が慌ただしくなったのだ。“どうしたのだろう?”と筆者には不安がよぎり、オーディエンスも同じだったと思うが、“ペダル・スティール・ギターの音が歪むために、解消する方法を探っている”というMCの的確な説明によって、状況を把握することができた。このときに限らず、専門的なことを解説したり、会場を和ませたりと、今回の特殊なレコーディングにおいてはMCの存在が重要だったと感じる。
3曲目の「大丈夫 だいじょうぶ」では思わぬトラブルがあった。レコーディングが中断し、ステージ上が慌ただしくなったのだ。“どうしたのだろう?”と筆者には不安がよぎり、オーディエンスも同じだったと思うが、“ペダル・スティール・ギターの音が歪むために、解消する方法を探っている”というMCの的確な説明によって、状況を把握することができた。このときに限らず、専門的なことを解説したり、会場を和ませたりと、今回の特殊なレコーディングにおいてはMCの存在が重要だったと感じる。 「今回の発想がKOKIAから出た時に、“面白い”と同時にKOKIAならできると最初は簡単に思ってましたね。でも今までのDVD用のコンサート収録や、スタジオでの同録と、どう違うのかをスタッフ、オーディエンス共に説明するのが大変だなと頭を悩ませてました。オーディエンスが居るという緊張感はありつつ、レコーディングのやりやすさを考えるのが、場所やシステムや時間も含めて考えどころでしたね。いざ曲数が決まりシステムを構築し始めると障害が多々あって……でも“チームKOKIA”のみんなのお陰で無事にできたと思ってます。ミュージシャンにレコーディング以上のパフォーマンスを発揮してもらいつつ、良い(音の)環境で演奏するにはどうするか。ホール(ステージ)という場所でもスタジオ並みのクオリティでレコーディングするにはどうするか。普段では聴けないような状況の音をどうやってオーディエンスに聴いてもらうのか。どれも今回の主旨では犠牲にできない部分なのでコンセンサスをとるのは大変でしたが、固唾をのんで見守っていたオーディエンスも含めてみなさん最高でした!」
「今回の発想がKOKIAから出た時に、“面白い”と同時にKOKIAならできると最初は簡単に思ってましたね。でも今までのDVD用のコンサート収録や、スタジオでの同録と、どう違うのかをスタッフ、オーディエンス共に説明するのが大変だなと頭を悩ませてました。オーディエンスが居るという緊張感はありつつ、レコーディングのやりやすさを考えるのが、場所やシステムや時間も含めて考えどころでしたね。いざ曲数が決まりシステムを構築し始めると障害が多々あって……でも“チームKOKIA”のみんなのお陰で無事にできたと思ってます。ミュージシャンにレコーディング以上のパフォーマンスを発揮してもらいつつ、良い(音の)環境で演奏するにはどうするか。ホール(ステージ)という場所でもスタジオ並みのクオリティでレコーディングするにはどうするか。普段では聴けないような状況の音をどうやってオーディエンスに聴いてもらうのか。どれも今回の主旨では犠牲にできない部分なのでコンセンサスをとるのは大変でしたが、固唾をのんで見守っていたオーディエンスも含めてみなさん最高でした!」 「今回の仕事を依頼されて、まず考えたのはどの音像、質感に収めるかということです。それは、スタジオ録音のように、できる限り個々の音をクリアに録音して聴かせるのか、それよりは、ライヴよりの音像で個々の音よりは全体感で聴かせるのかということですね。この方向性をどうするかで全てが決定されるので、平野さん、浦君とは、かなり話し合いをしました。一番悩んだのは何もない場所での録音ということで機材の選択ですね。録音するレコーダーはPro Toolsに決定していたので、そこに送るまでのMic PreやCompのセレクトです。最初の段階ではVenueというデジタルコンソールで全てを完結する予定でしたが、リハ1週間位にこのシステムは基本がPA用のため、このままでは録音はできてもダビングはできないということが発覚、急遽フルアナログでのシステムの再構築となりました。結果的にはフルアナログに移行したことが音的に良い方向に行きましたね。次に悩んだのはマイクのセレクトです。これはどこまでスタジオ寄りの音質にするかということと同じことなんですが、スタジオで使用しているマイクは音質はいいけど他の音のかぶりが多くてMix時にどこまで音をコントロールできるのか解らない。とはいってもライヴで使用しているマイクはかぶりが少ないけど音質が……ということで、リハでいろいろ試して何とか本番を迎えられました。今回KOKIAが使用したマイクは、通常スタジオで使用している真空管マイクだったのでかなりの冒険でしたけど。レコーディングをして感じたのは、音楽を表現する上での全員の一体感ですね。スタジオでも同時に録音すれば同じだと思われるかもしれません。しかし、スタジオの場合は各自ブースに入っているので人のプレイはヘッドホンを通して聴こえるのみなのに対し、今回のステージ・レコーディングの場合は、ドラム、パーカッションの前にパーテイションはあるものの、目の前で全員がプレイをして人の音を肌で感じてプレイしています。歌に対する一体感が凄いですね」
「今回の仕事を依頼されて、まず考えたのはどの音像、質感に収めるかということです。それは、スタジオ録音のように、できる限り個々の音をクリアに録音して聴かせるのか、それよりは、ライヴよりの音像で個々の音よりは全体感で聴かせるのかということですね。この方向性をどうするかで全てが決定されるので、平野さん、浦君とは、かなり話し合いをしました。一番悩んだのは何もない場所での録音ということで機材の選択ですね。録音するレコーダーはPro Toolsに決定していたので、そこに送るまでのMic PreやCompのセレクトです。最初の段階ではVenueというデジタルコンソールで全てを完結する予定でしたが、リハ1週間位にこのシステムは基本がPA用のため、このままでは録音はできてもダビングはできないということが発覚、急遽フルアナログでのシステムの再構築となりました。結果的にはフルアナログに移行したことが音的に良い方向に行きましたね。次に悩んだのはマイクのセレクトです。これはどこまでスタジオ寄りの音質にするかということと同じことなんですが、スタジオで使用しているマイクは音質はいいけど他の音のかぶりが多くてMix時にどこまで音をコントロールできるのか解らない。とはいってもライヴで使用しているマイクはかぶりが少ないけど音質が……ということで、リハでいろいろ試して何とか本番を迎えられました。今回KOKIAが使用したマイクは、通常スタジオで使用している真空管マイクだったのでかなりの冒険でしたけど。レコーディングをして感じたのは、音楽を表現する上での全員の一体感ですね。スタジオでも同時に録音すれば同じだと思われるかもしれません。しかし、スタジオの場合は各自ブースに入っているので人のプレイはヘッドホンを通して聴こえるのみなのに対し、今回のステージ・レコーディングの場合は、ドラム、パーカッションの前にパーテイションはあるものの、目の前で全員がプレイをして人の音を肌で感じてプレイしています。歌に対する一体感が凄いですね」
 レコーディングの場にいて、最も印象に残ったのはKOKIAの圧倒的な力量である。2日目は、初日と同じく、最後に「もう一度…」を歌った。ピアノとのデュオ。語りかけるように表現される歌詞の一語一語が胸に染みる。オーディエンスと“moment”を共有したことが、音楽にただならぬ説得力をもたらしているのだろう。
レコーディングの場にいて、最も印象に残ったのはKOKIAの圧倒的な力量である。2日目は、初日と同じく、最後に「もう一度…」を歌った。ピアノとのデュオ。語りかけるように表現される歌詞の一語一語が胸に染みる。オーディエンスと“moment”を共有したことが、音楽にただならぬ説得力をもたらしているのだろう。 「音楽の原点が全曲溢れていると思います。KOKIAは、“私たちミュージシャンの瞬間芸”と上手いこと言ってましたが、まさにその通り。ワン&オンリーの瞬間を記録しながら、いや、だからこそかな、何度でも感動を味わえる。そんなニュー・アルバムです。当日会場にいらっしゃれなかった多くの方にこそ、その素晴らしさが感じ取っていただける。そんな音楽が詰まっています。ミックスは確かに重要なんですが、もともと何が録れているかで、同じミックスでも意味合いが180度違ってくると思います。と、エンジニアの笹原師匠にプレッシャーをかけつつ(笑)。でもKOKIAの真骨頂、一瞬一瞬の集中した歌声をこれほどの密度で収めた、という意味ではキャリア最高の作品になるでしょう」
「音楽の原点が全曲溢れていると思います。KOKIAは、“私たちミュージシャンの瞬間芸”と上手いこと言ってましたが、まさにその通り。ワン&オンリーの瞬間を記録しながら、いや、だからこそかな、何度でも感動を味わえる。そんなニュー・アルバムです。当日会場にいらっしゃれなかった多くの方にこそ、その素晴らしさが感じ取っていただける。そんな音楽が詰まっています。ミックスは確かに重要なんですが、もともと何が録れているかで、同じミックスでも意味合いが180度違ってくると思います。と、エンジニアの笹原師匠にプレッシャーをかけつつ(笑)。でもKOKIAの真骨頂、一瞬一瞬の集中した歌声をこれほどの密度で収めた、という意味ではキャリア最高の作品になるでしょう」 【収録曲】
【収録曲】
 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。