村上ゆき ニュー・アルバム『Watercolours』発売記念
3週連続特集 COLOURS第1回目:アルバム『Watercolours』インタビュー

ジャズをベースにしたポップ・サウンドと表現力豊かな歌声に定評がある実力派シンガー、
村上ゆき。シャープAQUOSクアトロン、積水ハウスなど、さまざまなCMソングを歌うなど、お茶の間にもその歌声をさりげなく浸透させつつある彼女が6枚目のアルバムとなる
『Watercolours』を完成させた。
サザンオールスターズや
布袋寅泰らの作品を手がけてきた藤井丈司をプロデューサーに、アレンジャーの
宮川 弾や、作詞家の
覚 和歌子など、さまざまなクリエイターを迎えて制作された今作は、シンガー・ソングライター村上ゆきの、まだ見ぬ魅力をシンプルかつ瑞々しいサウンドとともに伝えてくれる一枚に仕上がった。CDジャーナルでは、このアルバムのリリースにあわせて3回連続で特集を掲載。1回目となる今作は、アルバム『Watercolours』の成り立ちと制作背景についてたっぷりと語ってもらった。

――今回のアルバムは“水”というコンセプトのもとに制作されたんですよね。
村上ゆき(以下同) 「はい、最初は火とか森とか、テーマの候補がいろいろあったんですけど、最終的に水に落ち着いて。そもそもは“人間の身体って、ほとんどが水で出来てるよね”という話からスタートしたんです。それで今回は聴く人の心に潤いを与えられるようなアルバムを作りたいなと思って」
――村上さん自身も普段、音楽を聴くときは“潤い”のようなものを求めるほうですか?
「いえ。どちらかと言えば、私自身は乾いた音楽が好きなんです。乾いた風のような音楽が好きで。とはいえ人から求められる自分の音楽というのは、意外にウェットなものを好まれることが多くて。でも、私自身はウエットにしようとか、ドライにしようとか特に意識したことはないんですね。シルクのような歌声だねと言われるときもあれば、麻のようだねと言われるときもあるし。あとは声が高いという人もいれば、低いという人もいて(笑)、みなさんの中で、全然違った感じに聴こえるんだと思って。だったら今回は、あえて自分から“潤い”というものに向かってみようと思ったんです」
――今回のアルバムでは藤井丈司さんがサウンド・プロデュースを手がけられています。藤井さんとのお仕事は初めてですよね?
「はい。藤井さんにはカヴァー曲の選曲も含めて、作品全体のプロデュースをお願いしています。藤井さんは今までロックやポップ・ミュージックの作品をたくさん手がけられてきた方なので、今回はあえて多くの部分をお任せしようと思って」
――藤井さんのプロデュース・ワークはいかがでしたか?
「すごく新鮮でした。私はどちらかというと、レコーディングでは完璧を求めてしまうことがあって、全体的に調和の取れたものを良しとしてしまうところがあるんですね。藤井さんはそれを壊しにかかるんです。壊れている方が面白いからって。でも私は壊し具合が分からないので、そのジャッジを藤井さんにお任せした感じです」
――最初はすごく不安だったんじゃないですか?
「そうですね。“これでOKなんですか!?”みたいなことが何度かあって。自分の中では1+1が2になるというシンプルなイメージしかないんですけど、藤井さんは1+1を3とか4にするようなスタイルで。私の場合、自分が作ったものがオーケストラになったらどうなるかとか、そういうイメージは漠然と持てるけど、それが頭の中で具体的に鳴っているかといえば決してそうではなくて。常に頭の中にあるのはシンプルなイメージなんです。だから今回は藤井さんに知らない場所まで連れて行ってもらうような感じだったんですね。もしかしたら一緒に谷底まで落ちてしまうかもしれないけれど(笑)、行くとこまで行ってみようって。どこか恐怖感を楽しむような感じもありましたね。実際、着いた場所の風景は絶景だったんですけど、今回のレコーディングは途中の行程もすごく面白くて」

――藤井さんをはじめ、今作ではさまざまなクリエイターとコラボレーションされています。以前から、複数のクリエイターと一緒にアルバムを作りたいという気持ちはあったんですか?
「そうですね。今回はいろんな方々の力をお借りして、自分では表現できない世界を形にできたらいいなと思ったんです。初めてご一緒させていただく方がほとんどなんですけど、私が今まで抱えてきたいろいろなものを、どんな風に活かしてくれるんだろうかと、すごく興味深かったです。私にとってはガラクタのように思えるものでも、活かしようによっては面白いものにしてくださるんじゃないかって。一人でできることは限られてしまうので、人の力を借りて、どう変われるかっていう。“そんなことやったら自分らしくない”とか、そういうことはこの際、どうでもいいやって(笑)。そこに、こだわっていたら何も変われないですからね」
――藤井さん以外にも今回コラボレーションしたクリエイターの方々について、お話をおうかがいしたいのですが。まずは、作詞家の一倉 宏さん。一倉さんとは、これまでに幾つかのCMソングでご一緒されていますよね。
「はい。一倉さんとはCMソングを一緒に作ることが多いので、ひとつのイメージを共有するというよりも、むしろ、それぞれがひとつの風景を見るような感じで作業を進めていく感じですね。お互い向き合わない感じというか。真っ直ぐ向き合ってしまうと“あれ?”ってなることが多くて(笑)。CMソングという大きなテーマに沿って作るほうが、自然な形でお互いの良さが出るんです。それぞれが同じ風景を見て、一倉さんは言葉を書き、私は曲を作って歌うという形がしっくりくる。そういう意味では、すごく良いパートナーなんです。しいていえば、一倉さんと真っ直ぐ向き合うときは、呑みに往くときぐらいですかね(笑)。“あの曲の歌詞は素晴らしいけど、私はあんな女じゃありません”とか(笑)、そういう無茶苦茶なことを言ったりして」
――気を使わずにコミュニケーションできる存在。
「そうですね。大御所なのに、大御所ぶったところが全然なくて。本当に優しくて懐の深い方だなと思います」
――作詞家でいえば、今回のアルバムでは覚 和歌子さんが「心の青」という曲で歌詞を提供されています。
「覚さんとは、数年前に私が谷川俊太郎さんの作品を歌わせていただいたときに、ステージでご一緒させていただいて。そんなご縁もあって、今回、歌詞を書いていただいただきました。覚さんの歌詞って、“詞”というよりも“詩”なんですね。圧倒的な言葉の力があって、どうやって歌ったらいいんだろうと試行錯誤しました。この曲では、ヴォーカル・ディレクションを含め藤井さんに本当にお世話になりました。苦労したぶん、すごく良いテイクが録れて」

――アレンジャーの宮川 弾さんとは今回が初顔合わせですよね。
「弾さんは、藤井さんが声をかけてくださったんです。私も鍵盤を弾けますけど、自分ひとりだと、アイディアの幅が狭くなっちゃうので、もう一人鍵盤を弾ける人が現場にいたらいいんじゃないかということで。宮川さんは人間的にもすごく魅力的な方なんです。スタジオにいらっしゃるだけで、その場の空気が和むというか。あるときは、パジャマみたいな服装でスタジオに現れたり(笑)。すごく、おいしいネタをいっぱい提供してくれました。弾さんは一言で言えば、“閃きの人”なんだと思います。出てくるアイディアやフレーズがとにかく斬新なんです」
――今回のアルバムは、サウンド的にシンプルだけど瑞々しくて、村上さんの歌声が持つ、多彩な表情がよりクリアに伝わってくるような印象を受けました。音像の部分でエンジニア小池光夫さんの存在もすごく大きかったように思います。
「そうですね。小池さんは、ずっとお願いしている方なので、私の声を本当に分かってくださっていて。今回のレコーディングでは、音のない空間を活かすということが大きなポイントになっていて、それを実現させるにあたって、小池さんにも本当に力を貸していただきました。過去に、たくさん要素が詰まったサウンドに乗せて歌ったこともあるんですけど、そういうのって全然良くないんですよ(笑)。歌声の大事な成分を消されてしまうというか。たぶん私の声って、生きている時間が短いと思うんです」
――生きている時間が短い?
「はい。何時間しか咲かない花とかあるじゃないですか。私の声って、どこか、ああいう花に近いような感じがして(笑)。今回のレコーディングで、私の声が生きてるか、どうかを見極めてくださったのが小池さんだったと思うんです」
「<夢で逢えたら>と<サヨナラCOLOR>は藤井さんの推薦です。<When the world turns blue>は、昔からライヴでよく歌っていた曲なんです。<夢で逢えたら>は私、サビの部分しか知らなかったんですけど、初めて1曲通して聴いて、すごく良い曲だなって。藤井さんからは、“力を抜いて、悲しい感じで歌ってほしい”と言われました。<夢でもし逢えたら素敵なことね>という歌詞のフレーズから、ウキウキした歌い方をイメージしていたんですけど、藤井さんいわく“この歌の主人公は、まだ逢いたい人に逢えてないんだよ”って。それで、ちょっと寂しげな感じの歌い方になってるんです。<サヨナラCOLOR>もメッセージ性の強い曲なので、歌い上げてしまうと曲の良さが伝わらなくなってしまうなと思って、意識して肩の力を抜いて歌いました」
――完成した作品をご自身で聴いてみて、どんな印象を持ちましたか?
「自分で聴きながら“これは眠れるぞ”と思いました(笑)。あと、何度も繰り返して聴けるようなアルバムになったかなと思います。余白をたくさん残してあるので、聴く人それぞれが、思い思いの色をそこに塗ってくれたらいいなと思います」
取材・文/望月 哲(2011年5月)

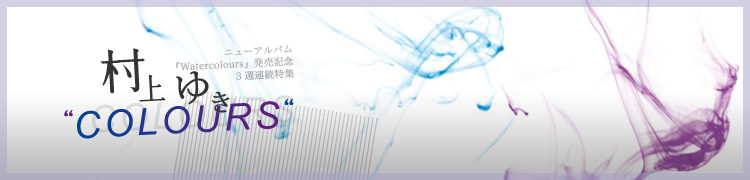
 ジャズをベースにしたポップ・サウンドと表現力豊かな歌声に定評がある実力派シンガー、村上ゆき。シャープAQUOSクアトロン、積水ハウスなど、さまざまなCMソングを歌うなど、お茶の間にもその歌声をさりげなく浸透させつつある彼女が6枚目のアルバムとなる『Watercolours』を完成させた。サザンオールスターズや布袋寅泰らの作品を手がけてきた藤井丈司をプロデューサーに、アレンジャーの宮川 弾や、作詞家の覚 和歌子など、さまざまなクリエイターを迎えて制作された今作は、シンガー・ソングライター村上ゆきの、まだ見ぬ魅力をシンプルかつ瑞々しいサウンドとともに伝えてくれる一枚に仕上がった。CDジャーナルでは、このアルバムのリリースにあわせて3回連続で特集を掲載。1回目となる今作は、アルバム『Watercolours』の成り立ちと制作背景についてたっぷりと語ってもらった。
ジャズをベースにしたポップ・サウンドと表現力豊かな歌声に定評がある実力派シンガー、村上ゆき。シャープAQUOSクアトロン、積水ハウスなど、さまざまなCMソングを歌うなど、お茶の間にもその歌声をさりげなく浸透させつつある彼女が6枚目のアルバムとなる『Watercolours』を完成させた。サザンオールスターズや布袋寅泰らの作品を手がけてきた藤井丈司をプロデューサーに、アレンジャーの宮川 弾や、作詞家の覚 和歌子など、さまざまなクリエイターを迎えて制作された今作は、シンガー・ソングライター村上ゆきの、まだ見ぬ魅力をシンプルかつ瑞々しいサウンドとともに伝えてくれる一枚に仕上がった。CDジャーナルでは、このアルバムのリリースにあわせて3回連続で特集を掲載。1回目となる今作は、アルバム『Watercolours』の成り立ちと制作背景についてたっぷりと語ってもらった。 ――今回のアルバムは“水”というコンセプトのもとに制作されたんですよね。
――今回のアルバムは“水”というコンセプトのもとに制作されたんですよね。 ――藤井さんをはじめ、今作ではさまざまなクリエイターとコラボレーションされています。以前から、複数のクリエイターと一緒にアルバムを作りたいという気持ちはあったんですか?
――藤井さんをはじめ、今作ではさまざまなクリエイターとコラボレーションされています。以前から、複数のクリエイターと一緒にアルバムを作りたいという気持ちはあったんですか? ――アレンジャーの宮川 弾さんとは今回が初顔合わせですよね。
――アレンジャーの宮川 弾さんとは今回が初顔合わせですよね。
 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。