
本田さんが所有する、思い入れのあるレコードたち
――まずはD-1ドラム選手権グランド・チャンピオン大会、優勝おめでとうございます。出場されて、いかがでしたか?
「実は1回目のD1を聴きに行っていて、優勝した竜巻太郎さん(
NICE VIEW,
TURTLE ISLAND他)を初めて観て、パンクの世界にね、音楽的なことを意識して演奏する人もやっぱりいるんだとびっくりして。今回彼が海外ツアーで欠場したため対戦が実現できなかったのはとても残念でしたね」
――パンクとの出会いについて教えてください。
「僕はもともとヘヴィ・メタルやスラッシュ・メタルが好きだったんです。
METALLICA、特にクリフ・バートンがとにかく好きで、彼の着ていた
MISFITSのTシャツがすごくかっこよく思えたんですね。どんな音なんだろう?って思いながら、〈Die Die My Darling〉を買ったんだよね(笑)。海外のメタル雑誌を買って、アーティストが着ているTシャツをチェックして、ロゴを覚えて、レコードのジャケ買いをして、広がっていきましたね。ファッション先行ですね(笑)。当時すでにMISFITSは活動していなかったから、廃盤を探すしかなくて。新宿のVINYL JAPANに飾られていたMISFITSのレコード、12inch盤の〈BEWARE〉を“いつか買いたいな”と眺めていて、5年後くらいにその飾られていた盤自体を買いました」
――もしグレン・ダンジグからMISFITSに誘われたら参加しますか?
「ドラムはやらないなあ(笑)。MISFITSに参加するならギターがいいなあ……。再結成に誘われて参加するんだったら
LED ZEPPELINがいいな、叩き甲斐がある(笑)。たとえば、『Doll』(パンク専門誌)の後ろの方に載っているレコード屋のセールの広告を全部チェックして買いに行くっていうのを繰り返してましたね。この宝島の『ラジカルスケートブック』(JICC出版局)で紹介された音源もほとんど集めました。
GANG GREENはこれがきっかけ。スケートボードに興味ないのにこういう本まで買ってましたね。LIFE SENTENCEはTシャツ、今でも欲しいんだけど出てこないんだよなあ……」

着込んで色の褪せたMISFITSのTシャツとラジカルスケートブックも本田さんの私物
――ネイティヴ・サンのライヴで出たギャラを握りしめて西新宿へ走るんですね(笑)。
「そうです(笑)。銀座のスイングに出ると1万円もらえるから、小滝橋通りから大久保まで回ってましたね。何時間かかったかなあ(笑)。すごい数のレコード屋があったからね!」
――パンクの何に夢中になったんでしょう? 魅力はどこにありましたか?
「パンクは演奏がどうこうじゃなくて、みんなで合唱できるような、楽しめるところがいいのかな。たとえばオイ・パンクや、
COCKNEY REJECTSなんかのシンガロング・スタイルのバンドやSxE系、
MINOR THREATみたいな叫べるような曲とか。展開がはっきりして、楽しいところが用意されていて、リフがかっこいいところが好きなんだろうな」
――パンクに夢中になる一方で、D-1では“ジャズ界のサラブレット”と紹介されていた通り、避けて通れない存在としてジャズとご両親があったと思いますが。
「親のことは大尊敬しているので、抵抗感や反抗心はなかったですね。……そうですね、自宅にはジャズも含めソウル、ロックもありましたね。おふくろ(ジャズ・ヴォーカリストの
チコ本田)も
ジャニス・ジョプリンが大好きだったりね。親父(ネイティブ・サンのリーダー、ピアニストの
本田竹広)にスラッシュ・メタルを勧めたことはさすがにないけど、聴いていても怒られなかったからなあ(笑)。20歳頃まで……
エルヴィン・ジョーンズを聴くまで、ジャズは全然聴かなかった。エルヴィン・ジョーンズも、最初は“まるで
ジョン・ボーナムだ! 俺の好みだ!”と思ったんだよね。それが切っ掛けでどんどんジャズにのめり込みました」
――ジャンルや特定のスタイルについてのこだわりがない、とても自由な耳をしていらっしゃるんですね。
「話はちょっとずれるけど、実は、初めてのリーダー・アルバム
『planet x』(2000年)をリリースしたころは……フリー・ジャズが嫌いだったんです。いわゆるフリーキーな演奏にはテクニックや美意識が見いだせなくて、簡単に言ってしまうと、ほとんどがでたらめだと思ってました。……2006年に父が亡くなって、このまま4ビート・ジャズを続けるべきなのか、“日本を代表する”なんて冠がつくようなジャズ・ドラマーになりたいのか?と、考えたんです。そこで、俺はそういうキャラクターではないな、ドラムを叩いて楽しいことをしたいって思ったんです。ならば自分にない世界に飛び込むしかないと思ったんですね。それがフリーだった。
大友良英さんとのデュオで演奏した時に、自分としては大失敗してしまって。ギターで共演して頂いたんですが、大友さんはグローバルな方法というか、テイストとかニュアンスを打ち出してきて、自分はそこにリズムで合わせるしか術がなくて、とても落ち込んだんです」
――それまでは美意識にとらわれていた?
「セッション相手や、お客さんのことを必要以上に気にしていたのかな。即興の人たちとの演奏ではいい結果には結びつかないうえに、自分も面白くなかった。その場のバイブレーションを感じていないと、まとまらない演奏になるし、躊躇していると何も発生しないってことが大友さんとの経験でよくわかりました。2008年に初めて
ペーター・ブロッツマンさんと共演したんですが、その時には、自分がドラムを叩くことで、そこで生き抜くのが役目だと彼から学び取れたというか、確信を得ることができました。しっかりジャズをやってきたからこそできる自由なことっていうのはありますね。そういう経緯を経たから、今は音楽に対して垣根はまったくないですね。ペーター・ブロッツマンさんと
渡辺貞夫さんともやってるドラマーなんて自分以外はいませんからね(笑)。ジャンルこそ違えど、この二人はステージのたたずまいだけで勉強させていただける。共演できることは本当に幸せですね。そして今秋には箏奏者の
八木美知依さんと長らく暖めて来たコラボレーション『道Dōjō場』が発売されます。これを聴けば現在の僕の活動が一聴瞭然です」
――今日はDROPDEADでおめかしされていますが、Tシャツでもパンク好きを公言されていますね。
「DROPDEADも音がすごいよね! 最初激しすぎてびっくりしたよ(笑)。
LARMとかSEEIN'REDなんかもすごいなって思ったけどさ、このバンドはほんとにすごいよね、"落とす死"ってなんだよって(笑)。僕がそうだったように、Tシャツで誰かが気がついてくれたら、嬉しいです。初代のMISFITSのTシャツはクリフみたいに袖を切っちゃったので、今日持ってきたのは二代目なんですよ。
ジム・オルークさんと共演したときもね、
BLACK FLAGのTシャツ着てたら“それ、大好き”って反応してくれて。コミュニケーションが生まれますね」

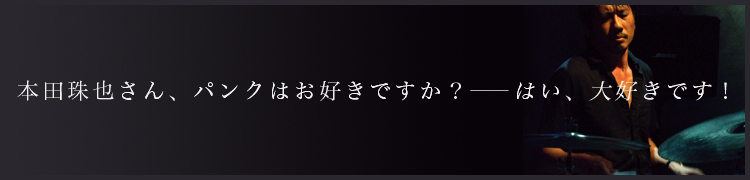




 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。