“Share a dream with us”。東京スカパラダイスオーケストラのニュー・アルバム『Perfect Future』の収録曲「Pride Of Lions」にあるこの言葉こそ、スカパラを音楽に向かわせている原動力として大きい。CDやライヴでのリスナーの歓喜がスカパラ・サウンドを次のステージへと押し上げている。言わば、スカパラとリスナーの“幸福な関係”によって生み出された新しいサウンドが、このアルバムには詰まっている。 ――今作『Perfect Future』は、“混沌としたアルバム”という印象を強く受けました。
川上つよし 「それは嬉しいですね」
谷中敦 「前作
『WILD PEACE』からの1年10ヵ月は、2、3日に一度ライヴを演るというタイトなツアーをしてたんですね。国内は隈なく回ったし、ヨーロッパをはじめシンガポールやベトナムとか海外も回って。今作はいろんな国のいろんな場所の、いろんな人の顔を思い浮かべながら作って、それぞれの町で呼吸してきたことが、“混沌とした雰囲気”に繋がったんだと思います」
――今回のジャケットもカオティックな雰囲気で。それと同時に“原点回帰”的な部分も感じました。東京タワーが登場するのは
『トーキョーストラット』(96年)以来ですし、“東京”や“日本”を想起させるアートワークはここ最近はなかったですよね。
谷中 「そうですね。こういう派手なのは久しぶりだし、
『ワールドフェイマス』(91年)に近い雰囲気もありますね。東京ってすごくゴチャゴチャした街だと思うし、いろんな人もいるし。そういうものが僕らの音楽に影響してる部分もあると思うんですよね」
川上 「音的な部分でも、
『FULL-TENSION BEATERS』(2000年)あたりから、ライヴ感をいかにCDに落とし込むか、いわゆる“一筆書き”みたいな部分にこだわってきたんですね。だけど、今回は逆にそういったこだわりを捨てて、一発録りは一発録りだけど、それをバラしたり音を加えたり、一曲一曲のキャラクターをより濃いものにしようっていうのがチャレンジでもありましたね」
――そこで思ったのは、ベスト盤の2作を基準に考えると、
『BEST(1989〜1997)』までは、ある種の混沌とした“なにが起きるか分からない”という雰囲気が強かったと思うんですね。そして
『BEST OF TOKYO SKA 1998-2007』は、そこで培われたものをいかに多くの人に届くように、“ポップスとして認識させていく”という時期だったと思うんです。今作には、その2つの作風を“統合させていきたい”というような意向を感じました。
谷中 「そうなったらいいですね。やっぱり、今作はスカパラにとって“新しい一歩”なので。今回はスタジオで出てきたすべてのアイディアを試すぐらいキメ細かく、かつ遊びながら作って。“Perfect”を目指して、“Future”の一歩をここから生み出すという気持ちですね。アルバムを出すたびに完璧を求めるのは常に変わらないんですけど、音楽そのものに身を任せるという感じが自由にできましたね」
――その新しい一歩を踏み出そうと思った動機はなんですか?
谷中 「前作からの1年10ヵ月の間ワールド・ツアーを続けて、“やることはみんなやったかな”と思って。ベスト盤についても“これだけのことをよくやったな”って気持ちもあったから、ここで改めて“スカパラ本体でどれだけのことができるか”ってことを試してみたかったんですよね。自分たちだけで新しい世界を作っていかなくちゃいけないということで緊張感はあったんですけど、そのぶん面白いことができたと思います」
――もう一度“スカパラとは?”という部分を見つめるということですね。
川上 「全世界をメンバーと一緒に回るうちに、みんながそういうモードになっていったんですよね。だから自然と」
谷中 「“なにかを感じる”って作業はじつは大変だし面倒なことで。だけど、なにも感じないと、なにも生み出せないと思うんですよね。常に新しい発見はあるわけだし。これだけ長い間一緒にいるのに、メンバーのなかでもいまだに新しい発見があるから不思議だよね」
川上 「最近驚いたのは、谷中がペン習字を習ってたこと。“あの字で!”って(笑)」
谷中 「“でも、初段だよ!”って(笑)」
川上 「あれはショックだったなあ(笑)」
――このアルバムは、そういった意味で言うとスカパラの“内”に目を向けていながらも、非常に外向きで。つまりポップですよね。
川上 「基本的にメンバー全員がオープンで、本当に人前で演ることが大好きだし、性格自体が外向きなんですよね。それが唯一の共通項なぐらい。それは当然音にも出るんでしょう」
――なるほど。今作に収録された「Pride Of Lions」では客演に
伊藤ふみおさん(
KEMURI)を迎えられましたね。今までは
奥田民生さんや
甲本ヒロトさんといった、他ジャンルからの客演でしたが、今回でスカ畑のアーティストを迎えた理由はあるんですか?
川上 「スカ同士は初めてですね。もともと歳が同じだし、キーボードの沖(祐市)は、ふみおくんと高校生のときからの知り合いだったりするんですよ。で、去年のライジングサン・ロックフェスティバルに、スカパラも、解散が決まったKEMURIも出演していて、スカパラのステージのときに飛び入りでふみおくんに1曲歌ってもらったんです。それが終わったあとに、“KEMURIは解散するけど、歌うことは続けていきたいと思ったよ”って言ってくれたんで、“じゃあ、ニュー・アルバムで1曲歌ってもらおう”って。だから必然的な流れです」
谷中 「ふみおがKEMURIで提唱していたP.M.A.(Positive Mental Attitude=肯定的精神姿勢)を踏まえ、ボクなりのP.M.A.を歌詞に込めたのですが、ふみおも大事に歌ってくれたし、スカパラにもKEMURIにもなかった音楽を作れたのが嬉しかったですよ」
――今作で谷中さんの書かれたリリックは、分かりやすく、かつ希望に満ちてますね。
谷中 「〈女神の願い〉は誕生ソングで、“子供や新しい命を大切にしよう”というメッセージがありますね。また、裏テーマとしては“名付け得ぬもの:だけれどももう生まれているもの”ですね。いろんな感情やムーヴメントが生まれたときに、“こういう名前じゃない?”って名付けることで、その感情をみんなで共有できるようになると思うんですけど、そういう名前を付けて歩きたいっていうのが僕の夢で。モヤモヤしたものに名前を付けることによって出口を作るというか、名前によって、まとまって、一点突破できると思うんですね。その気持ちは〈Pride Of Lions〉にも繋がっていて。“Share a dream”、一つの夢を共有することによって、みんなが一つになって壁を突破できる。そこでまた新しいなにかが生まれると思うんですよね。そういうことができればいいなって」
――なるほど。2枚のベスト盤をリリースされて、リスナーとしてはここから“第3期スカパラのスタート”という見方ができると思いますが、その新たな状況はどのようなものになりそうですか?
川上 「どうなるんですかねえ……。どんな“Perfect Future”が待ってるやら(笑)。この年齢じゃないと出せない音、言えないことがあると思うんですよ。年相応のリアリティというか」
谷中 「自分たちとしてもモチベーションを保つ工夫ができればいいと思いますね」
――今年でデビュー19年ですけど、モチベーションが保てるのはなぜですか?
谷中 「“スマイル精神”なのかな。本気で辛いときでも、お客さんが笑顔で踊ってくれてるのをみると、まだ頑張れると思うんですよね。それが原動力です。海外のライヴでも必ず言うのは、“エネルギーの交換”って言葉なんですよね。こっちもエネルギーを出すから、そっちも返してくれと。それは世界共通だし、健全な状態だと思うんですね」
――これから30本以上のライヴ・ツアーが控えてますが、どのようになりそうですか?
川上 「『FULL-TENSION BEATERS』以降は、先にライヴで新曲をガンガンやって、ある程度固まったところで一発で録る、って流れだったんですね。だけど、今回はほとんどライヴでやったことのない曲ばかりだから、今までにないくらいフレッシュな気持ちで臨めるツアーになるので、すごく楽しみですね」
――では、最後に。スカパラの目指す“完璧な未来”とはなんですか?
谷中 「先々で、嬉しいシンクロニシティや奇跡が起こるといいですよね。実際、一つの目標に向かって必死なときに――たとえばツアーだったり――シンクロニシティが起こったりするんですよね。そのキッカケになれるのが音楽だと思うんです。人と人と繋がることは本当に大事なことだと思うから、その一因にスカパラの音楽がなれるといいですね」
取材・文/高木晋一郎(2008年3月)
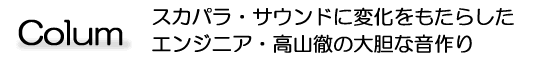
1989年のデビュー以来、インストゥルメンタルのスカを極めてきた東京スカパラダイスオーケストラ。ジャマイカ発祥のスカにアジア的なエキゾチシズムや東京らしい折衷感覚を加味し、“東京スカ”を育んできた。そして、2001年からは2度にわたる歌モノ3部作に挑戦。奥田民生や
ハナレグミ、
Charaといったヴォーカリストをフィーチャーすることで、インストゥルメンタルに忍ばせてきた滋味豊かな歌心を顕在化させた。
そして、2007年、彼らはスカに音楽の未来を託す。「銀河と迷路」や「世界地図」といった名曲をものにしているドラムの
茂木欣一のヴォーカル曲「女神の願い」やKEMURI解散後のファースト・ステップを刻んだ伊藤ふみおのヴォーカル曲「Pride Of Lions」といった強力フックも用意されている本作だが、最大の聴きどころは、
コーネリアスや
くるりを手掛け、時にリミックスに近い大胆な音作りを行なうことでも知られる日本のトップ・エンジニアの高山徹を起用したことで楽曲にもたらされた化学変化だろう。
冒頭の「Perfect Future」ではいきなりハード・ディスク上でのエディットやエフェクトが施され、ダブの手法でリズムを前面に押し出した「Punch'n Sway」やしっとり艶やかな音像を結んだ「Last Temptation」、はたまた、SEやエディットで曲のイメージを補強している「964スピードスター」や「Warrior Chant」、「A Song For Athletes」など、あくまでバンド・サウンドを基本として、音の配置や加工によって、曲の持つイメージが立体化させているのが本作の大きな特徴だ。10人編成の大所帯バンドである彼らだけに、そのサウンドに手を加えることは屋台骨を揺るがせるリスクをともなう危険行為と言えるが、淀みない作品を求めて変化の波に身を投じてきた歴史もまたスカパラなのである。ヒップホップやR&Bに触発されながら進化を遂げているダンスホール・レゲエが全盛のジャマイカにあっては過去の音楽と見なされているスカは、極東の島国でスカパラの導きによって、電気ウナギの夢を見ているのかもしれない。
文/小野田 雄
【東京スカパラダイスオーケストラ LIVE SCHEDULE】




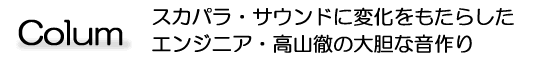

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。