「そうね。私と父と兄が中心になってやった企画よ」
――このアルバムは病気の子供たちへのチャリティのためにやったものだと聞いています。このアルバムを作る経緯を教えてもらえますか?
『Arts For Life: My Life Is Bold』
「“ARTS FOR LIFE”っていう組織があって、そこがやっているプロジェクトなの。私の故郷のノースカロライナが本拠地ね。重篤な病気で長期間入院している子供たちはなかなかアートに触れる機会がないから、詩とか音楽、その他のアートを教えるレッスンを子供たちに提供しようというプロジェクトなの。子供たちにとってはアートがヒーリングになるから。まずこのアルバムを作るにあたって、子供たちが描いた絵をジャケットにコラージュにして使うことにしたの。それだけじゃなくて、アルバムの中の歌詞も子供たちが自分の気持ちを表現して書いたものに私たちが曲を付けているわ。ちなみに収益はすべてARTS FOR LIFEに行くことになっているの」
――歌詞の中には病気の子供たちの本音がそのまま綴られているようなものもあり、かなり重いメッセージを受け取らなければならないものもあります。でも、全体的にそれをコンフォータブルなサウンドに乗せていますよね。このアルバムの音楽的なコンセプトを教えてもらえますか。
「コンフォータブルというのはその通りだと思う。軽やかでお茶目でちょっとふざけた詞もあるんだけど、かと思うと、すごくへヴィな内容の詞もあるから、聴いていて泣かずにはいられないようなものもあると思うの。たとえば、マイケルという子が書いた5曲目の〈Trapped Orca in an Aquarium(水槽に囚われたオルカ)〉はまさに子供たちの気持ちを表していると思う。海の生き物たちが水槽の中に囚われてしまって、外に出ていけないっていう内容で、水槽の前を人が通って、たまにガラスをとんとんと叩いたり、指さしたり、手を振って笑って、みんな通り過ぎてしまう様子を書いているの。病院の子たちはそういう思いを味わっていて、自分は水槽の中の生き物のようで、窓の外を見てもっと自由になりたいっていつも思っているという気持ちを書いているの。この話をもらったときに、父と一緒にもうひとりの企画者の家に行って初めに見せられたのがこの詞だったの。これを読んだから、既存曲を子供たちの前で演奏するだけではなくて、こういう素晴らしい詞に曲を付けて作品にしたらどうかってことになって、まず試しにこの曲をやってみたらとてもいいものが出来た。じゃあ、このやり方で他の曲もやってみようというきっかけになった詞と言っていいわね。聴いたときにすごく切ないような詞だけど、あまりへヴィにしたくないなって、たぶん、これを書いた本人もあまり深刻にしてほしくないって気持ちで書いたんじゃないかなって私は思ったから、その気持ちを大事にして作ったつもり。じつはその時は知らなかったんだけど、私がこの詞を初めて読んだ時にはもう彼はこの世の人ではなかったの。もし、そのことを事前に知っていたら、曲を書くことは私にとってはもっと大変だったかもしれないわね」
――ここではジャズ・ミュージシャンもたくさん参加して、ジャズっぽい曲もあるんですが、基本的には軽やかなフォーク寄りのサウンドの印象が強いです。
「軽やかさに関しては、マイケルの書いた歌詞でも、ナース・コールをがんがん鳴らしてナースに嫌がられるとか、じつはピザが好きとか、重い中にもユーモアのセンスが溢れている歌詞の魅力が音楽の軽やかさに繋がっているんじゃないかしら。ここでの私の役割は、NYの友達に声をかけてこのプロジェクトに興味を持ってもらうことだった。興味をもってくれたら、才能ある人やオープンな気持ちでやってもいいよって人に参加を呼びかけるってこともね。私がNYに行って、最初にやっていたのがジャズとかそういう音楽だったからNYの音楽仲間はジャズの人が多いの。だから、いろんな人が参加してくれたんだけどジャズの比率が高くなったのね。あとはノースカロライナの父と兄の知り合いのミュージシャンはブルーグラス系のミュージシャンが多いの。義理の兄のグリフ・マーティンはブルーグラスのミュージシャンだし、
ケイト・マクギャリー 、ケン・フラゼールもそうね。だから、ノースカロライナのブルーグラス系の人と、NYのジャズの友達と半半で作ったアルバムってところね」
テイラー・アイグスティ
「テイラーは大好きな親友の一人。繋がったきっかけはMy Spaceでテイラーが連絡をくれたの。そのころ、彼がフリー・エージェンシーというバンドをやっていて。グレッチェンもそこで歌ったことがあるし、そういえば、グレッチェンと初めて出会ったのもフリー・エージェンシーのセッションだったわ。
エリック・ハーランド 、ハリッシュ・ラグハヴァン、ジュリアン・ラージ、あとそのころはキーボードがもう一人いて、それが
ジェラルド・クレイトン だったわね。アルバムを作る前にテイラーが私に歌ってほしい曲をいくつか選んで見せてくれたんだけど、それがエリオット・スミスや
イモジェン・ヒープ や
ファイスト など私が好きでずっと聴いていた曲ばかりだったから、すぐにOKの返事をしたの」
――あのアルバムではあなたは歌詞も書いてますよね。
「フリー・エージェンシーで歌うことになって、あるときに電車の中で聴かされた曲にその場でパパッと歌詞をつけたのが、〈ミッドナイト・アフタヌーン〉なの。それを見たテイラーが気に入って、“そのまま使おうよ”ってことになったから、アルバムに収録されているの。〈マグノリア〉はロバート・フロストの詩にテイラーが曲をつける予定だったんだけど、最後の最後でフロスト側から詩の使用にNGが出てしまって、時間がなくて慌てて私が歌詞をつけて録り直したのが収録されているヴァージョンなんだけど、それも素晴らしいものになったのよね」
――次は現代音楽、エレクトロニカやアンビエントの作曲家アヤ・ニシナ Aya Nishina
「彼女がマンハッタン・スクール・オブ・ミュージックで作曲を勉強していた頃からの仲間だから、アヤとはかれこれ11年くらいの付き合いね。このアルバムでは彼女が〈ホワイト・フラワー〉を私が歌うために書いてくれたんだけど、それがすごく楽しかったの。アヤは私の声を重ねて重ねて、12くらいあるパートを何重にも重ねていって、あの曲を作ったんだけど、私はそういうやり方が好きなの。なぜなら、自分で曲を書くときもそうやって声を重ねて書いているし、デモを家でつくるときにも自分の声を重ねて作るから、やり方が似ていてやりやすかったのもあって、とてもエンジョイできたの。私は自分の声を二重に重ねたときのトーンが好きなんだけど、それがすごく活かせたレコーディングだと思うわ」
――このアルバムに「チエコ」という曲がありますよね。日本の詩集(※高村光太郎 「たしか、チエコという女性を主人公にした物語よね。本当はアヤに直接聞いてほしいわ(笑)。この曲の前半部分はミニマルに始まるんだけど、そこはアヤが水玉のアートを作る現代アート作家の草間彌生に触発されて作ったと言っていたわ。この曲もチエコが降る雪を眺めているようなところから始まるんだけど、声が雪のように降ってくるの。最終的にチエコは正気を失うのよね、たしか失恋か何かをきっかけに狂気の方へいってしまう。アヤは具体的なストーリーに基づいて曲を書いたって言ってたわ。チエコさんが正気を失って、気持ちの起伏が激しくなっていく感じが曲でもあらわれているはずよ」
VIDEO
――あなたの声が聞こえてきたとき、日本的な情景が浮かんだような気がしました。
「それは、たぶんアヤのヴィジョンによるところだと思う。レコーディング中も曲の細かなイメージをひとりずつ話して聞かせてくれたから、私たちは自分の声でどんなイメージを伝えればいいのかをきちんと形にすることができたんだと思う。あと、彼女は自分の音楽を自然とコネクトさせて表現したいという人なんだけど、それが成功しているのもあると思うわ」
――では、次はあなたが参加しているトラヴィス・サリヴァンによるビッグバンド、ビョーケストラ ビョーク Travis Sullivan's Bjorkestra
「ニュースクールの先生の一人がビョーケストラでサックスを吹いていたの。彼がライヴの案内のチラシを学校で撒いていたのをみて、ライヴに出かけたのがきっかけね。そのころの私はビョークの大ファンで、アルバムは全部持っているし全曲歌えますっていうくらいビョークが大好きだったの。ライヴに行ってみたらシンガーがいたので、私はこのバンドで絶対に歌いたいって思って、普通は自分から言うタイプじゃないんだけど、この時ばかりはすぐに先生のところに行って、“もし、アンダー・スタディ(見習い)が必要だったらやりたいし、歌詞も全部知っているからすぐにできます”って売り込んでおいたの。その半年後くらいに連絡があって、アンダー・スタディになって、それから2ヵ月後くらいに当時のシンガーが抜けて自分が歌えることになったの。ものすごく大変だったけど、ものすごく楽しい仕事の一つよ」
――このバンドはどこが大変なんですか?
「ヴォーカルの面でどうアプローチしたらいいのかってことかしら。私はファンだったのでビョークのヴァージョンに馴染み過ぎていて。マネになってはだめだし、自分らしい声で歌いたいんだけど、自分を出し過ぎるとビョークが持っていた純粋さみたいなものが失われてしまうの。しかも相手がビッグバンドなので、バンドの音が大きくて多彩な音が鳴っている中で、歌メロを自分の声で響かせないといけない。だから、自分なりに健全なやり方でもっとも美しいメロディを伝える歌い方を探すのには苦労したわ」
VIDEO
――ちなみにあなたから見たビョークの魅力ってどんなところにあると思いますか。
「とにかく素晴らしい。彼女が書くメロディもそうだし、独創的な声、音楽的な個性、オリジナルな歌詞。彼女は歌詞においても歌い方においても、すごく自由な人だと思う。私は彼女の音楽全体が持つあのエネルギーにやられたと思うし、その美しさにもやられたと思う」
――では最後に、ベッカ・スティーヴンス・バンド以外で今やろうとしている音楽について教えてもらえますか?
「ザ・ジャズ・ギャラリーのディレクター、リオ・サカイリがいろんな人に一定期間レジデンシーっていう形でライヴをやらせているんだけど、私にも声をかけてくれたの。そこで1時間、未発表の曲だけを演奏をするライヴをすることにしたの。そこでは自分のバンドにピアノのティモ・アンドレスを加えて、クワイアとして4人のシンガー、出来ればグレッチェンにも入ってもらって演奏しようと。なぜそれをやろうと思ったかというと、ギターなしで、自分が何も持たずに歌うことで、ストーリーを語ることに重きを置いた歌を軸にしてやってみたいと思ったから。そこでは曲ごとに異なるクイーン、女王の歴史を語っている曲をやろうかと考えてるの。クワイアを入れてやるのは、自分が曲を書くときにそういうふうに聞こえているから。声だけでいろんなパートがあって、ラインがあって、レイヤーになって……っていうようにね。それをそのままの形で出した曲を聴いてもらいたいなと思ったの」
取材・文 / 柳樂光隆(2015年1月)



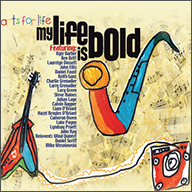




 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。