2013年、
『ピアノ・サウダージ』でメジャー・デビューして以来、最新作
『コバルト・ダンス』で早くもアルバム4作目。かたわらプロデュース作も発表するなど、ピアニストとしてだけに留まらない、精力的な活動を展開中のこの人、
今井亮太郎。が、ニュー・アルバムで何より印象的だったのが、どあたまに置かれた「青い瞳のアドリアーナ」に象徴されるキラキラしたポップ・フュージョン志向、それと並んで、シンプルな旋律に“ショーロ愛”をくるみ込んだ「色えんぴつ」のようなオリジナル曲が、ごく自然な物腰で収録されていることだった。
室内楽的な柔らかさと融通無碍なグルーヴ感、ふたつをあわせ持つ点において、ブラジル音楽の“粋(すい)”であり土台とも言えるショーロに、こんなふうに憧れてやまない日本の新世代(1979年生まれ)がいる。一体どういう道程をたどってこういうことになったのか、まずは知りたくなってくる。自身の音楽同様、気取りのない口調で、のびのびと語ってくれた。
――「色えんぴつ」を聴いて、今井さん、本当にショーロがお好きなんだなあと。反面、びっくりもしたんです。
「僕自身、もともとショーロという音楽ジャンルを知ってたわけじゃないんです。ただ、20代頭に初めてブラジルに行ったとき紹介してもらったのが、たまたま
エポカ・ヂ・オウロの人たちだった」
――ショーロの名門グループじゃないですか。初のブラジル滞在で、いきなりエポカ・ヂ・オウロと出会うって、すごくないですか。
「ただ、ショーロという名前は知らなくても、それ以前から聴き漁っていたブラジル音楽のコンピレーションに、
ピシンギーニャや
ジャコー・ド・バンドリンの名曲と並んで、(エポカ・ヂ・オウロの長老メンバーである)ジョルジーニョ・ド・パンデイロの演奏も入っていた。後付けですけど、あれがショーロというものかと。だから最初は言い出せなかったですよ、自分がブラジリアン・ピアノをやってますとは(笑)。ジョルジーニョと彼の息子であるセウシーニョ・ダ・シルヴァ、大物二人と先に仲良くなっちゃったものだから」
――それにしても、なぜブラジル音楽だったんですか。
「好きになったおおもとのきっかけは、子どもの頃、親父がクリスマス・プレゼントにくれた
渡辺貞夫さんの
『エリス』のCDだったんですけど、楽器に関してはじつは僕、ピアノに専念するようになる前は、打楽器をやってたんです」
――えっ(驚)。たとえば。
「それこそコンガとか(笑)。スルド(サンバ特有の大太鼓)も叩いていましたけど、当初はキューバ音楽のプロになりたかった。画像の悪い教則ヴィデオを海外から取り寄せて真似たりしたんですけど、手順もわかるしリズムもわかるんだけど、何かが決定的にわからなかったんですよ。要はキューバ音楽ならではのグルーヴ、ノリがつかめなかったんだなあと、今となったら理解できるんだけど」
――まだネットやYouTubeがなかった時代だから。
「だから大学に入ってブラジル音楽に専念するようになったとき、今度こそあきらめずに、ブラジル人と対等にできるようにグルーヴをつかもうと思った。逆に言うと、ブラジル人からすれば当たり前過ぎて、言葉では教えてもらえない“ツボ”を、現地に行ってつかんで来ようと。で、僕がはたち過ぎから参加させてもらっていた
シャカラのリーダーだった
加々美 淳さん、彼が親しくしていて紹介してくれたのが、ジョルジーニョとセウシーニョの親子だったんです」
――グルーヴって、じつはその土地その土地の言語と、深く結びついているような気がするんですが。

今井亮太郎
「その通りですね」
――そう実感したのは、ブラジル滞在のいつ頃から……。
「初めて行ったとき、基本ジョルジーニョたちにくっついていたので、連れて行ってくれるライヴもすごいものばかりだったんです。で、向こうの人たちは、それこそダンスしながらライヴを観てる。それを僕はじ〜っと観察して(笑)。最初2、3ヵ月滞在してたのかな。月極めで借りてたアパートに帰ったら、ピアノは持って行けないから鍵盤ハーモニカを、どこで乗ってたのかを感じながら吹いてみて。で、次行ったときジョルジーニョたちと演奏すると、やっぱり合わないんです(笑)。なんとか体得できた、と思えたのは、数えて5年目、それ以上かな。イメージ・トレーニングもしましたよ。壁に無限マークの“∞”を貼って(笑)。目で追いながら演奏すると、おのずと身体もそう動くから」
――ブラジルのポルトガル語自体、非常に“音楽的”であるとも思うんですが。
「ブラジル音楽ってシンコペートするじゃないですか。当のブラジル人は全然意識してないですけど、あれってポルトガル語のアクセントの直前に打点が来るんです。“amor”(愛)だったら“mo”の音を“喰う”かっこうで打っていく。“felicidade”(幸せ)だったら“da”の前とかね。言葉をしゃべる感覚が、結果、シンコペーションへとつながっている。滞在を重ねるたびに、少しずつわかってきたことなんだけど、どんなキメが来ても身体を壊さず対応できるようになるまでには、相当年数がかかった気はします」
――そういった修練が、「色えんぴつ」には反映されているんですね。
「母が亡くなった、その当日に書いていた曲なんですよ。亡くなるまでの2ヵ月ほど、ず〜っと絵手紙を描いてくれてたんだけど、前の日病院で見せてくれたのも、生命力あふれる絵だった。家に帰って、素敵な絵だったなと思い返すうちに、ショーロみたいな旋律がば〜っと浮かんできたんです。日付が変わる頃書き留めて、亡くなったのが同じ日の夕方だった。
この曲はジョルジーニョもセウシーニョも喜んでくれて、去年の3月に、彼らがブラジル国営ラジオで持ってる番組で演奏してくれたんです。今回収録したのは、それとは別のテイクですけど」
――この曲を聴くと、グルーヴを鳴らすことすなわち楽器の数ではないということが、よくわかる気がします。
「裏を返せば、ブラジルにいればすべての楽器が当たり前に存在している。あえてグルーヴを奏でようとする必要がないんです。日本人がブラジルで向こうの人たちとやると、できた気がしちゃうのもそのせいで、本人はできてなくても周りができてるから、その中にどっぷり浸かっているだけでできた気がしちゃう。でも、日本ではギターもいい人はごく少数だし、カヴァキーニョもなければバンデイロもいない、バンドリンもタンボリンも、ないないづくしだった(笑)。
そういう意味で僕のピアノは、たとえ他の楽器がなかったとしても、スルドの音が聞こえてくるし、ギターのカッティングも聞こえてくる。ちゃんとメロディを奏でたうえでそう聞こえるには、ピアノ1台でどういうふうに作ればいいのか、試行錯誤を重ねてきたものなんです。その意味では、ブラジルの人から見ると特殊なタイプかもしれない」
――ブラジル音楽のアンサンブルを念頭に置きながら、それをピアノに落とし込んでいくわけですね。
「まさにそうで、たくさんの人と演奏する場合は、そこから引き出していけばいい。ようやく最近納得のいくメンバーが揃ってきて、大所帯で演奏できるようになってきたんですけど、びっくりするくらいラクですよ。俺、こんなになんにもしないでいいんだ、みたいな(笑)」
――「色えんぴつ」とは対照的に華やかなのが、オープニング曲でもある「青い瞳のアドリアーナ」。アドリアーナちゃんという知り合いが実際にいたんですか?
「残念ながら、フィクションです(笑)。もとはといえば、セウシーニョが去年ひとりで来日したときに浮かんだ曲なんですよね。彼が一人旅だったせいかもしれないけど、青い海と空がある白壁の街。そこでふと立ち寄った音楽が流れるバーで、ひとりの女性に出会って一夜限りの熱い恋に落ちた……みたいな設定が浮かんできた。ただ舞台はリオじゃないよな、と思ったとき、アドリア海なら日本人にもイメージしやすいなと。一応チェックはしたんです。たまにブラジル人からすると、妙な意味合いのある女性名があるから(笑)。で、調べてみたら、アドリアーナ・リマという、ブラジル一のスーパー・モデルがいたので、ちょうどいいかなって。実在のアドリアーナちゃんは、こんなきれいな人、口説けるわけがないっていうくらい、きれいな女性なんですけど」
――一種、短編映画的なフィクションに基づいた曲なんですね。
「先に出来たのはメロディですけど、イメージとしてはそんな感じだった。今回のアルバムが始まるきっかけになった曲でもあるので、“コバルト・ブルー”を全体のイメージ・カラーにしてみたんです」
――今井さんのピアノを聴いていると、「アドリアーナ〜」のようなポップな曲だと、ごくメロディックに、華やかに弾いていて、一方、たとえばアントニオ・カルロス・ジョビンの「ルック・トゥ・ザ・スカイ」や「Wave」では、むしろ訥々と弾いているように聞こえる。「色えんぴつ」もそうですよね。それは意識的なものなのか。あるいはジョビンの作家性によるものなのか……。 「ぶっちゃけそれは両方あります。後者でいうのであれば、以前ジョルジーニョが僕に言ってくれて、以来すごく大事にしている言葉に、“自分の演奏をするな”というのがあるんです。“曲の言葉を聞け。どういう演奏をしてほしいか、曲が必ず言ってくれるから”。本当にそうだと思うんですよね。
だから今回ジョビンの〈Wave〉をやったときも、僕の思いをぶつけるんじゃなくて、〈Wave〉がどう演奏してほしいかを聞く。自分の曲であっても、〈アドリアーナ〉がどう演奏してほしいかを聞くように、心掛けてはいるんです。自然にそういうふうになるっていうか。
ジョビンの曲って、ジョビンの人となりを感じさせますよね。彼もマランドロ、“粋な遊び人”ですけど、どちらかと言えば憂いを帯びたマランドロだと思うんです。おそらくですけど、精神的にけっして明るい人ではなかったんじゃないかな。
僕自身の曲をジョビンの作品と比べるのはおこがましいですけど、客観的に見て、自分は感情がわっと表に出る瞬間があるなと。それは止めないほうが、自分らしくなる気はしています。ブラジル音楽以前に、僕自身の色、今井亮太郎の色彩感についていえば、中間がないタイプのピアニストだと思うんですよ。華やかに、ごきげんに奏でる自分と、内側に入っていって静かに陶酔している、その両極端。昔は真ん中がないことが悩みでもあったけど、今はそのふたつが強いのは、むしろ武器だという気がしています。今回のアルバムでは、そこがストレートに出ているのかもしれないですね」
――中森明菜さんの大ヒットをカヴァーした「ミ・アモーレ」もそうですけど、今井さんは必要とあらばベタな表現を選ぶことも、けっして恐れてはいないですよね。スカしてないっていうかさ(笑)。 「かっこつけてないってことですか? ははは。そうですね(笑)。僕のキャラクターとか人間そのものが、何か色をつけてかっこよく見せたりするのが得意じゃないと思うんで。せつない時はせつなく、楽しい時は楽しく、ば〜んとシンプルに行きたいんです。リオで経験したことで、これって僕の音楽のイメージそのものだなと思ったのが、晴れた日に外に出たら、いきなり雲が湧いてスコールが降ってきてびしょ濡れになった。けど、そのびしょびしょが気持ちいい。僕の音楽に感覚が似てるなあ、と思って。自分の音楽でも、そういう感じになりたい、と思ったんですよね」
今井亮太郎4thアルバム『コバルト・ダンス』の発売を記念し、直筆サインが入ったステッカーをCDジャーナル読者6名様にプレゼント!
プレゼント・コーナーより奮ってご応募ください。
応募締切: 2015年6月30日(火)まで 2015年6月22日(月)
神奈川 横浜 赤レンガ倉庫 MOTION BLUE YOKOHAMA開場 18:00 / 開演 19:30 & 21:00
前売 5,000円(税込 / 別途飲食代 / 自由席)[メンバー]
今井亮太郎(p) / 赤羽泉美(fl) / Gustavo Anacleto(sax,fl) / 外園健彦(g) / 大森輝作(b) / Alexandre Ozaki(ds) / Francis Silva(per) ![今井亮太郎 - コバルト・ダンス〜COBALT Dance〜 [CD] 今井亮太郎 - コバルト・ダンス〜COBALT Dance〜 [CD]](/image/jacket/large/411503/4115031170.jpg)


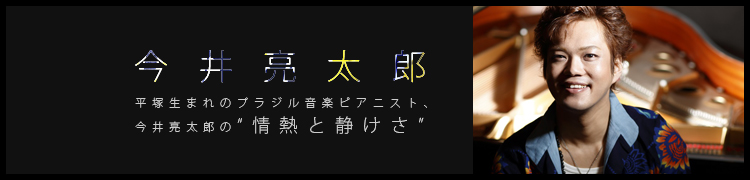

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。