
yes, mama ok?
『GREATEST HITS』
yes, mama ok?というユニットは、昔からとてもとらえどころのない、言葉にするのも大変難儀な、CD棚の置き場に常に迷ってしまうような存在である。渋谷系が商業ビジネス化してきた90年代半ばに登場したものの、一筋縄ではいかないポップ・ストレンジな曲者としてシーンの片隅でニヤニヤしながらアート・クーデターを起こしていたような彼ら。リーダーの
金剛地武志は今や
俳優としても大活躍、
高橋 晃も
デザイナーとして第一線で仕事をしているが、当時の彼らは“yes”とも“ok”とも言い切れない飄々とした風合いが魅力であり、武器でもあった。現在、主要メンバー2人が他フィールドで活動しているため、近年、活動そのものは不定期になっているが、しかしながら、彼らへの評価は近年ジワジワと高まり、日本コロムビア時代の全曲を収めた
ボックス・セットやオリジナル・アルバム『CEO』(2000年)の
デラックス・エディションがリリースされるや話題にのぼることも増えてきていた。
そんなyes, mama ok?を、優れたポップ・バンドとして敬愛するのが、
スカートの澤部 渡だ。中学の頃からyes, mama ok?のライヴに通い、いつしかスタッフとなり、そして今やライヴにおけるサポート・メンバーともなり……という変遷は、そのままyes, mama ok?というユニットへの深い愛情と忠誠心の現れとみることもできるだろう。yes, mama ok?のインディ・デビュー20周年を記念してリリースされたベスト・アルバム
『GREATEST HITS』は、その澤部 渡の監修・選曲によるもの。yes, mama ok?を骨の髄まで知り尽くした男の愛が目一杯詰まった“大ファインプレー仕事”と言っていいだろう。そこで、金剛地と澤部による“師弟対談”を企画。2人の出会い、共通する意識、それぞれのポップ・ミュージック観などを語ってもらった。
――金剛地さんは今年2015年がyes, mama ok?の20周年というのは気づいていたのですか?
金剛地武志(以下K) 「来年何月何日がイエママ20周年なんですよ〜というのは澤部くんから聞いていて(笑)。あ、そうなんだ、みたいな。だから、そこで何か特別なことをやるとかは全く考えてなかったですね。忘れていたというのは正直なところです。でも、外堀を埋められて(笑)今回のこのベストを出すことが決まった後は、ライヴもやろうかってことまでスッと決まりましたね。それならワンマンをやるのが美しいでしょう、と。で、ワンマンに向けて盛り上げようということで、今年に入ってからはライヴの回数を増やしましたね。ま、これを言っちゃうと恥ずかしいんですけど、フェスに出たい、というのがありまして(笑)」
澤部 渡(以下S) 「ははははははは!」
K 「僕らがメジャーに行った後から〈フジロック〉とかが始まったでしょ。僕らは90年代に活動していたけどそもそも渋谷系とかとも無縁だったし、どこにも属している意識がなくて。なんかそういうのに今はむしろ出たいんですよね。そういう気持ちもあって、じゃあ、ベスト出そうか、みたいな(笑)。実際、先日やったワンマン(2015年4月21日 東京・渋谷 Star lounge)、170人くらい入ったんですよ」
S 「あ、あの日ってそんなに入ったんだ!」
K 「僕の覚えている限りでは、コロムビア時代に渋谷クアトロでライヴをやったんですけど、その時に100人超えたかな、という程度で……あの時はしかもワンマンじゃなくて、
LD&Kのイベントだったんで……だから、たぶん今回のワンマンが過去最高の動員ですね(笑)」
S 「それって
『Q&A 65000』が出た時ですよね? 僕はその頃まだリアル・タイムで聴くには間に合ってなくて、
『CEO』で気になり出して、ちゃんと聴き始めたのって2001、2年だったんですよ」
K 「2000年の段階で澤部くんいくつ?」
S 「12とかです。でも、もう音楽はすっかり聴いていて、
MXテレビの音楽番組を熱心に聴いていましたね。そこでyes, mama ok?と
GEMINI(金剛地らがプロデュースした双子女子ユニット)とかを知って気になってきて。
ゆずとか
椎名林檎とかを聴きつつも、yes, mama ok?とか
シンバルズとかも聴いていたんで自分でもまだよくわかってなかったのかもしれないですね。でも、yes, mama ok?は、単純にそれまで聴いたことがない音楽だったというのが大きかったですね。僕はその頃はもう
YMOとか
RCサクセションとかも聴いていたんですけど、そういうのともまた違う新しいものと感じたんじゃないかなあ。〈Sun Oil〉のPVとかのちょっとしたユーモアとかもすごく気になったんだと思いますね。その頃の感覚ってもうあまり覚えてないですけど、今でも好きっていうことは、そういうことだったんだろうなあ」
K 「僕が澤部くんを知ったのって、彼が14歳くらいの時だったかな、僕らのライヴを見に来てくれていて。夜遅いイベントとかだとお母さんと一緒にね(笑)。その後、それから1、2年くらいして、06年のことですけど、yes, mama ok?の
トリビュート・アルバムが出た時には、もう澤部くんはスタッフとして入り込んでいたんです(笑)。で、そのままイベンターとかみたいになっていくのかな〜と思ってて、大学受験とかの時にも“絶対に音大なんて行くなよ、美大にしろよ”って言ってたのに、結局音大に行っちゃってね(笑)」
S 「いやあ、本当は美大に行くつもりで勉強もしていたんですよ。でもなんかしっくりこなくて。で、
(昭和)音大に行ったらもう最初の2年は苦行でしかなくて(笑)。つらくて仕方なかったですね。こりゃあ美大に行っとくんだったな〜って思いましたよ」
K 「でも、僕もその後、まさか澤部くんが自分で曲を作っているとは思ってなくて。卒業する前くらいに、こんなの作ってるですって感じで音源を聴かせてもらったんですよ。それが今ライヴでもサポートしてもらっているんだから……ほんとにわからないですよね(笑)」
――yes, mama ok?と澤部くんのスカートに共通しているのは、まず1曲が短いということですよね。3分程度の中にポップスの醍醐味が凝縮されている。
S 「そうそう、もうそこは本当に影響されましたね」
K 「単純に昔のポップスは3分以内に収まっていましたからね。まあ、そこには当時のレコードの制約上の理由があった、ということは後からもちろん知るわけですが、それよりも3分以内の中で完結できるその定型が美しいと思って。俳句とかの形式が美しい、と思えるのと同じで」
S 「様式美みたいな?」
K 「そうそう。え、これで終わっちゃうの?って短い曲がズルズルとたくさん入っているのって楽しいな!っていうね。あと、単純に曲を作る時に長くするのが大変だ、というのもあるんですけどね(笑)。でも、まあ、いいポップスはリピートさせてナンボだ!という意識があるのは間違いないですよ」
――金剛地さんは音楽自体はもう中学くらいからやっていたんですよね?
K 「そうですね。漠然とずっと音楽をやっていけたらいいなと思ったのは中学生……いや小学生くらいの頃だったかもしれないです。もちろん、これでやっていけるぞ!って確信持てたのはコロムビアに移籍した頃でしたけれど。でも、昔からポップ・ミュージックに対する思いは変わらないですね。小学校の頃から曲作りのまねごとみたいなことをやっていたんですよ。何かにソックリな曲ばかりでしたけどね。で、中学の時に姉の影響でリズム・マシーンを買って。(
ローランド)TR-606だったかな、最初に買ったのは。そこから姉が持っているシンセサイザーと両方使ってピンポン録音で多重録音するというね。で、実際に自分でもっとちゃんと音を作り始めたのは高校になってから。曲を作って録音して、高校2年の時にカセットにして学校内で販売したんですよ、500円とか300円とかで。そしたら100本以上売れたんです」
S 「ええーっ!」
K 「学校以外のところにも波及していって。僕、高校は和光だったんですけど、“和光の金剛地くんってこんなの作って出してるんだよ”って。で、大学に入ってから、当時のカセットを持ってる人がいてね。夏の合宿みたいなところで同じ部屋になったヤツが、“同じ部屋になる金剛地くんってきっとこれ作った人だよ”って予備校時代の友達にカセットを渡されてずっと聴いていたっていうの(笑)。面白いでしょう。そいつがのちに一緒にyes, mama ok?をやる高橋 晃くん。その頃から一緒なんですよ」
S 「僕もその頃の音源、いくつか聴いたことがありますよ」
K 「家でホームパーティとかをやって、俺祭りになったらかけたりしますね(笑)。照れながらもかけちゃう」
S 「これが出来がいいんですよ!」
K 「こんな高校生がいたら天才!って思っちゃうよね(笑)。ま、宅録ですよ。まだエレキ・ギターを持っていなかったから、フォーク・ギターとピアノとシンセサイザーとリズム・マシーン、シーケンサーでね。まあ、つまりはその頃から音楽を作ることが当たり前になっていたってことなんですよ。こういうことをやっていけたら嬉しいっていう。LD&Kと絡み始めて、でもまだyes, mama ok?をやる前に、僕、
Baby Allstarsという名義でLD&Kから子供向けの曲を出しているんですけど、あれをやっていた頃くらいから、これがプロだ、という自覚がもうありましたね」
――プロとしてお金をもらって音楽を作る、発表する自覚ってすごく大切ですよね。DIYスピリットとか90年代のオルタナ・ブームってそういう自覚とは少し距離があった気がするんですよ。でも、金剛地さんは最初からそこに根ざした意識があったのですね。
K 「そうですね。実は高校の一級下に
小山田圭吾くんがいたんですけど、高校の頃の文化祭の打ち上げとかで、小山田くんに“お前、プロになりたいの?”とかって聞いてみたことがあるんです。彼は“いやあ、なれれば……”みたいに答えていたですけど、“俺は絶対になりたいよ!”って散々言ってて(笑)。でも、その数年後に彼は
フリッパーズ・ギターでバーン!といっちゃって。悔しい羨ましい、あんなこと言ってた俺恥ずかしい、みたいな(笑)。小山田くんたちのすごかったのは、自分たちの好きなことだけをやって認められて伝説になっちゃった、というところでね。好きなところは曲げちゃいけないんだな、というのは彼らを見てて改めて思っていましたね。小山田くん、一個下の学年では一番ギターが上手かったんですよ。もちろん当時はネオアコのコピー・バンドとかやってましたけど、まさか自分で歌うなんて思ってもいなかったですね。でも、デビューした時にちゃんと聴いて、“うわあ、いいなあ”って純粋に思いました。羨ましかったです」
S 「ああ、でも、なんかわかるっていうか、僕も小さい頃から漠然と“プロになるんだ!”って思っていたんですよね。“プロになれたらいいな”っていうか。どういうことをやってプロになるのか、ということを考えてたわけじゃなくて、これだけ音楽が好きだったら何かしらのカタチでプロになれるだろう、みたいな感じで(笑)。で、少なくとも今に至ってる、というか」
K 「プロっていうと、楽曲提供とかプロデュースとかも仕事の一つだよね。僕もこれからもそういう話があればやっていきたいし、これまでもGEMINIとかを手がけたりしてきたわけですけど、やっぱりシンガー・ソングライター……というか、自分で作ってそれを歌うというスタイルが一番説得力があるのかなって思うんだよね。それは澤部くんも一緒だと思うけど。誰かの人気とか、可愛い女の子の美貌に頼らないというか」
――yes, mama ok?も最初はシンガー・ソングライターとしてのスタンスでいきたかったのですか?
K 「いや、当時はまだ僕も一歩引いていたんだと思いますね。例えば
小西(康陽)さん的なポジションというか、バンド内プロデューサーみたいなのに憧れていたのかもしれない。まあ、最初から僕自身半分は歌っていたし、演奏もしていたんだけども、でも、やっぱり仲澤真萠ちゃんという女性ヴォーカルがいたからメジャーのコロムビアに移籍もできたんだろうなと思ったりしますね」
――そもそも女性シンガーを立てる、というアイデアはどこから来たのですか?
K 「僕が好きな曲に
バグルスの〈ラジオスターの悲劇〉がありまして。あれにずっとヤられちゃってたっていうのがまずあって、そこへきて60年代のポップスが好きというのもあって、あの感じをやりたかったんですね。アメリカ60年代的な女の子、という漠然としたイメージです。キラッキラの女の子の声が入ったポップスですね。あと、
高橋幸宏さんの『音楽殺人』に入っている〈BLUE COLOUR WORKER〉とかね。
サンディーさんがヴォーカルで参加している曲」
S 「ああ!」
K 「ああいう雰囲気が好きなんですよね。なので、自然と女の子を入れるといのがあったんです。自分で曲は作るですけどね。でも、例えばコロムビアからメジャー・デビューする際に、“裏方に徹してください”みたいな捉えられ方もあったりして、やっぱり俺ちゃんと前に立たないといけないなって思うに至って、曲の中で女性パートがどんどん減っていくというね(笑)。で、彼女もモティヴェイションを保てなくてバンドを辞めていく、みたいな(笑)。そういう意味では、渋谷系とは関係のないところにいて、属してはいなかったですけど、やっぱり聴いていたし影響も受けていたんでしょうね。そもそも80年代のニューウェイヴは好きでしたからね。
ピチカート・ファイヴはその流れで聴いても自然でした」
S 「そうかあ……。僕も自分のバンドで自分で曲作って歌って、プロデュースもするようなポジションですけど、僕はいまだに一歩引いているようなところがあるんですよね。自分のことを客観的に見過ぎて、これはやめておいた方がいい、みたいなストッパーを自分でかけちゃってるところがあるんですよ……って、本当の悩み相談っぽくなってきちゃったけど(笑)」
K 「それは、でも、あるよね。これやっちゃ恥ずかしい、みたいなね」
S 「そうそう。で、そういうハードルみたいなのがいくつもあって。いくら売れたくても僕はこれ無理!できないな〜って思ったりするんですよね」
K 「わかるわかる。これやったらJポップっぽくなっちゃうしな〜みたいなね。そういうの、僕、いまだにあるよ。新曲作ってスタジオで合わせたりする時……澤部くんは今もうサポートで一緒にやってくれてるからわかると思うけど、僕、言うもんね、“これJポップっぽくて恥ずかしいな〜”とかって(笑)」
S 「よく言いますよね〜」
K 「僕の場合、一緒にやってる高橋 晃くんが“これ、カッコいいって思ってくれるだろうか?”みたいなのが一つ基準になったりするんですよ。“ダサ!”って思われたら恥ずかしい、とか」
S 「羨ましい!」
K 「実際に、高橋 晃が何かそれを聴いてジャッジすることってないんですよ(笑)。あとは、当時、レコーディングの際のエンジニアの方の判断とか意見もすごく参考にしましたね。でも、澤部くんみたいに1人だったら悩むんだろうなって思いますね。もちろん当時、僕も澤部くんみたいに1人で悩んだりしていたんですよ。女の子ヴォーカルだし、これでギター・ポップみたいな方向に行ったら、今更恥ずかしい、カッコ悪いって思っていて。おまけに、例えば1曲ボサ・ノヴァみたいな曲を作ったら、今度はその対極にあるような曲を作ってしまう傾向が自分にあった。反対のベクトルに走ってバランスをとりたいって意識が常にあった。要はあまのじゃくってことなんです。一個のモノとして見られたくない、というか。それがバンドの方向性を見えづらくしてたのは確かにあったと思うんですよ。だって、ブルーズならブルーズに特化したバンドの方が絶対にレコード会社としても売りやすいと思いますもん(笑)。聴く方も理解しやすいし、僕自身、聴くのはそういうひとつの方向に向かってるものばかり。チャラチャラと色んなことをやってるバンドとかって聴かないですもん(笑)。なのに、どうしても自分がやるとなると、あれも、これも……ってことになっちゃうし、それがカタチになるととても嬉しかったりする。“ああ、こんな曲できた!ジャズっぽいのができた!”みたいな手応えが楽しくてやっているようなところがありましたね。結果として、誰とも仲間じゃないな、というポジションになっちゃったんです。でも、それで良かったと思いますね」
S 「でも、それが痛快だったんですよね、yes, mama ok?って。めちゃめちゃふざけた曲も入っているし、めちゃくちゃいい曲も入ってるし、静かな曲のあとにうるさい曲もある、みたいな、それが痛快だった。そういうバンドって他にあまりいなかったんですよ、その当時僕の知る限りでは。で、これは取っ替えのきかない存在だって。こういうことをやれる人は信頼できるっていうか。僕はそう感じていましたね」
――当時、こんな引き出しもあるよ、こんな引き出しもあるよ、という感じで次々と手の内を見せていく快感もあったのですか?
K 「それはありましたね。俺、こんなこともできるんだぜ、こんなのもやれるんだぜってのを他人に見せたいって気持ちありますね。去年、高橋くんがデザインした
表参道ヒルズのクリスマスツリーの音楽を僕作曲したんですけど、それは完全なクラシックというか、ウィンナ・ワルツだったんです。そういうのもできるんだぜ!みたいなね(笑)。そういう意味では、宅録で音楽作ってた10代の頃と変わらないですね。音楽理論とかがわからなのも相俟って、いまだに曲を作って完成させるのはチャレンジですしね」
S 「僕もそうやって“こういうタイプの曲を作ろう”とかって自分で自分に発注したりするんですけど、出来上がったものはどうしてもそこから少しズレちゃうんですよね」
K 「そういうもんじゃないの(笑)?」
S 「つきぬけたポップスを作ろうってやってできた曲がすごく暗かったり(笑)」
K 「それがいいんじゃないの? 目的地が明確であればあるほどズレた時にそれがオリジナルになっていく。だいたい、曲を作る時にいきなり自分の中から湧いてきました、なんてこと、あるわけないじゃん。そんなこと言うヤツ信用できないよ(笑)。こんな曲を作りたいなあ!みたいな憧れからスタートするわけじゃないですか。そこから離れたり、近づいたりしながら……。僕自身も当時、新しいものが出たらどんどん聴いて取り入れたり刺激されたりしてましたしね」
S 「なるほどね〜」
K 「ただ、これが最先端です!というようなことだけは死んでもできない、やりたくない、というのはあったから、それでちょっとわかりにくい、外に伝わりにくかったのかもしれない。僕なんかは美大で現代アートとかが好きで勉強したりしていたから、見せ方とかにもこだわりはあるんです。僕はギルバート&ジョージとかジェネラル・アイディアとかに憧れてたので、高橋くんとはそういう雰囲気で……みたいな話はしていましたね。例えば、ジェネラル・アイディアみたいな雰囲気を、
ゼイ・マイト・ビー・ジャイアンツは持っている、とかね。そのヴィジュアル・イメージは持っていましたね。ただ、それがリスナーに訴求力があるのかどうかはわからない、ということだったんでしょうね(笑)」
S 「でも、僕は歌詞とかもすごく好きで、〈二枚舌のムニエル〉って曲、ボサ・ノヴァの洒落た曲なんですけど、急に“アパートの階段”とかって言葉が出てくるんですよ。日本的なイメージのアパートの鉄の階段がボサ・ノヴァ調の曲の中で、でも、メロディにはちゃんと乗っている。色んなパーカッションが入っててサンバになったりするんだけど、“アパートの階段”か!と。それによって絶対的なお洒落なものから一歩ズレたものになるんですよね。それがすごく見事というか、なんてカッコいいんだ!って思いましたね、当時。単純にお洒落なものにするのは意外と簡単なものだったりするんですよ。ある意味定型文みたいなものだから。でも、そこに何らかの違和感を挿入することによって頭の中から離れないものになるというか……」
――一歩ズレた洒脱さ、ですね。
K 「そこはそうしようと結構考えていて。何かハズすようなフックを作るというか」
――何かに対するアンチテーゼですね。
――ただ、2分、3分のポップスというのもフォルムとしては王道ですよね。
K 「そうなんですよね。だから、王道へのアプローチの仕方なのかもしれない。あるいは、時間が経過したら、自分の中にとりこめるようなものになるっていうことなのかもしれない。だって、
バカラックや
マンシーニとか大好きですからね。王道中の王道じゃないですか(笑)。あのくらい離れていれば逆にとりこめちゃうのかもしれない」
――オルタナティヴな感覚がある、ということなのかもしれないですね。
S 「ああ、
コール・ポーターもヘンリー・マンシーニもある種のオルタナティヴって気がしますからね。ロックとかの目からすると」
K 「だからね、“巨人、大鵬、卵焼き”っていうのがもう全然わからない。そんなのを表明することに何の意味があるのかって(笑)。そういう意味でも、普通の誰でも使うような言葉で曲にしちゃったら意味がないって思ったりするんですよね。僕は基本的にソングライティングって曲が先なんですけど、最後に曲にふさわしい言葉を選ぶんです。簡単なカタチで曲にしてメロディを歌っちゃうのはできるんですけど、そんなので完成させたら曲に申し訳ない。そういう捻くれた思いで歌詞も書いていますね」
S 「すっごくよくわかります」
K 「澤部くんの曲もそうだもんね〜」
S 「(笑)自分でも伝わってないと思います」
K 「すごく凝ってる、ちゃんと選んでるなっていうのがよくわかるよね」
S 「ありがとうございます!」
K 「悩んで作ってるな〜っていうのが伝わってくる。それって曲に対する誠意とかだよね」
S 「特別なものでありたい、という気持ちが強いんですよ。曲が自分にとっての特別なものでもありたいし、誰かにとっての特別なものでもありたいし」
K 「歌詞に関していうと、僕は好きな文学作品から影響を受けたりしたんです。でも、フリッパーズ・ギターがああいう曲を書いて、しかもそれが日本語になった時に、あれは特別な日本語って感じがしたし、みんな、やっぱり特別な日本語で歌詞を書こうって思ったもんなあ。あと、僕は横浜出身なんですけども、いわゆる横浜のど真ん中ではないんです。父親の実家ももともと東京の大田区の大鳥居ってところで東京23区の南の端。なんか、そういう東京プロパーなのに端っこ出身みたいなのが歌詞に出ているかもしれないですね(笑)」
S 「あ、それすごくよくわかる!僕は板橋の高島平なんですけど、やっぱり23区といってももうすぐそこは埼玉ってところ。やっぱり東京の南の端出身の
鈴木慶一さんの
ムーンライダーズとかに共感できるのもそういうのがあるかもしれない。都市出身生活者の性みたいな(笑)」
K 「
キリンジの2人も埼玉出身なんだよね。東京で生活してるのに、でも、家は遠い、みたいな(笑)。なんかそういうところで紐づけられるかもしれないね。今までどこにも属していなかったから、それはちょっと嬉しいかも(笑)」
取材・文 / 岡村詩野(2015年4月)
撮影 / 久保田千史

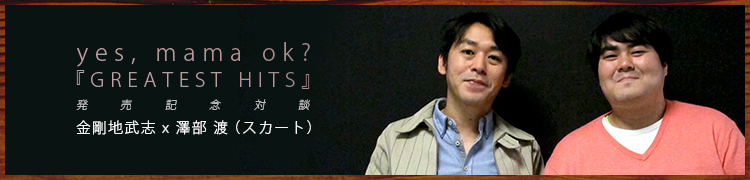







 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。