自在な歌声ひとすじ、これにサックスとチェンバロのプレイヤーがひとりずつ。その3人とも、ソングライター=作曲家としての顔も持っている。
ネーモー・コンチェルタートはそういう、ちょっと説明しにくいユニットだ。
チェンバロ(ハープシコード)はピアノが開発・普及されるより前、弦をはじく仕組みで作られていた鍵盤楽器。今から300〜400年前、バッハ以前の時代に広く使われていた昔の楽器だ。かたやサックスはピアノより遅れること100年ほど後に誕生、特許申請が通ってから160年そこそこの新しい楽器だし、クラシックでも使うけれど、どちらかといえば“ジャズ以後の楽器”というイメージが強いかもしれない。
そんな“ねじれ”の関係にある二つの楽器が、不思議な説得力で聴き手を釣り込んでしまう日本語をくりだす歌声とひとつになって、詩人・
谷川俊太郎の歌を彩ってゆく。
3人それぞれ、選んでくる詩も、それにつける曲も違う。
そんな3人でどんな絶妙のバランスが生まれるのか、言葉でどんなに説明しても伝わらないと思うけれど、聴けば一発でわかる。そんな一筋縄ではいかない音楽が詰まったCDを、その詩句や音楽と同じくらい味わい深い絵で隅々まで彩った本につけて、いつのまにかCDブックにしていたアルテスパブリッシングという出版社も、やはり一筋縄ではいかない。
……でも“聴けば一発でわかる”というのは、音楽記事としてはサッカーのハンドくらいアウトな表現。それでは始まらないので、どうにか彼らの魅力を伝える言葉をみつけようと、お話を伺ってみた。
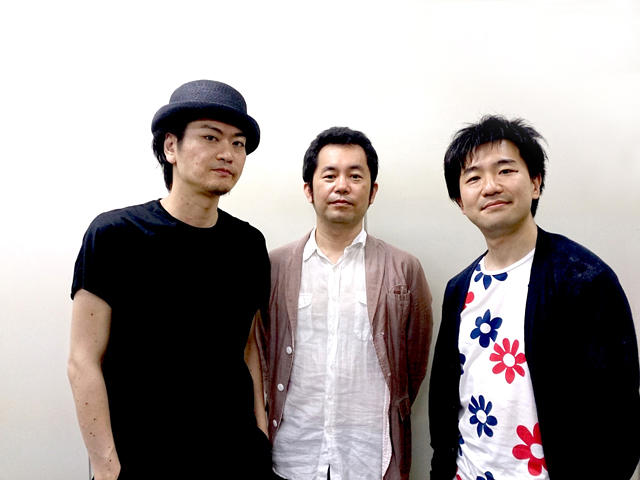
L to R 鈴木広志 / 辻 康介 / 根本卓也
谷川俊太郎さんは、自分の詩が音楽化されることをあまり制限しない人だという。ネーモー・コンチェルタートは、ヴォーカルの辻 康介と谷川氏子息の
谷川賢作が“ツルチック”というユニットを組んで共演するなど、詩人本人ともそう遠くはない。それで3人とも、しばしば谷川作品を歌詞にした曲を書いてきた。
「でも、ご本人とはそんなに会う機会があったわけではないんですよ」と辻は言う。
「自分は今回、この本の発売記念ライヴの時が初めてでした」と根本卓也。人間関係が先にあって曲をつけるようになったわけではない、とのこと。
この話題を伺ったとき「3人ともすごく本を読む人って印象あるんですが」と切り出したのだけれど、
鈴木広志に至っては
「ぼくは詩とか、とくに読まないですね。谷川俊太郎さん、いま生きている方なんだ!ってびっくりしたくらい」なんて言っていたくらいだ。でも、三人とも“音楽とつながりやすい言葉”には敏感だった。その嗅覚が、谷川俊太郎という詩人の世界を嗅ぎあてずにはいなかった。
鈴木 「言葉のかたちだけで記憶に残る詩」
辻 「自分もそんなに本を読んでいるわけではなくて、とくに詩なんかそれほど読んでこなかった。それで、あるとき日本語の詩に曲をつけることになって、あらためて現代詩の年鑑に目を通してみたら、歌になる詩というのがないんですよね。ほとんどの詩は、歌えなかった。言葉で伝える、という感じにならないんですよ。そこいくと、谷川さんの詩は音だけで伝わる、漢字を見なくても何を言っているかすぐわかる、そういう詩。貴重ですよ、すごく」
創作者としての踏み込み具合も絶妙だという。
根本 「近代の詩って、現代に近づくにつれて主観的になってくるじゃないですか。でも谷川さんは、すごく距離感をとるのがうまい。あと、表現技法のパレットがむちゃくちゃ多彩だから、軽やかに多種多様なことができてしまう」
辻も「谷川さんはこう、メッセージを言葉に乗せきらないんですよね」と続ける。わかるようでわからない、わからなくてもよい、というところなんだろうか?
辻 「目のつけどころがね、すごいんですよ。発想、インヴェンツィオの部分があるんだな」
イタリアで古い時代の音楽作法を学んできた辻ならではの見解だ。“インヴェンツィオ”とは英語で言うInvention、創作芸術における創意・独創性のことで、古代の哲学者たちやバロック期の音楽理論家たちが使う専門用語である。
独創性は、その場の即興性とも通じる要素かもしれない。
辻 「谷川さん、歌い手が歌いまちがえても平気、大歓迎だ、なんて言うんですよね。それで、じつはぼく録音で 〈スーパーマン〉の歌詞まちがえちゃってて。あーそうなのか、って安心して“〈スーパーマン〉歌いまちがえちゃって”ってお伝えしたら、谷川さん、なんとも言えない顔をしたんだな(笑)。あのときの顔、本当にいい顔だったなあ……」
そうやって曲も増えてきた彼らが、谷川俊太郎の詩によるオリジナル曲だけを集め〈谷川俊太郎特集 謎の落ちにはまって〉と銘打ったライヴを行なったのが2014年11月。このライヴが鮮烈な印象とともに客席を魅了、2015年にもふたたび谷川俊太郎特集ライヴを行なうところとなった。この時点ですでに関係者たちの興奮は高まり、録音の話まで決まっていたという。しかし、実際にどのような形態で発表するかまでは見えていなかった。
辻 「それで、ともかくも音を録ることになったんですね。その頃、たしか波多野睦美さんのコンサートでたまたまアルテスパブリッシングの木村さんと一緒になって。いま谷川俊太郎ライヴのプログラムを録音しているんですよって話をしたら“あ、じゃあウチで出しませんか”って」
こうして、アルバムはCDブックというかたちをとることになった。平素から彼らのフライヤー制作を一手に引き受けているイラストレーター&デザイナーの河合千明氏も引き込んで。文字組みにセンスあり、な書籍デザインも手がける河合氏の存在感も、このCDブックでは大きい。
「飼育係」「スーパーマン」など、プレイヤー3人のイラストにどこか似た人物が歌の物語を彩っているページもある。かと思えば「ポルノ・バッハ」のように、女体のパーツとおぼしき曲線がしなやかに引かれているだけのページもあって、ドキッとさせられる。絵本のような顔をしていながら、やはり“おとなのための”本なのだ。
辻 「河合さんにはおまかせでやっていただいて、“これほど自由に仕事できたことはなかった”って言ってましたね」
上がってきたイラストに、プレイヤー側から注文をつけることもあったんだろうか。辻と鈴木は首を振る。
根本 「〈ポルノ・バッハ〉のところ、なんか艶っぽいんですよね。女性の手の絵、あの肉厚なところが色っぽいのかな。あ、そういえばあそこで“爪の形が……”ってぼくが言いましたよね」
辻 「あ、あれは伝えてない」
根本 「ええ〜」
辻 「ぼくのところで握りつぶしました。あとでね、できてから言ったかな」
クラシックの世界にありながら、ブラームスやマーラーや……といった後世の音楽とは勝手がまるで違う、17世紀以前の声楽をイタリアでがっつり学んできた辻。同じく古い時代の音楽(いわゆる“古楽”)に親しみながら、留学先はフランスで、チェンバロ演奏もさることながら指揮者 / 作曲家として研鑽を積んできた根本。そしてサックスの鈴木はサキソフォネッツ、東京中低域、あまちゃんバンド(何を隠そう、連続テレビ小説『あまちゃん』で聞こえてきたサックスやリコーダーの正体は鈴木である)とさまざまなフィールドで活躍をみせる。いや、クラシックに根ざしながら気負わずジャンルレスに活躍できる21世紀型プレイヤーである点は、ほかの2人にも言えることではあるけれど。
そんな3人の作風の違いも、ネーモー・コンチェルタートの聴きどころのひとつだ。「谷川俊太郎の詩に曲をつけるっていうとき、選んでくる詩が3人それぞれ不思議とかぶらないんですよね」と彼らは口を揃えて言う。
ヨーロッパ古楽を本格的に学んだ2人に対して、鈴木だけはそうではない。
根本 「でもこの人、ぼくがいったん“古楽流儀の演奏スタイルで”やったことを聴いたら、それすぐに自分で再現できちゃうんですよ」
初めて自分がその分野で学ぶかはともかく、古楽との接点は多かったという鈴木。「ぼくが“面白いことやるな”って思う人は、なぜかみんなバロックとか古楽やってきた人ばかりなんですよね」
鈴木は谷川CDブックには「あくび」「つるつるとざらざら」のような触感的になごむ曲、「花屋さん」「飼育係」などスリリングでヒップな曲を提供している(こういう題の詩がスリリングでヒップになってしまうのが、谷川俊太郎世界なのかもしれない)。
オスティナート変奏、思わぬ転調、カンツォーナ風に楽節を連ねてゆく書法……そうしたバロック的手法に、やおら『トリスタンとイゾルデ』の一節が(チェンバロの音で!)なんとも自然に混ざり込んでくる「ポルノ・バッハ」など、根本の曲では古楽の音楽語彙が、前衛的な書法となんら齟齬なくまざりあう。CDの最後を飾る圧巻の長尺作品「臨死船」は鈴木の繰り出す各種管楽器の音色を筆頭に、朗読に音楽を重ねるメロドラマの手法で次から次へ、ネーモー・コンチェルタートという音響体から引き出し得る表現を限界まで究めてみせている。長い尺の音楽にも抵抗感がないのは、彼がオペラやオーケストラ作品を振る指揮者でもあるからだろうか。とくに初台の新国立劇場でも副指揮者 / プロンプターとして立ちまわるなど、オペラは根本の日常とも直結している。
根本 「新国でそのとき関わっていたオペラが、書く曲にも何らかのかたちで影響するんですよね。ヤナーチェクとか、ワーグナーとか」
それでいて、詰め込む一方ではなく“引き算”の美学もある。
根本 「どうもね、あれこれ考えぬいて組み立てた曲より、手数が少ない曲のほうが喜ばれるんですよね」
「楽譜がいちばんちゃんとしてるのが根本くん」とほかの2人が言うとおりで、根本の楽譜はそのまま出版できそうなほど明瞭に仕上げられている(ドビュッシー流儀の几帳面な楽譜、と言えば伝わるだろうか)。最初はざっくりしたメモのようなかたちで渡されるという、ほかの2人の楽譜とは対照的だ。
根本 「鈴木さんの楽譜もたいがいですよね、書き込みとかすごくて……」
鈴木 「そうかな……いやエイジングですよ、俺の書き込みは」
「そこへいくと、ぼくの曲は楽譜というかまあ、枠組くらいなものだから」と言うリーダー辻の曲にこそ、ネーモー・コンチェルタートらしさが最もよく出ているかもしれない(と言っても、ある意味彼らの持ち歌はどの曲をとってもそうなのだけれど)。あえて不道徳なところを突いてくる「おぼうさん」「うんこ」、シュールな物語展開がかわいい「スーパーマン」……そうした詩が、1600年前後のイタリアを思わせる旋法的な音使いの曲と妙にしっくり合ってしまう。
辻 「曲をつくるときは、こういうことをやってやろう、こういう様式でやろう、とか考えてないですね。何も考えてないかもしれない。“なにができてくるかな”と思いながら作ってます」
古楽の語法が、カンツォーネやイタロポップな感覚と自然になじむ。辻の濃密なイタリア修業時代が音に生きているように思うのだが。
辻 「クラシックや古楽の世界で勉強してきたんだけど、ほかのジャンルの人と音楽やるようになったから、今があるんですよね」
そういえば、辻はいつかライヴのトークで「ナポリ方言の歌もやってみた」と語っていた。
辻 「ナポリで知り合った女性にね、まあいいところ見せようと思って、現地の歌をすごい練習したんですよ。自分でもけっこう“これはいいところまでいった”と思ったので歌って聴かせてみせたら、大笑いされた。ぜんぜんちがうわよ、って」
それはどこから来た文化なのか、そして自分はどこにいるのか。ほかの文化圏で暮らしてみると、よけいに強く意識されること。そのうえで外国の音楽もやる、自分たちの音楽や言語にも意識的になる。『おとなのための俊太郎』には、彼らがいかに“日本語でうたう”ということを大事にしているかもよくあらわれている。
辻 「CDとして音を決めていくとき、古楽らしい生音感を生かしたものか考えましたね。最終的には、むしろ個々の音の要素がわかりやすく、日本語が言葉として聴こえてくる仕上がりにしていただきました。2日間でアルバム全部つくったので、それはもう大変でした。曲順もすごく悩みましたよ」
古楽系のCDは、18世紀以前の作曲家たちが実際に耳にしていたような、教会内での反響音など場の空気感をよりきわだたせた録音にしてあることも多い。
根本 「バッハ・コレギウム・ジャパンの録音など、ホール録音は立ち会ったこともありましたけど、スタジオは自分は初めてでしたね」
鈴木 「俺はむしろ、スタジオでの録音仕事はすごく多いですね。あ、こないだ録ったアレはこのトラックのここか……って、サンプル盤が届いてから思い出すこともあるくらい」
しかし、昔の宮廷音楽はもともと宮殿の私室など、比較的デッドな音響環境で演奏されることも多かった。ネーモー・コンチェルタートもビストロやカフェのような、演奏者と客席とが近い親密な空間でもライヴを行なうので、今回のCDの音も体感的にはその感覚に近いかもしれない。
鈴木 「スタジオで録った音らしさって、小さな会場での聴こえ方と何か似てるところがあるなって思います」
ライヴでは根本がとつぜん歌い出したり、3人がそれぞれに即興的な音を入れたり、一期一会のハプニング的な面白さがあるネーモー・コンチェルタート。正直、筆者も録音の話を初めて聞いたときには“ついに!”という興奮が先に立ちつつ“あの面白さをどう録音物というかたちに固着させられるのだろう”と思ったのはたしかだ。しかし、仕上がりはじつに完成度の高い、アルバムとして何度も聴きたくなる音源だった。畢竟、彼ら3人がCD音源というものをどう考えていたか、興味が出てくる。
辻 「湘南ビーチFMのクラシック番組でDJをやっていた頃がピークでしたが、CDは相当買ってきましたね。イタリアで古楽系のCDレーベルが続々出てきた90年代(=辻がイタリアにいた時期でもある)にはいろいろ刺激も受けましたし、そのあとフランスの古楽レーベルが伸びてきたときも。Alphaレーベルの白いシリーズ(=正統派の古楽と民俗音楽・現代・即興などが入り混じる、独特のジャンル越境型シリーズ)も買ったなあ」
CD文化のいいところのひとつは、誰かの家に行ったときコレクションを目の前で共有しながら、知見を広げあえる点だ。
辻 「福島久雄さん、ジプシー・スイング系のギタリストなんだけど、彼の家に行くとCDがものすごいたくさんあるんですよ。ジャンルもいろいろで。いろいろなことをあそこで教わりました」
根本 「ぼくは昔、オーケストラの演奏会に入りびたっていた学生だったんです。上野の東京文化会館に行く途中に御茶ノ水を通るのもあって、あそこのディスクユニオンはものすごく通いました」
録音物との出会いはエアチェックだという。
根本 「『FMファン』(=ラジオの番組表が付いていた雑誌)はずっと買っていましたね。でも録音物で古楽と出会ったのはずっと後で、はじめのうちはタリス・スコラーズ(=ルネサンス教会音楽を得意とする英国のア・カペラ・グループ)ぐらいだったかな。でもあるとき御茶ノ水のディスクユニオンで何気なく手に取ったCDに衝撃を受けた……それがパニアグワ兄弟のアルバムでしたね」
パニアグワ兄弟はギリシャ出身の古楽系プレイヤーで、民俗音楽との境界があいまいな、突き抜けたアルバム作りをいち早く提案、一部の古楽ファンを中心にリスナーたちを震撼させてきた異色派である。予備知識なしに店頭でそれを引き当てる根本も根本だ。
鈴木 「(実家のある)大宮ではクラシックのサックス吹いてる人のCDなんてぜんぜんなくって。それで自分で音源をいろいろ探すようになったかな。今でも御茶ノ水とか神保町とか、中古CD屋さんが多いところはよく行きますね……っていうか昨日も行ってきたばっかり。8枚買っちゃいました。ティグラン・ハマシアンっていう、アルメニア出身の異界的なジャズ・ピアニストのがデビュー盤から揃ってたから、3枚はそれ。あと“アルゼンチンのチャールズ・ミンガス”って触れ込みで売ってたのがあって……それは正直、思ってた感じじゃなかったな、とか」
圧倒的な音量差にもかかわらず、チェンバロとも合わせられてしまう鈴木。リアルでボーダーレスに未知の音を探り続けているからこそ、出せる音があるのかもしれないと思った。
“おとなのための”と銘打っていながら、絵本という子供のためのメディアの体裁をとっているCDブック『おとなのための俊太郎』。どこに置いてほしいですか? の問いに、辻は「図書館、公共の図書館に置いてあったら嬉しいですね」。鈴木も「あー、学校の図書館とかね」と続ける。おとなのための……の部分でPTAの反発を招かないことを、筆者も切に願う。
彼らはこれからも、谷川俊太郎の詩による歌を披露しつづけてゆくという。ライヴではどういうところで聴いてほしいだろうか。
辻 「ぼくらは基本的にPA(=マイク)なしで生音でやってきてるんだけど、もしかしたらPA使うようなところでやってもいいのかな、と思いますね」
根本 「そうですね、〈臨死船〉なんかもそうだけど、ぼくらの曲は語りの部分も多いですし」
「老人ホームなんかもいいね」なんてことを言い出すのも辻である。お聴きいただければすぐにわかることだが、じつは『おとなのための俊太郎』には何らかのかたちで死についてうたった曲が多い……そこをあえて、人生の大先輩たちはどう聴くのか、ということだ。
辻 「それから、外国人の方々にも聴いてほしい。日本語がわからない人たちにはどう聞こえるんだろう、って思うんですよね」
鈴木 「あと、子供。『子供のための俊太郎』って題して、同じプログラムで(笑)。子供の前でやってみたいですね、〈うんこ〉とか、ほら」
この件について、インタビュー時間の最後で鈴木が言っていたことが印象的だった。
鈴木 「ネーモー・コンチェルタートのライヴは小さいところでやることも多くて、客席との距離も近いし、自分たちのことを好きでいてくれる人が増えてきたのが嬉しい。そのうえで、子供とかもそうだけど、たとえばフェスに出るとか、今の自分たちを知らない人たちがもっといるところで、やってみたいですね」
おとなのための俊太郎
「猿楽祭 代官山フェスティバル 2016」参加企画


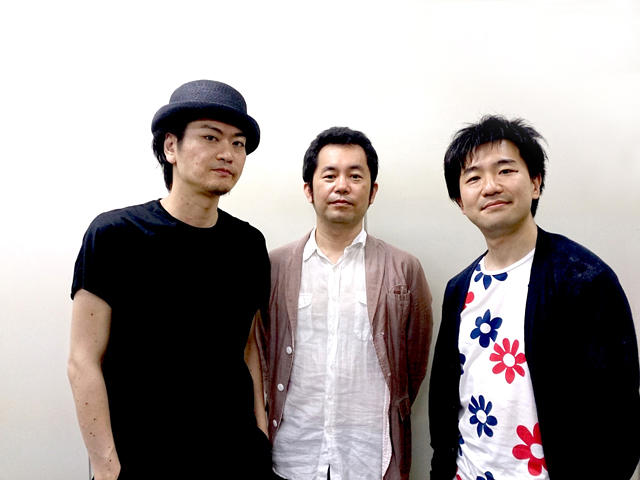

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。