――今回、MIKUMARIくんは名古屋から、そして、OWL BEATSは鹿児島からお越しいただいたわけですが、RC SLUMが度々ライヴを行っている鹿児島のシーンとつながりを持つようになったきっかけというのは?
OWL BEATS 「鹿児島に
LIFESTYLEっていうハードコアバンドがいて、その名古屋でのライヴについていった先でデモを配りまくってたら、それを聴いた(RC SLUMのオーナー)
ATOSONEが気にしてくれるようになったのが最初ですね」
MIKUMARI 「当時、僕は
HVST KINGSってグループで活動していたんですけど、2010年にEP『
BLACK FOCUS』を出す前のタイミングで、よくしてくれたLIFESTYLEのギターのYOHEIくんを頼って、鹿児島のイベントに出させてもらったんですけど、そこで初めて、OWL BEATSと話して。僕はそこで初めてデモを聴かせてもらって、ギャングスタラップばかり聴いていた自分にとっては聴いたことがないビートだったんですけど、それでも“これはヒップホップだ!”って思ったんですよ。そこから頻繁に連絡を取るようになり、ビートをもらうようになったんです」
OWL BEATS 「九州には同世代でヒップホップやビートミュージックをやってて、自分のように熱を帯びている人がいなくて。そんなこともあって、MIKUMARIをはじめ、RC SLUMの面々と打ち解けることが出来たんです」
――九州といえば、福岡にはOLIVE OILという素晴らしいビートメイカーがいますが、彼と親交はなかったんですか? OWL BEATS 「実は昔、福岡で彼と一緒に住んでいたことがあって、ひたすらビート作りとDJに没頭していた彼から学びつつも、正直に言えば、彼に対して、負けたという悔しい気持ちを抱えたまま、鹿児島に戻ったんです。でも、勝ちたい気持ちがすごくあって、そのためには福岡の流れとは違う自分なりのスタイルを作らなきゃ敵わないと思ったんですね。その試行錯誤の一環として、外に目を向けて、そんななか、RCの面々と出会ったんですよね」
MIKUMARI 「そして、そうこうするうちに、OWL BEATSが一人で名古屋に来たんです」
OWL BEATS 「(TYRANT、初期RCで活動していた)ラッパーの
HIRAGENに言われて、“面倒見るから、ビートを作りにこっちに来てくれ”って言われて。当時、バイトしてた職場を辞めて、YUKSTA-ILLの地元、鈴鹿の(文化拠点である)ビルに1ヶ月滞在しながら、ビートを作ったり、名古屋に遊びに行ったりしてたんですよ」
MIKUMARI 「そうやって一緒に遊んでるうちに、関係性がより密になって。帰る日に飲んでるうちに、“お前も鹿児島行ってこいよ!”っていう話になり、ATOSONEの店に置いてあった鶏の形の貯金箱をそのまま渡されたんですよ(笑)。それを脇に抱えて、“分かった。行ってくるわ”ってことで、鹿児島に行って、そこで初めて曲を作ったんですよ。ちなみにその曲は長らく未発表だったんですけど、今回のアルバムの特典CDに収録してますね」
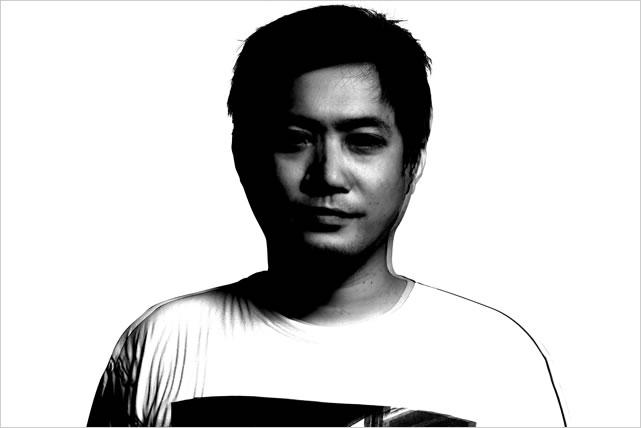
OWL BEATS
――RC SLUMの諸作には色んなビートメイカーが参加していますが、今回の作品を聴くと、RCらしい音楽性があるように思ったんですね。時にインダストリアル・ヒップホップとも称される硬質なビートに、ジャズ、ドゥーワップやソウル、レゲエやダブだったり、そうした様々な要素が1枚に凝縮されているし、OWL BEATSがRCの個性を担っているところもあのかなって。
OWL BEATS 「知り合った当初は仲良くなりつつも、音楽的な歩み寄りはまだまだだったと思うんですけど、自分が30代になって出来るようになったこと、彼らとの密な関係にあるからこそ出来るトラックが今回のアルバムでは表現出来ているんじゃないかなって。そこではもちろん、どれだけ格好いいことが出来るかというお互いの戦いがあるし、付き合っていくなかでMIKUMARIも音楽性の幅が広がって、それに従って、ラップも尖ってきていると思います」
MIKUMARI 「うん。聴く音楽も、ラップに対しても広がりが出たというか、柔軟になった気がする」
OWL BEATS 「こちらからすると、自分にしか出来ない、斜めからのアプローチの仕方を許容してくれる器がRCのみんなにはあるように感じたし、作品を作ったり、親交を深めるなかで、その予感は間違いなかったなって思いますね」
――そして、MIKUMARIくん自身は最初からソロ・ラッパーだったわけではなく、それ以前に活動していたHVST KINGSの一員として、RC SLUMに所属していたんですよね?
MIKUMARI 「そうです。ATOS個人とは昔からずっと一緒で、そこからRC SLUMが出来て、TYRANTが出来て、HVST KINGSがあったという感じです」
――今回の2曲目「Fine Malt」では“奥の細道の水の都”と歌っていますが、出身は岐阜県の大垣出身ということになるんですか?
MIKUMARI 「そうです。名古屋に某レコード屋があって、そこはもともとハードコアを扱うお店だったんですけど、ある時期からギャングスタラップを扱うようになって、高校生の頃、大垣から通っていたんですけど、18、19歳でそのお店で働くようになったんですね。そのお店がATOSの働いていた服屋とフロアが一緒で、仕事しながら、2人で遊んでるみたいな、そんな感じでしたね。当時、ATOSはブレーキが利かないチェロキーに乗ってたんですけど、繁華街に向かう車の中では爆音で(アメリカのメタルコアバンド)
Hatebreedがかかってて(笑)」
――チェロキーにHatebreedって、近くに居たら、絶対関わりたくない(笑)。
MIKUMARI 「ATOSはそんな感じでハードコアに詳しくて、俺は
South Central Cartelだったり、ギャングスタラップが大好きだったので、曲を共有し合って、お互い、こういう悪い音楽があるのかって思ったり、無茶して遊んでましたね。当時、自分はラップをやっていたんですけど、TYRANTには加えてもらえなくて、“畜生。TYRANTばっかり目立ちやがって”っていう思いを原動力に、HVST KINGSで活動していたので、もし、TYRANTに加わっていたら、今の自分はなかったかもしれないなって思いますね。ただ、そのHVST KINGSもなくなり、俺一人になったタイミングで、どうしよう?と思っているところに、OWL BEATSの後押しがぐいぐいあったんですよ」
OWL BEATS 「その時のMIKUMARIは、やりたいことが上手く回ってないんだろうなって思ったので、“曲なら作るよ!”って」
MIKUMARI 「その後押しがあったからこそ、OWL BEATSのアルバム『
?LIFE』の〈D.O.D〉でのコラボレーションを経て、ソロで活動出来るようになったところはありますね」
MIKUMARI 「そうですね。それも(RC SLUM主宰のイベント)METHOD MOTELの現場でぱぱっと決まったことだったりして」
OWL BEATS 「俺としてはリミックス・アルバムを作って、小遣い稼ぎをしたかったんですよ(笑)。みんな、音楽に心血を注いでも、なかなか見返りがなかったりするじゃないですか? でも、それを自分のやり方でどうにかならないかなって思って、ファーストに提供したトラックのギャラはいらないから、その代わり、ファーストのアカペラをもらって作ったリミックスアルバムの売り上げを分配しようって」
――そういう意味ではOWL BEATSが尻を叩いているところが少なからずありそうですね。
MIKUMARI 「俺に関しては、まさにその通りですね。エンジンかかるのが遅すぎて、今回のアルバムでも色々迷惑かけましたし」
OWL BEATS 「かといって、自分も鹿児島にいるだけでは、音楽のモチベーションがなかなか高まっていかないので、いい関係だなって思いますけどね」
MIKUMARI 「エンジンがなかなかかからない間に
SLUM RCのアルバム『WHO WANNA RAP?』を作ったり、状況は良くなっていると思うんですけど、良くも悪くも俺はそういう意識を持っていないところがあって。でも、今回のアルバムではようやく自覚が芽生えて、作品は作った以上は金が欲しいと思えるようになりましたね。俺、エンジンがかかれば、早いんですよ(笑)。今回もぱぱぱっといい勢いで録っていったんですけど、ラスト1、2曲というところで、目処がついたと油断して、ATOSのお叱りを受け、ようやく完成に至ったという(笑)」
――ファーストアルバムは初期衝動的にラップ出来ると思うんですけど、セカンドともなるとハードルは上がりますよね。
MIKUMARI 「そう。音楽や考え方だったり、進化を見せなあかんじゃないですか。でも、その部分は変に意識はしてなくて、日々生活しているなかでの変化や進化が自然とラップに表れているんじゃないかなって」
――これも自然な成り行きだと思うんですけど、MIKUMARIくんのラップは、名古屋弁なのか、尾張弁なのか、言い回しになまりを残しているじゃないですか?
OWL BEATS 「俺はあんちゃんラップって呼んでます」
MIKUMARI 「名古屋弁ではなく、大垣の言葉使いなんですけど、名古屋に来て、15、6年になっても、その部分は全然変わってなくて。かといって、大垣生まれということにこれといった思い入れがあるわけでもなく、自然な成り行きだったりするし、その言い回しも気取った感じは自分らしくないというか、それがラップの悪ノリに集約されているんでしょうね」
――MIKUMARIくんはMIKUMARINRADIN名義でDJもやっていて、そこではずっと好きなギャングスタラップをプレイしてますけど、MIKUMARIくんのラップにはギャングスタラップ特有の緩さがありませんよね。
MIKUMARI 「ギャングスタラップが好きだからといって、自分のラップはそうならないというか、そこは分けて考えてますよね。というか、俺がレイドバックしたラップをしたら、キモくないですか?(笑)」
――まぁ、そういうラップもありだとは思いますし、今回はトラックも新機軸といえる「Happy Go Lucky Me」に象徴されるような、レゲエのルーディーなノリも随所に表れているように感じました。
MIKUMARI 「そうですね。ここ何年かで音楽の幅が広がって、レゲエを聴くようになったことで、その影響がラップに反映されとると思いますね」
OWL BEATS 「〈Happy Go Lucky Me〉に関しては、明確なイメージがあったみたいで、最初に送ったトラックは反応がイマイチだったんですよ。MIKUMARIは俺の作るトラックに大分乗せられるようになってきているし、俺も進化していかないとなって思ったんですよ」

MIKUMARI
――OWL BEATSのトラックは音数も多かったりするし、スキルがないと乗りこなすのが難しいと思うんですけど、MIKUMARIくんのラップはさらに進化していますよね。
OWL BEATS 「そうですね。仲の良さがあって成立している音楽だなって思います」
MIKUMARI 「俺もそう思う。いま流行ってるビート、ラップのスタイルなんて、誰でも出来るじゃないですか。でも、OWL BEATSとの関係性はそういうことじゃない。じゃないと、あそこまではなかなか出来んよね」
OWL BEATS 「“今日、パチンコ負けた”とか、どうでもいいLINEのメッセージが3日に1回くらい来ますからね(笑)」
MIKUMARI 「それはお互い様よ(笑)。まぁ、でも、そういう繋がりがあってこそ、ずっと聴けるアルバムが出来ると、自分は思ってます」
OWL BEATS 「自分は音楽に対して、一切の嘘をつきたくなくて、イメージとしては自分のなかから、体から出てくる音楽を作りたいんですよ。そういう部分まで理解してくれるラッパーはそういないですよね。遊んだり、メールでのやり取りを重ねることによって、リズムをつかんでくれることもあったりするし、それこそが音楽の醍醐味だと思っているんですけどね」
MIKUMARI 「ホントそういうことだよね」
OWL BEATS 「だって、聴いてきた音楽は真逆というか、全然違うし、ヒップホップに関してはMIKUMARIが先生だと思ってるし」

MIKUMARI
――ギャングスタラップ好きのラッパーが乗せてるラップもギャングスタラップではない、酩酊感の強いパンチライン満載のオリジナルなものになっているし、WARPやNINJA TUNEがルーツというOWL BEATSのビートも、もはやその面影はないという。
OWL BEATS 「ははは。うれしいな。ありがとうございます」
MIKUMARI 「パンチラインは……最近はそう呼ばず、殺し文句って言ってるんですけど(笑)、殺し文句は満載だけど、今回は攻撃的なリリックも1、2曲だし、“ちょっと大人になりました。こんな俺ですが”っていう気持ちもあります」
――年齢、経験を重ねた、いい音楽としての熟成感や味わいの深まりは、ウイスキーのJACK DANIEL'Sのラベルを思い起こさせるアルバム・タイトルの『FINEMALT NO.7』にも打ち出されていますよね。
MIKUMARI 「まぁ、そうですね。“NO.7”というのは、ギャンブル好きで首に“777”のタトゥーが入ってる俺のことでもあるんですけど、JACK DANIEL'Sのラベルに書かれている“NO.7”は、プレイボーイだったとされるJACK DANIELがはべらしていた7人の恋人を意味しているとも言われていたり、諸説ある謎の数字らしいんですよ。だから、今回のアルバムもそんな風に捉えてもらえたら嬉しいですね」
取材・文 / 小野田 雄(2017年9月)
![MIKUMARI×OWL BEATS - FINE MALT NO.7 [CD] MIKUMARI×OWL BEATS - FINE MALT NO.7 [CD]](/image/jacket/large/411709/4117092309.jpg)



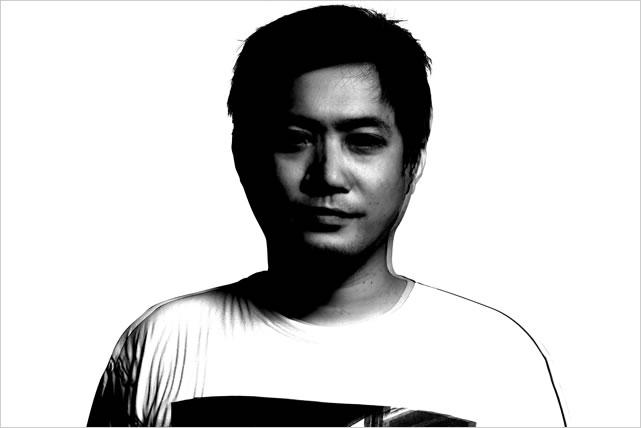



 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。