Nao Kawamura は1992年生まれのシンガーで、ソングライターでもある。
Suchmos 、
SANABAGUN. 、
WONK 、
FIVE NEW OLD 、AmPmなどのレコーディングやライヴに参加し、2016年にミニアルバム『
Cue 』でソロ・デビュー。FUJI ROCK FESTIVAL(2016年)、SUMMER SONIC(2017年)にも出演し、めきめきと知名度を上げている彼女が、初めてのフル・アルバム『
Kvarda 』を3月にリリースした。現行ジャズやオルタナティヴ・ソウルなどの先鋭的な流れを捉えつつ、絶妙のバランスで日本の音楽として成立させた力作である。
VIDEO
「バランスはいつも考えてますね。流行りは取り入れつつ、芯をブレさせないために、なんで作るのか、何を作るのか、というところに必ず立ち返って、一度自分を裸にした状態から始めるんです。本当に伝えたいことは何かとか、なんで歌うのかとか。そこから持っているものを引き出していくんです」
――なかなかしんどそうですね。
「めっちゃしんどいです。〈Awake〉は2年前に作った曲なんですけど、そのときにその方法を始めたんですよ。そうじゃないやり方ももちろんあると思うんですけど、せっかくソロ・アルバムを作るんだから、自分のことを考える時間は絶対に作ってあげたいなっていうか。今そうしておかないと、大きくなったときに“どういうふうになりたいの?”って訊かれて“何でもいいです”ってなっちゃったら、それまで積み上げてきたものも失っちゃう。多少流されてもいいくらいのものを作り上げたいなって。変わらないものって言っても多少変わっていくんですけど、その作業自体が大事だなと思っていて。たぶんわたしはドMすぎて(笑)、自分を追い込んで崖っぷちに立たせるのが好きなんですね」
――2年前というのはEP『AWAKE』を作ったときですよね。気持ちが入りすぎて重い作品になってしまった、と話しているのを読んだことがあります。
「世の中との距離感を考えないままに自分と向き合いすぎてしまった、みたいな。超個人的で、これはこれでいいんですけど、あまりに内に向きすぎたし、サウンドもシビアな感じになっちゃったから、ちょっと違うかなって。何年後かにポンと出したいな、とも思ってます」
――スタート地点として?
「実はその前にもう1作、大学生のときに作ったアルバムがあるんですけど、今の考え方になったのはその『AWAKE』からです。前の作品はさらに個人的な内容で、サウンドも全然違うんですよ。(現Suchmos、SANABAGUN.の櫻打)泰平が手伝ってくれたんですけど。それからいろいろあって、バランスを見ることを学んでいきました」
――どうしてそういう作り方をしようと思ったんですか?
「自分が生きる過程の、通過地点みたいな意識があるんですよ。だからどうしてもそこに立ち返らないとできなかった、今は。一方で社会がわたしに求めるものがあって、それはまたいろんな要因で変わっていくだろうから、個人的なものと社会との接点を見出したわたしの場所、みたいなものは今後も移っていくと思うんですけどね」
――しっかりされていますねー。
「全然そんなことないです。昨日も朝の5時までプロデューサーの澤近(立景)と電話してたんですよ。いつも大事なときは電話でミーティングするんですけど、12時から話し始めて、気がついたら5時でした(笑)。このままインタビューに持っていったら面白い内容なんじゃないか、みたいなことをずっとしゃべってました」
――Naoさんにとって作品は自分の成長の過程の記録みたいなところがあるんですね。
「あります! めっちゃあります。いつも自分が何を思ったかメモをとってるんですけど、その中にもありました。なんで音楽をやっているのかを自分に問うたときに“残したい”って言葉が出て。死んでも音楽は残るじゃないですか。わたしは明日死んでもいい生き方をしたいので、今はお金がなくても、やってる意味はあるかな、みたいな」
――音楽は社会と自分がつながるチャンネルでもあるんでしょうか。
「前は個人的な音楽を作ればいいと思ってたし、プロになる必要を見出せなかったんですよ。音楽大学に行ってたんですけど、“売るためには!”“武道館を目指せ!”みたいな講義もあって“いやいや、みんなが武道館いきたいわけじゃないんだけどなぁ”って思ってました。先生たちも学生の可能性を引き出そうと必死だったんだと思うんですけど、当時のわたしには“えっ、売れれば正解なのか?”みたいな」
――大学時代はあんまり授業に出ず、図書館にこもってCDやDVDを漁っていたそうですが、それも先生のお話に納得できなかったからですか?
「本当はそういうビジネス面のことも同時進行で学ばなきゃいけなかったんですけど、わたしの頭のキャパがなさすぎて、“ちょっと待って。それより先にやることあるわ”みたいな感じで、わーっと音楽を聴き始めたんです。わたしは本当に不器用だし、勉強もできないんですよ。できないっていうか、自分なりに方法論を見つけないと入っていけない性格だから、理解しきれないまま終わっちゃうんです。そういうこともあって、あんまり授業に出れなかったというか、出ても吸収しきれなかった。だから自分の好きなものは何なのか、ひたすら掘っていった感じですね」
――そこで見つけたものは何でしたか?
「やっぱりオリジナリティがないとダメだなっていうことでした。そのためにはルーツがないといけないし、何が好きで何が嫌いかっていう根本のところがないと。自分のやりたいことも少しずつ見えてきました。よくいろんな人に“ソロになりたいの? コーラスがやりたいの?”って問い詰められたんですよ。まだ失敗できるから何でも挑戦してみるべきなんですけど、コーラスの仕事が入ってきたときに“絶対違うわ”と思ってやめちゃったこともあったくらいで、サポートかバンドか、ソロかコーラスか、とか選別していったら、ソロのシンガーになりたかったんだな、曲を作りたいんだな、ってところにたどり着いたんです」
――その過程で影響を受けたのが、ユーミンとか?
「そうですね。あと
エリカ・バドゥ とか。けっこうソウルも聴きました。ライヴ映像を見たり、伝記を読んだり。ジャズも聴いたけど、まだよさがわかんなかったんですよね。ユーミンの
荒井由実 時代、特にファースト・アルバム(『ひこうき雲』)がめっちゃ好きで、黄金期だなって勝手に思ってるんです。当時はまだシンガー・ソングライターじゃなくてシンガーになりたかったんですけど、その例って
ホイットニー・ヒューストン とか
マライア・キャリー とかじゃないですか。でもそことはちょっと違ったんですよね。歌は歌いたいんだけど、めっちゃ歌うまいから聴いて!ってわけじゃなかった。じゃあ曲をすごく作りたいかっていったらそうでもないんですけど(笑)。歌いたいんですよ。でもオリジナルを作ったほうが自分の世界が作れるよなぁ、って」
――シンガーに専念するには自分の世界を表現したい欲求が少し強すぎた?
「うん。だと思いますね。あとシンガーの新しい形を作りたかったっていうのもあります。試行錯誤は今もしてますけどね。“曲書きたくないんだよ~”って先生に相談して“いや、今は書け!”みたいな(笑)。“Naoの曲いいじゃん”って言ってくれる人がひとりでもいるのなら、歌と同じようにやる必要があるのかなって感じてました。だから一応曲は書いてましたけど、早くやめたいな~と思ってたら澤近が現れた、みたいな(笑)」
――曲もいいと思いましたよ、アルバムを聴いて。
「ほんとですか? でも、前は“曲書くのやだな”って思ってたのに、アルバムを作り終えたときには、もっと作りたいって思いました」
――そう考えると、このアルバムはNaoさんのスタンスがシンガー・ソングライターに決まるひとつのきっかけになったんですかね。
「シンガー・ソングライターっていうのはもともと……いやシンガーか……難しいですね(笑)。シンガーでもいいし、シンガー・ソングライターでもいい、みたいな。ぴったりはまる言葉がないんですけど、両方とも属せるようになりたいんですよ。音楽をやるんだったら詳しくなきゃいけないから、もっとちゃんとやんなきゃな、とも思うし。澤近とか見てると、やっぱり作曲能力すごいから、そこに近づかないと対等に話もできないし。やりたいものを実現させるためには、やっぱり知識が必要なんですよね。あとは単純に、澤近はめっちゃいい曲書くのに、わたしが書けないのはやっぱり悔しいし。それでやり始めたんですけど、今は歌唱がこのへん(上のほう)としたら、作詞がこのへん(中くらい)で、作曲はこのへん(下のほう)なんですよ。それを30歳くらいまでに、こう(すべて上のほう)したい」
――それは大きな変化ですね。
「歌では最近遊べるようになってきました。前は歌うのに必死でしたけど、今回は例えば、酔っ払って声が出ないんだけど出してる声を出してみたいとか(笑)、すっごいバカにしてる声とか、コソコソ話してるような声とか。けっこうユーモアがあるアルバムだと思うんですよ」
――うんうん。そう思います。
「歌詞でも、ここにこんな言葉を入れたら変だけど面白いからいいか、みたいに思って入れたりとか。歌詞はわりとメロディに忠実に入れたつもりなんです。制約がある中で面白い表現をけっこう入れられたと思うんですよね。さっき言った歌唱面も含めて、表現の幅を勝手に広げていった。で、曲でもそれをしたいと思ったんです。まだ作曲ではやりたいって思ったことが再現しきれないから」
――「Time is not on our side」や「Hot shot」なんかまさに演じているような感じだし、例えば“領収書にサインして”(「Ego」)なんて表現にもユーモアを感じました。
「〈Hot shot〉は澤近からサビしかないものが送られてきて“あとはNaoが勝手にやってください”って書いてあったんですよ。“わかりました”って言って一日で仕上げました。アルバムの制作期間はトータル3ヵ月くらいで、1ヵ月で何をやりたいか考えて、2ヵ月目で曲を作って、3ヵ月目で歌詞を書いた感じだから、歌詞はありえないスピードで一気に書いたんですよね。この一日で3曲って決めて書く、みたいな。誰にも会わずに家にこもって、集中できる時間と精神状態を作って。修行僧みたいな3ヵ月でした(笑)」
「あ、わかる!“あれ? これわたしが書いたんだっけ?”って、けっこう思いました。わたしは作品ができあがったら手が離れたみたいな感覚で、あんまり聴かないことが多いんですけど、このアルバムは完成してからリリースまでに時間が空いたこともあって、けっこう何度も聴いたんです。なんか自分と離れてはいるんだけど距離が近いみたいな感覚がありますね。あとあと発見もあったし」
――思い入れもこれまで以上にあるんじゃないですか?
「2年間の集大成っていうのもあるし、2年前の曲が入ってるのもあるし、あと奇跡的な出来事が重なったのもありますね。去年の10月がすごい月だったんですよ。取りかかろうと思っていたことが向こうからやってきたりとか、自分の中にあったものがどこか別のものとリンクしたりとか、自分を本当にまっさらにする機会があったりとか。その勢いのまま制作期間になだれ込んだんですけど、どーんと落ちて“制作やめようかな”と思ったときに、不思議な後押しがあったりとか。決まってなかったことが決まるとか、意外な人とつながるとか。それで“これはやめちゃダメだな”って」
――見えざる力にも導かれたのかも。
「マジであるなって思います。そもそも、わたしが歌ってること自体がすごいことだと思ってるから。やりたくてもできないことのほうが多いわけだし、それをできてるってことは、やれってことだから。例えば音楽を東京で続けたいけど、家庭内の事情でどうしても実家に帰らなきゃいけない、と言う話を聞いたことがあったんですが、そういうときってそういう時期だと思うんですよ。やれない時期みたいな。私も実は大学卒業してからすぐ、足の手術をして活動できなかった時もあったし……。今は歌えてるし制作もできてるけど、これから歌えないときがきたらそれは歌えない時期ってことだし、また歌えって時期がきたら歌えばいいし。そういう流され方は大事かなと思います」
VIDEO
――運命論じゃないけど、起こったことは正しい、みたいな感覚ですかね。
「澤近のおかげは大きいです。サウンド・プロデューサーですけど、人間の教育もできるんだなって。あいつ自身の人間性は……?ですけど(笑)、言葉の節々に導きの力みたいなものを感じる。プロデューサー向きだと思いますね」
――澤近さんというパートナーを得たことはNaoさんのキャリアの中ではすごく大きそうですね。
「大きいと思います。なんでか知らないけどわたしのところに来て、なんでか知らないけどわたしがデモを持って行ったら作ってくれたりして、“なんでやってくれるんだろ?”って思ってたんですけど、ずーっとそれを続けてて。最初は疑ってたし、ケンカも何度もしましたけど、そのうち“あれ? これはやりたいからやってるんだな”って思えてきたんです。でも“やりたいからやる”って、なかなかないことじゃないですか。自分のプロジェクトでもないし、正直お金にもなってないし、有名にもなってないし、未来が保証されてるわけでもない。そんなものに自分の時間を投資してるわけじゃないですか。そう考えたら、彼がいてくれることで生じる責任はあるから、わたしがしっかりしないといけないし、もっとがんばらないといけないと思えるようになりましたね。それは澤近にとっても同じだと思うんですけど」
――そうですね。プロデューサーとして名前が出るわけだし。彼にとってもこの仕事はひとつの実績になるでしょうし。
「なってほしいです。いちばんあげたいのは、お金じゃないものを――お金はもちろん渡さなきゃいけないんですけど(笑)、それはそれとして、お金で買えないものがNaoとの仕事で得られたな、って思ってほしいですね。関わってくれてるみなさん全員にそうなんですけど。それがいちばんの恩返しっていうか、今のところ、それしかできないから」
――今後こんなふうになりたい、みたいなヴィジョンってありますか?
「超ざっくりですけど、こういう形のシンガーは今のところいないかなって思うから、Nao Kawamuraっていうジャンル、モデルをちゃんと作りたいですね。前例を見つけるために大学の図書館にこもって、自分はこうなのかな、こうじゃないのかな、ってやってたけど、結局見つかんなかったから、今もずっと捜してる途中といえば途中なんですよね。でもNao Kawamuraだ、っていうものがあればいいなって。それをいつもいつも考えてます。言葉にするのは難しいんですけど、それを言葉にするためにも、もっといろいろ挑戦したいですね」
――アーティストとしては未完成なのかもしれませんけど、だからこそ見続けていきたい感じがあります。
「それはありがたいですね。だし、見てる人は面白いだろうな~って自分でも思います(笑)。それもわたしの人間性のひとつだと思うんだけど」
――4月20日に渋谷のWWWでリリース記念のワンマン・ライヴがありますね。
「とにかく来てほしいです。ヴォーカル、トランペット、キーボード、ギター、ベース、ドラム、パーカッション、コーラスが2人の9人編成で、わたしの世界観がガッツリ伝わるものになると思います。WWWではずっとやりたかったんですよ。こないだ友達のライヴをWWWで見て、そこにわたしを置いてみたら“いいな”と思ったんで(笑)。わたしのライヴって、踊ったり盛り上がったりって感じでもないし、どうしたらいいかわからないみたいなお客さんがけっこういるんですけど、それも逆にいいのかなと思って。
坂本龍一 さんが提唱している“設置音楽”にすごく共感したんですけど、1枚の絵が1時間半展示してあって、それぞれ感じたことを持って帰ってください、みたいな」
取材・文 / 高岡洋詞(2018年3月)
2018年4月20日(金) 前売 3,500円 / 当日 4,000円(税込 / ドリンク代別 / オールスタンディング)チケットぴあ(107-161) ローソンチケット(75622) e+ 
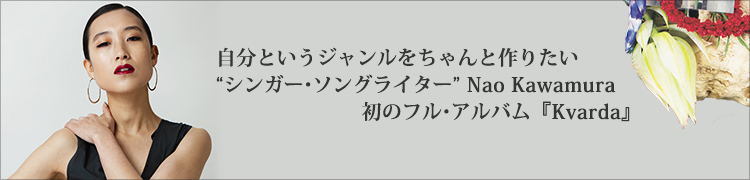
 読み込んでいます…
読み込んでいます…
 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。